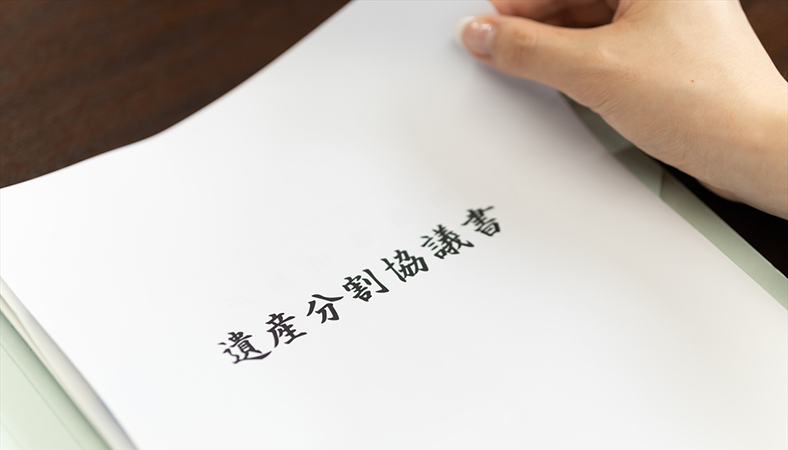無申告は危険!臨時収入も一時所得としてきちんと確定申告しよう

1年間に収入があった個人は、給与収入などを除いて原則、確定申告を行う必要があります。事業の収入だけでなく、臨時収入も確定申告が必要な収入に含まれます。
ここでは、どのような臨時収入があると確定申告が必要になるのか、確定申告をしなかった場合どうなるのかなど、臨時収入と確定申告について解説します。
一時所得の内容と計算方法
所得税では、個人の収入を収入の種類や性格に応じて、事業所得や給与所得など10の区分に分けて、所得金額や納める税額の計算をする必要があります。臨時収入の場合、事業所得ではなく一時所得になる可能性が高いです。
そこで、はじめに一時所得の内容と計算方法について見ていきましょう。
そもそも一時所得とは
一時所得とは、簡単にいうと「一時的・臨時的に得た収入(所得)」のことです。厳密には、国税庁のホームページで以下のように定義されています。
一時所得とは「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」のこと。
つまり、一時所得は、事業を行うなど利益獲得のための行為を行わずに得られた臨時的・偶発的な所得のことです。臨時収入も、事業など利益獲得のための行為を行わずに得られた臨時的・偶発的な収入に該当するため、一時所得になることが多いです。
一時所得の計算方法とは

個人が収入を得た場合は確定申告を行い、所得金額や納税金額の計算を行う必要があります。これは、一時所得でも同じです。
ただし、一時所得の金額の計算は、他の所得金額の計算方法とは異なるので、注意が必要です。一時所得の金額は、次の計算式で求めます。
このうち、課税対象となるのは、1/2になります。
例えば、臨時収入で100万円、収入を得るための支出が20万円だったとします。この場合の一時所得の金額は、以下のようになります。
課税される一時所得金額=一時所得金額30万円×1/2=15万円
なお、一時所得の計算で、収入から差し引くことができる「収入を得るために支出した金額」は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額のみです。
例えば、競馬で同じレースに5点、それぞれ5万円ずつ賭け、その内1点が的中して100万円払い戻されたと仮定します。この時、競馬で支払った金額は25万円ですから「収入を得るために支出した金額」を25万円としたくなりますが、これは誤りです。
100万円の払い戻しがあったのは5点のうち1点であり、その1点に支払ったのは5万円なので、「収入を得るために支出した金額」として計上されるのは5万円となります。
臨時収入もきちんと確定申告しよう
ここでは、一時所得になる具体的な収入の内容や、確定申告が必要なケースについて見ていきましょう。
一時所得になる収入とは
先述したように、一時的・臨時的に得た収入(所得)を一時所得とよびます。一時所得に該当する代表的なものには、主に以下の5つが挙げられます。
2.競馬や競輪の払戻金
3.生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等
4.法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除く)
5.遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得となる代表的なものとして、懸賞や福引、競馬の払戻金などがあります。実際に、福引や競馬などで収入を得たという人も多いでしょう。では、福引や競馬などで収入を得た場合は、必ず確定申告が必要かと言えば、そうではありません。
一時所得の計算では、最高50万円までの特別控除があります。そのため、福引や競馬などで得た収入が50万円以下であれば、税金を課されることはないので、確定申告は不要です。
次に「法人から贈与された金品」です。法人から個人への贈与は、二者間の雇用関係の有無に応じて性格が異なります。
すなわち、受贈者である個人が従業員ないし役員(法人から雇用している従業員への贈与)であれば、その所得は「給与所得」となり、雇用関係がなければ「一時所得」となります。給与所得と一時所得では、所得金額の計算方法が異なるので、この2つの違いはしっかりと認識をしておきましょう。
20万円超の一時所得は確定申告が必要!
個人が収入を得た場合は確定申告を行い、所得金額や納税金額の計算を行う必要があります。ただし、会社員の場合は、勤務先が年末調整を行い、1年間の税金の精算を行うため、確定申告は不要です。
では、会社員で臨時収入があった場合、確定申告はどうなるのでしょうか。会社員で臨時収入があった場合は、一時所得の所得金額によって、確定申告が必要かどうか異なります。原則、会社員は以下の場合、副収入があっても確定申告は不要です。
給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が、20万円以下の場合は、確定申告不要
2.給与を2カ所以上から受けている場合(給与の全部が源泉徴収の対象となる場合)
年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円以下の場合は、確定申告不要
最も多いケースが「給与を1カ所から受けている場合」です。ここで注意したいのが、確定申告不要の基準である20万円以下が収入金額ではなく、「所得金額」であるということです。
しかも、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算します。50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額が20万円を超える場合のみ、確定申告が必要です。つまり、一時所得の収入金額が90万円を超えると確定申告が必要となります。
課税される一時所得金額=一時所得金額40万円×1/2=20万円
総収入金額90万円以下だと、課税される一時所得金額が20万円以下となるため、確定申告は不要。
一時所得の確定申告をしないとどうなる?
20万円基準を超えているなど、一時所得の金額が一定金額を超えれば、確定申告は必要です。では、確定申告が必要な場合で、確定申告をしなければどうなるのでしょうか。
確定申告が必要な場合で、確定申告をしなかったことがわかれば、延滞税や無申告加算税などのペナルティがあります。延滞税とは、納期限より後に税金を納めることへのペナルティです。
延滞税の金額は、延滞税特例基準割合や納税までの期間などを基に計算されますが、理論上、最大で年14.6%になることがあります。
また、無申告加算税とは、無申告の場合に、通常の税金に加算されるペナルティのことです。原則として、50万円までの部分は15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントのペナルティとなります。
このほか、悪質の場合は、脱税とみなされ刑事罰に発展する可能性もあります。確定申告が必要な場合は、忘れずに、確定申告しましょう。
まとめ
一時所得とは、簡単にいうと、一時的・臨時的に得た収入(所得)のことです。事業を行うなど、利益獲得のための行為を行わずに得られた臨時的・偶発的な所得を指します。代表的なものとして、懸賞や福引、競馬の払戻金などがあります。
個人が収入を得た場合は、確定申告を行い、所得金額や納税金額の計算を行う必要があります。これは一時所得でも同じです。ただし、一時所得の金額の計算は、他の所得金額の計算方法とは異なるので、注意が必要です。
なお、一時所得がある場合でも、確定申告が不要なこともあります。例えば、給与を1カ所から受けている会社員の場合、一時所得の収入金額が90万円以下であれば確定申告は不要です。
確定申告が必要な場合で、確定申告をしなければ、延滞税や無申告加算税などのペナルティがあります。確定申告が必要な場合は、忘れずに確定申告しましょう。
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
米国向け輸出入企業必見!トランプ関税が導入されたら?国別影響と対応策を仮想シナリオで徹底解説
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ
-
裏金問題とは?政治資金の透明化と不正の実態を解説
-
5月末が申告期限!3月決算企業の法人税務申告ガイド
-
オフィスの観葉植物は経費計上できる?正しい仕訳方法と注意点を解説