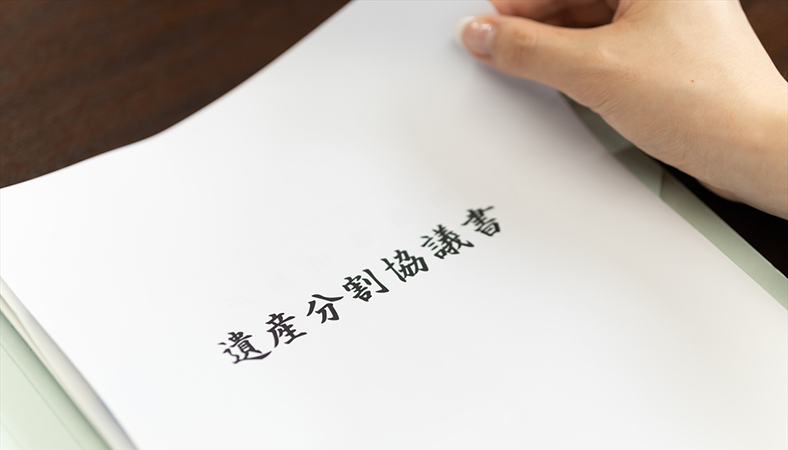消費税がかからないって本当?「非課税取引」について
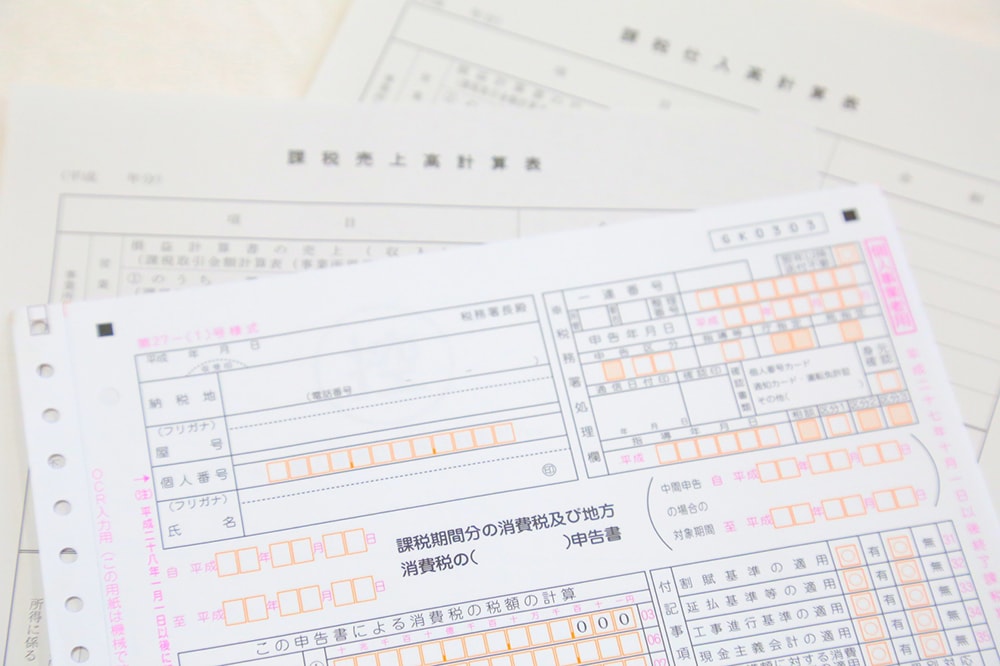
数ある税金の種類の中でも一番身近な消費税ですが、消費税の仕組みはとても複雑です。日頃生活をしている中で払うお金にも、消費税が含まれているもの、含まれていないものがあります。消費税の仕組みとはいったいどのようなものなのでしょうか?
消費税のかかる条件についておさらい
消費税はその名の通り、消費を対象として課税される間接税の一種です。間接税とは税金を負担する人と納める人が異なる税金のことですが、分かりやすく例を挙げてみましょう。
まず、問屋がメーカーから消費可能な商品Aを300円で購入します。このとき、消費税率は8%なので問屋はメーカーに324円を支払います。次に小売店がAを問屋から500円で仕入れます。すると小売店は消費税と合わせて540円を問屋に支払います。最後に消費者が小売店からAを1000円で購入します。消費者は当然、消費税80円を含めた1080円を支払います。
以上のような状況下では、消費税を最終的に負担するのは、実際にAを消費した消費者のみで、消費者が支払った消費税額80円のうち小売店が80-40=40円 問屋が40-24=16円 メーカーが24円を税務署へと、消費者の代わりに税務署に納税します。このように、消費税に関しては税金を負担する人と納税する人が異なるという仕組みになっています。
では、実際どのような商品やサービスに対して、消費税が課されるのでしょうか。国税庁によると、課税となる対象は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」とされており、商品のみではなくサービスも課税の対象となっていることが分かります。
非課税、不課税、免税の意味の違いとは?
消費税がかからない非課税、不課税、免税の三つの対象を把握していれば、消費税の支払いが必要か否かを判断することは可能です。以下ではこれら三つの違いを解説していきます。
非課税
消費税を課される対象にある商品やサービスの取引のうち、消費者に負担を求める税の性格から課税対象としてなじまないことや社会政策的配慮を理由として、国が特別に消費税を課税しないと認めた取引を非課税取引といいます。例えば、土地の譲渡や貸付け、有価証券の譲渡、介護保険サービスの提供などが該当します。
不課税
一般的に、消費税を課される対象としての条件を満たさない取引のことを不課税取引と呼びます。非課税取引との相違点は、課税対象であるかないかというところになります。例えば、国外取引、寄付や贈与などが該当します。
免税
輸出やそれに似た取引について一定の要件が満たされている場合、消費税が免除されることがあり、そうした取引のことを免税取引といいます。
非課税取引との相違点は、「仕入税額控除」を行えるか否か、という点です。仕入税額控除とは、先程例示したように、業者が消費税を納付する際に仕入の時点で既に払った消費税を差し引いて納める、というものです。
非課税取引では、そもそも消費税が課税されていないため、製造時に課税仕入が行われていたとしても控除することができません。それに対し免税取引では、外国で消費されるものには消費税を課税しないという考えに基づくもので、課税対象とならないのは輸出に関わる売上のみです。そのため、その製造時に行われた課税仕入については、原則として控除が可能になります。
非課税取引の対象とは?
国が定めるところの非課税取引の対象は以下に列挙する17の項目によって分類されています。
(1) 土地の譲渡および貸付
(2) 有価証券等の譲渡
(3) 支払い手段の譲渡
(4) 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等
(5) 郵便切手類の譲渡、証紙の譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
(8) 外国為替業務に係る役務の提供
(9) 社会保険医療の給付等
(10) 介護保険サービスの提供
(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供
(12) 助産
(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14) 一定の身体障碍者用物品の譲渡や貸付
(15) 学校教育
(16) 教科用図書の譲渡
(17) 住宅の貸付
(1)から(8)に関しては、消費税の課税対象である「消費」という概念にそぐわないものと考えられます。さらに(9)から(17)については、全て社会福祉や社会保障に関わる取引であり、憲法25条に記されている社会福祉や社会保険の増進のために、国が非課税取引の対象と決めた取引であると考えられます。
課税される場合もある?
上に記した17の非課税取引の分類のいずれかに当てはまっていたとしても、非課税取引の対象外とみなされてしまう、紛らわしい取引も存在します。そうした例を3つ紹介します。
土地に関する紛らわしい取引
土地の譲渡と貸付は非課税取引の対象に含まれますが、その土地の上に建てる建築物は非課税の対象には含まれません。また、土地の貸付が一か月未満である場合や、駐車場などの施設に土地が利用される場合は、課税対象とみなされてしまいます。
記念硬貨に関する紛らわしい取引
硬貨の取引は国の定める条件に則ると、非課税取引の対象とされています。これは、硬貨と現金との取引が両替と等しい行為であり、両替に消費税を課するのにそぐわないと判断されるからだと考えられます。しかし、記念硬貨などの収集品については、元々の硬貨よりも大きな価値を持つため、記念硬貨の取引は課税対象の取引になります。
医療に関する紛らわしい取引
社会保険医療に関する取引については、消費税の課税対象としてしまうと低所得者がサービスを受けることが困難になってしまうため、非課税取引の対象に含まれます。しかし、医療の中でも美容整形の費用や市販の医薬品の購入などについては課税の対象となってしまいます。
正しく消費税の課税範囲を理解するためには、税制に詳しい税理士にアドバイスをもらい、クリアな会計を目指しましょう。
まとめ
税金の中でも一番身近な消費税ですが、消費税のシステムや課税対象はとても複雑で正確に把握することは困難です。しかし一番身近だからこそ、正確な把握をしていないと、未納や滞納といった問題を起こしてしまう危険性があるので注意しましょう。
東京大学卒。現、同大学院所属。
ベンチャー企業の経営やビジネスを学んでおり、経営に役立つ様々な知識やノウハウを習得中。
新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
米国向け輸出入企業必見!トランプ関税が導入されたら?国別影響と対応策を仮想シナリオで徹底解説
-
裏金問題とは?政治資金の透明化と不正の実態を解説
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ
-
5月末が申告期限!3月決算企業の法人税務申告ガイド
-
オフィスの観葉植物は経費計上できる?正しい仕訳方法と注意点を解説