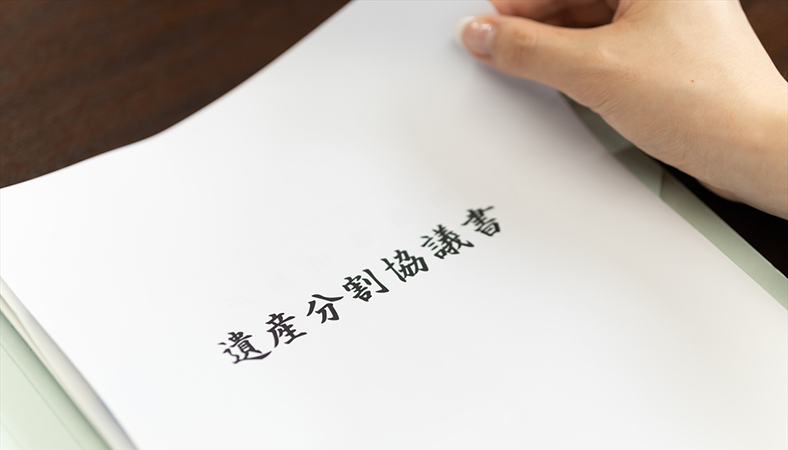起業したいと思ったらまずやらなければならない4つのこと

起業して人に雇われない仕事がしたいと考える人は少なくないでしょう。ただし「成功させる」という覚悟だけでは、事業を軌道に乗せるのは難しいと考えてください。独立して稼ぐには、しっかりしたプランや資金などの裏づけが必要になるのです。夢をかなえるために起業の前に考えるべきこと、やるべきことをまとめました。
【やるべきこと1】「なぜ起業するのか」を明確にする
「起業」には2つの方法がある
起業とは、独立して事業を起こすことです。それには、「会社を設立して経営者になる(法人)」「個人事業主(自営業)になる(個人事業者)」という2種類があります。会社になれば、社会的信用が高まり、仕事をもらったり融資を受けたりする際にも、有利になるでしょう。所得が一定水準を超えている場合には、税率面で節税効果もあります。ただし、会社の設立には、後で説明するような多くの手続きが必要で、「明日からスタート」というわけにはいきません。一方、個人事業主は、基本的に届けを出すだけでOKで、やろうと思えば、すぐにでも始められます。とりあえず個人でスタートし、事業がある程度大きくなった時点で「法人成り」(個人事業から法人になること)というのは、よくあるパターンです。
副業ではダメなのか?
ところで、そもそもあなたはなぜ起業を考えるのでしょうか?
- ①やりたいことがあるから
- ②得意なことがあるから
- ③今の収入に不満がある=とにかく儲けたいから
多くの場合、理由はこれらのどれか、あるいは複数、ということになると思います。
③の場合は、例えばサラリーマンなど今の仕事を続けながら、アルバイトなどの副業で収入を得るという道もあります。また、②を生かして「週末起業」のようなやり方で“二足の草鞋”を履くケースも、増えています。
そうではなくて、わざわざ独立起業しようという場合には、①が大事になります。事業を立ち上げた以上、継続させていかなくてはなりません。苦しいときにも踏ん張れるのは、会社でいう企業理念のようなものがあればこそなのです。
もちろん、②も重要です。逆に言うと、自分のスキルや経験とまったく無関係のフィールドで勝負しようというのは、無謀です。税理士の先生からよく聞く失敗例が、脱サラして飲食店を開いたけれど……というケース。
今の話にもつながりますが、起業には、これらに加え
④その仕事にニーズがあるから
という視点が必要です。どんなに①と②が合致していても、モノやサービスを買ってもらえなかったら、事業としては成り立ちません。
【やるべきこと2】事業計画書を作成する
「何をやるのか」を整理する
次のステップとして、説明したような概念的なビジョンを、具体的な「事業コンセプト」に落とし込み、資金計画などを含めた「事業計画書」にする必要があります。事業コンセプトとは、簡単に言えば、「何をやるのか」という事業の中身です。例えば、同じ飲食店でも、ラーメン屋なのかカレー屋なのか和風居酒屋なのか? 出店するのは、駅近か住宅街か? といったことを、自らのスキルや市場のニーズを検討しながら、明確化するわけです。
事業計画書が必要なワケ
事業計画書自体に、決まった書式などはありません。しかし、作るからには、自己満足のレベルでは意味がないでしょう。
計画書を作る理由の1つは、他ならぬ自分自身が「何をやるのか」を理解するためです。夢の実現に夢中になっていると、ついつい脇が甘くなって、「いいこと」しか目に入らなくなったりもします。事業を冷静に分析して、計画を練っていく中で、弱点や改善点が見えてくるかもしれません。
加えて、金融機関などから融資を受ける際には、「客観的でわかりやすい」事業計画書が不可欠になります。そういう予定がある場合には、必要に応じて税理士など専門家の力も借りて、説得力のあるものを作成すべきでしょう。
【やるべきこと3】起業の資金を集める
起業に必要な資金とは?
当然のことながら、起業のためにはお金が必要になります。すぐに利益が上がるとは限りませんから、ある程度それを見越した資金も用意しておかなくてはなりません。業種などにもよりますが、例えば次のようなコストが発生します。
〈初期費用(イニシャルコスト)〉
- 事務所の敷金・礼金
- 机・椅子
- 事務機器(パソコンなど)
- 内装費・外装費
〈運転資金(ランニングコスト)〉
- 仕入
- 外注費
- 事務所の家賃
- 光熱費
- 交際費
- 社会保険料(法人及び常時5名以上を雇用する個人事業)
すべてを自己資金でまかなえれば問題ないのですが、そうでなければ、以下のような方法で調達することになります。
金融機関から融資を受ける
すぐに思いつくのが、銀行からお金を借りるということでしょう。ただし、これから起業するという場合には、実績や信頼がないため、民間の銀行や信用金庫などからの融資は、ハードルが高いのが現実です。
そこで頼りになるのが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」です。無担保・無保証人で融資を受けることができ、限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)となっています。ただし、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」が要件となっており、公庫のフォーマットに沿った「創業計画書」を提出しなくてはなりません。
この融資を予定する場合は、さきほどの事業計画書を、初めからこれに合わせて作成するのがいいでしょう。また、融資を受けない場合にも、事業計画書のひな型として活用できると思います。
投資家からの出資を受ける
高い成長が期待されるベンチャーなどの場合には、ベンチャーキャピタルや個人投資家からの出資を受ける、といったことも選択肢になるでしょう。しかし、彼らの評価に値する技術やビジネスモデルを持っていることが前提になるため、かなりの狭き門と言わざるをえません。
補助金・助成金を利用する
国や地方自治体などの補助金や助成金には、融資と違って返済の必要がないという大きな魅力があります。ただ、基本的にすでに支払ったものに対する「援助」(すなわち後払い)で、起業に当たってすぐに調達できるという性格のものではありません。受付は年度初めに行われることが多いので、利用しようと考えるときには、期間を逃さないよう注意する必要があるでしょう。
受付は年度初めに行われることが多いので、利用しようと考えるときには、期間を逃さないよう注意する必要があるでしょう。
【やるべきこと4】起業してから必要になる知識を予習する
税金の知識
法人にしろ、個人事業にしろ、利益が出たら納税しなくてはなりません。全部会社がやってくれるサラリーマンとは違い、自らが責任を持って申告を行う必要があるのです。
しかし、同じ利益を上げていても、申告の仕方によって、支払う税金の額に大きな差が生まれることは珍しくありません。申告期限を過ぎたり、所得を実際より少なく申告してしまうと、ペナルティとして、さらに出費を迫られることになるでしょう。所得税や消費税、法人の場合は法人税なども含めて、基本的な税の知識は身につけておきましょう。
会計の知識
会計知識も、必須のものと言っていいでしょう。「数字は苦手」と税理士や担当者任せにするのは、考えものです。とはいえ、本格的に簿記を勉強したりする必要はありません。わかりやすい解説書などを1冊読んで、「決算書が正確に読める」程度の知識をつけておけば、十分でしょう。
決算書は、どれだけ売上があって、経費はどのくらい使って、残ったもうけはこれだけ。資産や、債権・債務はこうなっている――といったことがわかる、事業の通信簿のようなものです。それを活用して、常に事業の置かれた状況を把握し、将来に向けた手を打っていく姿勢が、起業家には求められるのです。
法律の知識
いざ起業というと、法律も気になるところ。「民法」、「税法」、会社にする場合には「会社法」などが関連してきます。これらについても、決して「恐れる」必要はありませんが、適切な事業の遂行やトラブル回避のために、やはり最低限の知識は持っておきたいところです。
他方、許認可事業などに携わるときには、関連する法規は熟知しておく必要があります。人を雇う場合の「労働法」や、よく問題になる「個人情報保護法」にも気を付けるべきでしょう。
マーケティングの知識
さきほども触れたように、どんなにいいものをつくっても、売れなければ事業の継続は難しくなります。常に、「誰をターゲットに」「何を」「どのような形で」提供するのかを考えなくてはなりません。その仕組みづくりが「マーケティング」です。
このマーケティングにはさまざまな手法があり、時代によってトレンドが変わったりもします。重要なのは、自分の事業内容や規模などに見合ったやり方を選ぶこと。実戦でそれができるように、基礎知識を備えておきましょう。関連する本を読んだり、興味のあるセミナーを受講したりするのもいいと思います。
起業したいがアイディアがない場合はどうする
起業したいと思ったら「なぜ起業するのか」を明確にしたり、起業してから必要になる知識を予習したりする必要があります。
しかし、そのほかにも大事なことがあります。それが、起業するためのアイディアです。どんな分野で起業するのか、どのような仕事をするのかのアイディアを考えます。
では、起業したいが、まだアイディアがない場合はどうすればよいのでしょうか。ここでは、起業のためのアイディアを出す方法を見ていきましょう。
自分の好きなことを挙げてみる
起業のためのアイディアを出す方法として、まず挙げられるのが、自分の好きなことが何かを考えることです。
起業を考える背景には「収入を増やしたい」「仕事環境を変えたい」など、様々な原因があります。しかし、よくあるのが、起業するのがゴールになってしまうことです。
起業は、あくまでスタートであり、起業後もずっと高いモチベーションを持って仕事を続ける必要があります。そのため、一番良いのが、できるだけ好きなことを中心に起業のアイディアを考えることです。
例えば、音楽が好きならば音楽家になる、楽器店を経営する、音楽を紹介するライターになるなど、好きなことから起業のアイディアが浮かんできます。
また、好きなことであれば、SNSなどで常に情報収集をし、流行や消費者のニーズを敏感にとらえることができるといったメリットもあります。
自分の得意なことを挙げてみる
自分の得意なことを挙げてみることも、起業のためのアイディアを出す方法のひとつです。自分が得意なこととは、例えば、文章を書くのが得意といった、スキル的なものがあります。
しかし、それだけではなく「人脈を作るのが得意」「得意な分野の資格を持っている」など、これまでの仕事や生活の中で身につけた得意なものも挙げるようにしましょう。自分の経験に結び付くアイディアで起業することで、より成功しやすくなります。
アイディアは質よりも量にこだわる
上記2つを挙げてみて、複数が重なる部分がないかを考察しましょう。アイディアは質よりも量にこだわって出すことが重要です。
アイディアの質を考えてしまうと、なかなかアイディアが浮かんできません。まずは、些細なことでもよいので、紙に多くの量のアイディアを書き出して、考えを深めていきます。
量にこだわってアイディアを作ることを心がければ、自分なりにアイディアを出すコツをつかむことができます。コツをつかむことで、起業後も多くのアイディアが出やすい体質になります。
フランチャイズで起業する
起業のアイディアが出ない場合は、フランチャイズで起業するのもひとつの方法です。
コンビニエンスストア経営や飲食店、掃除屋など、様々な分野でフランチャイズ制度が採用されています。その中で自分が得意とする分野、やってみたい分野のものを選びます。
フランチャイズ制は経営手法やスキルなどを学べたり、最初から知名度のある看板で仕事ができたりするメリットがあり、起業後すぐに仕事がスムーズに進みます。
一方、初期費用が必要である、起業後も一定割合のロイヤリティの支払いが発生するなどのデメリットもあるので、注意が必要です。
外部からのインプット・外的要因から起業アイディアを考える
起業するためのアイディアを出すためには、自分の好きなことや得意なことを挙げていくことが重要です。しかし、自分の過去の経験では、どうしても起業アイディアが浮かばなかったり、深堀りできなかったりする場合もあるでしょう。
そんな場合は、外部の力を利用することも必要です。外部からのインプット・外的要因から起業アイディアを考えることで、より具体的なアイディアを挙げることができるようになります。
起業アイディアを出すために利用できる外部からのインプット・外的要因として、次のようなものがあります。
出てきたアイディアを元にSWOT分析を行ってみる
SWOT分析とは、アイディアなどの状況を把握するための方法のひとつです。出てきたアイディアを強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)の4つのテーマに分類して考察します。強みと弱みは内部要因、機会と脅威は外部要因です。
| プラス要因 | マイナス要因 | |
|---|---|---|
| 内部環境 | 強み(Strengths) | 弱み(Weaknesses) |
| 外部環境 | 機会(Opportunities) | 脅威(Threats) |
例えば、飲食店のアイディアであれば、次のようなSWOT分析ができます。
強み:家庭料理が得意、安い値段で提供できる
弱み:知名度が低い、店舗が狭くなりそう
機会:お年寄りや家族のニーズが高い、健康志向な人の需要の増加
脅威:有名店との競争、感染症などによる客の減少
出てきたアイディアを元にSWOT分析を行い、さらに良いアイディアへとブラッシュアップしていくことが重要です。
先輩起業家からアドバイスを受けてみる
起業アイディアを出すために有効な方法のひとつが、先輩起業家からアドバイスを受けることです。実際に起業した先輩に、アイディア出しや起業について疑問に思うことなどをぶつけることで、経験に即した具体的な意見をもらえます。
また、自分に欠けている部分なども把握することができたり、話しているうちに出てきたアイディアがより具体的になったりするメリットもあります。
知り合いに起業家がいたり、起業セミナーなどがあったりすれば、ぜひ話を聞いてみましょう。
世界を旅行してみる
今までとまったく違った世界に身を置き、刺激を受けることも重要です。例えば、世界旅行をしてみるのもよいでしょう。
世界を旅行することで、世界に共通した社会的なニーズを見つけられたり、違った考え方や文化、生活環境を経験して、自分を見つめ直す機会を作れたりします。意外なところに、起業アイディアのヒントが隠れている場合も多いです。
世界旅行とまでいかなくても、起業アイディアを見つけるために、日本の中を旅してみるのもよいでしょう。
起業に必要な手続きは?
個人事業主の起業手続きとは?
起業してから1カ月以内に、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を提出します。
法人の起業手続きとは?
法人(株式会社)を設立するためには、大きく言って次の4つのステップを踏む必要があります。
- (1)定款の作成
「定款」は、事業の目的、会社名などを記した基本文書です。 - (2)定款の認証
公証人に(1)を認証してもらいます。なお、合同会社、合名会社、合資会社を設立した場合、定款の認証は必要ありません。 - (3)資本金の払込
「資本金」は、設立時に用意している運転資金です。 - (4)設立登記の申請
会社の「登記」とは、取引上重要な事項を法務省の部局である法務局に登録し、一般に開示できるようにすることを言います。登記申請書のほか、定款、資本金の払込証明書などの書類が必要です。
こうした手続きには、通常2週間から1カ月程度かかると考えてください。
まとめ
起業しようと思ったら、これだけの準備が必要です。もちろん、自分で努力すべきことなのですが、思い違いで失敗することなどがないよう、起業に詳しい税理士などの専門家のサポートも考えてみてはいかがでしょうか。
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025参院選】選挙公報・政見放送の見方と政策比較のポイントを徹底解説
-
【2025参院選】参院選で私たちの生活はどう変わる?各政党の政策を徹底比較・完全解説
-
【2025参院選】立候補にかかる費用とは?選挙活動の実態と供託金・公費負担を解説
-
米国向け輸出入企業必見!トランプ関税が導入されたら?国別影響と対応策を仮想シナリオで徹底解説
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ