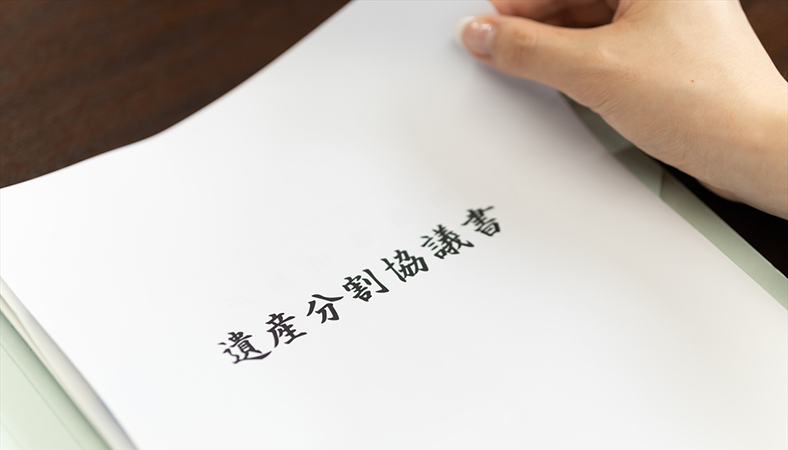ストックオプションとは?メリット・デメリットや注意点を解説

大企業だけでなく中小企業にも制度が定着しつつあるのが、ストックオプションです。ストックオプションは、経営者と従業員の両者にメリットがあるほか、税の優遇を受けられるケースもあります。ただし、デメリットもあります。
ここでは、従業員目線を中心に、ストックオプションのメリット・デメリットや注意点を解説します。
ストックオプションとは
はじめに、ストックオプションとはどのような制度なのか見ていきましょう。
ストックオプションとは、簡単にいうと、自社の株式を取締役や社員が購入できる制度のことです。この制度の良いところは、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で、自社株を購入できることです。
また、社員はストックオプションの制度をいつでも自由に利用できます(一般的には、権利行使期間が決まっています)。
例えば、権利行使価格を5万円で設定します。自社の株式の価値が10万円になった時にストックオプションの制度を利用すれば、5万円で10万円の株を購入することができます。購入してすぐに売却すれば、5万円の利益を得られます。もちろん、そのまま自社株を持ち続けて、さらなる価値の上昇を待つことができます。
このように、ストックオプションは、従業員にとって、とても魅力のある制度になっています。
ストックオプションのメリット・デメリット(従業員目線)
ストックオプションは、従業員にとって、とても魅力のある制度になっています。しかし、ストックオプションには、メリットだけでなくデメリットも存在します。
そこで、ここからは、従業員目線でストックオプションのメリット・デメリットを見ていきましょう。
ストックオプションのメリット(従業員目線)
従業員目線におけるストックオプションのメリットには、次のようなものがあります。
・会社に対する貢献が反映される
従業員にとって、自分の会社に対する貢献がどう評価されているのか、あるいは給料に反映されているのかといった点は常に気になるところです。正しく反映されていないと感じると、会社に対する不平や不満も増えてきます。
しかし、ストックオプションは基本、市場価格よりも低い価格で自社株を購入でき、基本的には従業員に有利なものとなっています。また、会社に対する貢献が株価として反映されるので、仕事に対するモチベーションもアップします。
・成果が正当に報酬につながる
従業員が成果を出すことは、会社の成長につながります。会社が成長すると、会社の株価の上昇につながります。
ストックオプションでは、従業員が自社株を購入することができるので、この制度を使って自社株を購入しておけば、会社の株価が上昇すればするほど、従業員一人ひとりの利益も増加します。つまり、成果が正当に報酬につながるといえます。
・リスクが少ない
従業員にとってリスクが少ないのも、ストックオプションのメリットのひとつです。
ストックオプションは、あくまで自社株を購入できる権利を得るものです。つまり、権利を行使しなくてもかまいません。自社株の株価が下落するまたは下落しそうな時は権利を行使せず、自社株の株価が上がる時に権利を行使すればよいので、従業員にとってリスクが少ないものとなっています。
ストックオプションのデメリット(従業員目線)
従業員目線におけるストックオプションのデメリットには、次のようなものがあります。
・自社の業績により、将来の報酬に影響を与える
ストックオプションのデメリットは、株価が下落することもあるという点です。自社の業績が悪ければ、株価も下落します。
ストックオプションによって購入した自社株を退職時に売却し、退職金代わりにする人も多いのですが、自社の業績によって株価が下落すると、将来の報酬額が減る可能性があるので注意が必要です。
・市場の変動など、自社の業績以外の要因でも将来の報酬に影響を与える
株価が下落すると、将来の報酬額が減ります。
実は、株価の下落は、自社の業績の悪化だけが原因で起こるわけではありません。例えば、海外での紛争や災害、投資家の思惑による市場の変動など、自社の業績以外の要因でも株価の下落は起こります。
いくら会社の業績が良くても、株価が思いのほか上がらなかったり、下落したりすることもあるので、こちらも注意が必要です。
税の優遇を受けられるかどうかに注意
ストックオプションには、税の優遇を受けられるものと税の優遇が受けられないものがあります。企業としては、従業員のためにも、税の優遇を受けられるストックオプションを導入したいところです。
ここでは、ストックオプションと税金について見ていきましょう。
税制適格ストックオプションとは
税制の優遇を受けられるストックオプションを「税制適格ストックオプション」といいます。ここでいう税の優遇とは、従業員にかかる所得税を指します。
原則、ストックオプションでは、株の取得時と株の売却時の二度、従業員に所得税が課されます。それぞれについて見ていきましょう。
・株の取得時
従業員は、第三者よりも優遇した価格で自社株を購入できるので、取得時の時価と実際の自社株の購入価格(権利行使価格)の差額分、得をしていることになります。この得した分を従業員の利益と考え、所得税が課されます。所得区分は給与所得(最大税率55%)です。
例えば、時価100万円の自社株を90万円で取得した場合の税金は、次のようになります。
(時価100万円-権利行使価格90万円)×所得税率(最大税率55%)
つまり、得した10万円に対して税金が課されます。
・株の売却時
株を売却して売却益が出たら、売却益に対して税金がかかります。所得区分は譲渡所得(税率20%)です。
例えば、上記の株を120万円で売却した場合の税金は、次のようになります。
(売却価格120万円-購入時の時価100万)×所得税率(税率20%)
総合すると、自社株の取得価格90万円と売却価格120万円の差額30万円に対し、株の取得時と売却時の2回に分けて異なる税率で所得税が課されます。
しかし、税制適格ストックオプションの要件を満たせば、株の取得時には税金が課されず、株の売却時のみ税金が課されます。また、税率も売却時の税率20%のみです。
上記の例の場合、株の売却時の税金は、次のようになります。
(売却価格120万円-権利行使価格90万円)×所得税率(税率20%)
給与所得の税率にもよりますが、一般的に税制適格ストックオプションを適用すれば、税金が発生するタイミングが減り、税率が低くなるメリットがあります。
税制適格ストックオプションの要件
次に、税制適格ストックオプションの要件について見ていきましょう。ストックオプションで税の優遇を受けるためには、次のようなさまざまな要件があります。それぞれを簡単に説明すると、次のようになります。
・発行価額
無償ストックオプションであること
・付与対象者
原則、その会社の役員や従業員であること
・権利行使期間
付与決定日から2~10年の間の8年間で権利行使すること
・権利行使価額
新株予約権の契約締結時の時価以上
・譲渡禁止規定
・権利行使限度額
年間の権利行使価額が合計1,200万円以下であること
・保管委託など
取得した株式は、証券会社などに保管委託されること
ストックオプション発行の流れ
ストックオプションの発行には、株主総会と取締役会の決議が必要です。ストックオプションの発行の流れは以下のようになります。
1.株主総会
株主総会では、総数や価格、行使期間など、ストックオプションの発行内容について決議します。
2.取締役会
取締役会では、対象者と割当数などストックオプションの詳細について決議します。
3.契約
株主総会と取締役会で決議された内容をもとに、契約を締結します。
ストックオプションの種類
ここまでは、一般的なストックオプションについて見てきましたが、ストックオプションにはさまざまな種類があります。
代表的なストックオプションを以下にまとめてみました。
・ストックオプション(通常型)
一般的なストックオプションです。権利行使価格はその時の株価よりも高く設定され、売却時に株価が高くなっていれば利益が出ます。
・株式報酬型ストックオプション(1円ストックオプション)
株式報酬型ストックオプションは、権利行使の価格を1円程度に低く設定したストックオプションのことです。1円に設定されることが多いので、1円ストックオプションともよばれます。権利行使の価格が低いため、権利行使時にその時の株価と同程度の利益が出ます。
株式報酬型ストックオプションは、退職金の代わりとして利用されることが多く、退職金として課税されます。
・有償ストックオプション
有償ストックオプションは、その名の通り、お金の支払いが生じるストックオプションのことです。付与時には、条件付きの発行価格(公正価格)を支払い、新株予約権を得ます。
お金の支払いが発生するため、受け手に資金が必要ですが、給与所得の課税はなく、譲渡所得のみ課税されるメリットもあります。
・信託型ストックオプション
信託型ストックオプションとは、ストックオプションを信託に預けて、満期まで保管するストックオプションです。信託で保管している間は従業員にポイントなどを付与し、満了時にポイントに応じて、ストックオプションが付与されます。ストックオプションを後から付与することができるため、優秀な人材を早期に確保したいスタートアップ企業などで、よく用いられています。
税金については、これまで権利行使時には課税がされず、売却時に譲渡所得として課税されると認識されてきました。しかし、2023年5月に国税庁と経済産業省が開催した信託型ストックオプションへの課税説明会で、国税庁が権利行使時に給与所得として課税される旨の見解を公表したため、混乱が生じています。また、すでに権利を行使している従業員については、過去にさかのぼって、源泉を徴収する必要があるともしています。
スタートアップ企業などからは反発も出ており、今後の動向を注視していく必要があります。
ストックオプションと従業員持株会・新株予約権との違い
ストックオプションと混同しやすいものとして、従業員持株会と新株予約権があります。ここでは、ストックオプションと従業員持株会・新株予約権との違いについて見ていきましょう。
ストックオプションと従業員持株会の違いは、実際に株式を保有するかどうかです。ストックオプションは株式を取得する権利が与えられますが、その時点では株式を取得していません。一方、従業員持株会は、給与から天引きされる資金などで、実際に株式を購入して保有します。
ストックオプションと新株予約権との違いは、対象者です。ストックオプションは会社の役員や従業員だけを対象としているのに対し、新株予約権は、社外の第三者も対象にできます。
大きな意味で、ストックオプションは新株予約権の一部ともいえます。
ストックオプション導入時の手続きと注意点
ストックオプションを導入する代表的な手順は、以下のようになります。
- 新株予約権の募集要件の決定
- 従業員・役員から申し込み
- 株主総会・取締役会の決議
- 契約
導入時は以下のような点に注意しましょう。
- 付与の条件を明確にして不満を出ないようにすること
- 上場時の審査や経営権のことも考えて、持分比率をどれだけにするのかをあらかじめ決めておくこと
- 導入に際してさまざまな法律・法令に従う必要があるため、税理士や弁護士などの専門家と相談しながら進めること
まとめ
ストックオプションとは、自社の株式を取締役や社員が購入できる制度のことです。あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で、自社株を購入できます。ストックオプションには、従業員にとって会社に対する貢献が反映されたり、成果が正当に報酬につながったりするなどのメリットがあります。
ただし、ストックオプションが税の優遇を受けられるかどうかで、税金のかかるタイミングや税率が異なるので、注意が必要です。税制適格ストックオプションの適用を受けるためには、多くの要件を満たす必要があります。ストックオプションの導入の際には、要件を満たすように注意しましょう。
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
米国向け輸出入企業必見!トランプ関税が導入されたら?国別影響と対応策を仮想シナリオで徹底解説
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ
-
裏金問題とは?政治資金の透明化と不正の実態を解説
-
5月末が申告期限!3月決算企業の法人税務申告ガイド
-
オフィスの観葉植物は経費計上できる?正しい仕訳方法と注意点を解説