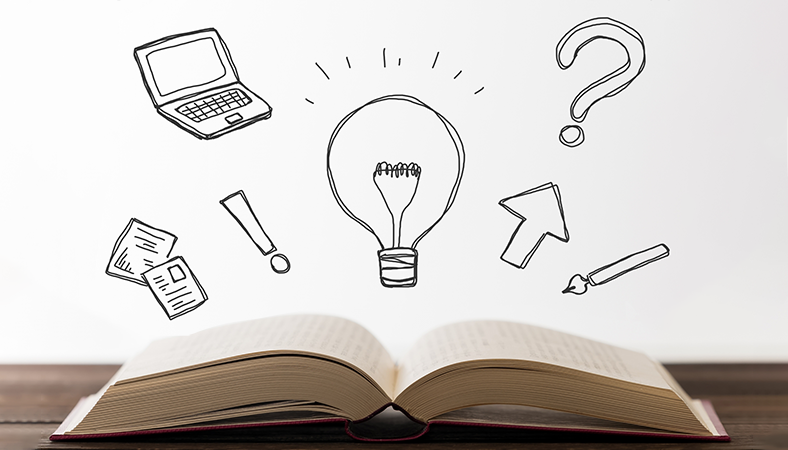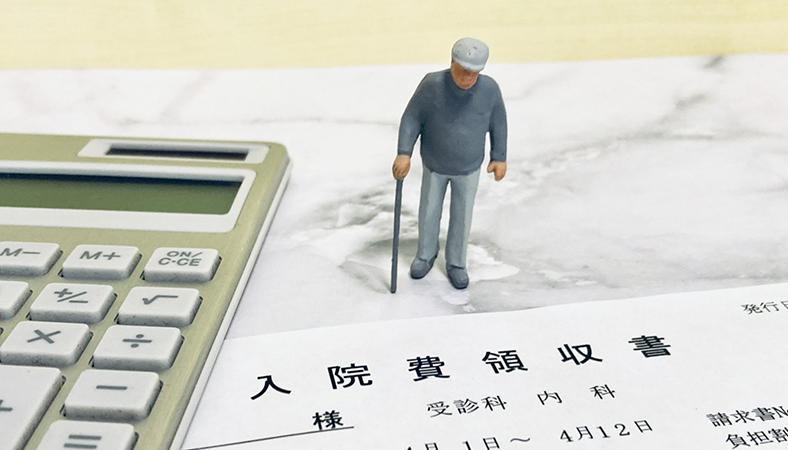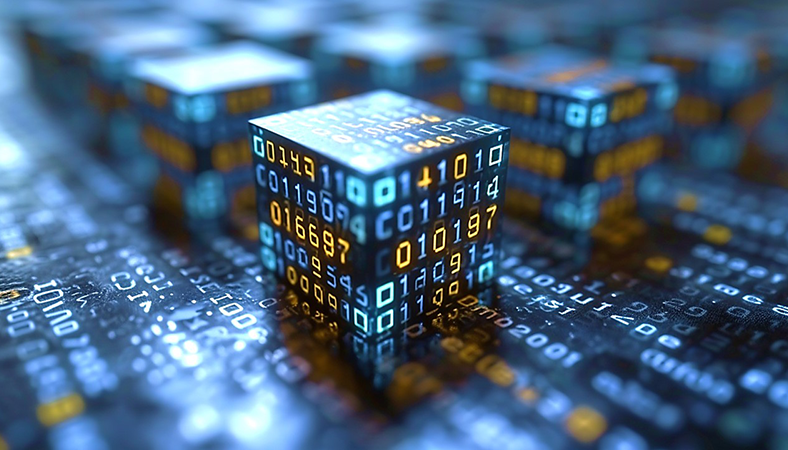携帯電話3大手、料金見直しで実質値上げ「官製値下げ」の流れに変化

日本の携帯電話業界において、大手通信会社であるソフトバンクが新しい料金プランを発表しました。これによって、データ通信量に対する料金単価が一部で上昇することとなります。
携帯料金プラン競争に転機か
同様の動きは、NTTドコモやKDDIなど他の通信大手でも確認されており、これにより従来の携帯電話料金の下落傾向が転換する可能性が高まっています。
ソフトバンクは、今年10月初旬から、自社の低価格ブランド「ワイモバイル」の料金プランを大幅に再編成する予定です。特に大容量プランにおいては、月間データ通信量を25ギガバイト(GB)から30GBに引き上げ、セット割引を適用しない場合の月額料金は4158円から5115円に上昇します。これによって、1GBあたりの料金は従来のプランよりも約3%程度高くなる見込みです。
同様に、小容量プランも見直され、月間データ通信量が3GBから4GBに増加します。セット割引を適用しない場合、月額料金は2178円から2365円に引き上げられる見込みです。通信利用が少ないユーザーにとっては、追加料金の負担が増加する可能性があります。
また、KDDIも2023年6月に自社の低価格ブランド「UQモバイル」において料金プランの見直しを行いました。セット割引を適用しない場合、一部のプランにおける1GBあたりの料金は約10%増加しました。
そして、NTTドコモも旧NTTレゾナントが提供していた低容量プランを廃止し、新たなプランを「irumo(イルモ)」を導入しました。光回線等とのバンドル割引を利用すると、月額料金は3GBプランで880円になりますが、この割引を適用しない場合は2167円となります。
これらの動きは、前首相の菅義偉氏によって進められた政府主導の「官製値下げ」政策によって、2021年以降、通信各社は新しい料金プランを導入した値下げ競争から一転、大きな転機となる出来事です。これまでの価格競争から、価格が一定以上に抑えられることで、通信各社が損失を被る懸念が浮上していたと考えられます。
総務省の調査によれば、NTTドコモの20GBプランの通信料金は官製値下げ前と比較して約60%減少しました。
従来、日本の携帯電話料金は他国と比べて高額であると指摘されており、東京では2019年時点で、各国のトップシェア企業が提供する同様の20GBデータプランは8175円となり、主要な6つの国際都市の中で最も高価でした。しかし、政府主導の価格引き下げ政策の影響で、2021年度時点での料金は2972円と大幅に低下し、これはロンドンやパリに次ぐ水準まで下がりました。
最近の動向からこの流れが変わりつつあることが示唆されており、今後の業界動向に注目です。
新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
ふるさと納税「ポイント還元」2025年9月30日で廃止へ!寄付者・自治体への影響と今後の活用法を解説
-
相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
-
防衛特別法人税とは?2026年4月から法人税に“1%の上乗せ”スタート
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
亡くなった人の口座は“凍結”される そのタイミングと解除する方法、注意点を解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
タクシーチケットの活用法とは?導入の流れや会計処理のポイント・注意点まで徹底解説!
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説