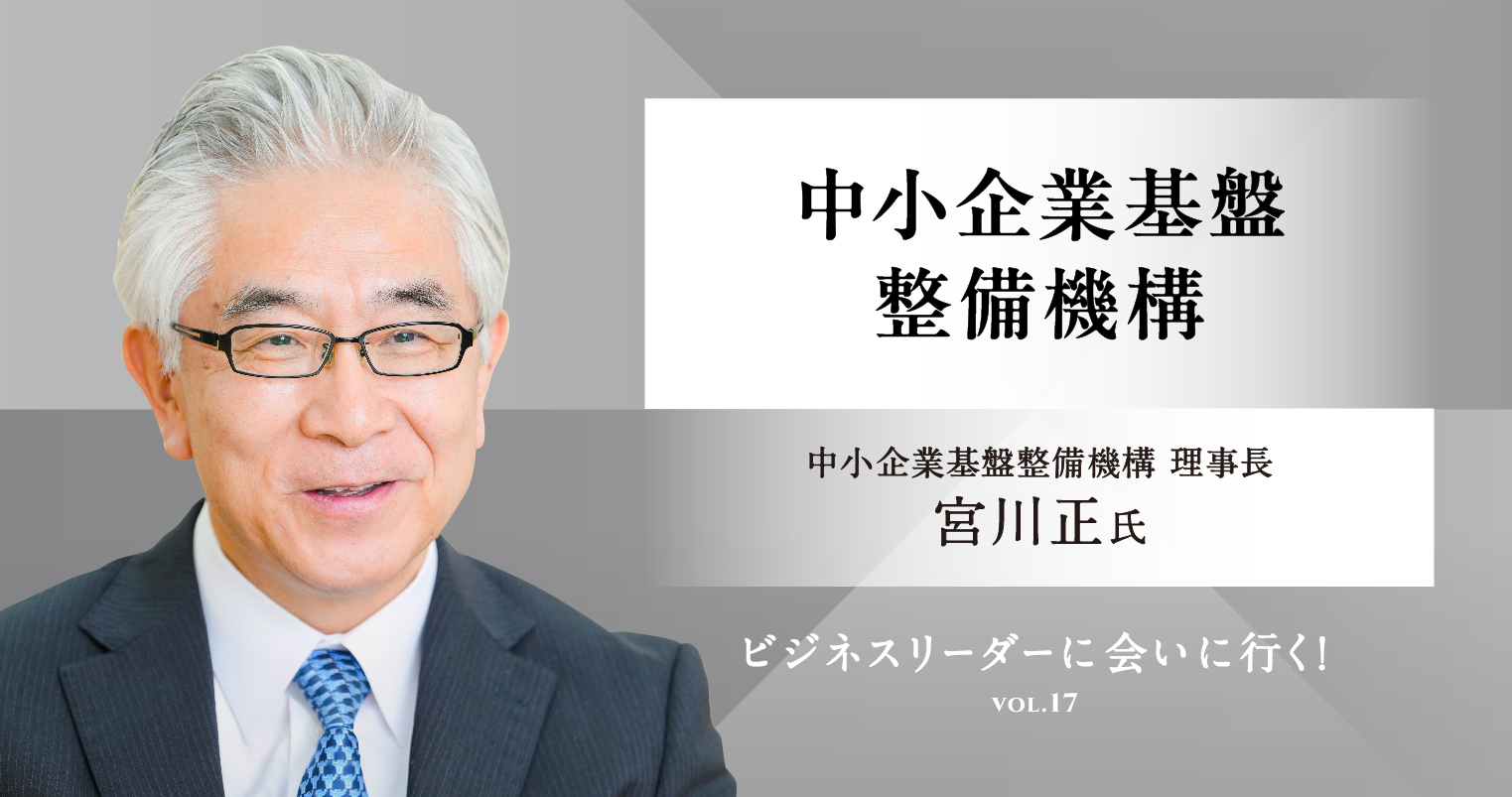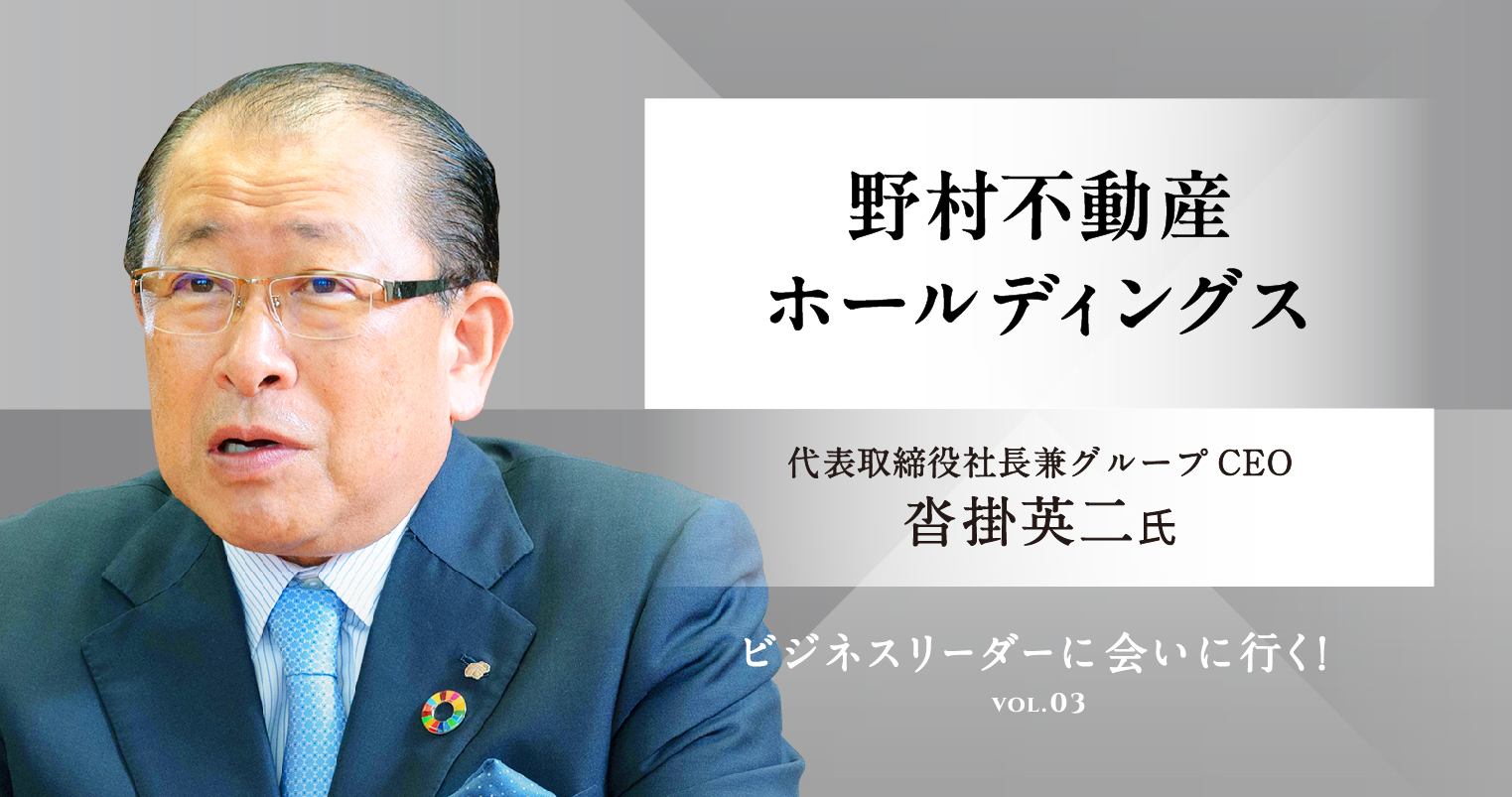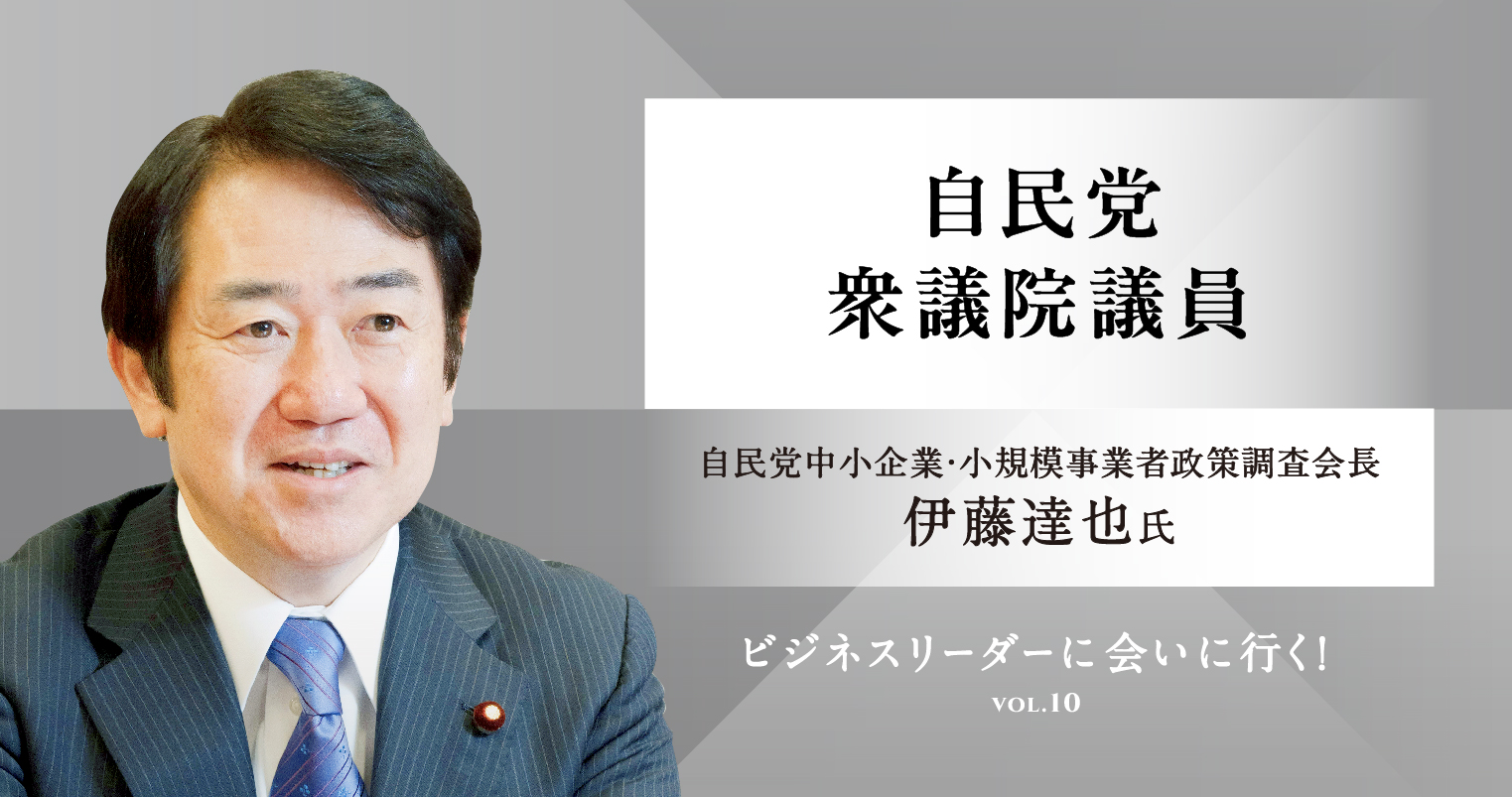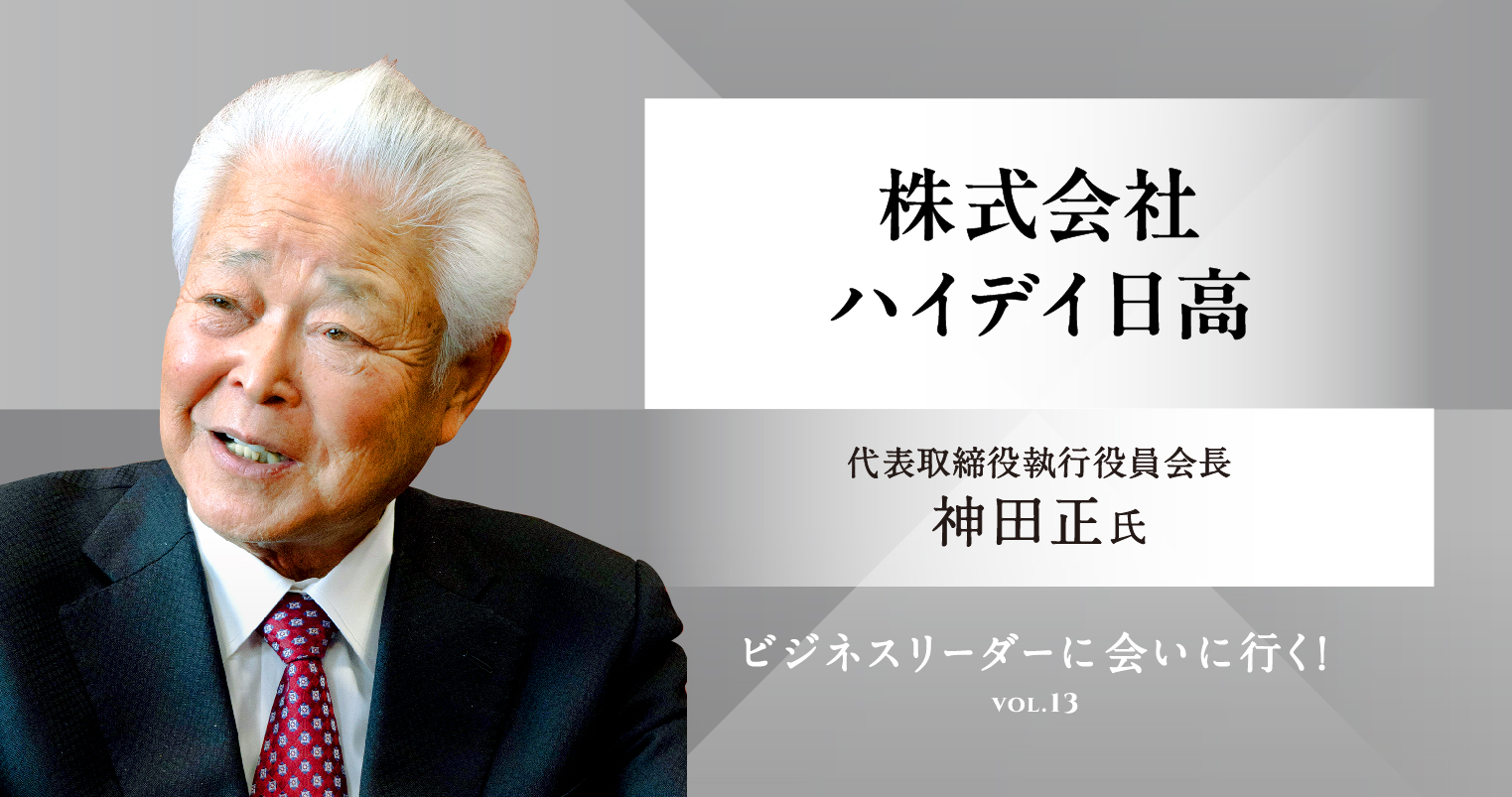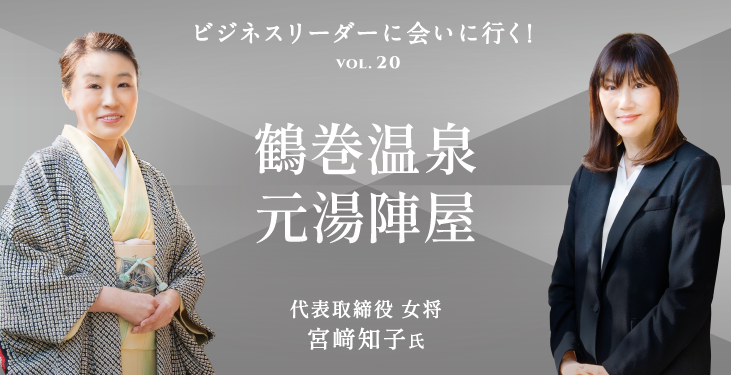
予約台帳など手書きの世界だった
老舗旅館をデジタル経営で再建
再建のため自前で作ったシステムを
全国600カ所の施設に導入
神奈川県秦野市の老舗旅館「鶴巻温泉 元湯陣屋」を廃業の危機から救ったのが、陣屋が実家の宮﨑富夫氏(現在、陣屋グループオーナー)と、妻で陣屋代表取締役 女将の宮﨑知子氏の夫婦だ。顧客台帳は手書きのアナログ経営、客獲得のための安売りの悪循環を断ち切った切り札は、自前で構築した宿泊管理システム「陣屋コネクト」。そのシステムは、自分たちの再建だけでなく、全国600施設に導入されるほどになった。地方創生担当大臣だった当時の石破茂現総理が訪れるなど、中堅・中小企業、地方創生の見本にもなっている。
八木美代子(以下、八木) 石破茂総理が地方創生担当大臣だったときにこちらの「鶴巻温泉 元湯陣屋」を訪問されていますね。今でも地方創生のモデルケースになっています。その後、石破総理は来られていますか。
宮﨑知子(以下、宮﨑)石破総理はいらしていませんが、石破総理に「見学に行ってきて」と言われて来られる政治家の方はいらっしゃいます。
八木 宮﨑知子さん(株式会社陣屋代表取締役 女将)がご主人の宮﨑富夫さんと実家に戻られて、旅館を引き継がれたときは赤字状態だったと思うのですが、数年で立て直された。どういう再建策が功を奏したのかを伺っていきますが、旅館を引き継がれた時の経緯から教えてください。
《鶴巻温泉 元湯陣屋》
元湯陣屋は、神奈川県秦野市にあり、創業100年を超える歴史を持つ老舗旅館。自然豊かな約1万坪の庭園や明治天皇ゆかりの貴賓室「松風」を備える純和風建築のたたずまいが魅力。将棋の藤井聡太七冠ら将棋・囲碁の名勝負が行われる舞台としても有名だ。


大きな借入金もあり、「旅館経営をやめてしまおうか」と話したことも
宮﨑 主人と実家に戻ってきたのが2009年秋です。 その前年に、オーナーである義父が急死しました。主人の母も体調を崩して入退院を繰り返していて、経営者が不在になっていました。運営できる人間がおりませんでしたので、長男である主人がホンダを辞めて実家に戻りました。
継いだのはいいけれど、後々わかったのが、大きな借入金があったことです。主人と「旅館経営をやめてしまおうか」みたいな話もしました。いろいろと話をして、「やってみよう」という話になりまして、再建に取り組みました。
八木 再建のスタートから大変でしたね。
宮﨑 私の体調がすぐれない時期でした。私たちには2歳の長男がおりまして、あと10日で第2子も産まれるというときでした。私は1人目も2人目も切迫早産でして、2人目の時に入院している期間が長かったので、体力的に起き上がれなかったです。それでも、出産して2ヵ月してから働き出しました。
経営の判断材料になるデータがほとんどなし、あるのは紙の決算書だけ
八木 旅館の立て直しはどこから手をつけたのですか。
宮﨑 1カ月経ってわかったのですが、どういう立て直しをすべきかの判断材料がありませんでした。あるのは決算書だけです。
日々の売り上げの推移がどうなっているかもわかりにくい。前年対比もわかりにくい。人件費比率がどうなっているのかのデータも、月が締まらないと計算できない。適正な人員配置だったのか、超過人員だったのかさえわからず、検証のしようがありませんでした。

手書き台帳だから、
コンピューターなら
1分でできることを、
手計算してました
八木 売り上げや経費などの細かいデータは経営の命です。お困りになったでしょう。
宮﨑 陣屋は1泊2食付きの宿泊だけではなく、食事を楽しんでいただく日帰りコースもやっていましたので、調理場の負荷が高かった。夕食と朝食に加えてランチも作るため、抱えているメニューが多かった。事業をスリム化したいのですが、原価率を出そうとしてもデータがないので計算できない、経営判断できないのです。
八木 もしかして、手作業で計算したのですか。
宮﨑 おっしゃる通りです。紙の会計簿を一つひとつ足す作業をしなければなりません。自宅に書類を持って帰って、夜中に計算したのですが、紙を見て計算するから時間がかかって、寝不足になってしまう。「コンピューターなら1分でできることを、なぜこんなに時間をかけなきゃいけないのよ」とイライラしてしまう。体にこたえました。
「予約管理システムを自分たちで作ろう」とエンジニア出身の夫が決断
八木 旅館を承継したときから、システム化しようとお考えだったのですか。
宮﨑 すべてが手書きで、仕事が煩雑になっていました。デジタル化しないと、ままならない状態でした。私たちが欲しいと思う条件に合うシステムを探したのですが、ありません。それで、主人が「自分たちでシステムを作ろう」と言い出しました。
主人は本田技術研究所で次世代燃料電池を開発するエンジニアでしたので、技術には明るい。それで、自分たちで作ろうという気になりました。
八木 ご自身でゼロから作るって大変でしたね。
宮﨑 必要だったのは予約管理システム、顧客管理システムです。システムを作るにしてもクラウド型のプラットフォームを使いたいと思っていました。自分たちでサーバーを持って、メンテナンスをやるのは小さな企業では無理です。
八木 宿泊業でIT化する際の大事なポイントは何ですか。

売り上げや経費などの
細かいデータは経営の命。
アナログでは経営できない
宮﨑 お客様の情報を扱うので、セキュリティーがしっかり担保されているのは大前提です。陣屋は、大きなホテルのような大規模経営ではありませんので、製品やサービスが安価であることも条件です。
八木 システムを構築する上で宿泊業特有の難しい点は何だったのですか。
宮﨑 ホテルの場合、夕食のレストランはホテルに入っているテナントさんが運営していることが多いです。その場合、ホテルは宿泊費だけを計上すればいいですよね。旅館の場合、1泊2食付きで販売することがほとんどです。その場合、室料の原価がいくら、夕食代、朝食代の原価がいくらと仕訳して計上しないと、正確な数字が取れません。一緒にしたらどんぶり経営になってしまいます。原価率をコントロールできるシステムを構築することが必須です。
八木 それでセールスフォース社のものを採用したのですね。
宮﨑 基本的なプラットフォームは、セールスフォース社のもので、宿泊業特有のところは自分たちで作っています。今は、アマゾンウェブサービス(AWS)も使えるようにして、ほかの宿泊業の方々が利用できる範囲を広げています。
八木 ビスカスも、税金や経営の悩みを解決するDX支援プラットフォーム「ビスカスpal」をローンチしています。構築するのに4年ぐらいかかり、同じような生みの苦しみがありました。
宮﨑 八木社長も同じような苦労されたのですね。
八木 ビスカスは営業会社ですので、クラウドやソフトウェアを導入するために大変苦労しました。エンジニアの人に「これはデフォルトです」と言われるのですが、その意味がわかりませんでした。「デフォルト、債務不履行のこと?」なんて頭が混乱していましたね。
宿泊施設の悩みは共通だから、陣屋コネクトを外販
八木 最初は「この人は何もわかっていないな」と思われながら、一つ一つやっていきました。でも、取り組んでよかったと思います。5年ぐらい経つと、苦労がとても勉強になっています。お客様のサービスのためにもなるし、従業員の仕事の効率化にも役に立つ。IT化はとても大事だと実感しました。当社のような営業会社でも独自のシステムは構築ができるという自信にもなりました。
陣屋コネクトを外販しようとしたのは、何かきっかけがありましたか。
宮﨑 ほかの旅館さんはどんなふうに経営しているのかを勉強したくて、いろいろな旅館さんのお話を伺う中で、根本的な問題がすごく似通っていると気づきました。陣屋コネクトの話題にもなり、「旅館がシステムを使うのですか。面白いことをやっているね」と興味を持っていただけたので、外販を始めました。
外販して自分たちに役立つ面もありました。陣屋コネクトを販売するためには、その旅館の課題に寄り添って、一緒に問題解決しなければなりません。こちらがシステムの提案をする代わりに、内情をいろいろ教えていただき、それが陣屋コネクトの改善にも役立ちました。
八木 旅館とは別の会社を立ち上げましたね。
宮﨑 旅館を経営しているのは「株式会社陣屋」ですが、宿泊業向けのDXソリューションの開発、販売をする会社として「株式会社陣屋コネクト」を立ち上げました。
夫がキャンピングカーで全国回り、600施設が陣屋コネクトを導入
八木 陣屋コネクトはどれぐらいの施設が利用していますか。
宮﨑 今、陣屋コネクトを利用いただいているのは600施設ぐらいです。旅館、ホテル、リゾート施設以外に介護施設でも利用いただいています。介護施設も、多くの利用者の人的管理が重要という点で宿泊施設と似たところがあるので、システムを改変して使っていただいています。
最初の100施設ぐらいまでは、主人が車好きなので、キャンピングカーで全国を回って売り込んでいました。

弊社も『ビスカスPal』の
構築に4年ぐらいかかり、
その時の苦労が
とても勉強になりました
八木 陣屋コネクトを他の施設に導入するときにはどんな苦労がありますか。
宮﨑 新しい仕組みを導入していただくと仕事のやり方を変えないといけない。どんなに優れた道具であっても、使っていただかないとスペック・性能を発揮することができません。従業員の皆さんのお気持ちを変えてもらい、使ってもらえるように新しい仕組みを浸透させるのが一番難しいことです。
加えて、システム導入は組織改革や人事制度の変更が伴います。会社の中の全部が連動してきますので、経営者だけではやり切れないところが多い。なので、私たちがコンサルティングに入り、支援させていただいています。
紙台帳はすべて取り上げ、鍵付きキャビネットにしまう
八木 元湯陣屋の場合、これまで手書きに慣れていた従業員の方々の抵抗はありませんでしたか。
宮﨑 抵抗する気持ちは大きかったとは思いますが、紙台帳はすべて取り上げました。これまでのお客様の情報は閲覧してもいいけれど、紙の台帳が手元にあったら、そこにメモを書きたくなりますよね。なので、鍵付きのキャビネットに紙台帳はしまって、鍵は私と主人が持っていて、夜は自宅に持ち帰りました。
調理場では、ホワイトボードにお客様のアレルギー情報や嫌いな食べ物などを書いて、対応していました。それだと、お客様が帰った後にホワイトボードを消します。そうなると、お客様の大事な情報が消えて、蓄積されません。
そこで、「ホワイトボードを使うのではなく、新しいシステムを使ってください」と調理場にお願いしたわけです。すると、調理場の職人さんからは「こんな小さい文字なんか読めるわけがない」と反発されました。
主人が「ホワイトボードと同じ大きさ、72インチのスクリーンを買いました。明後日には届きますから、必ず、それを見てください」とお願いしました(笑)。
八木 表立った反発はなかったのですか。
宮﨑 反発心はあったと思いますよ。だけど、デジタル化するしか生き残る道はなかったので、押し進めました。抵抗から学べることもありました。パソコンの画面の予約台帳を見て、紙に書き写す人がいるんですよ。「メモのほうが覚えられる」と言うわけです。「どうしてメモのほうがいいのですか」と聞くと、「メモだと順番にめくっていけるので、見やすい」との答えでした。なるほどと思って、パソコンのユーザーインターフェイス(UI)を一層見やすく変更しました。
高級旅館に戻すため、料理人が作りたい料理にブラッシュアップ
八木 ほかにどんな改革をしたのですか。
宮﨑 毎月、料理のメニューを変更するチャレンジをしました。日帰りのお客様は、料理を楽しみに来られる方が多いです。当時、単価を上げるのが課題でしたが、建物などのハードウェアに投資する余裕がありませんでした。料理なら、大きな投資をしなくても、工夫をして単価を上げることができるので、メニューをブラッシュアップしました。
調理部の担当の方に「原価はいくらかかっても構わないので、自分が作りたい料理を一度作ってみてください」と伝えたら、原価7万円の料理を作ってきました。「いくらで売るのだろうか」とビックリしましたが、料理人としては、理想的な料理を作ってみたかったのでしょうね。
それがきっかけで、一部は従来にない豪華な食材を使うけど、ほかは日常の季節の食材でもその料理人にしか出せない味で一品一品を作ってもらいました。
お料理がブラッシュアップされると、お客様が喜んでくださって、「来月も来るわ」とリピート率が高まりました。お客様が喜んでくださると、接客の担当もうれしいので、料理の説明に力が入りますし、調理場にも好評だってことが伝えられ、さらにやる気を出してもらいました。
お客様がリピーターとして来てくださる頻度が上がるにつれ、システム上で前回はどんなメニューをお出ししたかを確認するのが大事だと従業員も気づいて、なぜシステムを使うのかの意味を理解するようになりました。これこそ、私たちの成功体験になりました。
デジタル化でマルチタスクを採用し、従業員は120名から44名に
八木 従業員の数はどうなったのですか。
宮﨑 当時は120名でしたが、今44名です。急に減らしたのではなくて、8年ぐらいかけて人数を減らしました。一つの仕事だけをするシングルタスクからマルチタスクに切り替えた結果、人数が圧縮できました。
八木 客単価は変わりましたか。
宮﨑 2005年くらいまでは1泊2食付きを1万4000円くらいで販売していました。2009年当時はリーマン・ショックの直後で、安くしないとお客様が来てくれない状態でした。旅館の稼働を維持したいという焦りがありました。ついつい、直前割引のクーポンを発行して1泊2食付き9800円で販売してしまったほどです。とても忙しいのに、まったく儲からない悪いスパイラルに陥ってしまいました。
こんな売り方をしていたら、お客様を愚弄しているのではないかという気持ちもありました。この旅館を愛してくださるお客様には前もって予約してもらい、適正価格でお泊りいただいています。直前になったら空き部屋があるからと、価格を半分にしたら、先に予約いただいたお客様に失礼ですよね。
八木 富裕層の人たちに来てもらうために、ほかにどんな工夫をされたのですか。
宮﨑 一番大事なことは、お客様に対するサービスだと思っています。システム化でバックヤード業務を圧縮して捻出した時間を使って、毎週のようにサービス研修を実施しています。客室の改装工事も毎年少しずつ進め、その結果、1泊2食付きが9800円だった宿泊費を今は6万5000円まで上げることができました。
価格を上げたら常連のお客様が来られないかと言えば、そうではありません。来ていただいたお客様の4割がリピートしていただけるようになりました。リピート率の高さで、15年間の取り組みが少しずつ実っていると実感しているところです。
週40時間を4日でこなして、週休3日制を導入
八木 従業員の週休3日制を実現されました。
宮﨑 2014年から火曜日と水曜日を休館にする週休2日制をスタートさせました。やってみると、月曜日の宿泊も休館にしないと、火曜日チェックアウトのお客様のために出勤しなければならない従業員が出てしまいました。
そこで、2016年から月曜日の宿泊を止め、2018年から木曜日も基本的には休館にして週休3日制を導入しました。ただ、休館日を増やすと、事務作業が溜まってしまいます。事務作業に丸1日を費やさないといけないほどでした。
残業規制が厳しくなっていく中で、このままでは大変だというので、2020年に就業規則を改定して変形労働時間制に移行しました。週40時間を4日で消費するという働き方です。休憩をはさんで1日11時間労働に変えました。それでしたら、基本給を下げる必要もありません。その代わり、3日間は必ずお休みを取っていただいています。有給休暇を取得してもらえば、もっと休めます。
その結果、残業時間が激減したのはいいのですが、駆け出しの従業員、役付きでない従業員は給料の手取りが減ってしまう月が出てしまいました。そこで休みがしっかり取れる分、副業OKの制度にしました。

デジタル化のおかげで
「湯村温泉 緑屋」など
第2ブランドの旅館も
次々と開業
八木 新事業として緑屋ブランドの旅館を始められています。
宮﨑 陣屋グループのセカンドブランドとして2つの旅館を立ち上げました。一つは、2023年8月にオープンした長野県上田市の「別所温泉 緑屋」です。別所温泉にある老舗旅館が陣屋コネクトのユーザーで、お付き合いをさせていただいていました。経営者の方が高齢で後継がいらっしゃらない。そこで、陣屋グループで事業承継させていただきました。建物が老朽化していましたので、全面立て直しをしまして、リニューアルオープンしました。
もう一つは2023年3月にオープンした兵庫県・湯村温泉にある「湯村温泉 緑屋」です。いずれも、世界的な庭園デザイナーでいらっしゃる石原和幸さんにお願いして生まれた庭園がある旅館です。自分の旅館、システム会社、そして、第2ブランドと拡大していますが、これもシステム化のおかげです。

1977年東京生まれ。2000年昭和女子大学文学部を卒業後、東芝系リース会社に入社。結婚を機に退職し、2009年より夫・宮﨑富夫氏(陣屋グループオーナー)の実家である老舗旅館「鶴巻温泉 元湯陣屋」の女将に就任。2010年にはクラウド型旅館・ホテル管理システム「陣屋コネクト」を独自開発し、業績をV字回復させた。2017年に代表取締役 女将に就任。2児の母。
各業界のトップと対談を通して企業経営を強くし、時代を勝ち抜くヒントをお伝えする連載「ビジネスリーダーに会いに行く!」。第20回目は、「鶴巻温泉 元湯陣屋」の宮﨑知子・代表取締役 女将です。手書き、アナログだった旅館を、自分たちで作った宿泊管理システム「陣屋コネクト」を使って再建を果たしました。自前のシステムを構築したのは驚きですが、アナログな従業員が紙の台帳を使えないようにキャビネットに鍵をかけたり、悪戦苦闘ぶりを生々しくお話くださいました。デジタル経営、週休3日制、副業OKなど先進的な取り組みは学ぶところがたくさんあるインタビューでした。