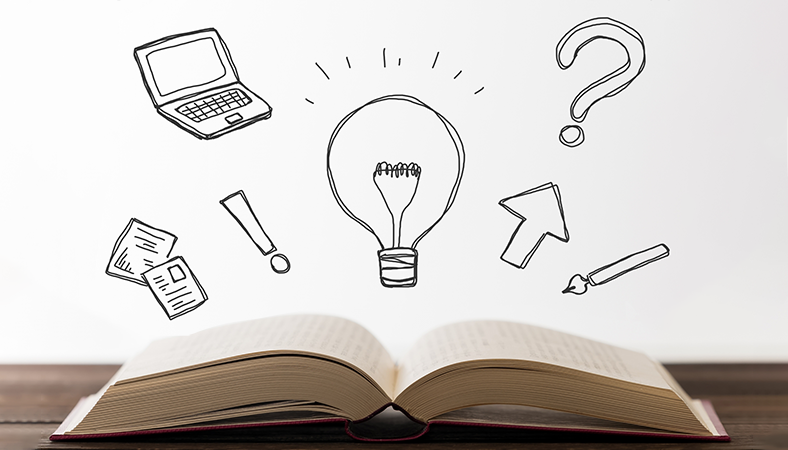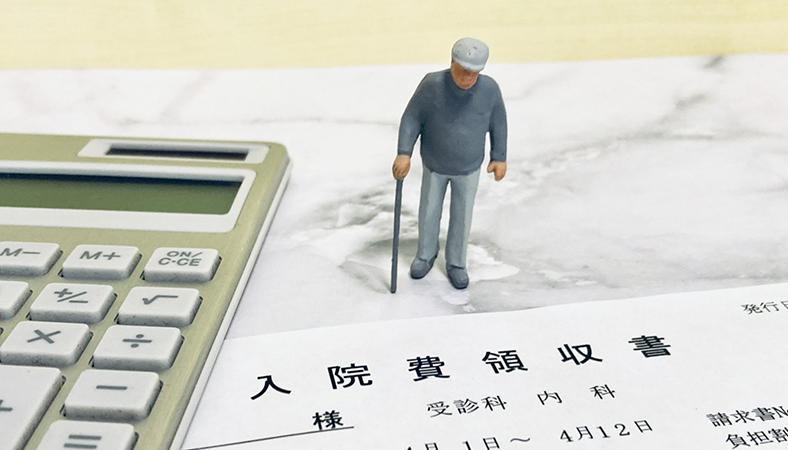2024年4月から義務化された不動産の「相続登記」とは 怠ると10万円以下の過料が課せられる可能性


2024年4月から、相続で不動産を取得した際の「相続登記」が義務化されているのをご存じでしょうか。いつまでにどんな手続きが必要なのか、しなかった場合にペナルティなどはあるのかを解説します。
そもそも相続登記とは
マイホームを購入する際には、法務局でその不動産の登記を行います。登記とは、土地、建物など不動産の所在地や種類、所有者などを登記簿に記載して、それが確かに所有者のものであることを公に示す行為をいいます。
親などが亡くなって相続になった際、被相続人(亡くなった人)の財産に自宅や賃貸アパートなどの不動産(土地、建物)が含まれていた場合、それを相続した人は、やはり登記(所有権の移転)を行わなくてはなりません。このように、相続に起因する登記を「相続登記」といいます。
全国で「所在不明土地」が大きな社会問題になっています。相続登記の義務化には、そうした状況にストップをかける、という目的があるのです。
相続登記義務化で何が変わる?
では、今回の相続登記の義務化で、それまでと何が変わったのでしょうか? ポイントを解説します。
相続登記が任意→義務に
法改正(民法等の一部を改正する法律の施行)により、2024年4月1日以降、それまでは任意だった相続登記が、文字通り法律上の義務とされました。
期限は「相続から3年」
説明したように、不動産登記には管轄の法務局での手続きが必要です。相続登記に関しては、その期限が「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」とされました。
例えば、2025年5月1日に不動産を相続したら、28年4月30日までに相続登記を行う必要があるということです。
しないでいるとペナルティの可能性
相続から3年を過ぎても、正当な理由なく登記を怠っていると、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。「過料」とは、国や地方公共団体が国民に課す金銭納付命令のことで、このペナルティも法改正で新設されました。
なお、「正当な理由」とは、次のようなケースをいいます。
- 数次相続(※)が発生して相続人が極めて多数に上るなど、必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する
- 遺言の有効性や遺産の範囲などが争われている
- 申請義務を負う相続人自身に重病などの事情がある
早期の遺産分割が難しい場合には「相続人申告登記」が可能
今述べた理由などにより3年以内の遺産分割が困難で、相続登記に支障をきたすような場合には、期限内に法改正で新設された「相続人申告登記」という簡便な手続きを行うことで、この義務を果たすこともできます。
相続人申告登記は、必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)などを添付して、自分が登記記録上の所有者の相続人であることなどを、不動産を管轄する法務局に申し出る、という制度です。申告を受けた法務局の登記官は、審査をした上で、申し出をした相続人の氏名・住所などを職権で登記に付記します。
手続きの基本的な流れは相続登記の申請と同様ですが、特定の相続人が単独で申し出ることができ、提出書類も少なくて済む、登録免許税がかからない、といった利点があります。
ただし、不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要があります。また、後日、遺産分割協議が成立し、不動産を相続する相続人が決まった際には、遺産分割の日から3年以内にその名義変更登記を行わなくてはなりません。
法務省:相続人申告登記について
2024年4月以前の相続にも適用される
注意しなくてはならないのは、この相続登記の義務化は、法改正以前の不動産相続にも適用される、ということです。こうしたケースには、法改正から3年間の猶予期間が設けられており、申請の期限は2027年3月31日となっています。
なお、法改正以前の相続だったものの、不動産を相続していたことを改正以降に知った場合には、その日から3年以内が、相続登記の期限になります。
相続の手続きは行政的なものや税務的なもの、そして今回の相続登記の義務化のような法規的なものなど様々あり、それぞれ期限が定められています。期限を超過しないように1つ1つスケジュール管理をしていきましょう。

河鍋公認会計士・税理士事務所代表 河鍋 優寛(税理士・公認会計士)
相続登記の方法
それでは、相続登記には具体的にどのような手続きが必要なのか、相続人の遺産分割協議による場合、法定相続分に応じて共有で相続した場合、被相続人の遺言書があった場合(遺贈)のそれぞれについて、みていきましょう。
【ケース1】相続人の遺産分割協議で相続した場合
被相続人の遺言書がないときには、相続人の話し合い(遺産分割協議)によって、財産の分け方を決めることができます。その結果、不動産を取得した場合の相続登記の流れは、次のようになります。
ステップ①
戸籍の証明書の取得:相続開始の証明と法定相続人の特定
ステップ②
遺産分割協議・協議書の作成:協議・話し合いによる土地・建物の所有者の確定とその書面化
ステップ③
登記申請書の作成:法務局(登記所)提出書類の作成
ステップ④
登記申請書の提出:法務局(登記所)へ提出
ステップ⑤
登記完了:法務局(登記所)から登記完了証・登記識別情報通知書の交付
〈ステップ①=戸籍の証明書の取得について〉
(1)相続登記の申請に必要な戸籍の証明書
相続登記の申請では、戸籍の証明書によって、①相続が開始したこと(土地・建物の所有者が死亡した事実)を証明するとともに、②法定相続人を特定する(他に相続人がいないことを証明する)必要があります。そのため、被相続人の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍の証明書を取得します。婚姻などによって新戸籍の編製がされている場合には、その新しい戸籍から古い戸籍にさかのぼって相続人が誰であるか(他に相続人がいないこと)を確認する必要があります。
(2)取得先(請求先)
戸籍の証明書は、それぞれの戸籍ごとに、本籍のある市区町村に請求します。なお、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍の証明書(戸除 籍謄本など)については、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます(コンピュータ化されていない一部の戸除籍を除く)。
請求の方法や交付に必要な手数料などについては、市区町村のホームページなどで案内されています。
〈ステップ②=遺産分割協議・協議書の作成〉について
相続人の間で、被相続人の財産をどのように分けるか話し合いを行い、まとまった結果に基づいて遺産分割協議書を作成します。
〈ステップ③=登記申請書の作成〉について
法務局(登記所)に提出する登記申請書を作成します。登記の申請は、作成した登記申請書(書面)を法務局(登記所)の窓口に持参する方法や、郵送する方法のほか、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で登記申請書を作成し、これをオンラインで申請(送信)する方法があります。
以下は書面(持参ないし郵送)の場合です。
(1)登記申請書の作成
登記申請書は、法務局ホームページから様式をダウンロードして作成することができます。
■登記申請書記載例(遺産分割協議の結果、法務一郎と法務温子が持分1/2ずつの共有名義で相続)
(2)登記申請書に添付する登記原因を証する書面(登記原因証明情報)
遺産分割協議による相続登記の申請では、「添付情報」として、一般的に、登記申請書に次の書面(添付書面)を添付して法務局に提出する必要があります(コピーは不可)。
◆戸籍の証明書
ⅰ被相続人の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍の証明書
ⅱ遺産分割協議の当事者である相続人全員の戸籍の証明書
ⅲ法務局の「法定相続情報証明制度」(※)を利用している場合には、法定相続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号(法定相続情報一覧図の写しの右上に記載された番号)を申請書に記載することで、ⅰ、ⅱの添付に代えることができる
ⅳ「被相続人の登記上の住所」が「戸籍の証明書に記載された本籍」と異なる場合には、「戸籍上の被相続人」と「登記上の所有者」とが同一人であることを証明するため、次のいずれかの書類を添付する
❶住民票の写し(被相続人の本籍及び登記上の住所と同じ住所が記載されているもの)
❷住民票の除票の写し(被相続人の本籍及び登記上の住所と同じ住所が記載されているもの)
❸戸籍の附票の写し(戸籍の表示及び登記上の住所と同じ住所が記載されているもの)
◆遺産分割協議書
遺産分割協議書には、相続人全員が印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、その印鑑証明書を各1通添付する
(3)住所を証する書面(住所証明情報)
相続人(土地・建物を相続した人)全員の住民票の写し(市区町村が発行した証明書の原本)
(4)登録免許税の納付(免税の場合を除く)
書面による登記申請では、次の方法により登録免許税を納付します。
・現金を国(税務署など)に納付し、その領収証書を登記申請書と併せて提出する
・収入印紙を登記申請書と併せて提出する
「法定相続情報証明制度」について:法務局
〈ステップ④=登記申請書の提出〉について
作成した登記申請書及び登記申請書に添付する書面 (添付書面)を、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局の窓口に持参する、または郵送する方法により、登記の申請をします。
郵送によって登記の申請をする場合は、登記申請書及び添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付してください。 登記の申請先となる不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)については、「管轄のご案内」:法務局を参照してください。
〈ステップ⑤=登記完了〉
法務局での登記が完了すると、登記完了証及び登記識別情報通知書(登記識別情報を記載した書面)が交付されますので、これを受領することですべての手続きが完了します。登記完了証及び登記識別情報通知書は、登記所の窓口で 受領する方法又は郵送により受領する方法があります。
登記所の窓口で受領する場合は、登記申請書に押印したものと同じ印鑑が必要です。郵送により受領する場合は、宛名を記載した返信用封筒 及び郵便切手を登記申請書とともに提出してください。
親族の遠方の不動産に関する相続登記を郵送で行ったことがありますが、書類が揃っていれば郵送でも滞りなく登記完了できます。送付と返送用封筒にはレターパックプラス(赤)が便利です。

河鍋公認会計士・税理士事務所代表 河鍋 優寛(税理士・公認会計士)
【ケース2】相続人が法定相続分に応じた共有で相続した場合
被相続人の遺言書がない場合、相続人には法定相続分(受け取れる遺産の割合)が認められています。不動産をこれに基づいて複数の相続人が相続した場合の相続登記の流れは、次のようになります。
ステップ①
戸籍の証明書の取得:相続開始の証明と法定相続人の特定
ステップ②
登記申請書の作成:法務局(登記所)提出書類の作成
ステップ③
登記申請書の提出:法務局(登記所)へ提出
ステップ④
登記完了:法務局(登記所)から登記完了証・登記識別情報通知書の交付
手続き、必要書類は、基本的に【ケース1】に準じます。法定相続分による分割なので、相続人同士の協議は不要で、遺産分割協議書の添付なども必要ありません。
登記申請書には、法定相続分に基づくそれぞれの相続人の「持分」を記載します。
基本的に不動産の共有の相続(共有名義にすること)は避けた方が良いです。その後の不動産の管理や固定資産税の負担、その後の相続などトラブルが付きまとうためです。

河鍋公認会計士・税理士事務所代表 河鍋 優寛(税理士・公認会計士)
【ケース3】被相続人の遺言書による場合
一方、被相続人が不動産を譲る人を遺言書で指定していた場合は、登記申請の流れは、次のようになります。
ステップ①
登記申請書の作成:法務局(登記所)提出書類の作成
ステップ②
登記申請書の提出:法務局(登記所)へ提出
ステップ③
登記完了:法務局(登記所)から登記完了証・登記識別情報通知書の交付
被相続人の遺言書がある場合には、法定相続人をあらためて確定させる必要はなく、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを用意する必要はありません。
〈ステップ①=登記申請書の作成〉について
(1)登記申請書の作成
基本的に相続人の遺産分割による場合などと同じです。
登記申請書の「登記の原因」には、「相続」ではなく「〇年〇月〇日遺贈」(年月日は死亡した日)と記載します。
(2)登記申請書に添付する書面
遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者=登記権利者)が単独でする所有権の移転の登記の申請(※)では、「添付情報」として、一般的に、登記申請書に次の書面(添付書面)を添付して法務局に提出する必要があります(コピーは不可)。
※2023年4月1日からは、遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者=登記権利者)は、その所有権の移転の登記を単独で申請することができるようになった。
(3)登記原因を証する書面(登記原因証明情報)
◆遺言書
遺言書(公正証書による遺言及び法務局で保管されている自筆証書遺言を除く)については、家庭裁判所の検認済証明書付きのものであること
◆戸籍の証明書
ⅰ遺贈者の死亡の事実の記載のある遺贈者の戸籍の証明書(戸除籍謄本など)
ⅱ遺贈を受けた相続人(受遺者)の戸籍の証明書
ⅲなお、遺贈者の最後の住所及び氏名が登記記録上の住所及び氏名と異なる場合や、遺贈者の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、遺贈者が登記記録上の所有者であることを証明するため、次のいずれかの書類を添付する
❶住民票の写し(遺贈者の本籍及び登記記録上の住所と同じ住所が記載されているもの)
❷住民票の除票の写し(遺贈者の本籍及び登記記録上の住所と同じ住所が記載されているもの)
❸戸籍の附票の写し(戸籍の表示及び登記記録上の住所と同じ住所が記載されているもの)
(4)住所を証する書面(住所証明情報)
遺贈を受けた相続人(受遺者)の住民票の写し
(5)登録免許税の納付
遺産分割協議による場合などと同じです。
〈ステップ②③〉
〈ステップ②=登記申請書の提出〉についてと〈ステップ③=登記完了〉も、遺産分割協議などによる場合と同じです。
まとめ
期限付きの相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを行わないでいると、ペナルティが課せられる可能性があります。とはいえ、不動産登記は煩雑で、専門的な知識も必要になります。対象になった場合には、司法書士など専門家によるサポートを検討しましょう。
記事監修者 河鍋税理士からのワンポイントアドバイス
今回ご紹介しました、2024年4月から3年以内の相続登記が義務化された件につきましては関心のある方が非常に多く、よくご質問を受けます。法改正で新設された10万円以下の過料も怖いところです。
不動産の権利に関する登記の代理申請は司法書士の独占業務ですので、お近くの司法書士に相談されるのが良いでしょう。
相続の対象となる不動産が近隣で、書類収集も問題なさそうでしたら相続登記は自身で行うこともできます。
その際は郵送にて手続きが完結できますし、法務局窓口では手順や必要書類について案内をもらえるため便利です。
税理士は不動産登記は業務として行えませんが、提携している司法書士の紹介はできるため、ワンストップで対応してもらいたい方にとっては税理士が相談の入口となるケースも少なくありません。
是非お近くの司法書士や税理士にご相談をお勧めいたします。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
ふるさと納税「ポイント還元」2025年9月30日で廃止へ!寄付者・自治体への影響と今後の活用法を解説
-
相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
-
防衛特別法人税とは?2026年4月から法人税に“1%の上乗せ”スタート
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
亡くなった人の口座は“凍結”される そのタイミングと解除する方法、注意点を解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
タクシーチケットの活用法とは?導入の流れや会計処理のポイント・注意点まで徹底解説!
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説