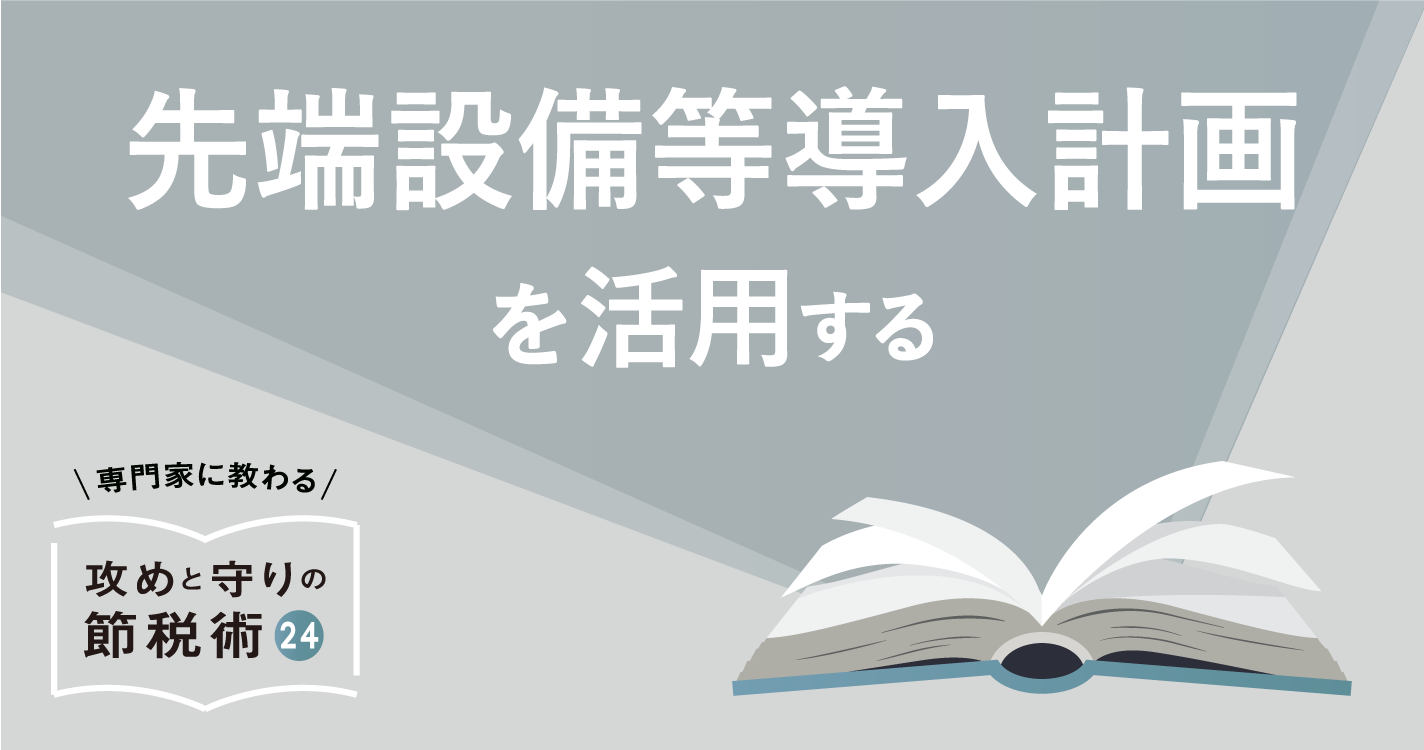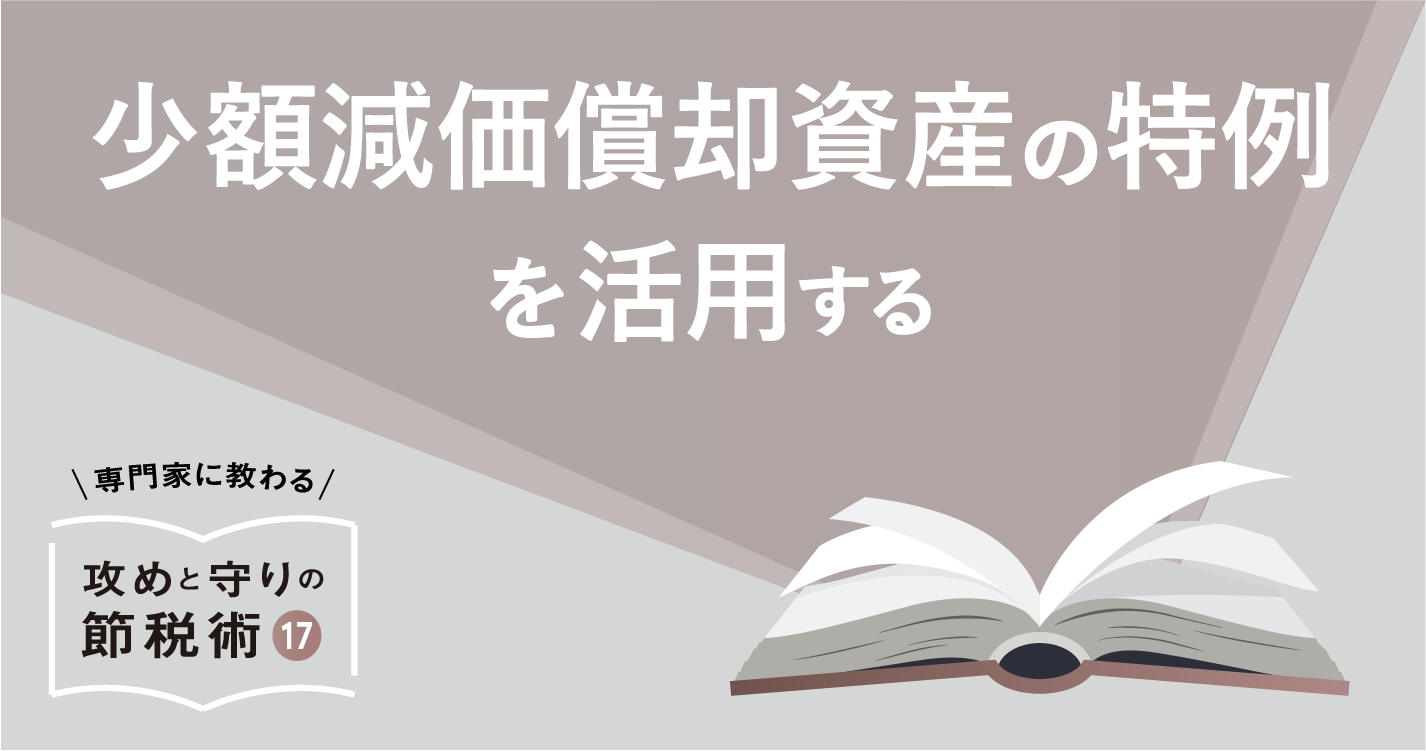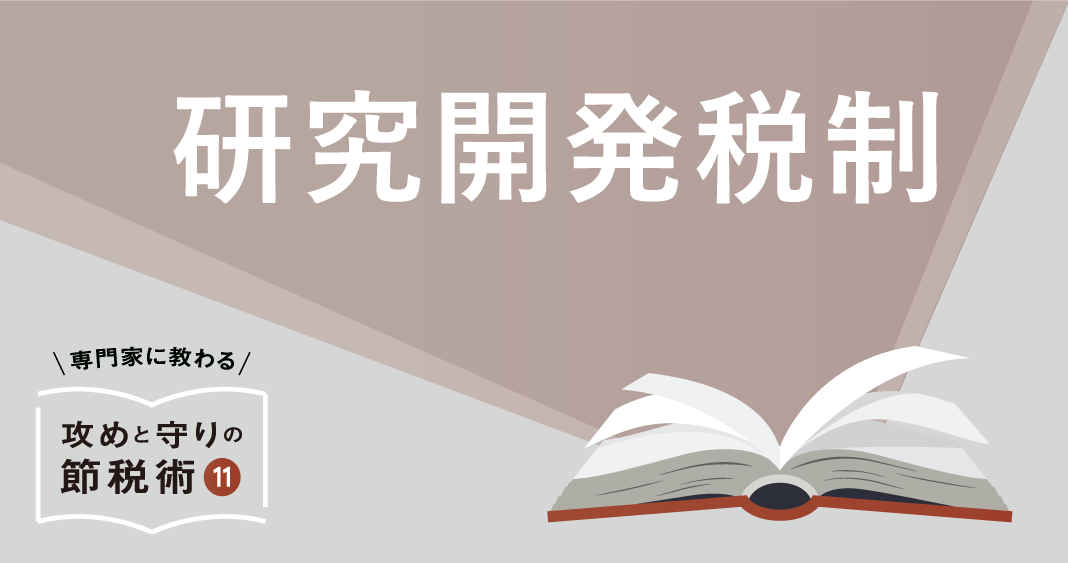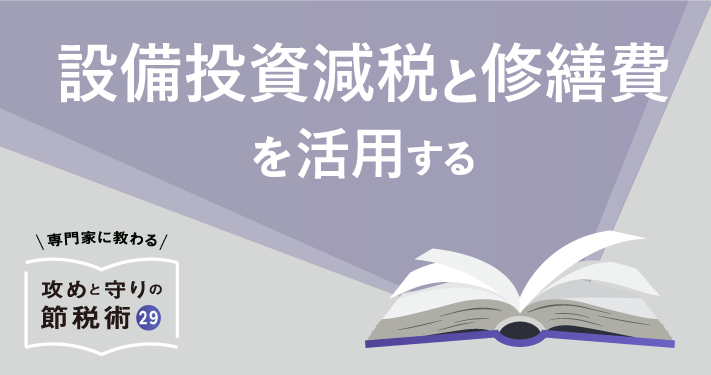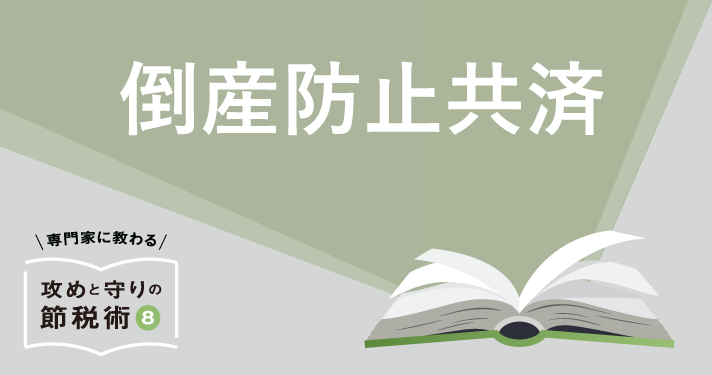「出張手当の非課税枠を活用する」という節税術
企業の従業員や役員が出張する際は、交通費や宿泊費などの旅費(出張旅費)とは別に、出張手当を支給することがあります。実はこの出張手当には「非課税枠」が設けられており、上手に活用することで法人税や所得税の節税につなげることが可能です。
特に従業員や役員の出張が多い企業では、その効果も大きくなるでしょう。この記事では、「出張手当の非課税枠」を活かした賢い節税術をご紹介します。
出張手当とは
出張手当(日当)とは、企業の従業員や役員が業務のために遠方へ出張する際に支給される手当のことです。交通費や宿泊費などの実費として支給される出張旅費とは別に支給され、出張に伴う従業員の金銭的負担の軽減や諸費用の補填を目的とします。
出張中は、会社への業務連絡や出張先での会食、雑費など、通常の業務よりも費用がかかることがあります。例えば、電車が来るまでの待ち時間にカフェでコーヒーを飲んだり、宿泊先で朝食を頼んだりすると費用がかかります。こうした従業員の金銭的な負担を軽減することが、出張手当を支給する主な目的です。
出張手当は単なる金銭的補助だけでなく、出張に伴う肉体的・精神的な負担をねぎらう慰労の意味合いもあります。従業員は出張手当を受け取ることで、モチベーションアップにつながることもあるでしょう。
(松﨑会計事務所 代表税理士 松崎 孝泰)
財務省が2023年(令和5年)に実施した「民間企業における出張旅費規程等に関するアンケート」によると、49.4%の企業が「往復行程(距離)」で、44.8%の企業が「宿泊の有無」によって出張手当を支給していると回答しています。
「出張手当を支給しない」と回答した企業は全体の11.6%にとどまり、何らかの形で出張手当を支給する企業が多数を占めていることがわかります。
出典:財務省「民間企業における出張旅費規程等に関するアンケート 報告」
出張手当の節税メリット
出張手当を活用すると、従業員の費用負担の軽減や慰労につながるだけでなく、次のような節税メリットも得られます。
節税メリット1 経費として計上できる
出張手当(日当)と出張旅費(交通費・宿泊費)は、適正な範囲内であれば企業の経費(損金)として計上が可能です。損金が増えれば、その分課税所得が減少するため、結果的に法人税の節税につながります。
また、この節税効果は企業側だけでなく従業員側にもメリットがあります。社会通念上相当と認められる金額の出張手当(日当)は非課税所得として扱われ、給与所得には含まれません。これにより、従業員の所得税・住民税の負担軽減にもつながります。
企業側の節税の例
出張手当(日当):1人あたり5,000円
出張日数:10日
対象人数:5名
法人税率:30%(概算)
年間の出張手当支給額
5,000円 × 10日 × 5名 = 250,000円
この分、法人の課税所得が減少するので、法人税の節税額は
250,000円 × 30% = 75,000円
つまり、75,000円分の法人税を減らせることになります。
※ただし、出張手当の額や頻度が過剰でないこと、社内規程に則っていることが前提です。
従業員側の節税の例
出張手当は、社会通念上妥当な金額であれば非課税所得として扱われます。給与として支給すれば所得税・住民税がかかりますが、手当として支給すれば所得税・住民税がかからず、従業員の手取りアップと節税につながります。
例えば、給与で5,000円支払えば、所得税・住民税・社会保険料が差し引かれますが、出張手当で5,000円支払えば、非課税でそのまま満額での受け取りが可能です。
出張手当は支払う企業側及びもらう従業員側の双方に税務メリットがあります。こんなお得な節税方法は、税理士として他に知りません。出張が少しでもあるという企業は是が非でも導入すべきでしょう。
(松﨑会計事務所 代表税理士 松崎 孝泰)
節税メリット2 社会保険料の負担軽減につながる
出張手当(日当)は、社会保険料(健康保険・厚生年金など)の算定対象となる標準報酬月額に含まれません。これにより、企業側は会社負担の社会保険料が軽減、従業員側は自己負担の社会保険料が軽減し、双方にとってメリットがあります。
節税メリット3 フリーランスや一人社長でも導入可能
出張手当(日当)は、小規模法人でも導入が可能です。法人格を持つことで、役員としての出張手当の支給が可能になり、一定の範囲内で非課税所得として扱えます。
例えば、遠方での取材や旅行記を執筆することが多いフリーライターや、全国各地で講演するコンサルタントなどが法人を設立すると、役員である自分自身に出張手当を支給できます。
ただし、個人事業主の場合、自身に対する「出張手当」という概念はなく、日当相当のものを非課税所得として扱うことはできません。
個人事業主が出張に関連して経費計上できるのは、実際に支払った交通費、宿泊費などの出張旅費のみです。飲食費なども、出張の目的によっては経費として認められる場合がありますが、日当のような形で包括的に非課税扱いにすることはできません。
出張手当を活用する際の注意点
出張手当は経費(損金)として計上できるため、税金や社会保険料の負担軽減につながりますが、適正に運用しなければ税務調査で否認されるリスクもあります。以下の注意点を押さえ、正しく活用することが大切です。
注意点1 社内規程の整備が必須
出張手当を支給する場合、あらかじめ「出張旅費規程」を整備し、手当の金額(役職・距離・宿泊の有無などによる区分)や支給条件、計算方法、支給方法(いつ、どうやって払うか)を明確に決めておく必要があります。
規程がないまま支給すると、給与とみなされ課税対象になってしまう可能性があるため注意が必要です。税務調査でもまず確認されるのがこの規程なので、必ず整備・保管しておきましょう。
出張旅費規程の作成には、特定の決まった形式はありません。経費精算システムを導入している場合、テンプレートを活用できることもありますし、わからない場合は税理士や社会保険労務士などの専門家に依頼したり相談すると安心です。
かなりお得な節税方法だけに、税務署も目を光らせています。しっかりとした導入をするためにも、ネットの情報に惑わされないように専門家に相談して適法な規程整備及び運用をしていきましょう。
(松﨑会計事務所 代表税理士 松崎 孝泰)
注意点2 金額は社会通念上妥当な範囲内に
出張手当は、社会通念上相当と認められる金額でなければ非課税と認められません。具体的な金額は特に決められておらず、2,000円~3,000円程度が目安とされています(役職・業種・規模・地域などによる差も考慮)。
財務省の「民間企業における出張旅費規程等に関するアンケート」によると、出張手当の金額は以下のようになっています。
国内出張における日当
| 最低額 | 平均額 | 最高額 |
| 1,780円 | 2,621円 | 3,786円 |
海外出張における日当
| 最低額 | 平均額 | 最高額 |
| 4,256円 | 5,441円 | 7,041円 |
出典:財務省「民間企業における出張旅費規程等に関するアンケート 報告」
上記の金額を参考に、適正な金額を設定しましょう。極端に高額だと出張手当として経費にはならず、給与として課税対象になるリスクがあります。
社長や役員の出張手当は従業員よりも高めに設定されるのが一般的ですが、あまりにも高額にすると税務調査で指摘されやすいので注意が必要です。税務調査があった場合に、社会通念上合理的であると説明できるようにしておきましょう。
適正金額を社内規程で定め、社会常識から大きく逸脱しないよう、定期的に見直すことも大切です。
注意点3 出張記録を保存する
出張手当を支給した場合、出張記録を残しておくことも重要です。出張記録がなければ、税務調査があった場合に出張の実態を証明できず、「カラ出張ではないか」と疑念を抱かれ、課税対象とされる恐れがあります。
出張記録の書類としては、出張届(出張申請書)や出張報告書などがあり、出張先や出張目的、出張期間など、以下の記載が必要です。
出張記録に記載すべき基本情報
- ・出張者の氏名
- ・出張先
- ・出張期間
- ・出張目的
- ・宿泊の有無
- ・交通手段
- ・出張費用
- ・交通費・宿泊費の領収書
税務調査においては、出張の実態が客観的に証明できるかどうかが重視されます。適切な出張記録は、税務署からの疑義に対して有効な証拠となり、出張手当の非課税扱いの根拠となります。支給のたびにしっかり管理・保存しておきましょう。
注意点4 手当の支給タイミングと方法を統一する
出張手当は「いつ、どうやって支給するか」も社内規程で定め、実務も統一しておく必要があります。
- ・出張前に前渡しするのか
- ・帰社後の経費精算と同時に支給するのか
- ・給与と合わせて振り込むのか、別に振り込むのか
これらを事前に決め、規程どおりに支給することが求められます。
支給方法やタイミングがバラバラだと、給与とみなされ課税対象になるリスクが発生するため、注意が必要です。
特に税務調査では「給与との区別」が重視されるため、タイミング・支払方法の一貫性は、非課税扱いを守るためにも重要なポイントとなります。
この節税術に必要な心構えとは
出張手当の非課税枠を活用した節税は、単に手当を支給するだけで成立するものではありません。
まず、社内規程をしっかり整備し、手当の金額や支給方法・タイミングを明確に定めておくことが大切です。さらに、出張の実態を証明できるよう、出張記録をきちんと残し、証拠として保存しておくことも欠かせません。
また、出張手当の金額は社会通念上妥当と認められる範囲で設定し、万が一、税務調査が入った際にも合理的に説明できる状態にしておくことが重要です。特に一人社長や小規模法人の場合、運用が曖昧だと否認リスクも高まるため、慎重に進めるべきでしょう。
こうした節税術を効果的かつ安全に活用するためには、税務の専門知識と実務経験が不可欠です。「この金額で適正なのか」「この規程で問題ないのか」など、少しでも不安がある場合は、迷わず税理士に相談することをおすすめします。
出張手当の非課税枠を活用した節税をお考えの方は、まずは信頼できる税理士に相談し、自社に合った最適な方法を確認してみましょう。
繰り返しになりますが、出張手当はなんせお得です。支払った企業側も、もらった従業員側もお得になる節税策は他にはあまりありません。出張が少なからずあるよという企業様は是非早期に導入していきましょう。導入する際には規程作成、運用方法の構築、報告書の作成、社内への周知、給与との関係性など検討すべきことが多いです。
のちに税務調査で指摘されてお得なものではなくなったとならないように、しっかり準備して日々の運用をしていきましょう。
(松﨑会計事務所 代表税理士 松崎 孝泰)

M&AのFA(ファイナンシャルアドバイザー)や、資金繰りの改善、資金調達に強みを持つ会計事務所。
M&Aについては、売手側もしくは買手側のFAとして、どちらか一方の立場に寄り添って、それぞれの立場としてより良くなるように交渉を行う。案件の最初からクロージングまで、FAとして寄り添って案件の成立を一緒に目指します。弊社は上記の理由から仲介は原則行いません。
資金繰りについては、将来1年間の資金繰り予測をして計画を作成し、時が進むに従って実績を毎月追いかけていくことで、いつ資金不足に陥るのか、もしくは新たな事業や投資をしても資金繰りには問題ないかなど、経営判断に使える情報をご提供します。
資金調達については、お客様にとって煩わしい金融機関との折衝や事業計画書の作成を弊社が行い、金融機関との面談にも同席します。また、必要な金融機関のご紹介も行っております。
事務所詳細はこちら
事務所公式ホームページはこちら