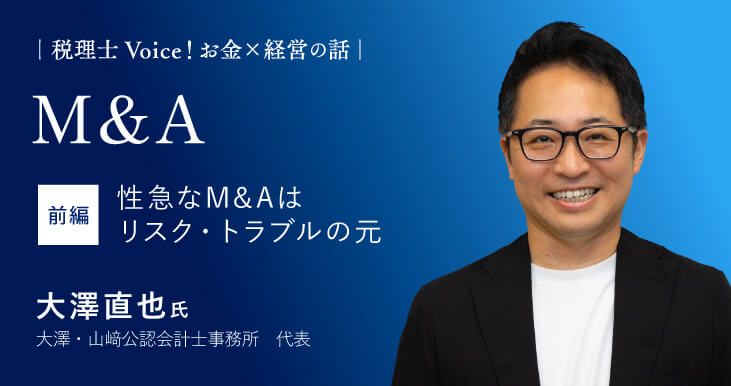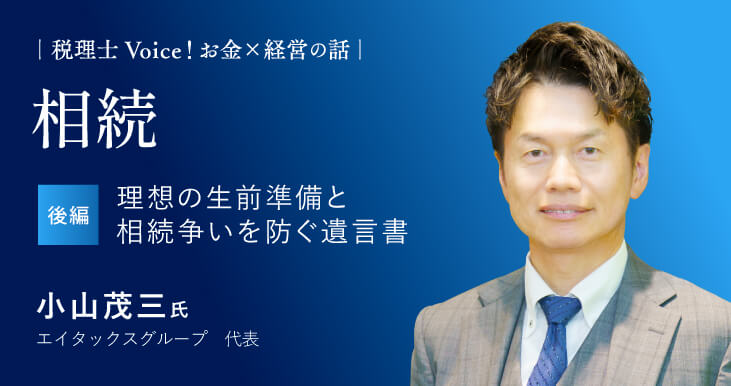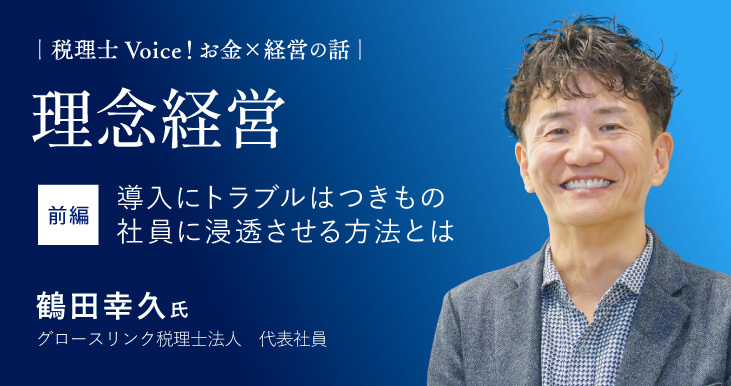【事業承継 前編】事業承継では、税金対策よりも現場の駆け引きが大事なこともある
税理士法人 仁科忠二郎事務所 代表税理士 仁科忠二郎氏(右)、代表税理士 小池桂治氏(左)社長の高齢化などに伴う事業承継が課題になっている。会社の経営権が移動するタイミングだけに、そこでは想定外の「ドラマ」も起こりがちだ。今回は、事務所設立来、40年以上中小企業の経営サポートに携わってきた税理士法人 仁科忠二郎事務所の代表税理士である仁科忠二郎氏、小池桂治氏に、後継者への事業承継やM&Aに関する印象的な事例、そこからくみ取るべき教訓などを語っていただいた。
記事では、「前編」で自社株をめぐる会社の危機を未然に防いだ事例など、「後編」では後継者問題が絡む事例、事業承継に必要な心構えなどを中心にまとめた。
相続でリスクを察知した
――最初に事務所の概要をお聞かせください。
仁科(敬称略) 東京の大田区蒲田に事務所を構え、中小企業オーナーのサポートをメインに、さまざまな業務に携わっています。メンバーは現在20名ほどで、税理士資格保有者が3名います。
顧問先は約400件で、個人のお客さまは約300件ほどいらっしゃいます。業種としては、製造業のほか、近年は建設、不動産業のウエートが高くなっていますね。

――本日は、そうした企業オーナーが避けては通れない事業承継をテーマにうかがっていきたいと思います。
仁科 理屈を述べる前に、印象的だった事例からお話ししましょう。売上数十億円規模の製造業の会社が、創業者の相続を機に、半分乗っ取られそうになったことがありました。
小池 成り立ち自体が少々ややこしいのですが、もともとAさん、Bさんが共同で立ち上げた会社で、当時は両家の親族外のCさんが社長に就いていました。C社長は会社たたき上げの人で、事業を大きく成長させた功労者でした。
ただ、会社の株式に関しては、引き続き創業家であるA家、B家ともに一定の割合を保持していました。ある程度を中小企業投資育成会社(※)や従業員持株会に持たせていたものの、C社長の強固な経営権の確保という点では、若干の問題も残していたわけです。
※中小企業投資育成会社 中小企業投資育成株式会社法に基づいて設立された国の政策実施機関。会社の自己資本の充実などを支援する。東京中小企業投資育成株式会社などがある。
そんな状態で、Aさんが亡くなりました。すると、Aさんの息子さんが、勤めていた会社を退職して、入社してきたんですよ。
――A家保有の株を持った状態で。
仁科 そうです。で、私にはそれが会社乗っ取りの布石に見えた。
小池 忘れもしないのですが、Aさんに相続税の申告を依頼されていたので、仁科先生と2人で会社に行って、Aさんの息子さんと面談したのです。すると仁科先生は、帰り道で入った喫茶店に会社の部長さんを呼んで、いきなり「Aさんの息子さんが持つ株を全部買い取って、すぐに会社を辞めさせたほうがいい」と。
――それは、言われたほうもびっくりしたのではないでしょうか。そのように判断した理由は?
仁科 勘ですね(笑)。Aさんの息子さんの発言からは、「私は創業家の人間なんだ」「会社の株を持っているんだ」というのが、ありありでしたから。そのままにしたら、後々、C社長の経営の足かせになる可能性がかなりある、と思ったのです。
小池 会社もそこを理解して、C社長がA家側に頭を下げる一方、弁護士さんに相談して株買い取りのための法的な手続きを進めました。当然、反発はあったのですけど、結果的には無事に全株を買い取り、Aさんの息子さんも会社から去りました。
――リスクを察知した時点ですぐに手を打ったことで、将来のトラブルの芽を摘んだわけですね。
創業家からすべての株を買い取る
小池 ただ、会社からすると、依然としてB家の保有株の問題が残っていました。実は、B家のほうが影響力が強くて、会社はそれまでも「持っている株を売ってほしい」と交渉を行っていたのですが、なかなか首を縦に振ってはくれなかったそうです。
――会社は、そっちの問題にも決着をつけたい。事務所としては、どのような対応をなさったのでしょう?
小池 会社の状況を率直にお話しして、理解を得るしかありませんでした。こちらは、ある時期から当事務所がB家の申告も請け負うようになり、信頼関係を築けたことが幸いしました。仁科先生と会社の部長さん、当事務所の担当者がB家の自宅にうかがってお願いしたところ、意外にすんなり「いいですよ」と。
仁科 細かなことですが、そのとき会社の部長さんは、すごく細かいお願い状みたいなものを用意していたんですよ。それではダメだ、と私が簡潔な合意文書を作り、持って行きました。
――そういうところで、相手の受ける印象はずいぶん変わってくると思います。
小池 そんな経緯で、最終的には両方の創業家からすべての自社株を買い取りました。今はさきほどの投資育成会社と従業員持株会、役員持株会が全ての株を保有していて、どこからか横やりが入ったりするようなことのない、経営の永続性が確保された会社になっています。
A家の側の突発的な事態への対応もそうですし、もし何かの行き違いでB家の株の買い取りに失敗していたら、今ごろこうはなっていなかったのではないでしょうか。相続が発生すれば、また新たな人が株主になるようなことも考えられましたから。
仁科 安定的な経営の基盤ができて、業績もますます好調ですよ。
――経営者にとって、会社の株がいかに重要なのかということが、あらためてわかる気がします。
絶好調の会社の株を「放棄」した社長

小池 株に執着する人がいるかと思えば、これもすごく儲かっている会社を経営しながら、急に「株は全部渡す」と言って、子どもでもない義理の弟さんにその座を譲った社長もいました。
建設業関連の会社なのですが、どのくらい儲かっているかというと、100人以上の社員全員で海外旅行に行くくらい(笑)。
――それはすごい(笑)。
仁科 その社長はまだ60歳前だったし、そんな会社の経営を手放すなんて、ちょっと信じられなかったのだけど。
小池 この会社の場合は、義理の弟さんがやり手で、どんどん業績を伸ばしていたんですね。想像ですが、経営者としてかなわないと思ったのかもしれません。
――では、事業承継自体は、わりとすんなりと行ったのでしょうか。
小池 いえ、それがそうでもなかったんですよ。前社長は、「株を渡す代わりに相応の退職金をもらいたい」と会社に要求して、引き続き毎月の役員会には顔を出していました。出費はできるだけ抑えたい会社側と、けっこうシビアなせめぎあいになったのです。
そういう交渉というか駆け引きの現場には、我々も何度か顔を出しました。前社長の姿勢も強硬で、正直、決着には時間がかかるかな、という雰囲気でしたね。
――社長も簡単には譲れないでしょうから。
小池 ところが、あるとき急転直下という感じで、話はまとまりました。何が直接のきっかけになったのか、細かなところはわからないのですが。
仁科 多くの経営者をみてきただけに、ああいう形でリタイアするというのは、私には意外でした。それで、この事例も印象に残っているんですよ。
事業承継税制を使って株を移動
小池 ちなみに、この事業承継には、もう1つの問題がありました。新しい社長が株を譲ってもらうのはいいのだけど、そのままもらえば、高額の贈与税が発生します。なにせ業績絶好調ですから、株価も跳ね上がっていました。
そこで、事業承継税制を使って株を移動させることにしたわけです。使うしかなかった、というのが正しいでしょう。
――事業承継税制を使って後継者に自社株を譲れば、贈与税や相続税の支払いが猶予されます。ただし、譲られた後もいろいろ要件があって、それらを満たせないと、猶予されていた税金を一括で納めなくてはなりません。
仁科 そういう使い勝手の悪さ、リスクがあるので、あまり使われていませんよね。
小池 ある程度自社株が高いケースでも、退職金を出して株価を下げた状態で渡すとか、遺言書をきちんと用意しておくとかの対策で、たいてい間に合います。この会社の場合は、それでは足りないくらい株価が上がっていました。
さらに言えば、同社が株券発行会社(※)だったというややこしい事情もありました。事業承継税制を使うには、自社株などを担保にする必要がありますが、株券発行会社だと、株券そのものを提供しなくてはなりません。
※株券発行会社 旧商法の下で設立された会社が該当する。2006年の会社法施行後に設立された会社は、株券不発行会社に該当することが原則とされている。
実は、今回退いた社長は、先代からやはり事業承継税制を使って自社株を譲り受けていました。その際に株券を担保にしていたため、手元にはなくて日銀に保管されていたのです。
――なるほど。ややこしそうですね(笑)。
小池 どうすればいいか、確認のために東京国税局に仁科先生と何度も足を運びました。最終的には担保の書き換えで対応することができたのですが、途中にはちょっとした「ピンチ」もあったんですよ。会社側と協議して、これを機に株券不発行会社に衣替えしようかと考えたのです。で、念のため国税局で尋ねたら、「それをやった瞬間に、納税猶予は打ち切りの可能性もありますよ」と。
――そういうことも、事業承継税制の要件に触れてしまう。
小池 早まらないでよかった、と胸をなで下ろしました。そんなこともありましたし、当事務所としては、今後も毎年の税務署などへの届け出をフォローしていかなくてはなりません。
まあ、そういう大変さはあるのですけど、会社にとっては、実力者がしっかり経営権を握ることができました。その息子さんたちが経営陣に入っていますから、当面、事業承継に向けたいい流れもできたと思います。
――デメリットも指摘される制度ですが、要は「使いよう」ということですね。
小池 同時に、振り返ってみると、そういう税金うんぬんの前に、そもそも前社長に株を譲ってもらえなかったら、今の姿はありませんでした。地道に話し合いをして、社長の決断を引き出したことが、勝負の分かれ目だったわけです。
多くの事業承継のお手伝いをしてきましたが、率直に言って、うまくいくかいかないかのポイントになるのは、税金以外の話の場合がほとんど。
仁科 そう。税金の話は大したことない(笑)。
小池 より重要なのは、関係者の心を動かす現場での対応、駆け引きではないでしょうか。それが簡単ではないのですが。
「後編」では、引き続き事例を紹介していただきながら、事業承継に対する心構えなどについてうかがいます。
注:記載の「事例」に関しては、情報保護の観点により、お話の内容を一般化したり、シチュエーションなどを一部改変したりしている場合があります。
大田区を中心に、中小企業オーナーをサポートする専門家集団。税務・会計だけではなく、事業承継・相続、経営コンサルティング。税務調査、会社設立まで幅広いサービスを提供。
URL:https://www.nishina.gr.jp/