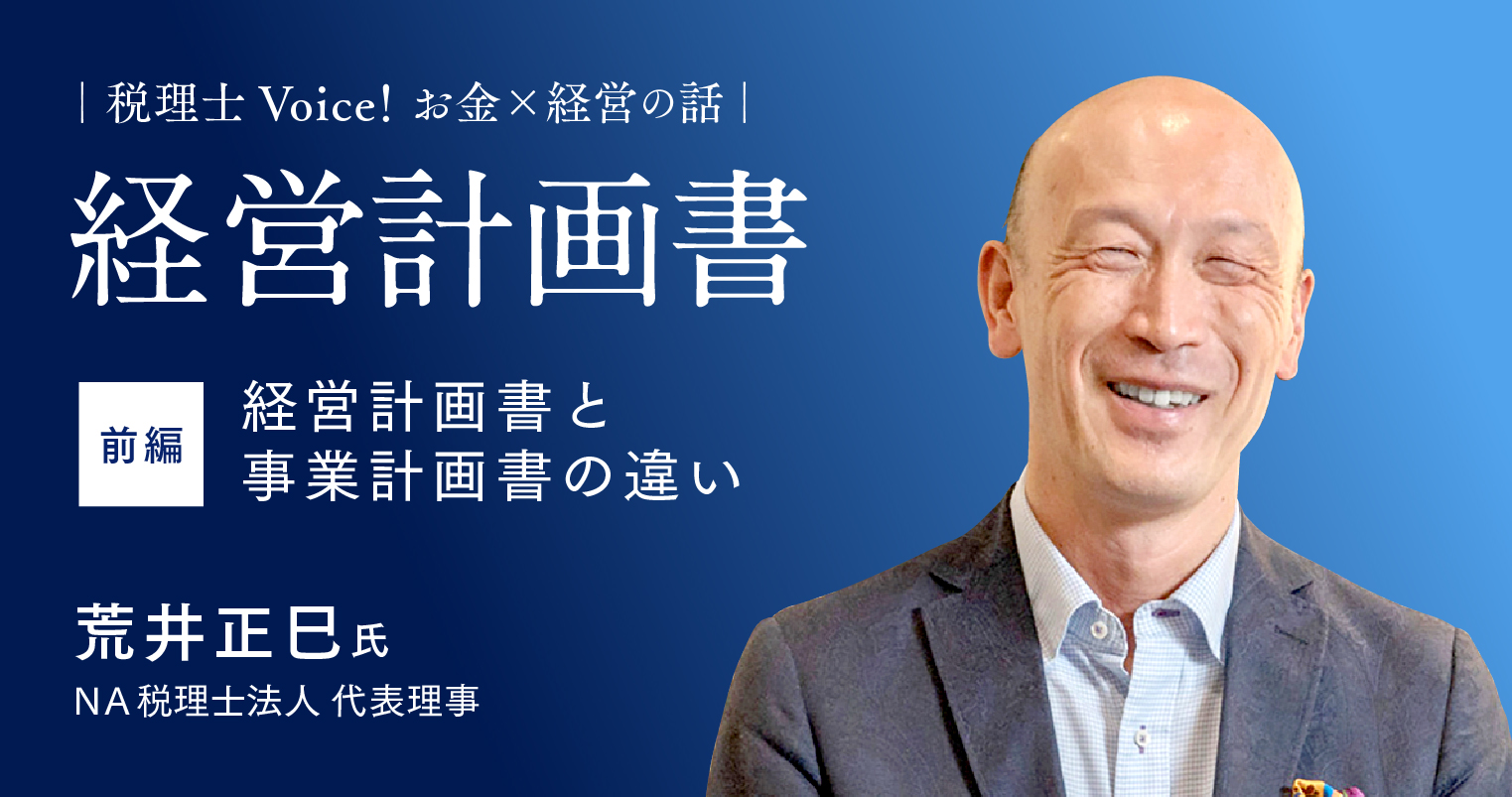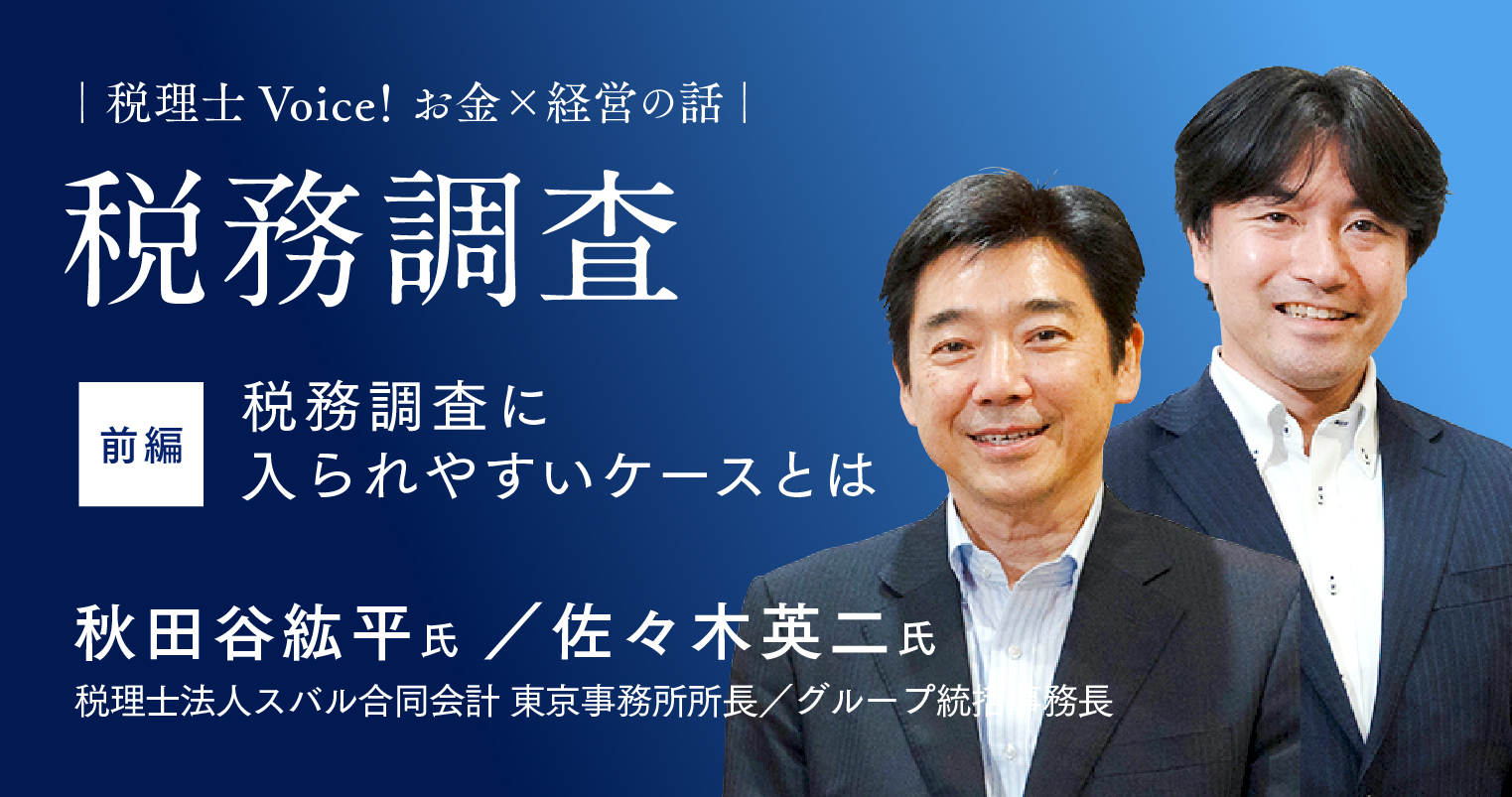【事業承継 後編】事業承継では、税金対策よりも現場の駆け引きが大事なこともある
税理士法人 仁科忠二郎事務所 代表税理士 仁科忠二郎氏(右)、代表税理士 小池桂治氏(左)親族内承継を阻むもの
――前編では複雑な事情を抱えた事例をご紹介いただきましたが、やはり顧問先で事業承継に悩んでいる社長は、数多くいらっしゃると思います。
小池 最初に問題になるのが、そもそも自分の子どもが会社を継いでくれるのかどうか、ということです。
仁科 昔だったら、当然のように長男などが家業を継いだのだけど、そういう時代ではなくなりましたから。
小池 ある業界のかなり規模の大きな会社なのですが、やはり息子さんに後継者になる気持ちがあるのかどうかが今一つ明確ではなく、当事務所に相談に来られた社長がいらっしゃいました。息子さんは、最近になって父親の会社に入り、後継社長に就いたのですが。
――その息子さんは、ずっと違う仕事をしていた。
小池 ええ、別業種の大手企業に勤めていたんですよ。そんなこともあって、父親のほうは、「うちを継ぐ気持ちはないんじゃないか」と、一時期、会社のM&Aも検討していたのです。
仁科 結果的に親族内承継になったのには、業績が非常に良かったというのが大きかったと思いますね。土地もたくさん持っていたし。
――確かに、先行きが危ないような会社では、継ぐのに二の足を踏むかもしれません。
仁科 今は、この息子さんのように、大学を出て一般企業に勤めるケースが多いでしょう。そうすると、いろんなことを「学ぶ」のです。
例えば、「継がないか」と言われて父親の会社を調べてみたら、財務状況が非常に悪いことがわかった。じゃあやめておこう、と。「跡継ぎ問題」に関しては、そういう経済的な要因の比重が高いと感じます。
小池 大企業に勤めていると、1つの事業部のある部署の一員、という感じになりますよね。でも、中小企業の社長は、会社の全部をみなくてはなりません。事務職だった人が、現場にもどんどん入っていかなければならなくなる。そういうところに戸惑いを覚えるケースも、けっこうあるように思います。
仁科 突き放したような言い方になってしまいますが、いずれにしても、息子さん、娘さんが事業を継いでくれるかどうかは、当人たちが決めることなんですね。我々のような他人が話をして、どうこうなるものではありません。
――それだけに、子どもを後継者にしたいと思ったら、早めに話し合いを始めるべきなのでしょう。
「二代目」の問題もある
――この会社の場合は、父親が半ば諦めながらも、最終的に息子さんが「継ぐ」という決断をしたわけですね。
小池 でも、それでハッピーエンドといかないところが、事業承継の難しさでもあります。経営者として事業を維持・発展させていけるかどうかは、これからの問題ですから。
そういう点で少し気になるのは、会長になったお父さんと、息子さんの「目線」の違いでしょうか。会長の目は常に商売に向いていて、息子にも経営で大事になることなどをできるだけ多く教えたい。他方、息子さんのほうは、どちらかというと、自分にかかってくる相続税とかに関心があって、我々との話も「税金はどうなるのでしょう?」といった中身が多いんですよ。

――会社が土地をたくさん持っているというお話ですから、それらを引き継いだ以上、どうしても気になるのでしょう。
小池 そういう親子の「思いのズレ」みたいなものは、親族内承継をした会社にけっこう共通するのかな、という気もします。
仁科 会社を1からつくり上げた初代と、それを受け継いだ二代目とでは、やっぱり発想が違うのです。いちがいには言えないけれど、例えば二代目の社長が経営者のあり方を学ぼうとせずに、「初代のつくった会社のいいとこ取りをしよう」というような意識でいると、従業員にはすぐにわかります。形の上で親族内承継ができたとしても、その後彼らがついてきてくれなかったら、会社は危うい。
小池 確かに会社のベテラン社員などには、前社長の頑張る姿を見ているからこそ、自分たちも一生懸命仕事をしよう、というタイプの人も多いですよね。そういう部分も含めて承継できるかというのは、簡単ではないけれど、大事なポイントでもあると思います。
M&Aも簡単ではない
――先ほどお話に出ましたが、親族や従業員に後継者が見つからなかった場合の選択肢として、M&Aがあります。近年、件数が増えていますよね。
小池 我々もM&Aの支援をしていて、非常にうまくいく例もあります。その一方で、実は失敗例もけっこう目撃しているんですよ。
――どんなことで失敗するのですか?
小池 M&Aは、言ってみれば、異なるDNAの会社同士が合体することなんですね。当事者がそうしたことをしっかり理解していないと、せっかく1つになっても、社内にハレーションが起きたりして、最悪「破談」になることもあります。
――移籍先で混乱が起きれば、従業員にとっても辛いことになってしまいます。
小池 これは買い手側の会社の事例なのですが、当事務所がタッチする前に、数件のM&Aを失敗させた社長がいました。
仁科 IT関連の企業でしたが、事業を大きくするために会社を買ったものの、最初は失敗続きだった。それで我々のところに相談にいらっしゃった。
小池 失敗の原因は明らかで、デューデリジェンス(DD:買収対象の会社の事業や財務などについての詳細な調査)を省いたまま買っていたのです。
――会社を買うというのに、DDをしないというのは、信じられない感じもしますが。
小池 M&A仲介会社を信頼したのか、その辺の事情はわからないのですが、社長は後々問題が起こるとは思わなかったのでしょう。そのように、ある程度お金も時間もかかるDDを端折る例は、少なくないようです。
でも、M&Aが双方の会社、従業員に与える影響は、たぶん社長が頭の中で考えていることよりも大きいと思うのです。その会社は、無理なM&Aをしたばかりに、逆に人材がほとんど流出してしまい、結局お金を使っただけで終わるような経験もしました。
――貴社が請け負ってからは、そこを改めたわけですね。
仁科 我々は、たいてい2人体制でDDをきっちりやります。その会社に関しては、相談を受けてから3、4件の買収をしたと思いますが、今度はうまくいって、業績も大いに伸びています。
会社のどこを見るのか
――会計事務所が買い手側からM&Aの依頼を受けた場合、DDについては、専門の会計士系のコンサル会社などに振るケースも多いと思うのですが。
仁科 当事務所は、自分たちでやります。あくまで一般論ですけど、会計士は財務的な数字などには詳しいかもしれませんが、中小企業の事業や業務の内実を知るのは、やっぱり税理士なんですよ。我々は、「机上の論」で終わらせずに、そういうところにどんどん突っ込んでいきます。
小池 コンサル会社などの作る書類はカッコいいんですけど、それで終わっていることも少なくないように思います。もちろんDDをやれば、例えば在庫に問題があるとか、資産性のないものが帳簿に載っているとかの、数字的なものは出てきます。ただ、M&Aを成功させるためには、それだけではない大事なものがあると思っていて、そこをつかみきれるかどうかが勝負なんですね。言葉にするのは難しいのですが。
そのために、我々は買収対象の会社に行って、自分たちの目で現場を確かめます。DDって、けっこう“泥臭い”ものなんですよ。
――現場では、どのようなところを見るのでしょう?
仁科 社屋を見て、社員さん一人ひとりを見ます。買う側からすると、その人たちに来てもらうことになるわけですから。社長は社員に甘いか、厳しいか。工場があれば、きちんと整理整頓されているか。
小池 ある意味で、税務調査よりも厳しいですよ(笑)。考えてみれば当然で、買い手であるお客さまの社運がかかっているわけですから。
別件では、仁科先生と一緒に、買われる予定のレストランに「お忍び」で出かけて、味を確かめたりもしました。先生に「トイレを見てきなさい」と言われて、清掃の状況までチェックして。
―― 一般的なDDのイメージとは、かなり違います。
仁科 でも、我々が手掛けた案件は、どこもうまくいっていますよ。そういう現場主義を貫いている結果だと、私は理解しています。
――今お話しいただいたのは買い手側の事例でしたが、裏を返せば、事業承継でM&Aをしようと思ったら、しっかりしたDDに耐えられえる会社であることが求められますね。

小池 それが理想なのは、いうまでもありません。事業承継で売却を考える場合も、できるだけ早めに準備を進めるべきでしょう。
仁科 M&Aで売るほうへのアドバイスとしては、交渉になったら会社の状況を全部さらけ出すべき、ということです。変に隠し事をしたりすると、「何かおかしい」と手を引かれてしまう恐れがありますから。
――わかりました。本日は具体的な事例を踏まえたお話をしていただき、とても勉強になりました。最後に、貴事務所の今後の展望をお願いします。
仁科 これからも中小企業経営者のよきパートナーとして、税務以外のことも含めたサポートに全力を尽くす、という基本方針に変わりはありません。
小池 お話ししたような“泥臭い”現場主義というのは、まさに仁科先生が創業以来培ってきたこの事務所のDNAです。今後もそれを大切にしながら、時代に則したサービスを提供していきたいですね。
――ますますの発展を期待します。本日はありがとうございました。
大田区を中心に、中小企業オーナーをサポートする専門家集団。税務・会計だけではなく、事業承継・相続、経営コンサルティング。税務調査、会社設立まで幅広いサービスを提供。
URL:https://www.nishina.gr.jp/