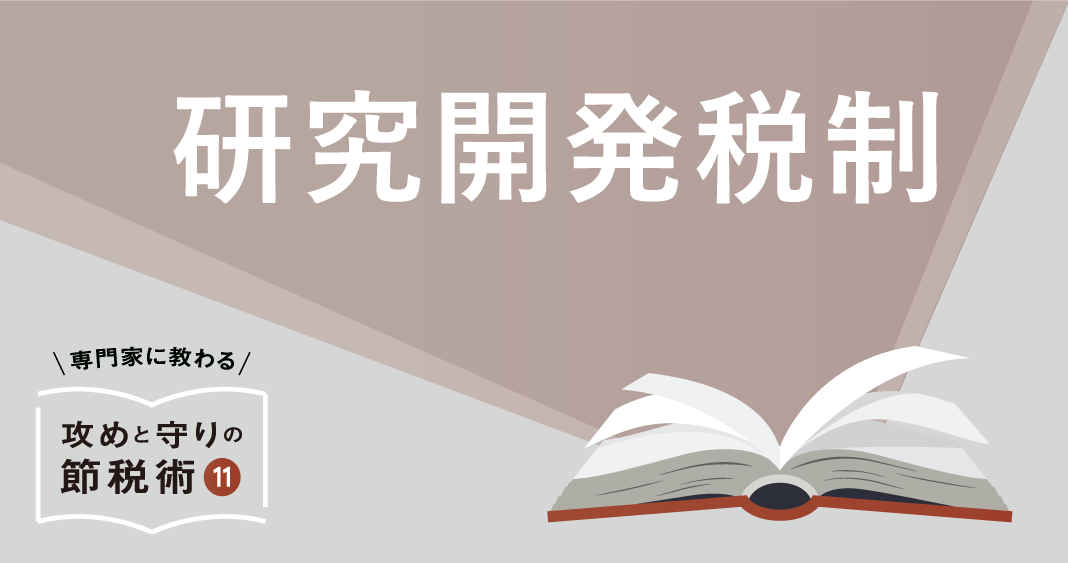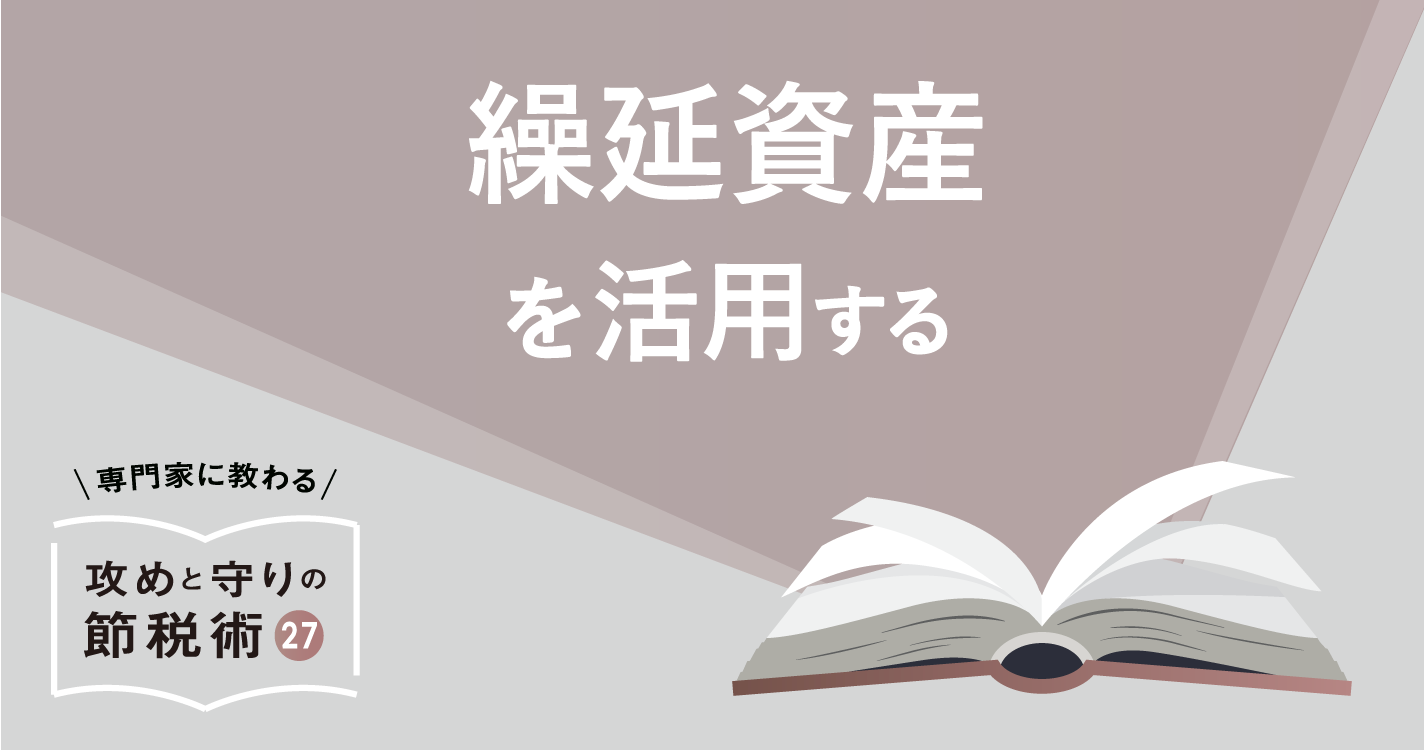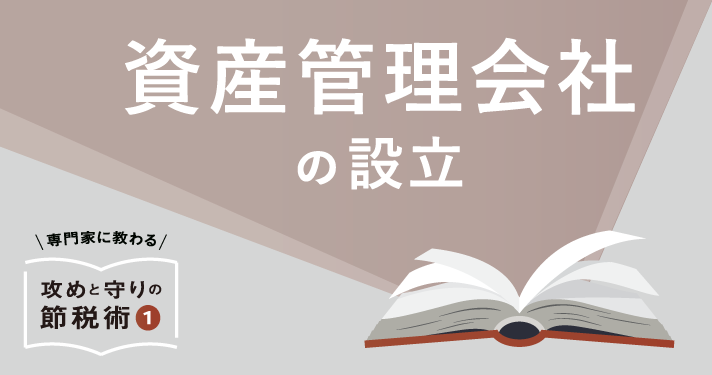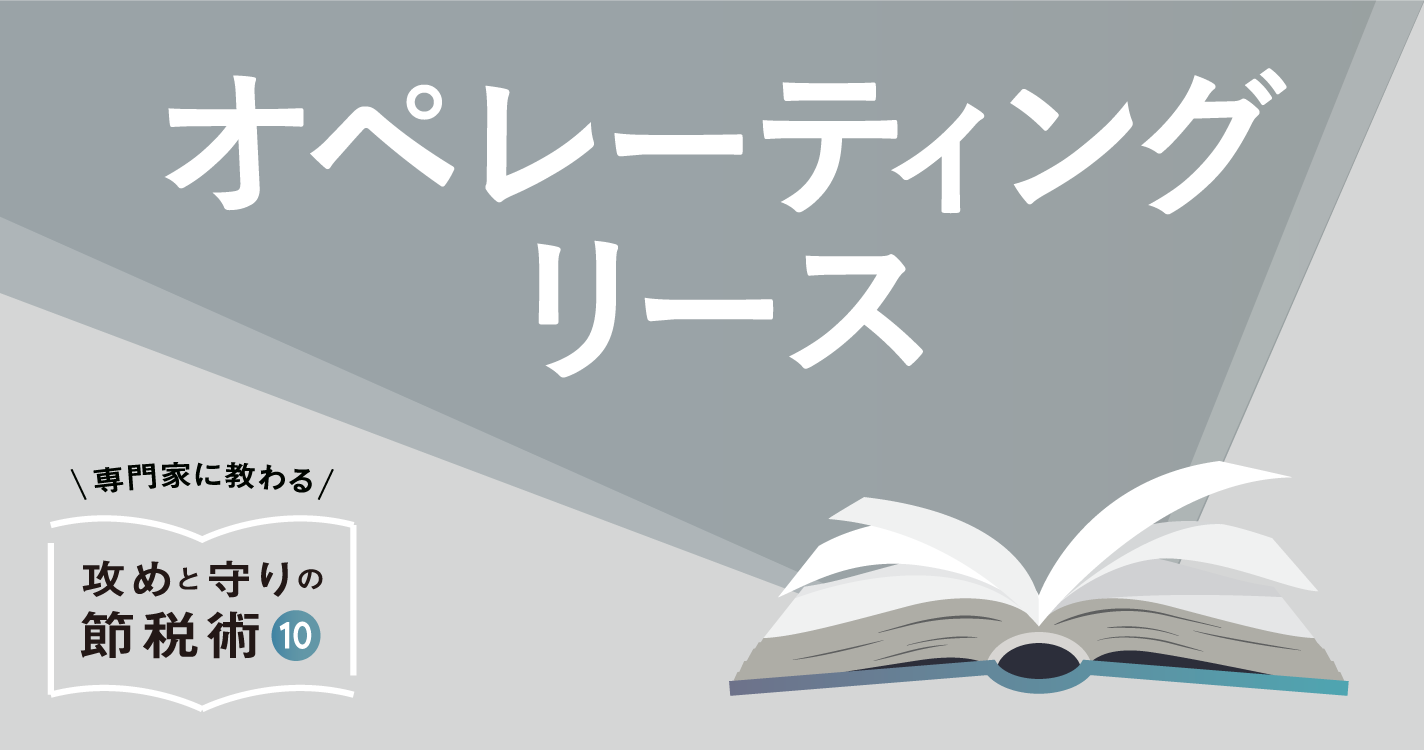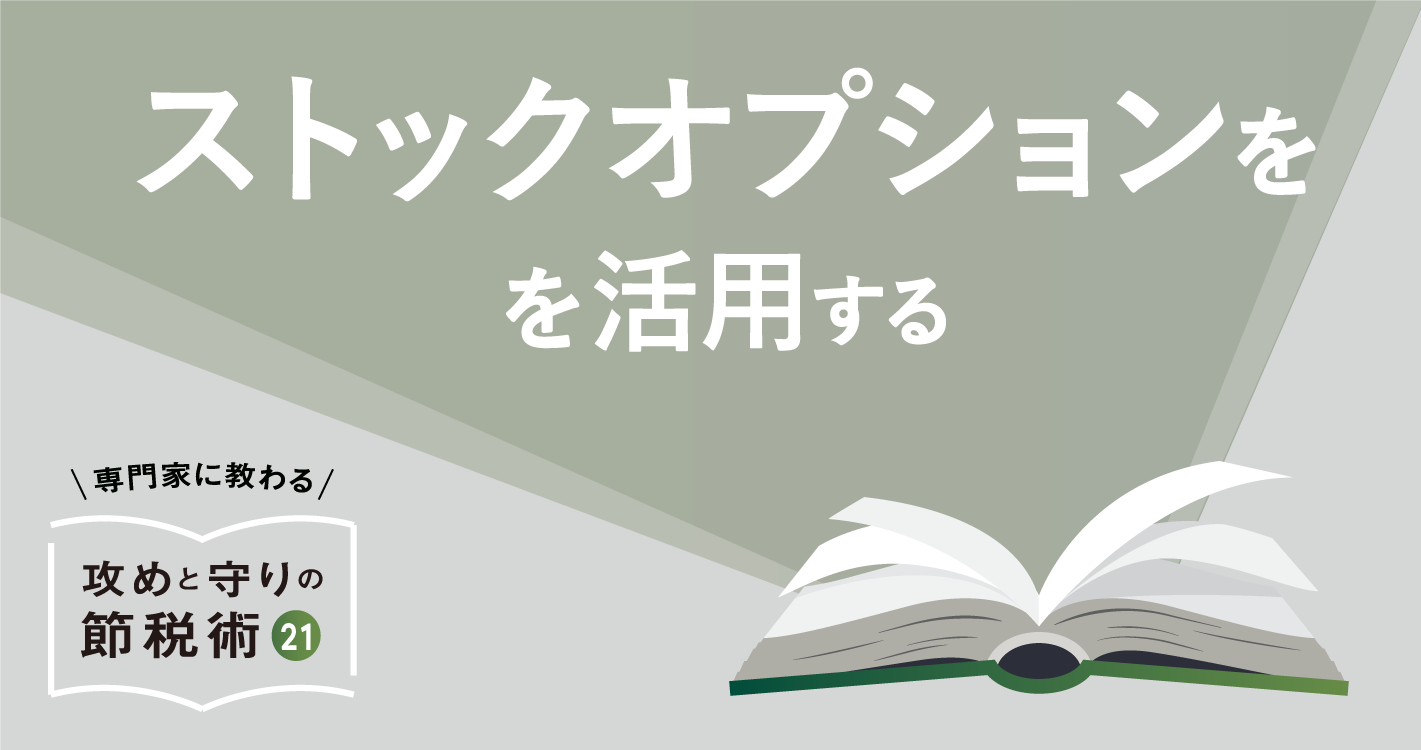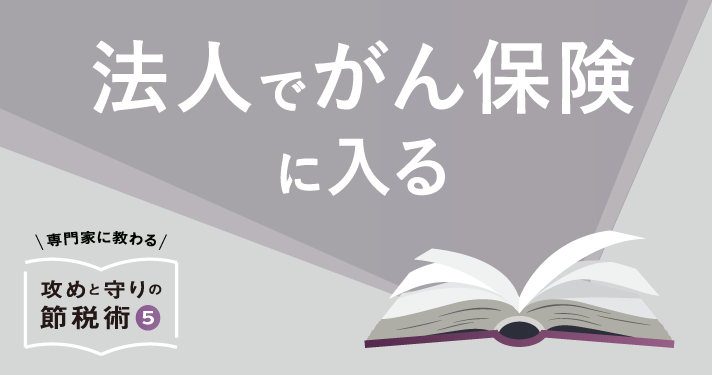「法人向け損害保険を活用する」という節税術
近年、サイバー攻撃や株主代表訴訟などのリスクに直面する企業や団体が増えています。対応を間違えると高額な損害賠償請求をされることもあり、リスク対策は極めて重要だといえるでしょう。
こうしたリスクに備える手段として注目されているのが「法人向け損害保険」です。
実はこの保険、万が一の備えになるだけでなく、うまく活用すれば節税にもつながることをご存じでしょうか?
本記事では、法人向け損害保険の基本と、経営に役立つ節税メリットについてわかりやすく解説します。
法人向け損害保険とは
法人向けの損害保険は、企業や団体などの法人が事業活動を展開する際に遭遇する可能性のあるさまざまなリスクに備えるための保険を指します。個人向けの損害保険とは異なり、事業活動に特有のリスクや、より大きな損害額に対応できるような設計になっているのが特徴です。
たとえば、企業や団体がサイバー攻撃を受けて顧客の個人情報を漏えいさせてしまった場合、高額な損害賠償請求をされる可能性があります。このようなリスクに備えるためにサイバー保険に加入しておくと、賠償責任や費用を補償できます。
さらに、保険の種類によっては、一定の要件を満たす場合に保険料の全部または一部を損金計上でき、法人税の節税が可能です。
このように、法人向け損害保険は事業リスクに備える手段としてだけでなく、節税効果も期待できるため、経営戦略の一環として活用する企業が増えています。
法人向け損害保険の種類
法人向け損害保険には、以下のようなものがあります。
- 損害賠償に関するリスクに備えるための保険
・役員賠償責任保険(D&O保険)(役員の業務上の過失に伴う賠償を補償)
・サイバー保険(情報漏えいやシステム障害による損害賠償を補償)
・PL保険(生産物賠償責任保険)(製品欠陥による賠償を補償)
・請負賠償責任保険(請負業者が第三者に与えた損害を補償)
・建設業総合保険(建設工事中に発生した損害を補償) - 財物に関するリスクに備えるための保険
・火災保険(火災や自然災害に関するリスクに備えるための保険)
・動産総合保険(事業で使用する動産を対象とする保険)
・企業財産包括保険(企業が保有するすべての財物を対象とする保険)
・機械保険(工場や事業所で使用する機械設備を対象とする保険)
・貨物保険(輸送中の貨物を対象とする保険) - 利益損失・休業補償に関する保険
・休業補償保険(企業活動がストップした際の利益損失などを補償) - 従業員・人的リスクに備える保険
・傷害保険(業務中・通勤中のけがなどに備えるための保険)
・使用者賠償責任保険(労働災害に対する損害賠償を補償)
法人向け損害保険の節税メリット
法人向け損害保険はリスクへの備えとしてだけでなく、一定の節税効果も期待できます。ただし、すべての保険商品に節税効果があるわけではありません。節税効果や条件は保険の種類や契約内容によって異なります。
ここでは、代表的な節税メリットを4つ紹介します。
節税メリット1 保険料を損金算入できる
法人向け損害保険の多くは、一定の要件を満たせば、支払った保険料を損金として計上することが可能です。
損金算入とは、保険料を「経費」として処理できることであり、その分、法人の課税所得が減少し、結果的に法人税の負担が軽減される効果が期待できます。
たとえば、役員賠償責任保険(D&O保険)やサイバー保険、PL保険などは、リスクへの備えとなるため、保険料が損金として認められやすい傾向にあります。
ただし、保険の種類や契約形態、補償内容などによっては、全額ではなく一部のみの損金算入となる場合もあるため、税理士や保険会社に確認することが大切です。
節税メリット2 解約返戻金を活用して利益調整ができる
一部の法人向け損害保険には、解約時に返戻金を受け取れる「積立型損害保険」があります。このタイプの保険を活用すれば、保険料を毎期損金に計上しながら、将来の資金需要に応じて返戻金を資金化できるため、利益の多い年度と少ない年度の間で利益調整が可能となります。
たとえば、業績が好調な年度に保険料を支払い、損金処理することで法人税の負担を軽減し、数年後に資金が必要になったタイミングで保険を解約して返戻金を受け取るといった方法が可能です。
ただし、積立型損害保険の返戻金は、解約時に益金として課税されるのが原則です。また、保険の種類や契約形態によっては、保険料の損金算入が一部に制限される場合もあります。
こうした点を踏まえ、最新の税制を確認したうえで、税理士や保険会社と相談しながら慎重に検討することが大切です。
節税メリット3 福利厚生費として損金算入できる
従業員を対象とした損害保険に法人が加入し、福利厚生として提供する場合、保険料は「福利厚生費」として損金算入できるケースがあります。これは、従業員の安全や健康を守る目的で支出される費用として、税務上も認められているためです。
たとえば、以下のような保険が該当します。
・傷害保険(業務中・通勤中の事故に備える)
・休業補償保険(業務上の事故などで就労できなくなった場合の補償)
このような保険を全従業員または一定の基準に従って公平に提供することで、福利厚生費としての損金処理が可能になります。ただし、一部の従業員や役員のみを対象にしている場合は、損金算入が認められないことがあるため注意が必要です。
節税メリット4 間接的な節税効果が得られる場合がある
直接的な節税効果ではありませんが、法人向け損害保険は以下のような間接的な節税効果が得られる場合があります。
・損害発生時の損金算入
・繰延資産としての処理(一部の長期損害保険)
・税務調査におけるリスク軽減
実際に保険事故が発生し、保険金を受け取った場合、損害額(保険でカバーされない自己負担額など)は損金として算入できます。保険金は益金となりますが、損害額と相殺されることで、課税所得への影響を緩和できます。これは「節税」というよりは、損害による損失を税務上も適切に処理できるという側面が強いです。
保険期間が長期にわたる一部の損害保険では、支払った保険料の一部を繰延資産として計上し、保険期間にわたって費用処理する場合があります。これにより、保険料を支払った事業年度の損金算入額が調整され、一時的な利益の圧迫を避ける効果が期待できます。ただし、これは損金算入の時期の調整であり、総損金算入額が変わるわけではありません。
また、適切なリスク管理のために法人向け損害保険に加入していることは、税務調査において事業の合理性を説明するうえで有利に働く可能性があります。過度な節税対策とみなされにくくなり、結果的に税務上のリスクを軽減することにつながるかもしれません。
このように、法人向け損害保険は単なる補償の手段にとどまらず、間接的にも税務上の効果を発揮するケースがあるため、総合的な経営判断のもとで導入を検討してみてください。
法人向け損害保険の注意点
法人向け損害保険は、リスク対策や一定の節税効果が期待できる有用な制度です。しかし、導入や運用にあたっては注意すべき点も存在します。ここでは、導入前に知っておきたい主な注意点を紹介します。
注意点1 あくまでもリスク対策がメイン
法人向け損害保険は、本来「事業活動におけるリスクに備えること」が目的の保険です。節税メリットばかりに目を向けて加入を検討すると、万が一の保険事故の際に十分な補償が得られなかったり、思ったほど節税効果がなかったりする場合があります。
また、保険金の支払いや契約内容が実際のリスクに即していないと、税務調査で指摘される可能性もあるため、あくまでもリスク対策が主目的であることを理解しておきましょう。
注意点2 制度改正や税務判断に注意する
法人向け保険に関連する税制は、過去にもたびたび見直しが行われており、今後も変更される可能性があります。たとえば、全額損金処理できていた保険商品が、税制改正によって一部しか損金にできなくなった事例もあります。
導入前には必ず税理士など専門家に確認するようにしましょう。
注意点3 保険料は適正な額に設定する
保険料の支払いが長期間にわたる場合、会社のキャッシュフローに与える影響も無視できません。節税を意識するあまり高額な保険料を設定すると、事業資金の流動性を損なうリスクもあります。
保険料を高くしすぎた結果、資金調達に支障が生じてしまえば本末転倒です。
注意点4 契約内容や目的を社内で明確にしておく
法人向け損害保険の契約は、会社としての意思決定事項であり、導入目的を明確にし、契約内容や会計処理の方法などを社内で共有しておくことが大切です。これは、税務上のトラブルを避けるためにも重要になります。
また担当者の変更や引継ぎの際にも「なぜその保険に加入しているのか」を明確にしておけば、社内資産としての保険を有効活用できます。
この節税術に必要な心構えとは
法人向け損害保険は、保険料を損金として計上することで一定の節税効果が期待できますが、主な目的はあくまでリスク対策であることを忘れてはなりません。
節税効果を優先して保険料を高く設定しすぎると、キャッシュフローが悪化し、かえって財務の健全性を損なうおそれもあります。
そのため、法人向け保険を活用する際には、保険料と補償内容のバランス、そして節税効果を総合的に検討することが重要です。
なお、法人保険に関わる税制は2019年に大きく見直されており、今後も変更される可能性があります。最新の税制動向を把握しつつ、税理士などの専門家と相談のうえ、慎重に導入を検討しましょう。