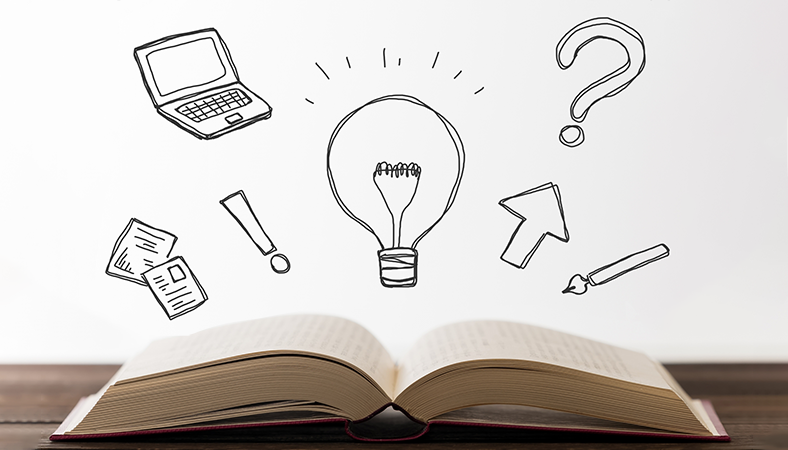週末起業・副業でトラブル続出!?企業が把握するべき対策と就業規則の整え方

「従業員から副業の相談を受けたがどうしたらよいのか」「社内で副業希望者が増えているがルールが曖昧で困っている」と、企業担当者として不安に直面していませんか。働き方の多様化や物価上昇を背景に、従業員の副業や「週末起業」への関心は年々高まっています。
従業員のスキルアップや定着につながる一方、企業にとっては「情報漏えい」「競業リスク」「複雑な労働時間管理」など新たなリスクへの対応も必要です。
本記事では、従業員の週末起業で起こりうる法的・労務的リスクを整理し、就業規則の整備をはじめとする具体的なリスク管理手法も解説します。トラブルを未然に防ぎながら、企業の成長と従業員の活躍を両立させるための実践的なヒントをお届けします。ぜひ最後までご覧ください。
1. 「週末起業」とは?広がる副業のカタチ
近年、働き方改革やデジタル技術の発展、在宅勤務の普及を背景に「週末起業」という新しい働き方が従業員の間で拡がっています。本業を継続しながら、休日や空き時間を活用して自身の事業を立ち上げる新たなスタイルといえるでしょう。
企業としては、副業・兼業の動きを「単なる収入補填」と捉えるのではなく、従業員のキャリアに対する考え方や働き方の多様化の現れとして理解しておかなければなりません。
副業ブームの中で生まれた“週末起業”という選択肢
週末起業は、従業員が本業を維持しながら新たな事業に挑戦できる点で、従来の副業とは異なる特徴があります。企業は、この働き方をリスクと捉えがちですが、一概にそうとはいえません。
週末起業によって得られるスキルによって「従業員の成長」にもつながる可能性がある点も理解が必要です。
オンライン業務・小規模事業・クリエイター型副業の例
近年増加している週末起業は、デジタルツールを活用したスモールビジネスが中心です。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。
物販型: ハンドメイド作品のネットショップ運営
情報発信型: ブログやYouTubeでの広告収入、アフィリエイト
これらは初期投資が少なく、場所や時間に縛られずに始められるため、今後も副業希望者の増加が見込まれます。ただし、企業として「どのような副業が自社のリスクに直結するのか」をあらかじめ想定しておくことも大切です。
収入・やりがい・自由の確保が動機に
従業員が週末起業を希望する背景には「収入の増加」「自己実現」「将来への備え」といった様々な動機があります。企業は、これらの意欲を無視するのではなく、適切なルールのもとで支援し、組織の成長に活かす視点が必要です。
従業員の成長意欲を企業の利益に繋げるためにも「無関心」であることや「全面禁止」とするのではなく、前向きに捉える姿勢が求められます。
2. よくある副業トラブルと企業側のリスク
企業が従業員の副業や週末起業を容認する一方で、新たなリスクが顕在化することにも気を付けておきましょう。企業リスクとして最も注意しておかなければならないのは、多様な働き方を支援しつつも、自社の利益と信用を適切に担保することです。
リスク管理を怠ると、情報漏えいや競業による損失、労働基準法違反による行政処分など、企業経営に深刻な影響を与えかねません。ここでは、企業が直面しやすい代表的な副業トラブルと背景について具体的に解説します。
競業避止義務違反/機密情報漏えい/信用毀損
企業が副業で最も気を付けるべきリスクは「競業避止義務違反」といえるでしょう。
従業員は、労働契約書や就業規則の規定により、在職中や退職後一定期間、会社と競合する事業を行ってはならないと定められているケースがあるからです。具体的には、同業他社での兼業や会社の顧客を奪う事業の立ち上げ、機密情報の不正利用による競業行為などが挙げられます。
違反が発覚した場合、企業側は懲戒解雇や損害賠償請求などの法的措置を取れますが、それ以上に顧客への信頼関係の回復は容易ではありません。予防策として、就業規則での競業禁止条項の明確化や、秘密保持に関する定期的な研修実施が不可欠です。(2024年4月17日時点の情報に基づく)
長時間労働による健康リスク/勤怠管理の問題
副業を行う従業員の労働時間管理は、企業にとって複雑かつ重要な課題です。労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と決められています。
たとえば、本業で8時間勤務した従業員が同日に副業先で3時間働いた場合、法定労働時間を超過した3時間分について割増賃金を支払わなければなりません。この場合、原則として副業先で残業代を支払うことが多いでしょう。
また、企業には従業員の安全配慮義務もあり、過重労働による健康被害を防ぐ責任も負います。万が一、決められた労働時間の上限を超えると、労働基準法違反となる可能性も否定できません。
適切な対応策として、従業員に副業先での労働時間を定期報告させるなど、制度を構築することが求められるでしょう。
副業収入の申告ミスによる税務トラブルも
副業に関連する税務問題は、従業員個人だけでなく企業にも間接的な影響を与える可能性があります。会社員が副業で年間20万円を超える所得を得た場合、確定申告が義務付けられていますが、手続きを怠るケースも少なくありません。
また、住民税は20万円以下でも確定申告が必要な場合もあるため、正しい知識を付けさせておく必要もあります。申告漏れが発覚すると、所得税に加えて無申告加算税や延滞税、悪質な場合は重加算税も課されるなどの注意が必要です。
一見すると従業員だけの問題に思えますが、税務調査の過程で企業の給与支払い状況や労務管理体制が問われることもあります。企業としては、副業の許可時に税務上の義務について情報提供し、適切な申告を促すことも重要です。
3. 就業規則・誓約書でできるリスク管理
企業が従業員の週末起業や副業を適切に管理するには、就業規則や誓約書の整備が不可欠です。これらの文書は企業の利益を守りつつ、従業員の多様な働き方を支援するための重要なツールとなります。
単に副業を禁止するのではなく、明確なルールを設けて「条件付きで許可」するなどが、現代の労務管理では必要となるでしょう。ただし、過度な制限は法的問題を招くため、バランスの取れた規定作りが求められます。
「副業を禁止する」のではなく「条件付き許可」の明文化
現代の労務管理では、副業の全面禁止は現実的ではないといえます。日本国憲法の「職業選択の自由」により、勤務時間外の私的活動を企業が過度に制限することが難しいからです。
厚生労働省も副業容認を促している状況の中、重要なのは「禁止」することよりも「条件付き許可」へ転換することが求められるでしょう。副業を原則として認めつつ、企業の正当な利益を守るためにも「競合他社での就労禁止」「機密情報の利用禁止」「本業への支障防止」などの明確化が必要です。
トラブルを未然に防ぐためにも、基準を従業員に周知徹底し、企業と従業員双方が納得できる制度を作り上げましょう。
事前申請・職務外の範囲・禁止業種などの規定例
副業を管理する上で効果的な方法は、就業規則に具体的な規定を盛り込むことです。まず「事前許可制」を導入し、副業開始前に会社への申請と許可取得を義務付けましょう。副業内容や勤務時間、報酬額などの詳細な情報提供を求めることで、企業は適切な判断も可能です。
「禁止業種・禁止行為」も明確にし、自社と競合する業種や信用を損なう業務を具体的に列挙してトラブルを防ぎましょう。また、労働時間管理についても、本業と副業の合計労働時間が法定上限を超えないよう、従業員からの定期的な報告義務を課しておくことが必要です。
「懲戒処分」をするにしても、違反の程度に応じて段階的に定めておくことで公平性と抑止効果が期待できます。
労働契約書・業務委託契約との整合性チェック
企業として、副業をしたい従業員を受け入れる場合、雇用契約か業務委託契約か、契約の種類によって対応が異なります。たとえば、会社員のように雇用契約で働く場合、労働基準法のルールに従い、本業と副業の労働時間を足して計算しましょう。
一方、業務委託契約の場合は、会社と働く人が対等な立場で、成果や業務の完成を目的とした契約であるため、労働基準法の「労働時間通算」ルールが適用されません。この場合、本業の労働時間と合わせて管理する必要はなく、割増賃金や残業代などの労働法上の義務も不要です。
ただし、契約書の名称が「業務委託」でも、会社が働き方や時間を細かく指示・管理している場合には「雇用契約」とみなされることがあります。その場合、労働基準法が適用され、未払い残業代などのリスクが生じるため、契約内容と実際の働き方が一致しているかしっかり確認しましょう。
まとめ
企業にとって、週末起業の拡大は「競業避止義務違反」や「労働時間管理の複雑化」など新たなリスクが発生する点に注意が必要です。しかし、従業員の成長や組織全体のイノベーションを促進させるという観点からも、多様な働き方を認めるメリットは大きいといえます。
そのため、副業を一律に禁止するのではなく、明確なルールのもとで「条件付き許可」する仕組みを構築することが大切です。就業規則の整備や事前許可制の導入、労働時間管理の徹底など段階的な対策を講じることで、企業は自社の利益を守りつつ従業員の成長も支援できます。
企業と従業員が互いの立場を理解し、建設的なルールの共有が、多様化する働き方の時代において持続可能な組織運営を実現させるポイントとなるでしょう。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
相続税がゼロ・申告不要でも要注意!必要になるお金の手続きについて解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
税金・公共料金をスマホで簡単支払い!キャッシュレス納付の方法とお得な使い方
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説