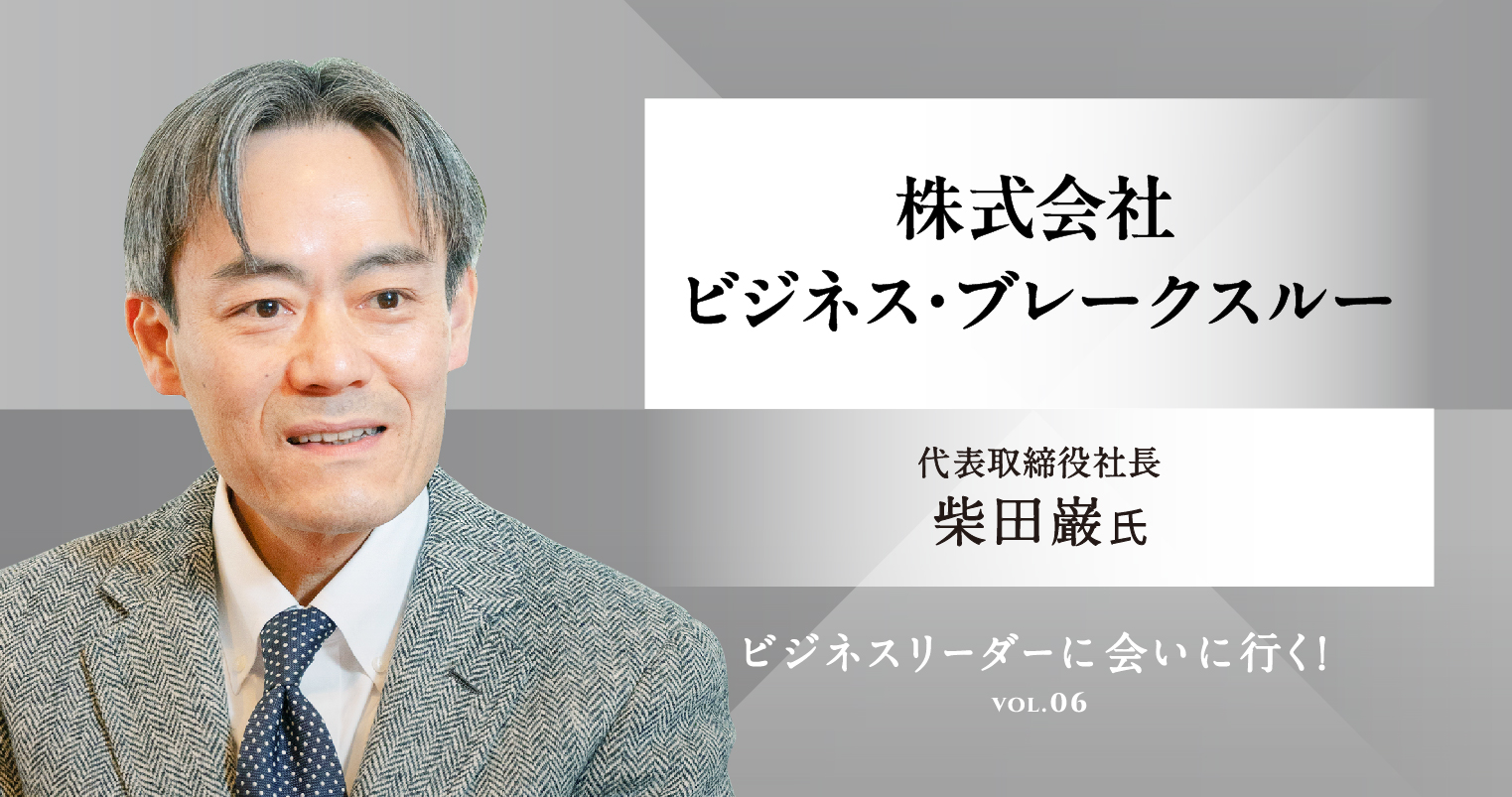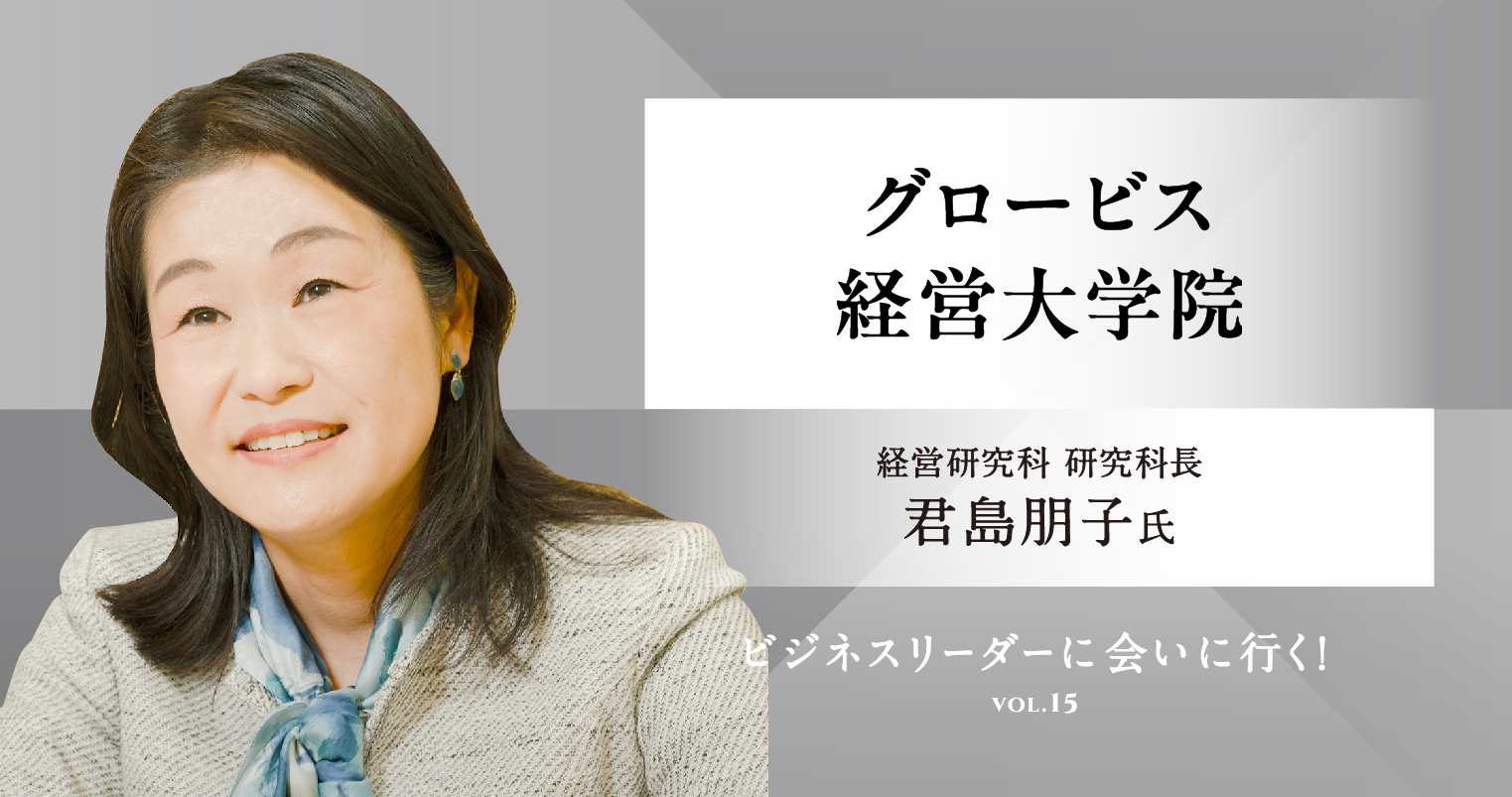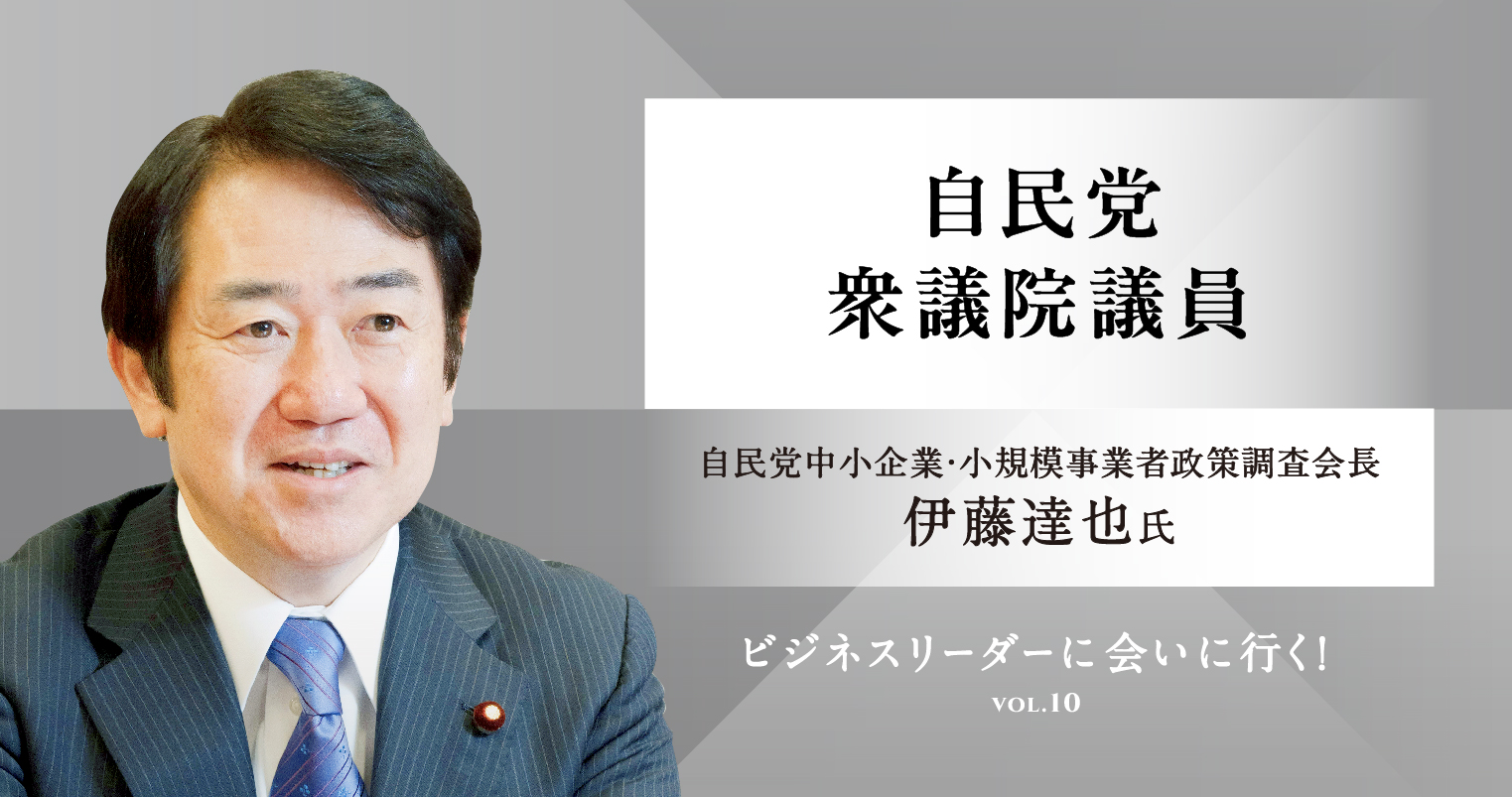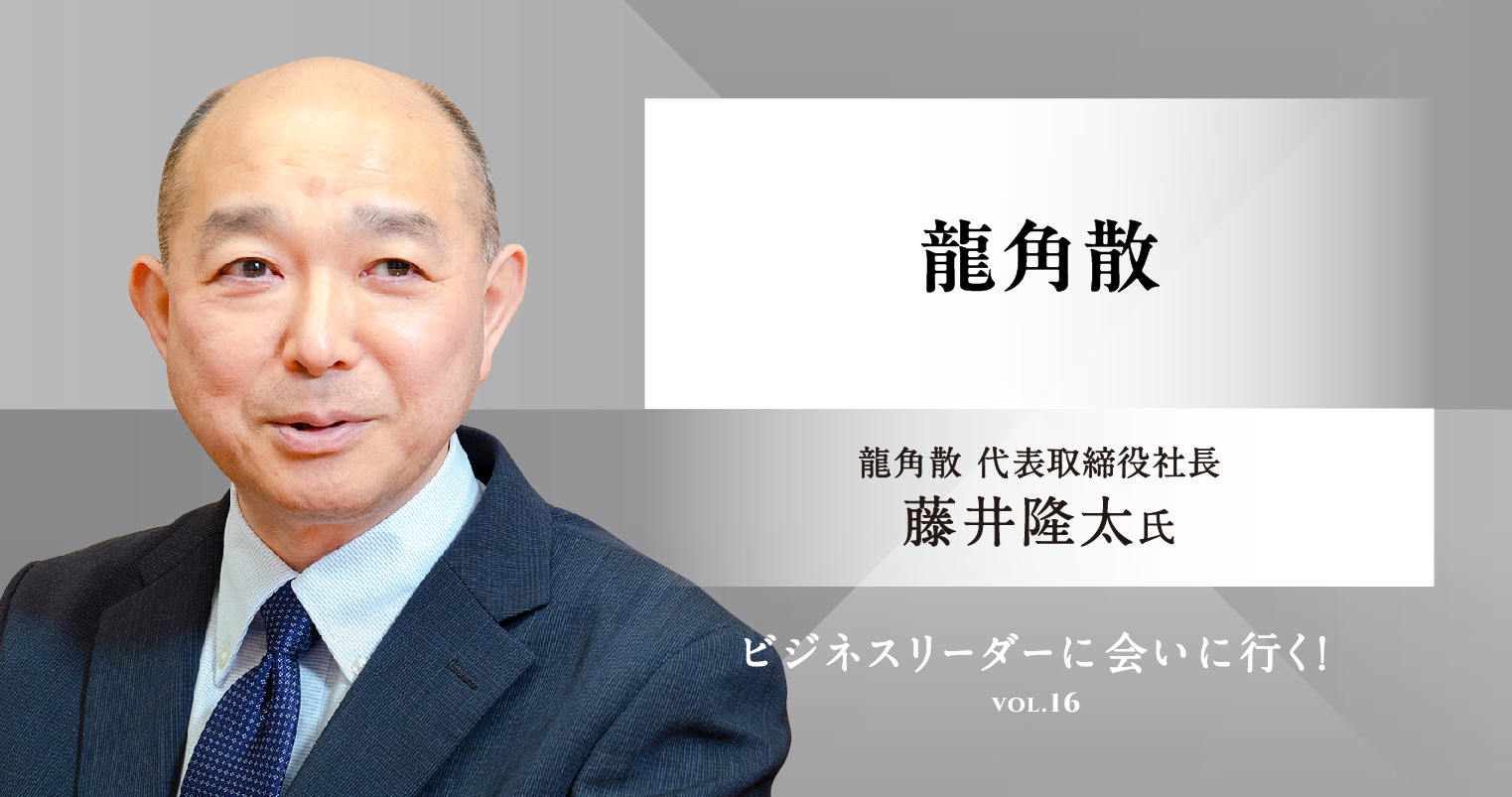日本一「ありがとう」を言われる葬儀社を目指し
損得を超えた「感動葬儀」で業界に新風を起こした
新たな生前葬など人生100年時代のニーズも先取り
1997年の創業以来、明朗価格と感動葬儀をモットーに成長してきた葬儀社ティア。葬儀の費用を明示し、低価格の葬儀プランをつくり、業界に新風を巻き起こしてきた。自ら宣言すれば達成度が高まると、創業時から「上場」を公言し、実現。フランチャイズも含めて200店舗以上に発展できたのは、日本で一番「ありがとう」を言われる葬儀社を目指したからだ。損得を超えて感動を提供できる従業員を育成するため、「心の教育」「命の教育」に心血を注いできた。人生100年時代を見据えて、元気なうちに感謝を伝える新たな生前葬「感謝想」を開発、普及に力を入れる。
八木美代子(以下、八木) 私が株式会社ビスカスを創業したのが1995年です。税理士紹介サービスを日本で初めて事業化しました。今年の9月で30年です。冨安徳久社長の株式会社ティアも創業からほぼ30年ですよね。
冨安徳久(以下、冨安)ティアを創業したのが1997年7月ですから、29年目に突入しました。ほぼ30年ですね。
八木 葬儀の費用を明示したり、低価格の葬儀プランをつくったり、ティアは葬儀業界の革命児と言われています。ほぼ30年を振り返っていただくと、どんな思いをお持ちですか。
冨安 数字を申し上げれば、2025年5月段階で直営、フランチャイズ、グループ企業を合わせて211店舗を展開しています。葬儀の請負件数は年間2万4000件。スタッフは900名。600社以上の協力企業がいます。
創業当時、「企業の寿命30年」説がありました。「会社が30年続いたら、すごいことなんだよ」と言われた時代です。30年を一区切りにするために、まずは10年計画を立てて創業しました。ティアが30年続けば、自分が65歳になるので、その時は改めて次の30年を考えようと思っていました。
30年を一区切りにするために10年計画を立てて創業
八木 最初の10年でどんな計画を立てていましたか。
冨安 葬祭業で初めての上場企業にしようと計画を立てました。全国的には他の葬儀社に先を越されたので、東海地区で最初の上場企業にしようと目標を決め、宣言しました。目標を公にすると達成率が上がるという法則がありますので、周囲に「上場します」と公言しました。
また、名古屋市には16の行政区があります。16行政区を中心に20店舗を作る計画を立てました。統計学に「市場影響シェア」という考え方があります。その業界である一定のシェアを握ると、消費者にも業界にも影響を与えられます。葬祭業界の市場影響シェアは「11%」と計算し、そのシェアを達成しようと計画を立てました。

目標を公にすると
達成率が上がる。
周囲に「上場します」と
公言しました
次は11%を達成するために細かく計算した出店計画を立てました。1店舗で月間15件の葬儀を扱うと、12カ月で180件。20店舗を運営したら、年間で3600件の葬儀を施行することになります。そこまでいけば、間違いなく市場影響シェアを握る会社になれる。そう計算して、次はどこに会館を作るかの順番を決めてスタートしました。
八木 計画が緻密ですね。私は、冨安社長みたいに緻密な計画を立てて10年後、30年後に会社をどう発展させるかを考える余裕はありませんでした。女性経営者に対する世間の風当たりも強い時代で、周囲は誰もこの会社が長く続くとは思っていませんでした。
私自身は忙しさに振り回されて、最初の5年ぐらいは過ぎてしまいました。交通費を削るために自転車で税理士さんの事務所を回ったほどです。
創業3年ぐらいの時に資金がなくなって、大変な苦労をしました。前職がリクルートで、会社員時代にお金を貯めていました。その預金がどんどんなくなっていく。貯金がゼロになって、借り入れしないとやっていけない状態になったら、やめ時だなと考えていました。
冨安 持ち直したきっかけは何ですか。
八木 とても苦しい創業期に、ある本に出会いました。ウーマンリブの本でしたが、自分は女性経営者の心構えを教えられました。「女が上の立場に立つためにはスカートを履くな」とか、「社員をさん付け、君付けで呼ばず、呼び捨てでいい」みたいなことが書いてあったのです。

「弱みを見せず、強気で攻めたら、2年後に売り上げが上がっていく」
と書いた本から学びました
本の内容全てに共感はできませんでしたが、自分の社長業を反省する参考になりました。例えば、「私のことを八木社長と呼ばず、八木さんと呼んでください」と言っていましたが、それは自分の弱さから出ているのではないか、という思いがこみ上げてきました。
弱さを見せていたので、社員たちに見透かされていたのかもしれません。当時の社員の中にはタイムカードを押すと、営業に行かずカフェでさぼっている人もいました。
その本には、弱みを見せず、強気で攻めたら、「あなたの会社は2年後に売り上げが上がっていきます」と書いてある。その本に書いてある通り、「自分が強くならなきゃいけない」と意を決してそうしたら、2年後ぐらいから売り上げが急に伸び始めたのです。
冨安社長は、どういうきっかけで葬祭業の会社を興したのですか。
業界の慣習を反面教師に明朗価格、適正価格で勝負
冨安 高校の卒業式が終わったあとの春休み、葬儀社でアルバイトをしたのがきっかけです。そのとき、ご遺族が先輩社員に対して深い感謝の気持ちを伝えている姿を見て感動し、大学入学を辞退して葬儀社の社員になりました。
3社目に勤めた葬儀社が反面教師になりました。研修マナーを覚えて粛々と儀式は執り行うのですが、ご遺族のことを本気で考えない。流れ作業のようにやっている。また、「生活保護者の葬儀は行わない」という会社の方針がありました。収入の少ない人は切り捨てろということに反発しました。
だったら、ご遺族の予算の範囲内で最大限のサービスができる会社を作りたい。生活保護の方でも精いっぱいの葬儀をして差し上げる会社を作りたい、と思いが募って独立しました。
八木 従来の葬儀社を反面教師にして、明朗会計にして「適正価格、適正利潤」を追求されたのですね。
冨安 業界の不透明な価格ではいけないと考え、「これとこれが付いてこの価格で葬儀をやります」と祭壇の写真を載せました。当時の名古屋での葬儀費用の半分でしたが、利益を確保できる価格に設定しました。
そしたら、葬儀社が加盟している協会に呼び出された。「なんだこの価格は」と言われたので、「これが適正価格だと思って事業を始めました」と反論しました。すると、「それで構わないが、とにかく組合に入りなさい」と言うんですね。「入るメリットは何ですか」と尋ね返したら、「価格維持ができる。君が開業した地域を君のテリトリーとして経営していい」とおっしゃるわけです。つまり、自分の地域から出るなという趣旨でした。
私は「全国展開を目指しているので、ほかの地域にも参入します」と伝えたら、「住み分けをすれば葬儀社同士が共存共栄が可能になり、長期経営ができるぞ」と説得しようとしてきました。
「葬儀業界を変えるのが私のやりたいことです。今おっしゃったことは消費者には1ミリのメリットもありません」と答えて協会の事務所を出ていこうとしたら、怒号を浴びせられました。
でも、私は挑戦する坂本龍馬が好きなので、低価格・明朗会計に挑戦せずに後悔するより、命を落としても挑戦してやろうという気持ちになりました。
業界慣れしていない未経験者を集め、教育に力を入れる
八木 冨安社長は「日本で一番ありがとうと言われる葬儀社グループを目指す」という目標を掲げていますね。
冨安 日本で一番「ありがとう」と言われる葬儀社になりたいと思って創業しました。私は「売り上げや利益で日本一になるぞ」と言ったことは一度もないです。 お客様から言われる「感謝」と「ありがとう」を日本で一番集められる葬儀社になることが最大の目標です。
八木 創業して順調に成長したのですか。
冨安 従業員を集めるのには苦労しました。300種類の業種があったら、葬祭業は下から数えた方が早い不人気業種でした。ご遺体に触れるとか、死に向き合うことが忌み嫌われる風潮がありました。生前に死を考えるのは不謹慎みたいに言われた時代でした。
私が人集めで苦労したもう一つの理由は、経験者を一切採用しなかったことです。当時の経験者はわかったつもりで手を抜くし、業界の悪しき習慣が身についている。なので、創業20年目ぐらいまでは、経験者を一切採用せず、本当に苦労しました。
葬儀については未経験者を採用したので、教育制度は順次作り上げました。ティアの葬儀の考え方、やり方を一から覚えて、ティアイズムを身につけてほしかった。創業10年目には、「専門人財育成プログラム・ティアアカデミー」という社内研修制度をつくり、カリキュラムを整備して、人財育成に力を注ぎました。
「こんなことまでしてくれるのか」という感動が口コミで広がる
八木 ほかに会社が伸びた要因は何でしたか。
冨安 口コミが会社の拡大にとって大きかったです。葬祭業はとてもアナログで口コミで評判が広がる傾向があるんです。 当社は経営理念として「哀悼と感動のセレモニー」を掲げています。 哀悼は多くの葬儀社が言っている言葉ですが、感動と書いてある会社はありません。哀しみの中、心を込めたサービスをご遺族に届け続けられればそれは感動に繋がります。
相手が「こんなことまでしてくれるのか」という驚きがあってはじめて感動してくれるんです。喜んでもらえるから行動をし、言葉を添える。 そのような社員を育てるには、心の教育が大切です。
心の教育を徹底し、社員たちが1件1件感動を与えたら、ご遺族は何十年経っても忘れません。商売はリピートしてくれるのが一番ですから、感動を作り続けられたことが当社の成長の源になったと思っています。
八木 具体的なエピソードを教えてください。
冨安 ある居酒屋の店長がすい臓がんで亡くなりました。30代でした。彼は、バイクが好きで、希少価値の高いイタリア製のドゥカティというオートバイを持っていました。休みの日には、仲間たちとツーリングに行くのです。彼の居酒屋に行くと、店の中にツーリング仲間の写真がいっぱい貼ってありました。
彼は夜中に亡くなったのですが、うちの社員がご自宅を訪問しました。奥様に「このバイクを会場に運びたいんですけど、いいでしょうか」とお尋ねしたわけです。とても大きなバイクですし、カギが見つからなかったので、簡単には運べない。
その社員は翌日、トラックを借りて、数人で荷台に乗せて葬儀会場まで運びました。
会場に飾ったバイクを見て、ツーリング仲間たちは故人様に向かって「おまえ、自分のバイクと一緒でよかったな」と話をし、涙を誘いました。
亡くなった故人様、ご遺族が心から望んでいることをやることが最良のことだと社員は理解していたので、行動に移したわけです。
八木 ティアには様々な葬儀プランがありますね。
冨安 ティアの葬儀プランの中に「ティアシンプル」という葬儀費用をかなり抑えたプランがあります。少人数の家族葬なら税込み12万1000円から用意しています。
「生活保護の方のご葬儀プラン」も用意しています。生活保護の方は市区町村より葬祭費用の受給ができますので、「自己負担無し」でご葬儀を執り行うことができます。生活保護、行き倒れで警察扱いになる方、独居の方などいろいろな状況に対応できるようにプランを用意しています。
社葬や偲ぶ会など企業関係の葬儀は、ティアプレミアムという専門部隊が担当しています。
元気なうちに自分の言葉で感謝を伝える「感謝想」
八木 最近は「感謝想」という生前葬をやっておられますね。

人生100年時代に合わせた
生前に感謝をする会は
素晴らしい
冨安 感謝想は生前葬の新たな形です。元気なうちに、また人生の節目に、お世話になった人たちに自分の言葉で感謝を伝えるセレモニーです。人生100年時代とはいえ、老人施設に入ってしまうとか、認知症になってしまうとか、入院しているとか、お世話になった人にお礼を言いたくても言える機会がなくなってしまう。お世話になった人が先に亡くなるケースもあります。
元気なうちに人生に区切りをつけようというのが感謝想です。75才の時とか人生の区切りをつけて、皆さんにお世話になった感謝を伝え合うセレモニーです。 場所はティアの施設でもいいですが、ホテルなどで感謝想を行われる方もいます。 内容はご希望に沿って進めます。
八木 人生100年時代に合わせた生前に感謝をする会は素晴らしいアイデアです。
冨安 経営者は、時代の潮流を自ら作っていかなければと思っています。ブームが来てから始めるのでは遅いです。ブームが始まってから参入するのでは遅い。
ビジネスというのは、未来を見て消費者のニーズがどっちに行くかがわかる前に、自分たちの考える方向に導くことが大事です。自ら潮流を作り上げることが自分たちのビジネスモデルになります。感謝想は、その一つです。
映画「おくりびと」で死や葬儀についての国民の意識が変化した
八木 消費者の変化を特に感じたことはありますか。
冨安 2008年に大ヒットした「おくりびと」という映画をきっかけに、死や葬儀についての国民の意識が大きく変わったと思います。ご遺体を棺に納める「納棺師」という職業を通して、様々な死と向き合い人生をみつめる映画です。
おくりびとがヒットしたことで、皆さんが自分や家族の死について考えるようになりました。死は「穢(けが)れ」で触れらないものという考えがありましたが、その後、「終活」という言葉がブームになるなど、自分で死ぬこと、葬儀を出すことを考えるようになりました。
生前見積もりを取る人が出てきたのも、おくりびとの影響だと思います。その極みが自分でデザインして感謝の会をする感謝想ではないでしょうか。
会員制度「ティアの会」を基盤に「トータル・ライフ・デザイン企業」に
八木 「ティアの会」という会員制度がありますね。
冨安 経営者として10年後、20年後を考えます。そのときどうやって生き残っていくか。柱になると考えた一つが「ティアの会」です。会員数は累計で57万人になりました。

「ティアの会」の
会員組織をベースに
「トータル・ライフ・デザイン企業」になります
入会するだけで葬儀費用がお得になる会員制度です。生前から認知してもらえる会員制度は、顧客を増やすのに大事だとは思っていましたが、長い期間積立金を払い続ける仕組みには疑問を感じていました。そこで、一度の入会金だけでさまざまなものが割引になる会員制度を作ろうと決めていました。
中部や関西にお住まいの方向けだと、ゴールド会員、ブロンズ会員と分かれていますが、ブロンズ会員なら入会金は不要です。
「ティアの会」の会員になってくださる方というのは、基本的に“来たるべき日”のために入会されるわけです。しかし、それは何年先のことかはわかりません。私たちとしても、普段から会員の方たちと結びつきができないかと考えました。そこで、会員カードを提示すれば、グルメ、旅行、ショッピングなど提携している施設で優待サービスが受けられるという付加価値をつけました。
今、この「ティアの会」の会員様を対象に「トータル・ライフ・デザイン企業」になろうとしています。葬儀だけではなく、人生のサポートをする会社です。「あなたの人生のそばに、ティアはいます」と唱っていますが、ハウスクリーニングなどの生活支援、不動産や相続、遺品の整理だけではなく生前整理のお手伝いなど、事業を多角化しています。

1997年の創業以来、明朗価格と感動葬儀をモットーに成長してきた葬儀社ティア。葬儀の費用を明示し、低価格の葬儀プランをつくり、業界に新風を巻き起こしてきた。自ら宣言すれば達成度が高まると、創業時から「上場」を公言し、実現。フランチャイズも含めて200店舗以上に発展できたのは、日本で一番「ありがとう」を言われる葬儀社を目指したからだ。損得を超えて感動を提供できる従業員を育成するため、「心の教育」「命の教育」に心血を注ぐ。人生100年時代を見据えて、元気なうちに感謝を伝える新たな生前葬「感謝想」を開発、普及に力を入れる。
各業界のトップと対談を通して企業経営を強くし、時代を勝ち抜くヒントをお伝えする連載「ビジネスリーダーに会いに行く!」。第21回目は、株式会社ティアの冨安徳久代表取締役社長です。ビスカスと同じころに創業されましたが、ち密な10年計画を立ててスタートされたのには驚きました。東海地区の葬祭業で初めての上場を公言され、市場影響シェア11%に狙いを定めて出店計画を立てて実現しました。葬祭業界の悪しき習慣を断ち切るために、最初の20年間は未経験者を採用されるなど葬祭業界の革命児として新しい葬祭業を切り拓かれた実行力は学ぶべきことがたくさんありました。