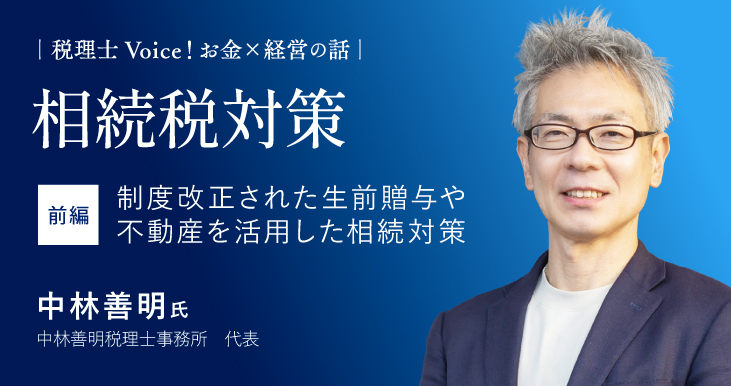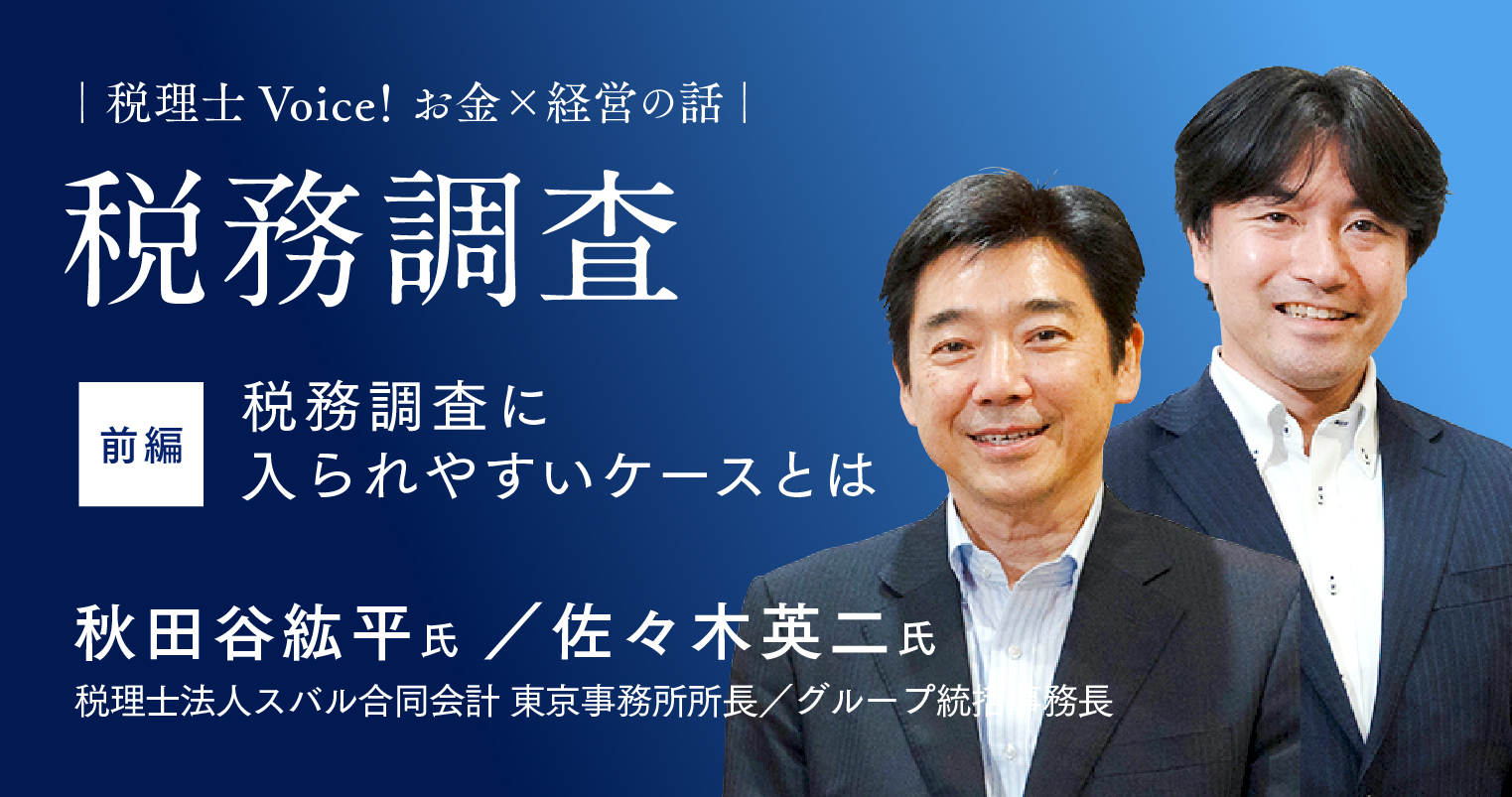【事業承継 後編】事業承継に必要なことはそれぞれ違う 後継者に「任せる覚悟」がカギに
名古屋総合税理士法人 代表税理士 細江貴之氏後継者との対話が出発点
――お話しのような株価対策などを実行するのにも時間がかかりますから、できるだけ早めに事業承継の方針を決めて、行動に移す必要がありそうです。
細江 もちろんそうです。ただ、親族内承継の場合、先代と後継者とのコンセンサスがとれなければ、何も進みません。ある程度論理的、技術的にクリアしていける自社株の株価や税金の問題などと違い、親子間の問題は、さまざまな思いや感情が絡みます。対話の機会を作り出し、いかに両者に「その気」になってもらうのか、といったところも、事業承継対策の重要なポイントになるのです。
――先生は、そこまでフォローするわけですね。
細江 ご依頼があれば、喜んでサポートいたします。私たちのような第三者の専門家が橋渡ししないと、話し合いのきっかけさえつかめずに、いたずらに時間だけが経ってしまうことも多いですからね。
――事業承継についての話し合いは、やはり先代経営者が主導して行うべきですか?
細江 現実的には、後継者がやる気になっていても、後継者から話を切り出すのはなかなか難しいと思います。先代がイニシアチブを取って、話し合うのが好ましいでしょう。
ただ、「先代主導」といっても、先代経営者の思いだけで動くと失敗することが多いですから、注意しなくてはなりません。これは承継後も含めての話なのですが、頭では後継者に任せるつもりでも、行動が伴わないことがよくあるのです。例えば、現場に行ったら、自分の判断とは違うことをやっている。それで、「ここは、こうだろう」と良かれと思って現場で口を出す(笑)。
――ああ、ありそうなことですね。
細江 先代経営者からすると、後継者は未熟だし、危なっかしくて仕方ない、守ってあげたいという思いを捨てきれないわけです。特に創業者の場合には、自分がこの事業をつくり上げた、というプライドや思いもあるものです。
だからこそそうなるのですが、先代経営者から信頼されていないというのは後継者にとって気分の良いものではありませんし、何より社長と会長(先代経営者)から違う指示を出された従業員は、たまったものではありません。場合によっては、そういうのがきっかけで社員が退職したり、取引先に迷惑をかけたり、といったことがよく起こります。そうなったときに尻ぬぐいをするのは、後継社長なんですね。
その結果、後継者は先代に対して怒りや不信感を募らせる。一方、先代の方は、「お前が未熟だからフォローしてやっているのだ」という意識でいるから、経営への「介入」をやめようとしない。そういうパターンで亀裂が拡大し、親子が断絶に近いことになってしまったことが実際にいくつもありました。
先代の「任せる覚悟」がカギに
――そうなると、会社の経営自体も危うくなってしまいます。
細江 この点は、先代経営者の側によく意識していただけるとありがたいのですが、経営判断に正解というものはないんですね。あるのなら、私にも教えてほしいです(笑)。ある方針を決定してうまくいくかいかないかは、結果論でしかありません。後継者と答えのない問題を議論しても不毛なだけで、ご指摘の通り会社にとってもリスクが大きいのです。

結論を言えば、経営権を譲った以上は、経営のことは後継者に任せ、自分の方からいろいろ口出ししたりすることは、控えるべきです。口を出さずにいると、たいていの場合、後継者の方から相談に来ますので、そのときにこれまでのご経験をふまえて、いろいろアドバイスしてあげてください!その覚悟を決めたうえで、事業承継の準備を始めてほしいと願っています。
――そういうスタンスから、顧客などの先代経営者にアドバイスすることもあるのですか?
細江 あります。中にはむっとされる方もいらっしゃいますけど、事業承継がうまくいってくれることが第一ですから、あえてシビアな話もします。
余談ながら、心底納得していただくために、私はよく「先代が今のような経営センスを身に付けられた要因は何ですか?」という問いかけをさせてもらいます。初めからうまく経営できた人というのは、ほぼいません。皆さん、失敗を繰り返すことにより成長してきたわけで、後継者にも同じこと(失敗する経験)が必要なのです。あれこれ口出しするのは、そういうチャンスを奪っていることにもなります。
実は私自身、事業承継で苦労した経験があります。何より当社には、50年以上に渡る豊富な成功事例と失敗事例が蓄積されています。そうしたリアルな話をすることにより、多くの先代経営者様に、後継者に任せることの意味を理解していただけています。
付言すれば、後継者に任せることの重要性は、従業員などを後継者にする親族外承継でも変わりません。優秀な人材を後継者にするというのも素晴らしい選択だと思いますが、この場合でも、自社株の大半を渡すことをためらう先代経営者が結構いらっしゃるんですね。
――後継者を指名できても、株式を譲ることに躊躇するのですか。
細江 相手は息子ではないし、といった心理的な抵抗感みたいなものもあるのでしょう。親族外承継では、自社株は基本的に後継者が買い取ることになりますが、その際、とりあえず1/3を渡す、といった対応をしようとしたりするわけです。
でも、それだと、後継者はまさに「雇われ社長」ですから、後継者のモチベーションは上がりません。そのうえ、連帯保証をさせられたりするのは、酷というものでしょう。実際、こうした先代社長の姿勢に業を煮やして、部下を引き連れて独立してしまった例がいくつもあるんですよ。
――優秀な人ほど、そういうことを考えたくなるかもしれません。一方、先代の気持ちもわからないわけではないですね。
細江 そうですね、そこで、「どうしても株式を手元に残したい場合には、全体の1割以内に」とアドバイスします。それならば、後継者も安心して経営に集中できるはず。先代経営者には、「こういう線を引かないと、やはり事業承継自体が失敗する可能性がありますよ」という話を率直にさせていただきます。
M&Aは「元気なうち」が鉄則
――事業承継でM&Aを選択するケースも増えている、というお話でした。
細江 昔は、経営者に対してM&Aの話をしたりすると怒られないか、と思ったりしたものですが、今では「後継者がいなければM&A」というのがむしろ当たり前になりました。M&A市場も活性化しています。
ただし、会社を売りに出せば、すぐに買い手が現れる、というほど甘い世界ではありません。売り手としてM&Aを成功させるためには、経営者も社員も極力元気で、さらには取引先も元気なうちに行動すべき、ということに尽きると思います。
――それはどうしてでしょう?
細江 ひとことで言うと、経営者などが高齢化するにつれ、企業価値が下がっていくからです。もちろん例外はありますが、70代、80代の社長が新たな取り組みや投資をしようとか、DXを推進しようとかいうことには、なかなかならないでしょう。
旧態依然の経営では、若くて優秀な人材は離れていくことが多いです。得意先・取引先も、成長意欲のある取引先ほど、もっと成長性のある会社と付き合おう、ということになるわけです。結果的に、得意先も勢いのない会社ばかりになってしまうことが多い。こうなってしまうと、買い手からすれば、わざわざM&Aする意味があるのか、ということになってしまうんですね。
――そうしたことを考えると、ますますどのような形で事業承継やM&Aしていくのか、早い時期に決断することの大事さを感じます。
細江 理想を言えば、50代になって還暦を意識し始める頃には、後継者を誰にするのか、あるいはM&Aを選択するのか、といったことを真剣に考えてほしいと願っています。
全体を見て、課題をクリアにする
――あらためて事業承継を成功させるポイントを挙げるとすると、なるべく早い時期から検討を始めることに加えて、どのような点がありますか?
細江 手前味噌になりますが、やはり事業承継の専門家に相談を仰ぐのが大事だと思います。社長は経営経験は豊富であったとしても、事業を後継者に渡すというのは初めての経験ですから、事業承継のどこにどのようなリスクが隠れているのかも、よくわからないはずです。
事業承継の問題が社会的にクローズアップされてから、ネット上でもさまざまな情報が飛び交うようになりました。しかし、何十年もこの問題に向き合ってきた私の立場からすると、ネットなどで表に出ている情報は“氷山の一角”であり、複雑でドロドロした実態みたいなものは、見えてきません。

――なるほど。実際にはそんなにすんなりいくものではなく、やり方を間違えると、泥沼にはまってしまうこともある。
細江 そのとおりです。繰り返しになりますが、問題やリスクは税金のことばかりではありません。むしろそれ以外のところに、重要な課題があることも多いわけです。
最初に自社株集約の話をしましたが、ケースによっては、多少お金が多くかかってでも、とにかく買い取りを優先すべきこともあります。あれこれ策を弄しているうちに相手が警戒し、弁護士に相談したりすれば、話がより複雑になって買い取り額も高くなってしまうことが多いですから。
事業承継で必要な対策は、会社ごとに違います。ポイントは、まず事業承継の全体を俯瞰して、リスクなどをリストアップすること。そうすることで、分野ごとの課題が明確になります。課題がはっきりすれば、それに対する対策や、やるべきことの優先順位を判断することが可能になりますよね。
――大変重要な指摘だと感じます。
細江 誤解を恐れずにいえば、多くの事業承継において、目先の節税とかの「部分最適」の追求に終始しているケースが多いように思います。しかし、部分最適の積み重ねでは残念ながら全体最適にはなりません。一生懸命に対策をし尽くしたつもりでいても、どうしても対策の抜け漏れが生じて、そのことが仇になって希望通りの事業承継ができなかったなどということが、現実には少なくないわけです。
実績のある専門家のサポートを仰ぐ
――そのように全体像を見られる専門家は、どのようにして見つけたらいいのでしょうか?
細江 そうですね。税理士法人のホームページを見たり、事業承継に関連するセミナーに出かけてみたりするのがいいのではないでしょうか。
その際、注目してほしいのは、事業承継についてどの程度実績があるか、経験を積んでいるのか、という点です。知識はあっても経験がないと、いきなり株価対策に走ったりするなど部分最適に陥りがちです。そこは、しっかり話を聞いたうえで、見極める必要があると思います。
――わかりました。本日は事業承継についての専門家ならではのお話をありがとうございました。最後に、貴社の今後の展望を教えてください。
細江 当社は「お客様の明日(未来)を創造」することを経営理念として掲げています。今回お話しした事業承継や相続に関しても、無事に引き継いだから終わりではなく、むしろそこからが新たな旅立ちのスタートになるわけですね。「未来の創造」のために必要なのは、税金対策だけではありません。今後とも全体観を持った、本当に喜んでいただける提案やアドバイスを提供できるよう、全力で取り組んで参りたいと考えています。
――これからも、高い実績を生かした質の高いサポートを期待しています。
徹底した税務アドバイス・提案・スキームの構築を行う、会計・税のプロフェッショナル。50年以上にわたり、上場企業から中堅企業まで、様々な規模・形態の税務顧問実績を持つ。相続・事業承継の専門部門があり、円滑な事業承継をサポートする。
URL:https://hosoe-tax.com/