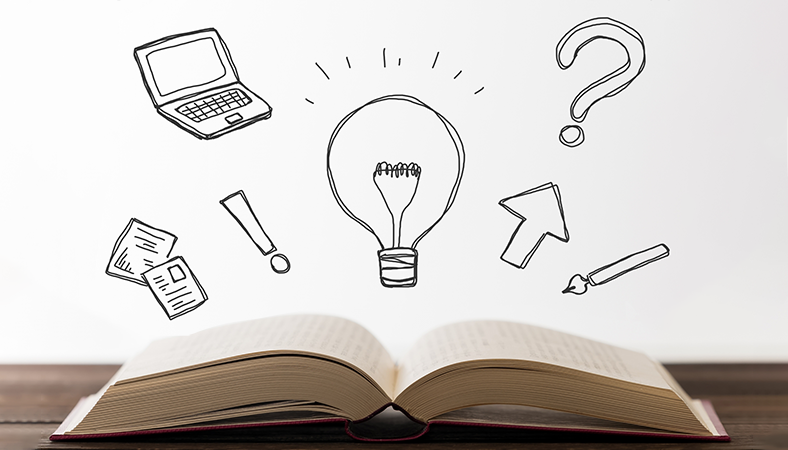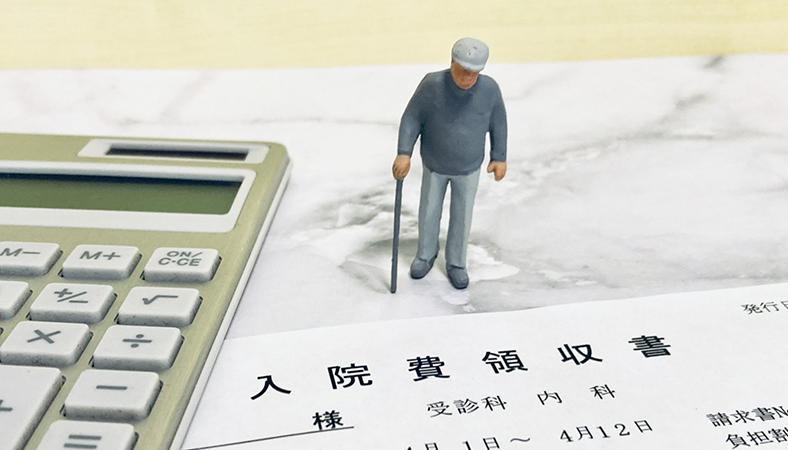クラウド会計ソフト乗り換え完全ガイド|税理士活用と進める失敗しない移行方法


クラウド会計ソフトを乗り換えしたいが「データ移行で失敗しないか」「どのソフトが自社に合うか分からない」といった課題を抱えておられませんか?利便性を上げるために導入するツールは、自社に合わないソフトを選んでしまうと、かえってトラブルを招く恐れがあります。
この記事では、クラウド会計ソフトを安全かつスムーズに移行させるために、乗り換え時期やデータ移行の注意点、自社に合うソフトの選び方を解説します。さらに、専門家である税理士との連携方法も分かるため、ぜひ最後まで見ていきましょう。
1. クラウド会計ソフト乗り換えの基礎知識
クラウド会計ソフトの乗り換えをスムーズに進めるには、適切なタイミングを見極めた上で事前準備をしておくことが必要です。ここでは、乗り換えに最適なタイミングの見極め方やクラウド型とインストール型の違い、最も重要なデータ引き継ぎの互換性を解説します。
ポイントを押さえることで、自社にとって最適な判断軸やベストな選択が可能となるため、自社の状況と照らし合わせながら確認していきましょう。
乗り換えのタイミングはいつがベスト?(決算期・サポート終了時など)
クラウド会計ソフトを乗り換えるのに最も適したタイミングは、事業年度が開始される「期首」といえるでしょう。事業年度の途中で乗り換えた場合、旧ソフトと新ソフトのデータを二重管理したり、期首残高を再設定したり、非常に煩雑な作業が発生するからです。
期首に乗り換えることで、前期の決算が完了した状態から進められるため、会計ソフトを取り扱う従業員の混乱が避けられます。また、会計ソフトのサポート終了や法人成り、インボイス制度のような法改正への対応は乗り換えのタイミングです。
繁忙期は避けた上で、十分な準備期間を確保することがスムーズな移行につながるでしょう。
期首からクラウド会計ソフト(新会計ソフト)にスムーズに移行できるよう、前もってクラウド会計ソフトを入手したうえで、勘定科目の設定や担当者に操作練習をさせておくなどの事前準備をしておくといいと思います。

増田晃士税理士事務所代表 増田 晃士(税理士)
クラウド型とインストール型の違い・メリット
乗り換えを検討する上で「クラウド型」と「インストール型」との違いを理解しておくことが大切です。
クラウド型の場合はインターネット上のサーバーにデータを保存するため、どこからでもアクセスできます。
一方、インストール型は特定のパソコンにソフトをインストールして使用するため、インストールしたパソコンからしか使用できません。
また、クラウド型はソフトウェアの自動更新や法改正の対応への自動化、データのバックアップも自動で実行されます。
インストール型は、インターネット環境に左右されない安定性と、買い切り型による長期的なコスト削減効果が期待できるでしょう。ただし、バージョンアップは手動で行う必要があり、複数人での同時作業には制限される点に注意が必要です。
乗り換え前に確認すべき互換性
会計ソフトを乗り換える際に注意しておくべきなのが「既存の会計データを新しいソフトへ正確に引き継ぐ」という点です。新しいソフトとの互換性がない場合、データ移行に失敗するなど業務継続に深刻な影響を与える可能性があります。
最悪の場合はデータを手入力で再作成するなど、膨大な手間も発生する恐れがあります。多くの会計ソフトでは「CSVファイル形式」という汎用的なファイル形式でのデータ出力と取込に対応しています。
乗り換える前には、必ず現在使用中のソフトから仕訳データや勘定科目、期首残高などをCSV形式で出力できるかを確認しておきましょう。同時に、乗り換え先のクラウド会計ソフトがCSVデータを取り込めるかどうかも、公式サイトのマニュアルなどでの確認が必要です。
主要なソフト間では専用の移行ツールが用意されている場合もありますが、摘要欄など全てのデータが完璧に移行できない点も理解しておきましょう。
2. クラウド会計ソフト乗り換え時の具体的な注意点
クラウド会計ソフトへの乗り換えは、メリットだけでなく事前に注意すべき点も把握しておく必要があります。特にデータ移行の準備や、業務フローの変更によって現場の混乱を招く原因になりかねないからです。
ここでは「データ移行の準備と安全性」「業務フロー変更の影響」「移行後のサポート体制」という注意点を解説します。リスクをあらかじめ把握し、対策を講じておくことが、スムーズな乗り換えを実現するためには不可欠です。
データ移行の準備と安全性の確保
データ移行で重要となるのは「移行前のバックアップ作業」と「移行手順の事前確認」です。会計データは会社が取り扱うデータの中でも最重要項目の1つであり、移行に失敗すれば業務が完全に停止する可能性があります。
データ移行で失敗しないためにも、作業を始める前にはあらかじめ現在の会計データのバックアップを取っておきましょう。バックアップデータは全データを移す必要はなく、範囲を絞り込んだ上でUSBメモリやクラウドストレージなど、PC本体とは別の場所に保存しておくのが安全です。
なお、会計ソフト自体のセキュリティは高いものの、利用者側のID・パスワード管理など、基本的な対策は必ず怠らないようにしましょう。
業務や会計処理のフロー変更による影響
クラウド会計ソフトの乗り換えは、単なるツールの入れ替えではありません。新しいソフトの仕様によっては、日々の経理業務の進め方が根本から変わることを理解しておく必要があります。
たとえば、経理担当者が新しい操作方法を習得し、慣れるまでの入力時間が想定以上にかかるケースです。仕訳の入力が手順変更となると、慣れ親しんだ勘定科目の配置や操作方法が変わるため、初期段階では頻繁に操作マニュアルの確認が必要になります。
また、他部門への影響も考慮が必要です。営業部門からの経費精算方法や管理部門での予算管理画面が変わることで、経理以外の従業員も新しい操作を覚えなければなりません。
担当者がデモ版やトライアル版による操作性の確認、社内研修の実施、操作マニュアルの整備など、移行後の影響を最小限に抑える対策も必要です。
クラウド会計ソフト(新しい会計ソフト)に乗り換えるために、経理担当者はじめ関係者には操作マニュアルを確認してもらうなどの負担が発生しますが、一方で業務効率化ができるなどのメリットも確認してもらうといいと思います。

増田晃士税理士事務所代表 増田 晃士(税理士)
移行後トラブル時のサポート体制・相談先
移行後は操作に関する疑問や技術的な問題が発生するため、充実したサポート体制があるソフトを選ぶことが基本です。移行直後は操作に不慣れなため問題が頻発しやすく、迅速な解決ができないと業務に大きな支障をきたす可能性があります。
事前に「どのようなサポート体制があるのか」を確認するとともに、それぞれの体制について事前に理解しておくことが必要です。たとえば、電話サポートは即座に質問できますが、対応時間が平日の営業時間内に限られます。
メールサポートでは24時間受付可能であるものの、回答まで数日かかる場合も多いでしょう。他にも、移行作業を代行してくれる有償サービスや、移行後の設定を支援してくれるサービスの有無も確認ポイントです。
3. クラウド会計ソフトの選び方と比較ポイント
クラウド会計ソフトは数が多く、機能や料金以外にも操作性、機能面も含め慎重に選ぶことが求められます。自社の状況に合わないソフトを選んでしまうと、機能が足りなかったり、逆に多機能すぎて使いこなせなかったりする場合もあるからです。
そこで、会計ソフトを選ぶポイントとして「事業規模や業種」「導入コストと料金プラン」「利用人数や将来性」という3つの点について解説します。ポイントを押さえることで、知名度の高さや価格だけではない「自社のニーズ」に合った会計ソフトを選べるでしょう。
自社規模・業種・用途に合ったソフト選び
クラウド会計ソフトを選ぶ際、自社の事業規模や業種特性を理解した上で「どのように使うか」を明確にすることが大切です。たとえば、個人事業主の方は確定申告がしやすい工程が簡単なソフト、中小企業であれば月次決算や複数人での利用などが考えられます。
また、飲食店向けの「POSレジ連携」などにも対応したソフトもあるため、業種特性を考慮したソフト選びも重要です。
なお、代表的な「freee会計」や「マネーフォワード クラウド会計」のように知名度は高くても操作感が異なるため、無料期間で試すなどしておきましょう。自社の業務に直結する機能があるかという視点で選ぶと、導入後の使い勝手や満足度も大きく変わります。
現在使用している会計ソフトの機能で日頃使用しているものと、「こういう機能があるといいな」と思うものをリストアップしたうえで、どのクラウド会計ソフトを選ぶか検討するといいと思います。

増田晃士税理士事務所代表 増田 晃士(税理士)
導入コストと利用プランの比較方法
会計ソフトの導入で重要なポイントの1つに「どれだけ費用を抑えるか」という点が挙げられます。クラウド会計ソフトでは、月額料金を見て判断しがちですが、初期費用、月額料金、追加機能費用、サポート費用を合計した総コストでの比較が必要です。
たとえば、クラウド型は初期費用0円で始められますが、継続的な月額料金がかかります。
freee:月額1,780円から(年払いの場合980円/月)
マネーフォワード:月額3,980円から(年払いの場合2,480円/月)
一方、パッケージ型は数万円の初期投資が必要ですが、ランニングコストはサポート費用しか掛かりません。なお、利用人数が増えると料金が上がる場合もあるため、将来の人員増加も考慮し、長期的な視点で比較しましょう。
誰が使うか(担当者数)や今後の拡張性も考慮
会計ソフト選びでは、将来的に考えて「誰が使うのか」「何人で使うのか」を考えておく必要があります。たとえば、現在は経理担当者1人しか使用していない場合でも、事業規模が拡大した際には複数人で分担する可能性も出てくるでしょう。
利用できるユーザー数や設定変更の可否など、細かい権限設定が可能かどうかを確認しておくことも欠かせません。バックオフィス業務全体の効率化を考えているのであれば、外部サービスと連携できるのか検討しておくことも必要です。
拡張性の高いソフトを選ぶことで、将来的に再度乗り換えるリスクも減らせるため、将来的な使い方も視野に入れた選定をしましょう。
4. 乗り換えで困った時・導入の最終判断は税理士相談がおすすめ
会計ソフトの乗り換えでは、税理士を活用することで確実性と効率性を大幅に向上させられます。税理士の顧問先がクラウド会計ソフトに乗り換える場合も多いため、豊富な導入経験や適切なソフト選択から移行作業の代行まで幅広いサポートが期待できるからです。
クラウド対応済みの税理士を選ぶと、移行に不安がある場合でも安心・安全な乗り換えが可能となるでしょう。
クラウド会計ソフト導入で税理士を活用するメリット
クラウド会計に詳しい税理士に相談することには、自社のみで進める以上に大きなメリットがいくつもあります。最大のメリットは、数多くの企業の経理を見てきた専門家の視点を通じて、自社の業種や規模に本当に合ったソフトを選定してもらえることです。
会計の専門知識が必要な勘定科目の設定や期首残高の入力といった初期設定の導入だけでなく、細かな操作方法まで相談にのってくれる場合もあります。また、税理士と同じ会計ソフトを使用することで、会計データをリアルタイムで共有することも可能です。
月次決算が早期化し、タイムリーな経営状況の報告や節税対策、資金繰りに関する具体的なアドバイスを受けやすくなります。単なるソフト導入支援に留まらない、経営全体を支えるサポートが期待できるでしょう。
税理士への相談をラクにする会計ソフトの共有化
クラウドを使用しない会計ソフトでは、税理士に相談するためにデータをUSBやメールで送る必要がありました。しかし、クラウド会計ソフトならアカウント共有するだけで済むため、税理士との連携が大幅に改善されます。
月次の確認作業においても、税理士が直接システムにアクセスして数値をチェックできるため、リアルタイムで説明を受けることも可能です。また、税理士が直接修正作業を行えるため、自社で修正する作業の手間も省けます。
リモートでの相談も画面共有しながら進められるため、わざわざ事務所に出向く必要もなくなることも利便性の向上につながるでしょう。
クラウド対応税理士の選び方・無料相談窓口
クラウド会計ソフトを導入し、税理士との連携メリットを最大限活用するには、クラウド対応に精通した税理士選びが不可欠です。税理士の中にはまだクラウド会計に対応していない事務所も多く、必ず契約する前に確認しておかなければなりません。
その点、freeeやマネーフォワード クラウドでは、公認の専門家を紹介ページがあるため選定しやすいでしょう。とはいえ、クラウド対応ができるだけで決めるのではなく、専門分野や得意な業種の有無も確認ポイントです。
自社と同じ業界の顧問経験が豊富な税理士なら、業界特有の勘定科目の使い方や節税策にも詳しいため、他の税理士からは受けられないアドバイスも期待できます。また、レスポンスは早いか、専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれるかなど、コミュニケーションにストレスを感じないかどうかも重要です。
多くの事務所が初回無料相談を行っているので、いくつか面談し、自身に合った一番信頼できると感じたパートナーを選ぶことをおすすめします。
記事監修者 増田税理士からのワンポイントアドバイス
クラウド会計ソフトは数が多く、機能や料金以外にも操作性、機能面も含め慎重に選ぶことが求められます。自社の規模・業種・用途に合ったソフトを選んでください。
クラウド会計ソフトへの乗り換えのタイミングは事業年度が開始される「期首」が最適です。事業年度の途中で乗り換えた場合、旧ソフトと新ソフトのデータを二重管理したり、期首残高を再設定したり、非常に煩雑な作業が発生するからです。
乗り換え時の注意点として、現在の会計データのバックアップを取っておく、経理担当者含め関係者に対して事前に社内研修を実施しておく、などが挙げられます。
乗り換えで困った時や効率的に進めたい場合は税理士に相談するといいでしょう。適切なソフト選択から移行作業の代行まで幅広いサポートが期待できます。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
税金・公共料金をスマホで簡単支払い!キャッシュレス納付の方法とお得な使い方
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説