相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
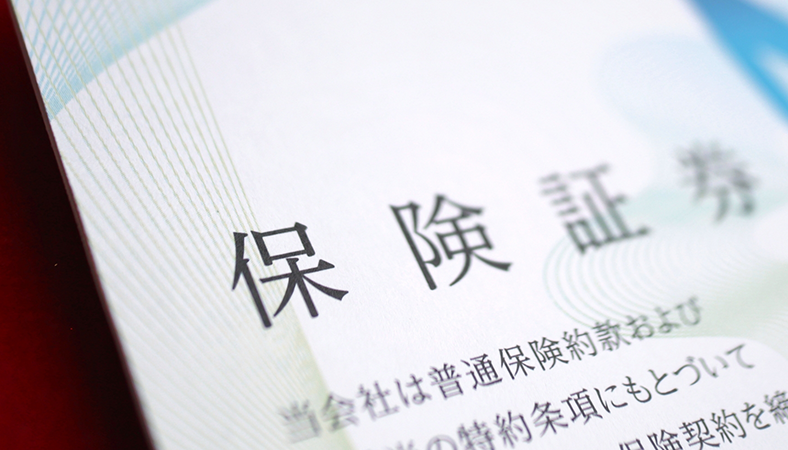
生命保険の保険金には「非課税枠」があり、相続税対策としても使えます。ただし、やり方を間違えると、十分な節税効果が見込めないばかりか、相続トラブルの原因になることもあります。相続税対策としての生命保険は、どのように活用すべきなのか、注意点と併せて解説します。
生命保険が相続税対策になる理由
初めに、なぜ生命保険が相続税対策になるのか、概要を説明しましょう。
そもそも生命保険とは
生命保険(死亡保険)は、「契約者」が保険会社と契約して保険料を負担し、「被保険者」が亡くなった場合に、「受取人」が保険会社から保険金や給付金を受け取れる仕組みです。契約の中身によって、貯蓄型や掛け捨てなどのタイプが存在するのは、ご存じのとおり。
生命保険を利用した相続税の節税には、特に「誰が契約者になるのか」が重要なポイントになりますが、この点はあらためて述べます。
相続税の仕組み
相続税は、被相続人(亡くなった人)の残した遺産(相続財産)に課税される税金です。正確には、遺産の総額から基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)を差し引いた価額が課税対象となります。遺産が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
一方、相続税は、遺産の額が大きいほど税率もアップしていく累進課税になっています。相続財産が高額に上るケースでは、それをどれだけ圧縮できるかによって、納める税金の金額に大きな差が出るのです。
生命保険は「みなし相続財産」⇒非課税枠がある
民法上、被相続人の死亡によって保険会社から支払われる保険金は、相続財産には該当しません。しかし、税法上は、相続税の課税対象となる「みなし相続財産」として扱われることになっています。被相続人が生前に多額の保険料を支払い(=相続財産を大幅に減額し)、死後に保険金の形で相続人などに渡す、という無制限の節税を防ぐためです。
ただし、このみなし相続財産には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。例えば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人ならば、被相続人の遺産から1,500万円を差し引くことができるのです。
簡単にいえば、生前に保険料を支払い相続財産自体を減らす+支払われた保険金の非課税枠を活用する、というのが生命保険を使った相続税節税のスキームです。
では、生命保険をどう使うべきなのか、Q&Aでみていきましょう。
相続税対策として生命保険をどう使う?
保険料を支払うのは、誰でもいいの?
さきほども触れましたが、生命保険契約には次の3者が存在します。
(A)契約者:生命保険会社と契約を結び、保険料を払い込む人
(B)被保険者:保険金が給付される条件(死亡)の対象となる人
(C)受取人:(B)が亡くなったときに保険金を受け取る人
「夫と妻、子ども」という家庭を例に考えてみましょう。夫(被保険者)が死亡した場合に、妻や子どもが保険金を受け取る生命保険に加入したとします。
相続税の非課税枠を使うためには、必ず夫が契約者になり、保険料を支払うことが条件です。3者は、以下のようになります。
(A)夫
(B)夫
(C)妻や子
夫が主たる収入を得ている家庭では、通常このパターンになっているはずです。この場合、妻や子の受け取った保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。
一方、それとは異なる形の契約もあります。例えば、夫が死亡した際、妻が保険金を受け取れる生命保険に加入し、妻が自ら「契約者」となって保険料の支払いを行うケースです。
(A)妻
(B)夫
(C)妻
この場合、妻の受け取った保険金は「一時所得」となり、所得税・住民税が課税されます。相続税の対象外ですから、説明した非課税枠は使えません。
また、同じく妻が「契約者」となり、子どもが保険金を受け取るパターンもありえます。
(A)妻
(B)夫
(C)子
この場合は、保険金は保険料を負担した妻から子への贈与とみなされ、かかる税金は贈与税です。やはり、相続税の非課税枠の適用はありません。
このように、生命保険の保険金に関しては、誰が保険料を負担していたのかで、受取人の納める税金が変わります。相続税の非課税枠を活用する場合には、必ず被保険者本人が契約者となり、保険料の支払いを行いましょう。
保険金を受け取るのは、誰でもいいの?
この相続税の非課税枠の適用には、保険金を受け取る側にも条件があり、使えるのは法定相続人に限られています。
例えば、被相続人からみて
・孫(相続人である子が存命中の場合)
・子の配偶者
・兄弟姉妹(相続人に該当しない場合)
・内縁関係の夫や妻
といった人たちは、適用外です。受け取った保険金の全額が、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
保険金はすぐ降りる?
相続になり、遺産をもらえる立場になっても、実際にそれを手にするまでには、一定の時間がかかります。遺産分割をめぐって揉め事が起きたりすれば、なおさら。そうでなくても、相続財産の大半が不動産である場合などは、高額の相続税が発生するのに手元の現金はわずかで、納税資金に困ってしまうような事態も起こりえます。
その点、生命保険の保険金の支払いはスムーズです。仮に「争続」になっていたとしても、受取人固有の財産である保険金は、申請すれば速やかに受け取ることが可能なのです。
「口座凍結」の対策になると聞いたけど
金融機関は、口座の名義人の死亡の事実を知ると、その口座をいったん凍結します。その間、基本的に現金の引き出しや振り込みはできず、葬儀費用などを故人の預金で賄おうと思っても、できなくなってしまいます。
生命保険の保険金は、やはりそれと関係なく支払われるため、相続の際の急な出費などにも対応することができるでしょう。
亡くなった人の口座は“凍結”される そのタイミングと解除する方法、注意点を解説 | MONEYIZM
子どものうち、次男にだけ保険金を渡したい
生前に遺言書を書いておけば、遺産は原則としてそのとおりに分割されます。ただし、あまり偏った分け方にすると、遺留分(※)の侵害が問題になるかもしれません。また、遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議で分け方を決めることになります。
※遺留分 兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている最低限受け取れる遺産の割合。遺留分を侵害すると、遺産を多くもらった人が、侵害された人から「遺留分侵害額請求」を起こされる可能性がある。
これに対して、生命保険の保険金は、受取人を指定しておけば、他の相続人との話し合いなどを経ることなく、まとまった現金を渡すことができます。原則として、遺留分の対象にもなりません(相続財産に対して高額過ぎる保険金は、遺留分の対象になることもあります)。
例えば、相続人である3人兄弟のうち、次男だけを受取人に指定することも、もちろん可能。さらに、仮に相続人が3人ならば、非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」です。保険金を受け取った次男は、この枠をフルに活用することができるのです。
このように、生命保険を使えば、特定の相続人に多くの現金を有利な条件で渡せるわけですが、その人が有利になり過ぎることにも配慮が必要です。例えば、それが原因で、自分の死後に子ども同士のトラブルが発生するかもしれません。
そうしたことを防ぐために、生前に保険金についての考え方を家族に説明し、合意をつくっておくのが理想です。
相続放棄したら、保険金はもらえないの?
被相続人が多額の借金を残して亡くなったような場合、相続人はそのマイナスの財産も引き継がなくてはならないため、相続放棄を選ぶケースもあります。その場合でも、故人が加入していた生命保険の保険金は、変わらず受け取ることができます。
ただし、相続放棄は「法定相続人ではなくなる」ことを意味するため、非課税枠の対象からも外れます。受け取った保険金は、そのままみなし相続財産とカウントされ、減額はできません。
そもそも、節税対策が必要になるのはどんなケース?
生命保険を活用した節税策を中心に説明してきましたが、生命保険はあくまでも「万一の備え」であるという基本を忘れないようにしましょう。
基本的に高い保険料を払うほど、支払われる保険金の金額は上がり、生前の相続財産の減額効果も大きくなります。とはいえ、特に長期に渡って保険料を支払う場合、家計に与える影響なども考慮する必要があるでしょう。
節税という観点でみると、生命保険を活用して対策を取る必要があるのは、相続財産が高額に上るケース。ちなみに、すべての相続のうち、基礎控除額を超えて実際に相続税が課税されているのは、毎年10%程度です。
そもそも生命保険を使った節税対策が必要なのか、必要ならば保険料や保険金をどの程度に設定すべきなのかは、きちんと検討すべきでしょう。迷う場合には、相続に詳しい税理士などの専門家に相談してみることをお勧めします。
生命保険の相続対策については、併せてこちらも参考にしてください。
まとめ
生命保険の非課税枠を活用することで、相続税を減額することが可能です。相続財産が多く、相続税が高額になりそうな場合には、節税策の1つとして検討してみましょう。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
「知らないと危ない」2026年労働基準法改正で何が変わる?企業が今から備えるべきポイント
-
相続税がゼロ・申告不要でも要注意!必要になるお金の手続きについて解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
サナエノミクスとは?アベノミクスとの違いと日本経済への影響を徹底解説
-
高市政権の本当の影響とは?自民・維新連立の政策を解説
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説


















