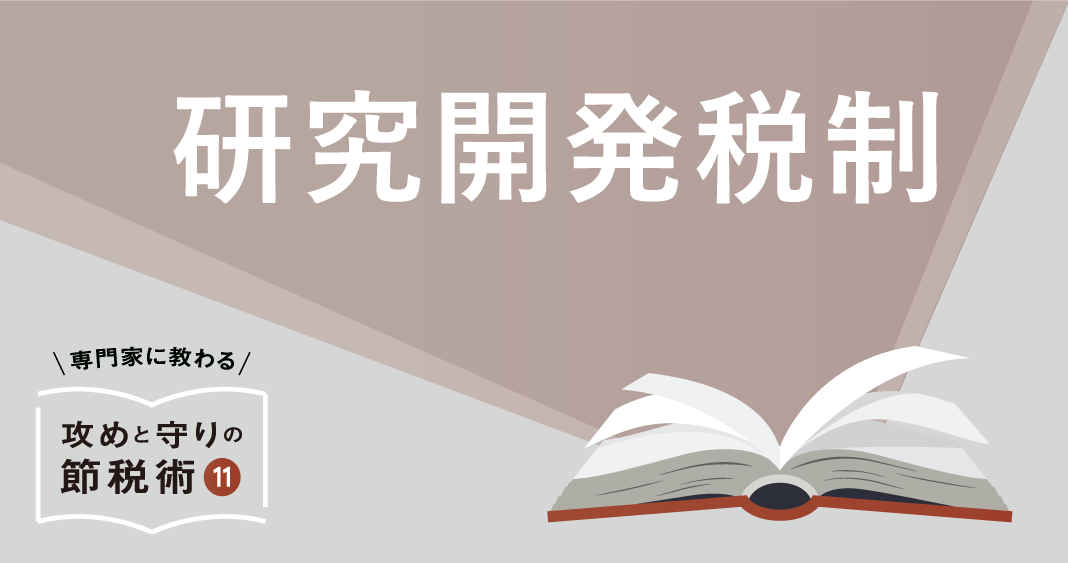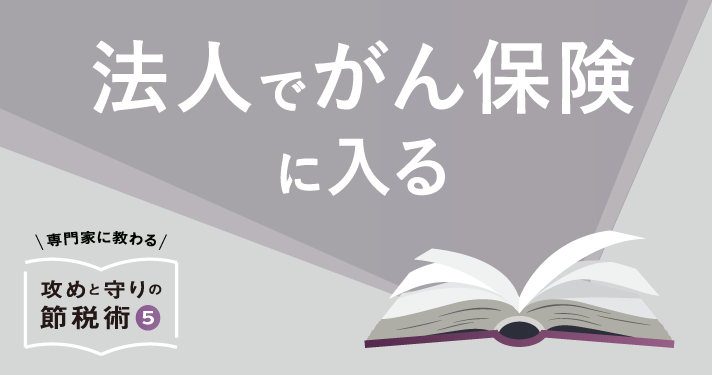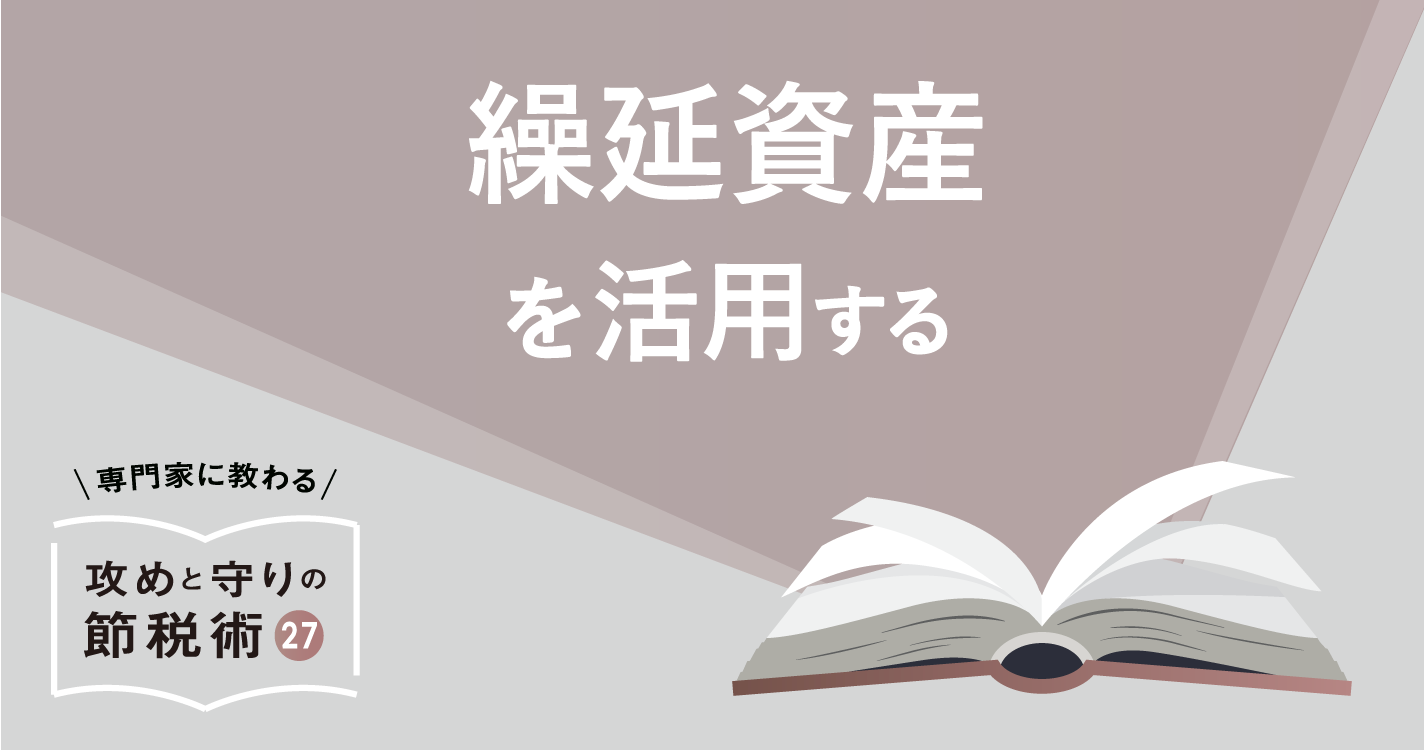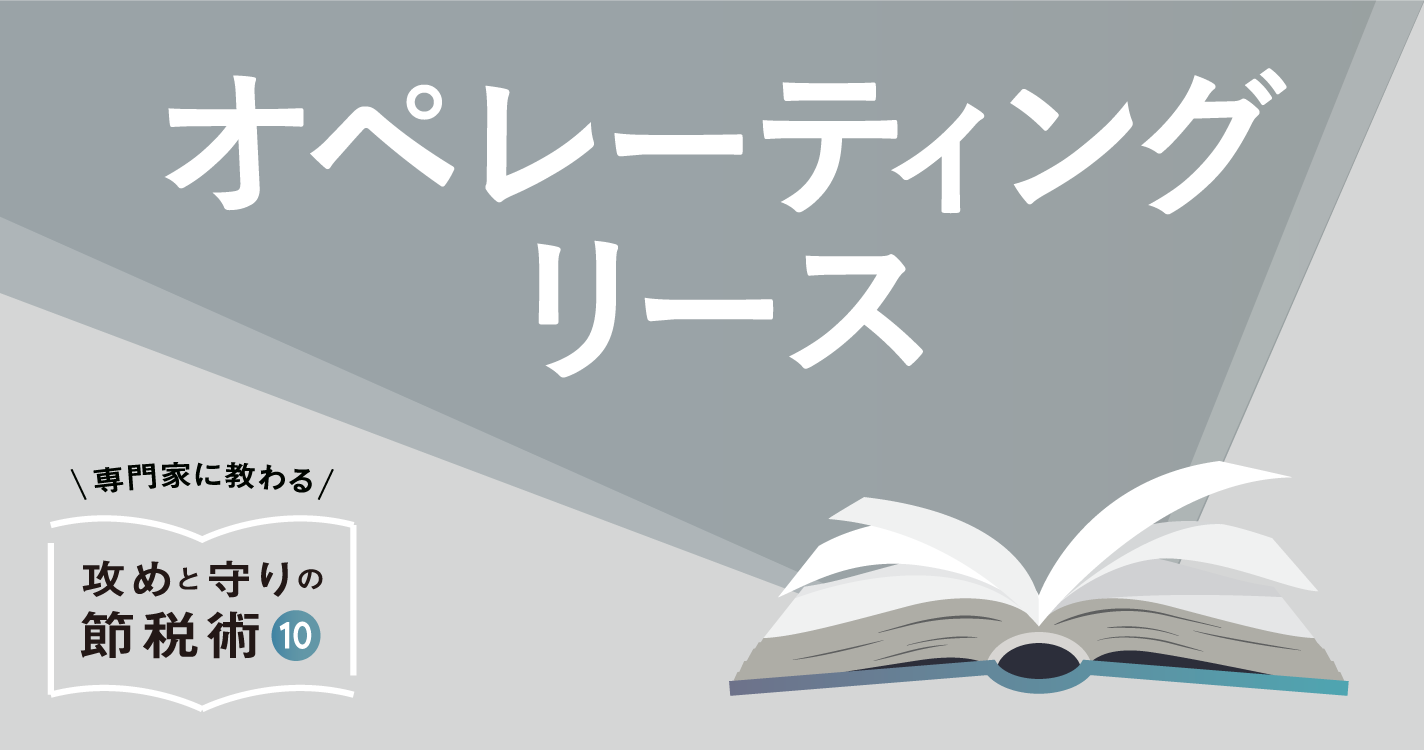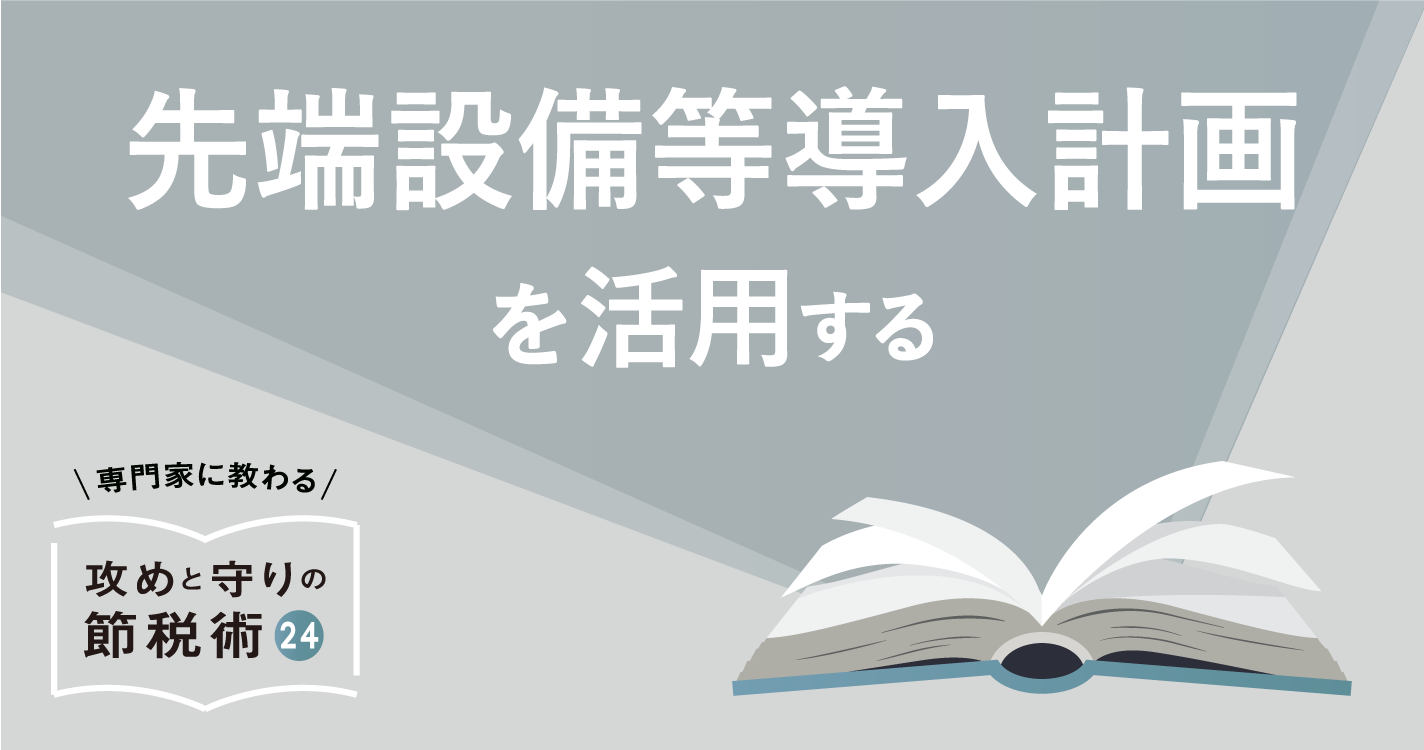
「先端設備等導入計画を活用する」という節税術
中小企業の経営者の皆さま、新たな設備投資をお考えではありませんか?
いま注目を集めているのが、市区町村に申請するだけで固定資産税が最大5年間、1/4に軽減される制度の「先端設備等導入計画」です。
この制度は、生産性向上を目的に設備投資を行う中小企業を支援するもので、これまで令和7年(2025年)3月末までだった認定期限が令和9年(2027年)3月末まで延長され、ますます活用のチャンスが広がりました。
制度の理解と適切な活用で、設備投資と節税の両立が可能です。
この記事では、税理士の視点から「先端設備等導入計画」の概要、節税メリット、注意点をわかりやすく解説します。
先端設備等導入計画とは?
先端設備等導入計画とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業が最新の設備を導入し、年平均3%以上の労働生産性の向上を目指す計画を、市区町村に申請・認定してもらう制度です。
認定を受けると、固定資産税の軽減などの税制支援に加え、金融支援の優遇も受けられます。
この制度は、国が推進する「中小企業の生産性向上」を目的としており、単なる節税効果だけでなく、賃上げの実施によるさらなる税制優遇や、資金調達支援も連動する点が大きな魅力です。経営力の強化にもつながるため、中小企業にとってメリットは大きいといえるでしょう。
対象となる設備は、機械装置(取得価額160万円以上)や測定・検査機器、ソフトウェアなど、幅広いものが該当します。ただし、いずれも「投資利益率5%以上の見込みがあること」や「中古品ではないこと」など、一定の性能・生産性基準を満たす「先端設備」であることが要件(※)となります。
※「取得価額」「設備の種類」「ソフトウェアの扱い」などの細部要件は、自治体ごとに導入促進基本計画で異なることがあります。申請前に、お住まいの市区町村の「手引き」や「チラシ」等で最新の要件を確認してください。
対象となる中小企業者は、中小企業等経営強化法に定められた中小企業者です。具体的には、製造業で資本金3億円以下または従業員300人以下など、業種ごとの規模要件を満たす事業者(個人事業主も含む)が該当します。
申請の主な流れは以下のとおりです(必ず設備取得前に認定を受けるようにしてください)。
- 導入計画書・事業計画書を作成:年平均3%以上の労働生産性向上目標を具体的に記入します。
- 認定経営革新等支援機関による確認:税理士や商工会議所などの認定支援機関に、計画の妥当性(投資利益率5%以上など)の確認を受けます。
- 市区町村に認定申請書を提出:「先端設備等導入計画に係る認定申請書」を提出し、認定を受けます(認定に要する期間は自治体によりますが、2~3週間程度が目安です)。
- 認定後、設備を取得・導入:認定後に設備を購入・設置し、税務申告時に認定書を添付することで、固定資産税の軽減措置が適用されます。
申請書類の記入方法や添付資料の詳細は、各自治体が公開している「手引き」や「チラシ」を参考にするとスムーズに行えます。初めての申請で確実にメリットを得るためにも、専門家である税理士に相談してミスを防ぎましょう。
参考:中小企業庁「先端設備等導入計画 策定の手引き(令和7年度税制改正後)令和7年4月版」
先端設備等導入計画を活用する節税メリット
この制度の最大の魅力は、設備投資と税負担の軽減を両立できる点です。特に、固定資産税の優遇措置は、令和9年(2027年)3月末まで延長されたことで、活用のチャンスが広がっています。
税制改正により、固定資産税の優遇措置を受けるために賃上げ方針の表明が必須となり、単なる節税にとどまらず、企業の生産性向上や人材定着にもつながるため、多くの中小企業にとってメリットは大きいです。
以下では、具体的な節税メリットについて順に解説します。
節税メリット1:固定資産税を最大5年間1/4に軽減できる
「先端設備等導入計画」の認定を受けた企業は、対象設備にかかる固定資産税を軽減(減免)できます。年平均1.5%以上の賃上げ方針表明で3年間は1/2に軽減され、さらに年平均3.0%以上の賃上げ方針を連動させると最大5年間で1/4に軽減可能です。軽減率は自治体により若干異なりますが、中小企業にとって非常に大きな節税メリットです。
令和7年度税制改正により、認定期限は令和9年3月31日まで延長され、令和7年(2025年)以降の設備投資も活用可能となっています。
具体的な節税効果の例
固定資産税は「課税標準額 × 1.4%(標準税率)」で計算されます。中小企業向けの実例として、1,500万円の設備投資(例: NC工作機械)の場合を考えてみましょう。
通常の固定資産税: 1,500万円 × 1.4% = 21万円/年
基本軽減(3年1/2): 10.5万円/年 → 年間10.5万円、3年総額31.5万円の節税
最大軽減(5年1/4、賃上げ連動): 5.25万円/年 → 年間15.75万円、5年総額78.75万円の節税
規模の大きい設備投資ほど節税効果は顕著で、キャッシュフロー改善や次の投資資金に回すことも可能です。
軽減期間と賃上げの関係
基本軽減期間:3年間、固定資産税が1/2に軽減(賃上げ1.5%以上表明で適用、2025年4月以降必須)
最大5年への延長:年平均3%以上の賃上げ方針を計画に表明し、実際に従業員の賃金をアップさせることで、5年間1/4に軽減可能
賃上げは「雇用者給与等支給額」(パートを含む、役員を除く)の増加を指し、表明書類の提出で認定されます。
注意点として、設備取得前に必ず認定を受けることが必須で、軽減措置の適用には「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の添付が必要です。
次に、賃上げ連動のさらなるメリットを見ていきましょう。
節税メリット2:賃上げ方針でさらなる税制優遇と人件費のコントロールができる
「先端設備等導入計画」と賃上げ方針を連動させることで、固定資産税の軽減期間延長だけでなく、法人税・所得税の優遇も受けられる可能性があります。計画に賃上げ方針を明記し、実際に賃上げを実施することで、「賃上げ促進税制(旧・所得拡大促進税制)」をスムーズに活用できる点が大きな特徴です。
賃上げ連動による相乗効果
固定資産税の優遇拡大:年平均3%以上の賃上げ方針を表明することで、固定資産税の軽減期間が3年から最大5年に延長されます(3年間1/2軽減の適用には年1.5%以上の賃上げ表明が必須です)。
法人税の優遇:賃上げを実施することで、賃上げ促進税制が適用され、法人税や所得税の負担を軽減できます。
これにより、設備投資と人件費増加の双方にかかるコストを税制面から効果的に抑えられます。
経営戦略としての賃上げと人材定着
優秀な人材の確保・定着:生産性向上で得た利益を賃上げに還元することで、従業員のモチベーション向上や離職防止につながります。
計画的な人件費コントロール:「先端設備」の導入を原資とした賃上げは、場当たり的ではなく、長期的な経営安定を支えます。
税制優遇を最大限に活かすには、制度の要件を的確に整理することが重要です。認定支援機関である税理士に相談することで、節税効果と賃上げ目標の両立を実現できる実践的な計画を策定できます。
節税メリット3:対象設備の投資効率化と生産性向上の長期リターンが得られる
対象となる「先端設備」は、生産性向上に資する設備に限定されます。具体的には以下のとおりです。
- 生産ラインや加工機械などの機械装置
- 品質管理や検査精度を高める測定・検査機器
- 省エネ・自動制御システムなどの建物附属設備
- 生産管理や在庫最適化を行う業務用ソフトウェア
投資利益率が5%以上見込める場合、税制優遇の対象となります。固定資産税の軽減と合わせて、長期的な生産性向上や投資効率化を同時に実現できる点が大きな魅力です。
節税メリット4:金融支援の追加枠活用で資金調達の負担が軽減される
認定を受けた企業は、信用保証協会の保証枠拡大や低利融資など、各種金融支援策を利用できる場合があります。これにより、設備投資に必要な資金調達の負担を軽減できます。
たとえば、自己資金が不足している場合でも、認定による金融支援を活用することで、キャッシュフローを圧迫せずに設備の導入が可能です。固定資産税軽減と金融支援を組み合わせることで、実質的な投資コストを大幅に削減できます。
以上の4つの節税メリットを活用することで、中小企業は設備投資と税制優遇を同時に享受でき、経営戦略上も大きなメリットとなるでしょう。計画的に制度を活用することが、キャッシュフロー改善や生産性向上に直結します。
先端設備等導入計画を活用する際の注意点
先端設備等導入計画は魅力的な制度ですが、タイミングや書類のミスで優遇が受けられなくなるケースも少なくありません。特に、2025年4月以降の改正で賃上げ方針の表明が必須になった点や、変更申請時の添付資料準備を事前に押さえましょう
以下では、4つの主な注意点を解説します。
注意点1:申請期限を厳守する
この制度は設備取得前に申請・認定を受けることが原則です。契約や取得を先に行ってしまうと、軽減措置の対象外となってしまいます。
認定期限は令和9年(2027年)3月末までに延長されていますが、余裕を持った申請が大切です。
注意点2:申請書類を正確に記入して添付資料を準備する
申請に必要な書類は、「先端設備等導入計画に係る認定申請書」や「確認書」など複数あります。変更認定申請の場合は、最新の事業計画書や設備見積書の再提出も必要です。
自治体によっては「記入例」や「確認書の記載例」が公開されていますので、必ず確認のうえ、正確に記載しましょう。不明な点があれば、税理士や支援機関に相談することでスムーズに進められます。
注意点3:認定支援機関の選定と事前調整が重要
計画の策定には、認定経営革新等支援機関の確認が必要です。全国の支援機関一覧は中小企業庁の公式サイトに掲載されています。
税制効果や設備要件の判断には専門知識が必要なため、税理士など専門家と連携して進めることをおすすめします。
注意点4:対象外となるケースを把握する
中古設備は対象外となり、市税の滞納がある場合も認定されません。また、賃上げ要件を満たす場合は「賃上げ方針書面」の提出が必要になるなど、細かな条件があります。
計画変更が生じた場合には、速やかに「変更認定申請」を提出し、認定を維持するようにしましょう。
この節税術に必要な心構えとは
「先端設備等導入計画」は、単なる節税制度ではなく、中小企業の経営強化を目的とした国の支援策です。設備投資を行うことで固定資産税の軽減や金融支援を受けられるだけでなく、事業の生産性向上にもつながります。
制度の活用を検討されている方は、まずは税理士など認定支援機関に相談し、自社に最適な活用方法を確認しましょう。適切な手続きを行えば、固定資産税の軽減だけでなく、長期的な経営改善につながる可能性があります。
節税と経営強化を両立する「先端設備等導入計画」は今が活用のチャンスです。認定期限は令和9年(2027年)3月末までなので今ならまだ間に合います。