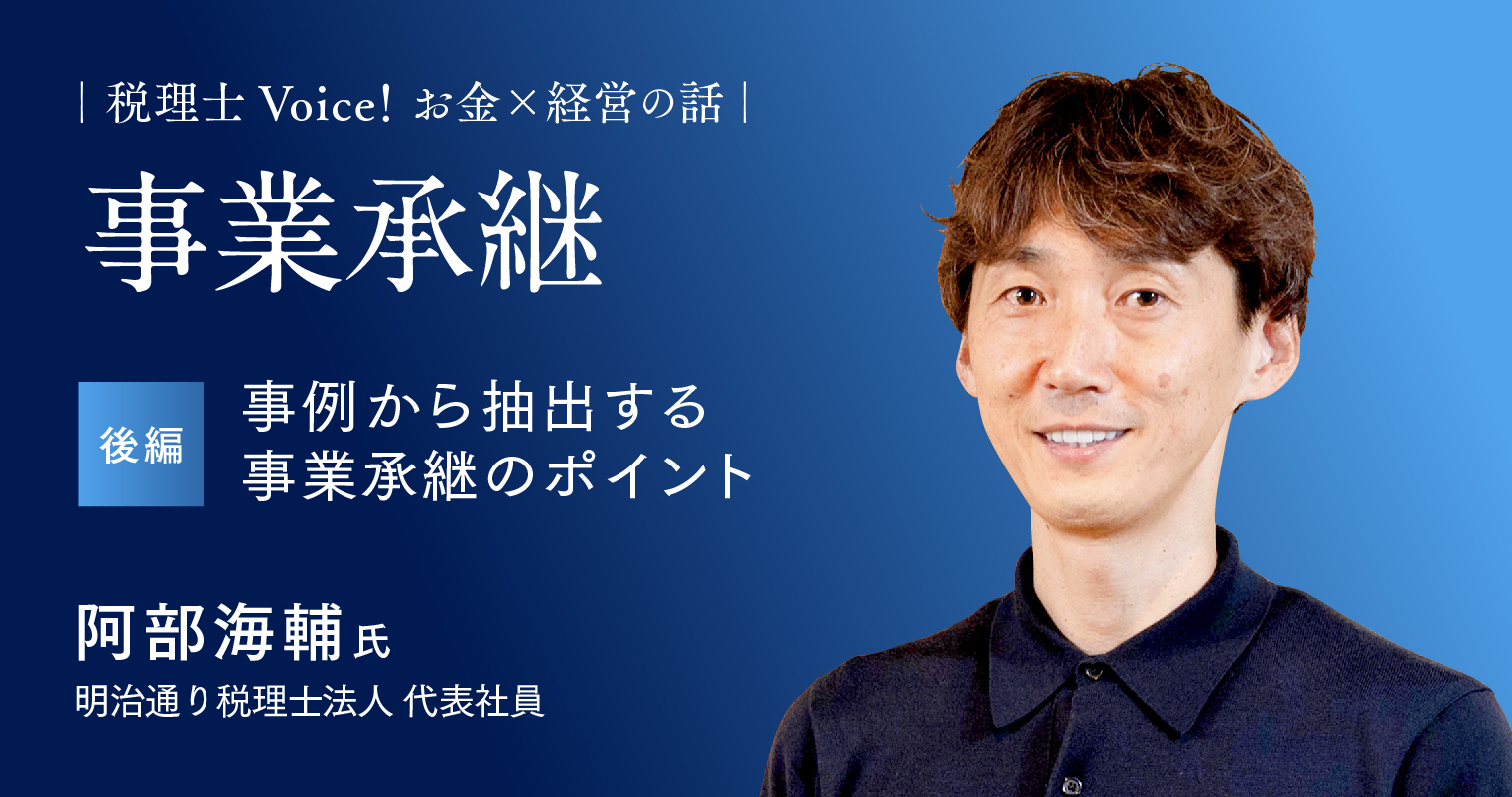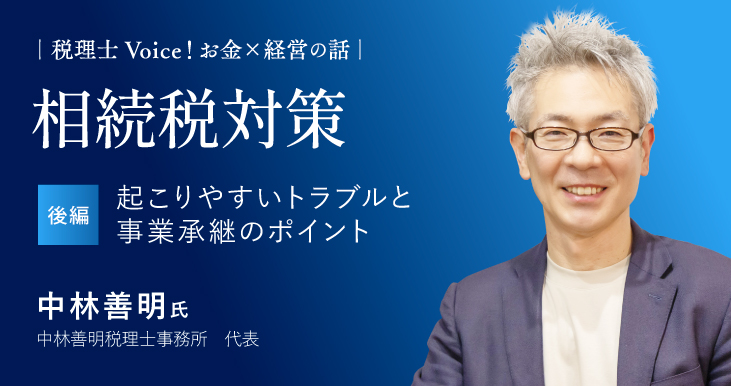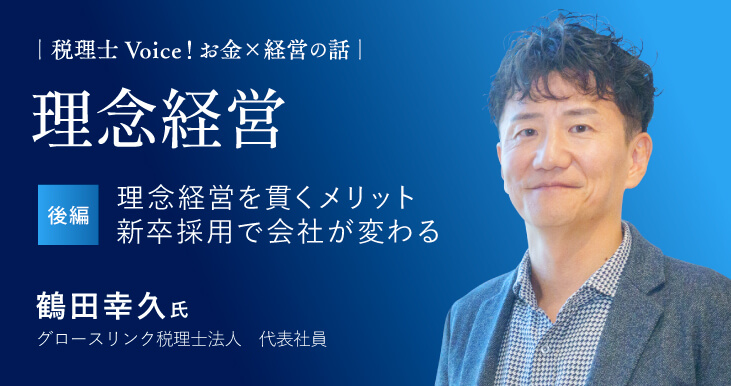【福祉 前編】福祉事業に専門特化する税理士が「会計」と「税」の問題点、今後の動向について解説
全祐貴税理士事務所 代表 全祐貴氏社会福祉法人、NPO法人などで公益事業を展開する場合にも、「会計」と「税」に対する正しい理解と対処は不可欠だ。神戸市を拠点に、この分野に特化して顧問業務に携わる全祐貴氏(全祐貴税理士事務所)は、「会計基準の順守や、消費税の解釈といった点で、不十分な状況にある事業所は少なくない」と指摘する。問題を放置した場合のリスク、改善で得られるメリットなどについて、話をうかがった。
インタビューでは、「前編」で一般事業会社と異なる会計基準への対応について、「後編」で社会福祉事業に関わる消費税、収益事業の法人税の“盲点”などを中心に、語ってもらった。
多様化する障がい福祉サービス
――貴事務所のホームページでは、「障がい福祉に強い思いがあります」とうたっています。
全(敬称略) はい。私自身、知的障がいを持つきょうだいが2人いる環境で育ち、子どもの頃からずっと福祉に貢献する仕事がしたいと思っていました。そういうモチベーションで税理士になる人間も珍しいと思うのですけど(笑)、大手税理士法人と地元神戸の税理士事務所を経て、4年ほど前にこの分野に特化する事務所を開いたんですよ。顧問先には介護系などのクライアントもいらっしゃいますが、大半は障がい福祉です。
――専門の事務所というのは、あまりないと思います。
全 そうですね。事務所は神戸にあるので、兵庫県のお客さまが多いのですが、関東などの遠方の事業所の方から依頼をいただくこともあります。
――今日は、そうした事業に関わる会計や税金の話を中心に、お話をうかがっていきたいと思います。まず、福祉事業の最近の動向からお話しいただけますか。

全 高齢化の進展の中で、介護福祉事業に対する需要が大きく拡大しているのは、ご存じのとおりです。一方、私たちがメインで対応している障がい福祉事業に関しても、ニーズが高まっていることを実感するんですよ。あくまで私見ですが、これには2つの理由があるように思います。
1つは、やはりこれも高齢化が関係していて、第1次ベビーブーム世代の方たちなどがお年を召されて、障がいを持つ子どもの面倒を自分たちでみるのが難しくなってきた。それで、グループホームなどの施設に預けるケースが増えているのです。
第2に、かつてに比べて障がいに対する社会的な理解が進み、家族などがその事実をカミングアウトしやすくなった、という点も大きいのではないでしょうか。
――カミングアウトして、専門の施設にサポートを依頼したりすることもしやすくなった、ということですね。
全 そうです。そういうニーズに対応して、サービスの中身も多様化しています。ちょっと専門的になりますが、障がい者の日常生活を支援する「生活介護」、一般企業への就職が困難な人に対する「就労継続支援」のA型(雇用型)、B型(非雇用型)に加えて、企業への就職を目指す「就労移行支援」とか一般就労した方を対象とした「就労定着支援」とか、利用者の状況に応じた選択肢が増えました。それに伴い、新規に事業所を開設する動きも活発化しているわけです。
そうした動きは喜ばしいことなのですが、一方で給付金の不正受給などの事件が後を絶たない、という現実もあります。神戸市でも事件が頻発した結果、自治体による事業所開設の審査などが、一気に厳しくなりました。
まずは一般企業と異なる会計が“ネック”に
――お話しのような不正の意思はなくても、会計・税務に関しては、不理解などから問題が起こることもあります。こうした事業に携わる方は、どのような悩みをお持ちなのでしょう?
全 社会福祉法人などの場合は、税以前の問題として、会計でつまずいているケースが珍しくありません。会計基準が一般企業とは異なり、かつ複雑なのが大きな理由です。
――そのようなところが複雑なのですか?
全 例えば、ある法人が「生活介護」と「就労継続支援B型」のサービスを提供していたとします。それとは別に、法人本部がある。普通の会社ならば、経理は全部ひっくるめてやればいいのですが、社会福祉法人の会計基準では、それぞれ別々に処理することが求められるのです。イメージとしては、3社の経理をやる感じ。事業活動計算書(以下:損益計算書)も貸借対照表も「3社分」になります。
で、何が複雑なのかというと、それぞれの間に生まれる内部取引の管理なんですよ。「財布」は別々なので、資金の移動があったら、その都度、「貸した」「借りた」などの仕訳を行い、最終的にはそれが個々の貸借対照表に反映されていなくてはなりません。
例えば、障がい福祉サービスを行っていますから、国に保険請求を行い、お金が振り込まれます。その際、入金は基本的に例えば本部などの口座に一括で行われるんですね。本来、それを速やかに「生活介護」「就労B」と別々の口座に分けて管理しなくてはいけないのですが……。
――実際には、基準に則った処理が行われていないこともあるのですか。
全 そうした不備は非常に多い、というのが実情だと思います。こういうのは、いったん「まあいいか」という感じで流してしまうと、その後は“総崩れ”です。新しく関与させていただいた法人で、「先生、お願いします」といわれてふたを開けてみたら、貸借対照表は1つだけ。内部取引はどこがどうなっているのか皆目わからないというケースや、貸借対照表が複数あっても内部取引の処理はバラバラな場合がとても多かったです。
――そんなことになるのも、個々の法人での対応に限界もあるから。
全 そうですね。ですから、我々に対しては、「とにかく経理をサポートしてほしい」というのが、事業者の方の第一義的なニーズになるのです。この点は、やはり独自の会計基準のあるNPO法人も同様です。
意識すべき「新会計基準」
――一般の企業とは違う会計の難しさがあることは、わかりました。ただ、だから問題点をそのままにしておいていい、ということにはなりませんね。
全 地元の神戸市の場合、法人に対する行政監査が3~5年に1度くらい行われます。その際、内部取引の処理が適切に行われているかというのは、重要なポイントになっています。その点を行政に指摘されて、「頼んでいる会計事務所に、『手に負えない』といわれました」と、当事務所にいらっしゃる事業者さんも、けっこういますよ。
――行政の監査というのは、かなり厳しいものなのですか?
全 実態的には、自治体による「温度差」のようなものも感じます。不正が大きく取り上げられた神戸は、非常に厳格な部類に入るでしょう。一方で、「貸借対照表が1つ」でも監査で何もいわれなかった、といった例も聞きます。まあ、複雑な経理を監査するには、する側にもそれなりの専門知識とか体制も必要になりますから、そういう事情もあるのかとは思いますが。
ただし、今まで「見逃されて」いたから今後も大丈夫と考えるのは、ある意味危険だと私は感じています。社会福祉法人に対する新たな会計基準ができて、旧基準から完全に移行されたのが2015年です。例えば税務署マターだったら、一気に切り替えられるのでしょうけど、自治体の運用には、今説明したような濃淡があったわけですね。
でも、新基準になって10年経ちましたから、自治体の側の理解や対応も進んでいるでしょう。社会福祉事業に関連する不正は全国規模で起こっていますし、新会計基準を順守させようという方向に動いていくのは、間違いないと思うのです。
適切な経理にはメリットもある

――先生が会計に問題を抱える法人を担当した場合、どのようにして改善を図るのでしょう?
全 一般論でいえば、まずは基準に即したあるべき経理と現状のズレが、どこにどれだけあるのかの全容解明ですね。これが大変です。で、それがわかっても、どうやって修復するのかには、けっこうエネルギーが必要です。法人の規模や状況にもよりますが、全部「きれい」にするのは、1年がかりの仕事になります。
当然のことながら、私が一人で帳簿を眺めていても、ことは進みません。そこには、職員さんたちの協力が不可欠です。正常化した後、それを実際に運用していってもらわなくてはなりませんから、意識自体を変えてもらうことも必要になります。多くの場合、関連する人たちの仕事量は増えることになるので、シビアなやり取りになることもあるんですよ。
――そうなんですね。
全 ただ、そのようにして新基準に適合した会計に生まれ変わると、みなさんに「やってよかった」と喜んでもらえます。貸借対照表が整備されると、今どこにお金や資産があって、それぞれの貸し借りの実態がどうなっているのか、といった部分が“見える化”されるのです。無駄というか、お金の使いすぎがあったことも浮き彫りになったりします。
そのように、財務状況が明確になると、気づかなかったいろいろな課題も見えてくるんですね。そのメリットは予想以上に大きいというのが、私の実感です。
――新基準への対応を単なる義務ではなく、より良いサービスを提供するためのステップだととらえる必要がありますね。
「後編」では、気をつけたい税務やNPO法人をめぐる最新動向などについて、引き続きお話をうかがいます。
注:記載の「事例」に関しては、情報保護の観点により、お話の内容を一般化したり、シチュエーションなどを一部改変したりしている場合があります。
知的障がいのあるきょうだいと共に育った経験を持ち、税理士の立場から障がい福祉業界に深く寄り添う神戸の税理士事務所。社会福祉法人、NPO法人、障がい福祉事業所を中心に、全国のお客様の専門的かつ細やかなニーズに応える。
URL:https://shougai-fukushi-zen-zeirishi.com/