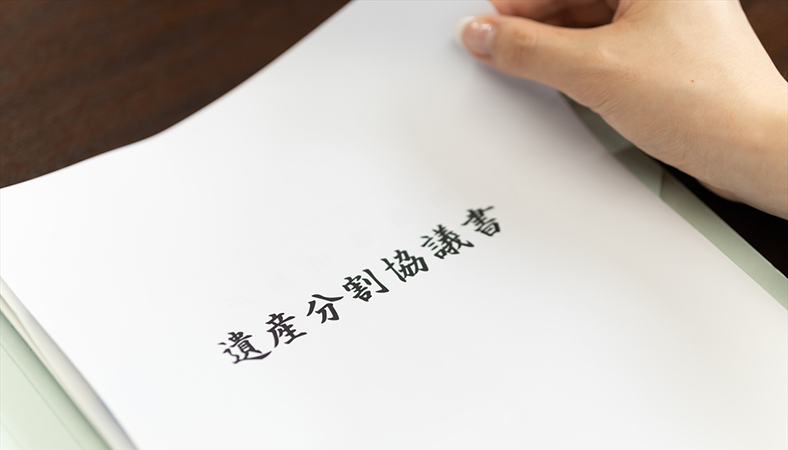相続で問題となる「名義預金」とは その「怖さ」と対処法を解説


「名義預金」とは、「本来は被相続人(亡くなった人)の財産にカウントされるお金にも関わらず、違う人の名義になっている預貯金」をいい、相続税の申告から漏れるとペナルティの対象になることがあります。どんなケースが該当するのか、税務署に名義預金とみなされないための予防策などを解説します。
税務署が注目する「現預金」
相続税の申告では、高額の不動産や貴金属などが問題になりやすいとお思いではないでしょうか。税務調査で申告漏れを指摘される件数が最も多いのは、実は「現金・預貯金」で、全体の64%近くに上ります。申告漏れ金額の割合で見ても約30%を占め、「土地・建物」の15%、「有価証券」の11%を上回っているのです(いずれも国税庁「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」)。
この数字は、税務署がそれだけ「現預金」に目を向けている、ということの証ともいえるでしょう。税務署は、被相続人だけでなく、相続人の預貯金口座を過去に遡って調べる権限を持っています。申告の内容などからみて不自然なお金の流れは、“筒抜け”になっていると考える必要があります。
これから説明する名義預金についても、税務署は目を光らせています。被相続人とは違う名義の口座だからといって、そのまま見逃されるわけではないのです。
名義預金とは何か
「名義預金」は法令に記載のある用語ではありませんが、相続税の申告漏れの「よくあるケース」として認識されています。その「要件」と、具体的にどのような場合が当てはまるのかをみていきます。
財産の「出どころ」が被相続人である
預貯金口座の名義が被相続人以外の人になっていても、そこにあるお金が実質的には被相続人から出たものである(資金源である)場合には、名義預金と判断されることになります。
例えば、黙って子どもや孫名義の口座を開設し、そこに将来渡すつもりで自分のお金を積んでいたら、これに該当します。また、収入のない専業主婦が、夫の給料の一部を自分名義の口座に貯めるいわゆる「へそくり」も、資金源は夫ですから、その相続時には名義預金とされます。
なお、名義預金ではありませんが、被相続人が資金源となっている株などの有価証券で、家族名義あるいは無記名のものや、同じく被相続人が新築した不動産で登記が済んでいないものなども被相続人の財産であり、相続税の申告に含める必要があります。
生前贈与が成立していない
よくある誤解が、今の例のように子や孫名義の口座に預金するのは生前贈与ではないのか、というものです。贈与は、財産をあげる人ともらう人の両方の合意があって成り立つ契約です。もらったほうにその認識がない場合には、贈与にはなりません。
ですから、子どもなどの名義の口座を勝手に作ってお金を貯めていても、そのまま相続になれば、「子どものもの」にはできないのです。後述するように、貯めていたお金はいったん相続財産に戻し、通常の遺産分割を行う(相続税が発生すれば納税する)ことになります。
現在では他人名義の預貯金口座を開くのは困難ですが、これから相続を迎える高齢者世代にはそれが可能でしたから、注意が必要です。
口座の管理を被相続人が行っていた
では、今の「あげる・もらう」という合意を交わしたうえで、子ども名義の口座にお金を貯めていたものの、通帳やカードを被相続人が管理していた場合はどうでしょう? 子どもに早い時期からお金を渡すことにためらいを感じて、そのような行動を取りたくなる気持ちは理解できますが、これもアウト。
財産が贈与された場合は、もらった人がそれを管理し、利用できる状態でなければならないのです。そうでなければ、やはり被相続人の財産、すなわち名義預金とされます。
名義預金のペナルティは
加算税などが発生する
税務調査で名義預金の申告漏れ(被相続人の財産に加えなかった)の指摘を受けた場合は、税務署に修正申告を行わなくてはなりません。その際には、併せて加算税というペナルティが課せられます。
加算税には、過少申告加算税や無申告加算税などがあり、悪質な仮装隠蔽があった場合には、より税率の重い重加算税が課せられることもあります。税務署の指摘を受ける前に自主申告した場合には、ペナルティが不適用になったり軽減されたりすることもありますから、名義預金の存在に気付いたらすぐに申告すべきでしょう。
なお、これとは別に、納税の遅れに対して延滞税がかかります。延滞税は納期限(相続税は相続発生から10ヵ月)の翌日から完納するまでの日数で日割り計算されます。
名義預金には時効がない
贈与税には、原則6年(悪質な隠蔽などの場合は7年)という時効があり、それを過ぎれば、たとえ申告漏れがあっても課税はされません。しかし、説明したように贈与が成立していない名義預金には、時効が存在しません。どれだけ前に入金されたものでも、名義預金とされれば、相続税の対象になるわけです。
名義預金は相続税計算の取扱い上、被相続人の預金を相続人名義の口座で預かっていたということになり、預り金等として相続財産にカウントされてしまいます。そのため、名義預金に贈与税のような時効は存在しません。

河鍋公認会計士・税理士事務所代表 河鍋 優寛(税理士・公認会計士)
名義預金とみなされないための対策
贈与には非課税枠がある
説明してきたように、名義預金は、現実には生前贈与のつもりで行われることが多くなっています。
贈与には、年間110万円までという非課税枠があります(※)。これを使って子どもなどにお金を渡していけば、無税ないし少額の納税で親の財産を移動し、相続財産を減らす(=相続税を節税する)ことも可能です。
一方、相続時に子ども名義の預金が名義預金とみなされた場合には、贈与税の非課税枠は適用されず、全額を親の相続財産に加算しなくてはなりません。相続税が発生する場合には、納税も必要です(※)。
正しい贈与を行う
税務署に名義預金だと疑われないためには、「きちんとした贈与」を実行する必要があるでしょう。ポイントは以下の2点です。
●贈与契約書を作成する
繰り返しになりますが、前提として、「あげる・もらう」という合意が必要です。そのうえで、贈与の事実、日付、両者の氏名などを記して捺印した「贈与契約書」を作成すれば安心できます。
法的には、贈与契約は口頭(口約束)でも成立します。しかし、名義預金が疑われるようなケースでは、亡くなった被相続人の「証言」を得ることができません。書面にしておくことを考えましょう。
●口座の管理を「もらう人」が行う
名義人が口座の管理をしていれば、それは名義預金ではありません。通帳や印鑑、カードは、財産をもらう人に渡すようにします。
「へそくり」には要注意
例えば、普通の専業主婦が、夫の相続の時点で1,000万円の残高のある自分名義の口座を持っていたら、税務署は当然疑いの目を向けるでしょう。
ただし、そこにあるのが、親から受け継いだ遺産だったり、パートで働いてコツコツ貯めたお金だったりするかもしれません。そうした場合には、きちんとそれを証明できる証拠を残しておくようにしましょう。
前述のとおり、名義預金としてみなされてしまうと相続財産にカウントされます。時効が存在する贈与として認定・主張するためには、正しく順序を立て実行に移すことが大切です。

河鍋公認会計士・税理士事務所代表 河鍋 優寛(税理士・公認会計士)
名義預金、こんな場合はどうすれば
名義預金を「なかったこと」にしたい
名義預金を解消するには、その口座の預貯金を自分の手元に戻すだけでOKです。他人名義の口座であっても、そこにあるのは「自分の財産」ですから、移動させても贈与税が課税されることはありません。
ただし、次のように名義人がそのお金に手を付けてしまっていた場合には、事情が異なります。
名義預金を使ってしまった
口座の名義人が、そこにあるお金を引き出して使った場合には、その段階で贈与が成立したとみなされます。名義預金ではなくなるのですが、当初口座に入っていた金額がさきほどの贈与税の非課税枠110万円を超えていれば、贈与税の申告・納税をしなくてはなりません。
ただし、生活費や教育費としてお金が入金された都度利用した場合は贈与税は課税されません。この場合は非課税枠110万円を超えても問題ありませんが、通常必要と認められるものに限ります。

河鍋公認会計士・税理士事務所代表 河鍋 優寛(税理士・公認会計士)
まとめ
子や孫のためにと思って貯めている預貯金が、名義預金になっているかもしれません。申告漏れになりやすいケースでもあり、税務署も目を光らせています。該当する場合には、きちんとした贈与に切り換えるなどの対応が必要です。疑問や不安があったら、相続に詳しい税理士に相談するようにしましょう。
記事監修者 河鍋税理士からのワンポイントアドバイス
相続税申告の件数が年々増えており、今まで相続税とは無関係だった方も他人事ではなくなってきています。相続財産を少しでも減らすために、当記事で紹介した名義預金や、相続開始前に毎日のように口座からお金を引き出す方も増えております。ただし、それらはご紹介しましたように、残念ながら相続税対策にはなりません。相続開始前の出金は手元現金として計上されることになるためです。
相続税対策は間違って実行してしまうと、加算税や延滞税などに繋がる可能性があります。税制改正で使いやすくなった相続時精算課税制度や、住宅取得等資金贈与の非課税の特例など、贈与税が一定額非課税となる制度を使って、財産を正しく贈与して相続税対策を行いましょう。
このあたりはご自身で判断が難しいことも多いため、相続税に精通した税理士にご相談されることをお勧めいたします。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025参院選】選挙公報・政見放送の見方と政策比較のポイントを徹底解説
-
米国向け輸出入企業必見!トランプ関税が導入されたら?国別影響と対応策を仮想シナリオで徹底解説
-
【2025参院選】参院選で私たちの生活はどう変わる?各政党の政策を徹底比較・完全解説
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ
-
トランプ政権の“品目別関税”とは?業界別影響と企業がとるべき対策を解説