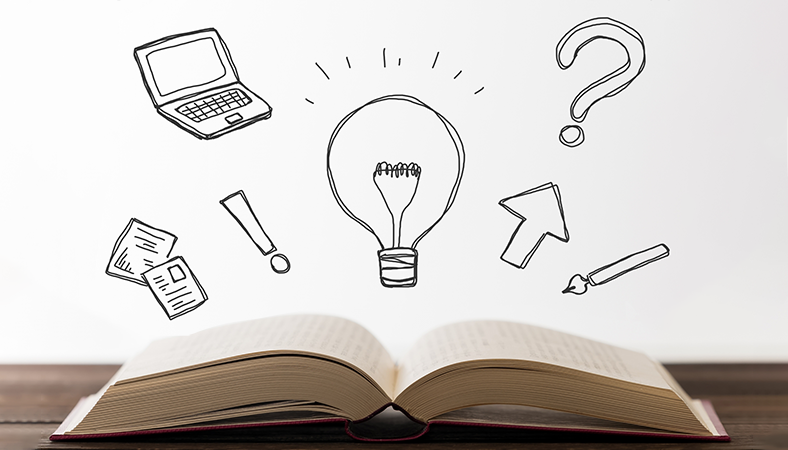後継者不在でも安心!親族外承継×補助金×税制優遇で進める事業承継の方法
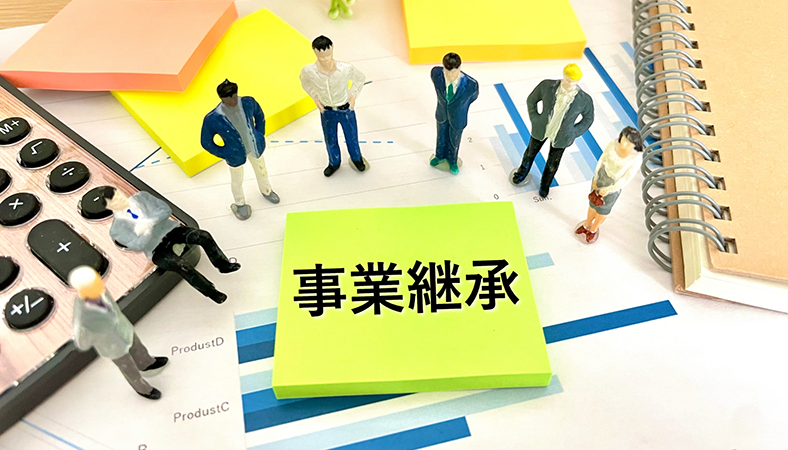
「後継者がいない」「自分の代で会社を終わらせたくない」。経営者として、このような思いを抱えていませんか?中小企業では後継者不在という状況が多く「M&Aを検討したいが費用面で踏み出せない」と、資金の壁が事業存続を阻んでいるケースも珍しくありません。
そのような状況を打開するためにも、親族以外の第三者に事業を託す「親族外承継」なら、経営意欲と能力を兼ね備えた後継者を幅広く探せます。さらに「事業承継・引継ぎ補助金」を活用すれば、資金面での課題も大幅に軽減させることも可能です。
この記事では、親族外承継の進め方と補助金の賢い活用法以外に、税制優遇との連携や見落としがちな注意点をまとめました。ぜひ最後までご覧ください。
1. 親族内承継とは?親族外承継の違い
会社を引き継ぐ方法は、大きく分けると「親族内承継」と「親族外承継」の2つに分かれます。親族内承継は、子どもや兄弟などに経営権を譲る従来の方法に対し、親族外承継は経営者の親族以外の第三者に会社を引き継ぐ方法です。
親族外承継は、さらに役員・従業員への承継である「社内承継」と、第三者承継である「M&A」に分類されます。なお、親族外承継の最大のメリットは選択肢の広さです。
仮に親族に適任者がいなくても、事業内容を熟知した従業員から新たな視点を持つ外部企業まで、経営意欲と能力のある人材を社内外から幅広く探せます。事業承継において選択肢を狭めることなく、自社にとって最適な承継方法を検討することが求められるでしょう。
2.「事業承継・引継ぎ補助金」の最新内容と申請スケジュール
「事業承継・M&A補助金」は、事業承継で課題となる資金面において中小企業を力強く支援する制度です。ただし、最新の公募では、従前の内容と比べると申請期間が1か月と非常に短く、期間を考慮すると事前の十分な対策なしでは実質不可能といえます。
そのため、タイトなスケジュールの中で、質の高い事業計画書や必要書類を準備するには、公募開始までに準備することが必要です。特に、補助金制度は年々変更されるため、最新動向を正確に把握しなければなりません。
公募開始前から専門家と連携して計画的に準備を進めることが、採択を勝ち取るための絶対条件といえるでしょう。
11次公募(2025年5〜6月):専門家活用枠のみで申請期間が限定的
2025年の事業承継・M&A補助金11次公募は、M&Aの専門家を活用する費用を支援する「専門家活用枠」に特化していました。また、申請期間は約1か月という非常に短い期間であり、実施は準備不足の企業をふるいにかけるという厳しい内容です。
補助対象には、M&A仲介業者やFAと呼ばれるフィナンシャルアドバイザーへの手数料、企業調査費用などが含まれます。なお、前回の公募から一部ルールが変更され、原則2社以上の相見積もりを取得することが必須となるなど、業者選定の透明性もより一層厳しく問われるようになりました。
新たな条件をクリアし、補助金を確実に活用するには公募が始まる数ヶ月前からM&A支援機関と連携しておくなどの準備が欠かせません。
補助額・支援対象の変化:専門家活用枠・PMI推進枠の強化
令和6年度の事業承継・M&A補助金は、従来の制度から大幅に拡充されました。特に、M&Aの「専門家活用」と、M&A後の経営統合プロセス「PMI」を支援する枠が強化された点が大きな変更内容です。
改正のポイントとして、国がM&Aの実行だけでなく、その後の事業統合によってシナジー効果を創出することを重視していると考えられます。新たに「PMI推進枠」が設けられ、M&A成立後のシステム統合や業務効率化にかかる費用も補助対象となりました。
また「専門家活用枠」では補助上限額が大幅に増額され、買い手支援では最大2,000万円という手厚い支援が受けられるよう変更されています。しかも、専門家活用枠とPMI推進枠の併用も可能です。
自社の状況に合わせてこれらの枠を戦略的に活用することで、承継コストを抑えつつ、M&Aの成功確率を格段に高められるといえるでしょう。
申請スケジュールがタイト、早期準備が鍵
補助金を活用する上で最も注意すべき点が「公募開始から締切までの期間が極めて短い」点です。期間中には、事業の現状分析、事業計画書の策定、複数の専門家からの見積もり取得、その他必要書類の収集をすべて完了させるのはほぼ不可能といえます。
特に補助金の審査では、事業計画の具体性や実現可能性が厳しく評価されるため、表面的な計画ではまず採択されることもないでしょう。補助金の採択を勝ち取る企業は、公募開始の数ヶ月前から専門家と連携した上で事業計画を作りこみ、ほぼ完璧に準備しています。
補助金の活用を少しでも視野に入れているのであれば、今すぐにでも情報収集を行い、計画策定に着手することが重要です。
3. 他支援策との連携:税制や準備金制度も確認
事業承継を成功させるためには、補助金だけでなく「税制優遇措置」や「準備金制度」といった他の支援策との連携が効果的です。補助金がM&Aの専門家費用や設備投資といった「入り口」のコストを支援します。
一方、税制優遇は承継に伴う贈与税・相続税や、M&A後の法人税といった「継続的な」コストを軽減する役割を担います。支援の目的や性質が異なるため、多くの場合で併用が可能で、複数の支援策を戦略的に組み合わせることで、事業承継にかかるトータルコストも圧縮できるでしょう。
たとえば、準備金制度でM&A実施年度の税金を繰り延べ、さらに事業承継税制で後継者の税負担をゼロに近づけるといった対応も可能です。
準備金制度で将来の損金計上が可能に
M&Aを検討する中小企業は「中小企業事業再編投資損失準備金制度」の活用をおすすめします。M&Aにかかる投資リスクに備えつつ、実施年度の税負担を合法的に繰り延べられるからです。
経営力向上計画の認定を受けた中小企業がM&Aで他社の株式を取得した際、取得価額の最大70%を準備金として積み立てるとともに、その全額を損金に算入できます。損金が増えると課税所得が圧縮されることで法人税負担の軽減につながるため、キャッシュフローを安定させる上では非常に有効な手段です。
準備金は決められた据置期間を経て、その後5年間で均等に取り崩して益金に算入するため、あくまで課税の繰り延べですが、資金繰りは楽になります。そのため、補助金と合わせて必ず活用を検討すべき税制優遇措置といえるでしょう。
税制優遇と補助金の併用メリット
事業承継・引継ぎ補助金は「事業承継税制」や「経営資源集約化税制」などの税制優遇措置と併用できるため、承継コストを大幅に削減できます。補助金がM&A仲介手数料や設備投資といった「直接的な経費」を支援するのに対し、税制優遇は相続税・贈与税などの「税負担」の軽減が可能です。
資金調達と税金対策の両面をカバーすると、承継後の経営における不安を抑えた上でスタートできます。なお、専門家活用枠の補助金で、M&Aの仲介手数料の負担を数百万単位で軽減させることが可能です。
また、M&A後の設備投資を行う際の経営資源集約化税制を活用し、税額控除または全額即時償却させることで法人税の圧縮につながります。さらに親族内承継であれば、事業承継税制により後継者が負担すべき贈与税・相続税の納税が猶予・免除も期待できます。
しかし、承継計画を立てる際には必ず税理士などの専門家に相談し、適用可能な税制優遇を最大限活用するプランを設計することが不可欠です。
4. 親族外承継における実務上の注意点
親族外承継を成功させるには、親族内承継での「あいまいさ」を排除した厳格な手続きが求められます。特に、契約書の整備や役員体制の変更といった法的な「形式化」は、後々のトラブルを未然に防ぐための重要な手段です。
また、事業承継・M&A補助金は非常に有益であるものの「補助金があるから大丈夫」と安易に考えてはいけません。すべての経費が対象になるわけではなく、対象外の費用を正確に把握しておかないと、資金計画がすぐに破綻してしまうリスクがあります。
弁護士や税理士といった専門家を交えて法的な手続きを確実に進めると同時に、実務的な注意点を深く理解し、万全の体制で承継に臨むことが大切です。
契約書・役員体制など「引き継ぎの形式化」が必要
親族外承継の中でも、M&Aや従業員への承継を成功させるためには、当事者間の合意内容をすべて書面で明確にする「形式化」が絶対条件です。親族内承継のような「暗黙の了解」は第三者との間では一切通用せず、後のトラブルの引き金となりかねないからです。
承継後に起こる紛争を未然に防ぐためにも、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書など、あらゆる取り決めを法的に有効な形で文書化しなければなりません。たとえば、従業員に事業を承継させる場合、先代経営者の親族が「株主」として残っていると、後から経営に介入してくるリスクがあります。
リスクを防ぐためには、事前に親族から株式を買い取る、あるいは議決権のない種類株式に転換してもらうなど、株主間協定書として締結しておくことも重要です。契約書や議事録といった客観的な証拠を残し、円滑でトラブルのない親族外承継を実現させましょう。
補助金が支援しない経費もあることを認識
事業承継・引継ぎ補助金は非常に有効な支援策の1つですが、申請する経費のすべてが補助対象となるわけではありません。事前に「対象外経費」を正確に把握しておくことが求められます。
補助金は国民の税金を原資としているため、使途は事業の承継や革新に直接結びつくものでなければなりません。事業に直接関係ない経費や汎用性が高く他の目的にも流用できる費用、公的資金で賄うにはふさわしくないと判断される経費などは補助の対象外です。
理解せずに資金計画を立ててしまうと、採択後の計画自体がすぐに頓挫する危険性もあります。補助金を申請する際は、必ず公募要領の「補助対象経費」の項目を確実に理解した上で、少しでも判断に迷う経費があれば事務局に問い合わせるなどしておきましょう。
まとめ
親族外承継という会社の一大イベントを成功に導くには、事業承継・M&A補助金の活用と、税制優遇も含めた対応が不可欠です。新たな補助金は条件面が拡充されているものの、一方で申請期間は極めて短く、手続きも複雑化しています。
契約書の整備といった法的な形式化や、補助対象外経費の存在をあらかじめ認識しておくことも、計画を成功に導くポイントです。なお、今や親族外承継は事業存続のためには非常に有益な選択肢の1つといえます。外部の知見を取り入れ、会社を次のステージへ飛躍させるための、積極的な経営戦略です。
ここで紹介した内容を踏まえ、いつでも事業承継ができるように準備しておくことをおすすめします。まずはM&A相談センターや税理士などの専門家に相談し、自社に最適な承継戦略を検討することから始めていきましょう。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
相続税がゼロ・申告不要でも要注意!必要になるお金の手続きについて解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
税金・公共料金をスマホで簡単支払い!キャッシュレス納付の方法とお得な使い方
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説