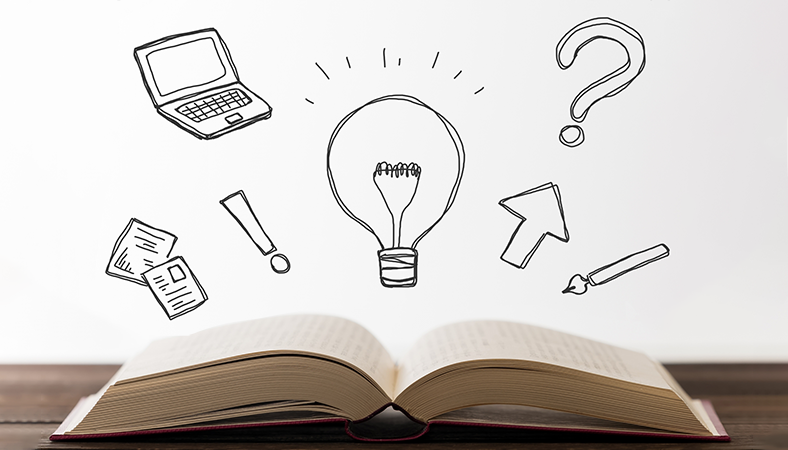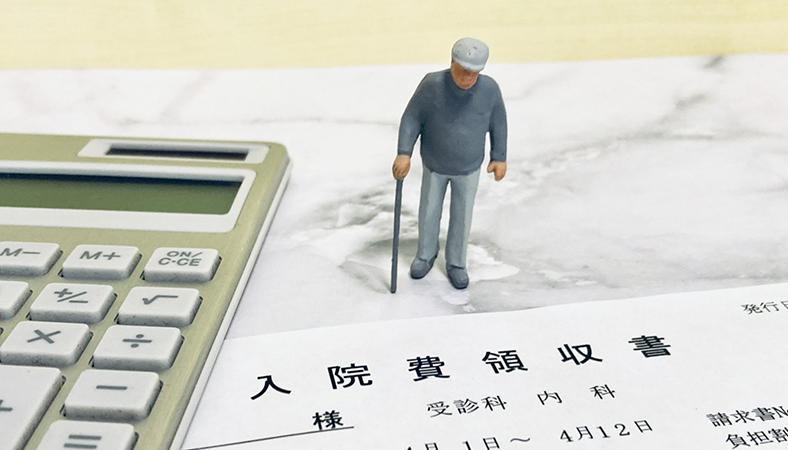【2025年版】取引先の倒産リスク急増!中小企業が取るべき対策とは?


「最近、取引先の支払いが遅れ気味…」「あの会社、ちょっと雰囲気が変わってきた」取引先に対して、このような不安を感じたことはありませんか。2024年の企業倒産件数は直近9年で最多件数を記録し、多くの中小企業が倒産の危機に直面しています。
主要取引先の突然の倒産によって、数千万円単位の売掛金が回収不能となることも珍しくありません。とはいえ、「信用チェック」「契約整備」「債権保全」「支払管理」など、正しいステップを実践すれば、最悪の事態を未然に防ぐことも可能です。
この記事では、最新の倒産動向から企業が発する危険信号の察知方法、取引信用保険の活用まで、会社を守る実践的な対策を網羅的に解説します。倒産リスクが高まる状況において、少しの遅れが致命的となる前に、ぜひ最後まで読んで明日から実行できる対策を身につけていきましょう。
1. 倒産件数が増加傾向にある今、何が起きているのか?
自社のリスク管理を行う上で、企業の倒産状況を把握することは重要といえます。2024年は国内法人の倒産件数が直近9年間で最多を記録するなど、異例ともいえる状況です。
倒産件数は2025年にかけてさらに厳しい局面を迎える可能性が指摘され、もはや「他人事」では済まされません。特に中小企業では、一社の倒産を引き金に「連鎖倒産」に直結するリスクも抱えています。
最新の倒産動向が自社にどのような影響を及ぼすのか、厳しい現実を正しく認識した上で有効な対策を講じることが大切です。
2024年前半の企業倒産はコロナ前超え、2年連続増加
2024年の企業倒産件数は、コロナ禍以前の水準を大きく超え、過去9年間で最多を記録するなど深刻な状況です。異例な状況は単なる景気後退ではなく、物価高騰や深刻化する人手不足、さらに「ゼロゼロ融資」の返済開始など、複数の要因が関係しています。
ゼロゼロ融資とは、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した中小企業などに対して、実質無利子・無担保で行う融資制度です。特に、製造業や建設業、小売業では倒産件数が増加し、原材料費やエネルギーコストの上昇が経営を圧迫していると考えられます。
さらに、高リスク企業の9割超が、売上高「10億円未満」の、比較的規模の小さな企業で占められているという点にも注意が必要です。特定の業界や地域の問題ではなく、日本経済全体が直面する構造的な課題に対し、すべての経営者が対策を講じておかなければなりません。
出典:
全国企業「倒産リスク」分析調査(2024年)|株式会社 帝国データバンク[TDB]
倒産集計 2024年上半期(1月~6月)
仕入れ先・販売先の破綻が中小企業の連鎖倒産リスクに直結
中小企業にとって脅威となるのは、取引先の破綻が自社の経営危機に直結する「連鎖倒産」といえます。売り上げの大部分を少数の取引先に依存しがちなビジネスモデルであるため、1社が倒産すると売掛金が回収不能な「貸し倒れ」となるからです。
また、古くからの取引先に対しては「長年の付き合いだから」と関係性を優先しがちですが、突然の倒産によって売掛金が回収不能になったというケースも珍しくありません。「主要取引先の支払い遅延」は、連鎖倒産への危険なシグナルであるため、すぐさま対処が必要です。
仮に、自社の経営が黒字であったとしても、取引先が破綻するという外部要因によって、築き上げてきた事業が一瞬にして破綻する可能性もあります。日頃からメイン取引先の動向監視と情報収集を心がけることが、連鎖倒産を回避するためのポイントです。
自社で内製化できない業務を外注し、その業務が外注先しかできない場合、もしその外注先が倒産したときは、製品を製造することができなくなってしまいます。

増田晃士税理士事務所代表 増田 晃士(税理士)
2. 倒産リスクを事前に察知するためにできること
取引先の「倒産」という事態は、突然訪れるわけではなく、事前に何らかの危険信号を発しています。いかに取引先から発せられるサインを早期に察知し、事前に策を講じられるかがポイントといえるでしょう。
そこで大切なのが「与信管理」です。与信管理とは、単に取引相手を信用しきるのではなく「相手の支払い能力」を客観的に評価した上で、安全な取引をするという戦略的なリスクマネジメント手法を指します。
たとえば、営業担当者の個人的な勘や経験だけに頼るのではなく、社内で統一された基準に基づくチェックと、専門的なツールの活用も大切です。与信管理の仕組みを構築することで見えないリスクを可視化し、連鎖倒産という最悪の事態を未然に防いでいきましょう。
取引先の財務情報や支払遅延を日常的にチェック
取引先の倒産リスクを早期に察知するためには、日々の業務における些細な「違和感」を見逃してはいけません。多くの倒産企業は、破綻する前には必ず財務状況や社内の雰囲気において何らかの危険信号を発しているからです。
たとえば、貸借対照表上で資産が負債を下回る「債務超過」ではないか、損益計算書で「営業赤字」が続いていないかは最低限確認しておきましょう。
さらに、資金繰りが悪化していないかをチェックするために、キャッシュフローのマイナスが続いていないかも注意しておく必要があります。とはいえ、支払日に遅延が頻発したり、経理担当者を含む従業員が相次いで退職したりと、決算書には現れない変化に目を配ることも大切です。
数字上では見えない情報は個人の感覚だけにとどめず、取引先に関するチェックリストを作成するなどし、全社で共有しておきましょう。
信用調査・与信管理ツールの導入も検討すべき
連鎖倒産を防ぐには、自社内での日常的なチェックだけでは限界があるため、信用調査会社やツールの活用をおすすめします。たとえば、信用調査会社である「帝国データバンク」の活用です。
帝国データバンクでは、取引先の情報に加えて専門家が分析した客観的な評点や詳細な財務レポートを入手できます。中には、取引先から決算書の開示を受けた上で分析しているため、新規取引や大口契約の際の判断が向上させられるでしょう。
また、近年進化しているクラウド型の与信管理ツールの導入も効果が期待できます。複数の取引先のリスク状況を継続的にモニタリングし、反社チェックや信用スコアリングを自動化できるため、貸し倒れを減らすことも可能です。
連鎖倒産のリスクから自社を守るためにも、紹介した各種ツールを積極的に活用しましょう。
3. 万が一に備える「保険」や「保証」の選択肢
自社で考える完璧な与信管理体制を築いても、倒産リスクを100%排除することはできません。ただし、優れた経営者であれば、最悪の事態を想定した上でいくつかの選択肢を持っています。
たとえば、売掛金が回収不能になった際のダメージを最小限に抑える「取引信用保険」や公的な「保証制度」の活用です。自社の財務状況やリスク許容度に合わせた選択が、不確実な倒産リスクを排除するためのポイントとなります。
売掛金回収不能時に備える「取引信用保険」の活用
万が一、取引先から売掛金が回収できない場合は「取引信用保険」を活用しましょう。「取引信用保険」とは、売掛金の貸し倒れという直接的な損害から会社を守るための、最も強力な選択肢の一つです。
売掛金の回収不能分のうち、損害額の大部分は保険金として受け取れます。キャッシュフローの急激な悪化を防ぐとともに、連鎖倒産という最悪のシナリオを回避できる効果の高い方法です。
たとえば、3,000万円の売掛金が回収不能になっても、保険に加入していればその80〜90%が補填されます。当然ながら「保険料」というコストは発生しますが、リスクを考慮すれば非常に価値の高い投資と考えられるでしょう。
不測の事態に備えた対策を講じておくことで、財務基盤を安定させられるだけでなく、安心して事業を拡大させられます。
売掛金回収不能に備えて事前に会計上、貸倒引当金を十分に積んでおけば、万が一、売掛金が全額回収不能になった場合においても、会計上、貸倒損失額を軽減することが可能になります。

増田晃士税理士事務所代表 増田 晃士(税理士)
セーフティネット保証制度の概要と活用場面
セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)は、経済環境の変化や取引先の倒産、災害などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、金融機関から融資を受けやすくするために信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
通常の保証枠とは別に「無担保8,000万円、有担保2億8,000万円(6号は3億8,000万円)」まで保証可能。保証料率は、保証協会・ケースにより異なりますが、おおむね1.0%以内で原則無保証人・無担保対応が可能です。
経営が厳しい会社であっても、セーフティネット保証を利用することで、経営を維持したり持ち直したりできる可能性があります。セーフティネット保証についてのメリットをしっかり理解して、自社においても適用できないか検討しましょう。
出典:セーフティネット保証制度 | 中小企業庁
4. 実際に倒産が発生した場合の初動対応とは?
取引先の倒産が確実となった場合、自社の損失を1円でも多く回収するためには、冷静かつ迅速な対応を心がけましょう。倒産手続きには厳格なルールがあり、初動が遅れるほど法的な権利を失い、回収の可能性は限りなくゼロに近づいてしまうからです。
まずは、倒産の事実と法的手続きの種類を正確に把握し、自社の債権額を確定させましょう。その上で、内容証明郵便の送付や債権届出といった法的な手続きを、定められた期間内に実行していく必要があります。
そのためにも、極力自己判断を避け、速やかに専門家と連携する体制が不可欠です。
内容証明・債権届出など法的手続きの基本
取引先が倒産した場合、自社の債権を回収するためには法的な手続きを迅速、かつ正確に進めることが不可欠です。倒産手続きにおいて、裁判所に対して債権を持っていることを知らせるための「債権届出」を行わなければ、原則として配当を受け取る権利がなくなります。
なお、債権届出は裁判所から通知される期間内に、必ず行わなければなりません。さらに、契約書や請求書、納品書といった、債権の存在と金額を証明する証拠書類の提出も求められます。
仮に、書類が不十分だと、破産管財人に債権を認めてもらえない可能性もあるため注意が必要です。倒産の知らせを受けたら、まずは慌てずに自社でやるべき一連の流れを間違いなく実行できるよう心がけておきましょう。
出典:破産の手続・債権届をされる方へ | 裁判所
弁護士・税理士との連携で損失の最小化を図る
倒産が発生した場合は、自己判断で動くのではなく、速やかに専門家と連携することが損失の最小化につながります。債権回収には複雑な法律知識と交渉力が求められるだけでなく、相手方にも弁護士がついているため、専門家なしで対等に渡り合うことは困難だからです。
弁護士に依頼すれば、法的に有効な催告書の作成や送付、さらには訴訟や強制執行といった法的な手続きまで、最適な手段を実行してもらえます。また、税理士の場合、回収不能となった売掛金の適切な処理によって、法人税の負担を軽減するなど税務面でサポートを受けることが可能です。
専門家のサポートを活用することで、法務と税務の両面から損失を最小限に抑えるだけでなく、本業に注力することも可能となるでしょう。
売掛金の回収不能額は税務上全額損金になりますが、貸倒損失の計上時期は相手先会社の破産決定した日が属する事業年度など細かく規定されているため、税理士に確認するようにしてください。

増田晃士税理士事務所代表 増田 晃士(税理士)
まとめ
2024年以降、倒産件数は高水準で推移しており、もはや取引先の倒産は「他人事」ではありません。連鎖倒産という最悪の事態を避けるためには「リスクの認識」「事前の対策」「事後の迅速な対応」など、一連のプロセスを体系的に構築することが不可欠です。
そのためにも、まずは支払遅延などの危険なシグナルを日常的にチェックし、与信管理ツールや信用調査で客観的な評価を行うことが求められます。さらなる与信管理を強化するためにも、取引信用保険やセーフティネット保証制度によって、万が一に備えることも大切です。
さらに、実際に倒産が発生してしまった際は慌てずに債権届出などの法的手続きを行い、弁護士や税理士と連携して損失の最小化を図る準備もしておきましょう。
記事監修者 増田税理士からのワンポイントアドバイス
国内における物価高騰や人手不足などを背景に、今後も倒産件数は増加することが懸念されます。
こうした環境のもと、取引先の倒産リスクを事前に察知すべく、財務情報や支払遅延を日常的にチェックするとともに、信用調査会社のレポートや与信管理ツールを導入することが望ましい対応だと思います。
併せて、取引信用保険に事前に加入しておくことや、セーフティネット保証制度を活用することで、万が一、取引先から売掛金が回収できなくなった場合においても損失を最小限に抑えることが大切だと思います。
取引先が倒産した場合は、自己判断で動くのではなく、速やかに専門家(債権回収面は弁護士、会計・税務面は税理士)と連携することで損失の最小化を図ってください。

新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
税金・公共料金をスマホで簡単支払い!キャッシュレス納付の方法とお得な使い方
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説