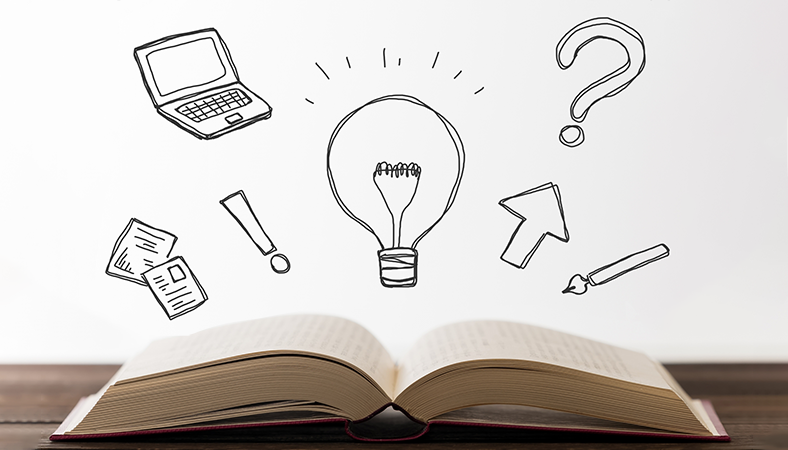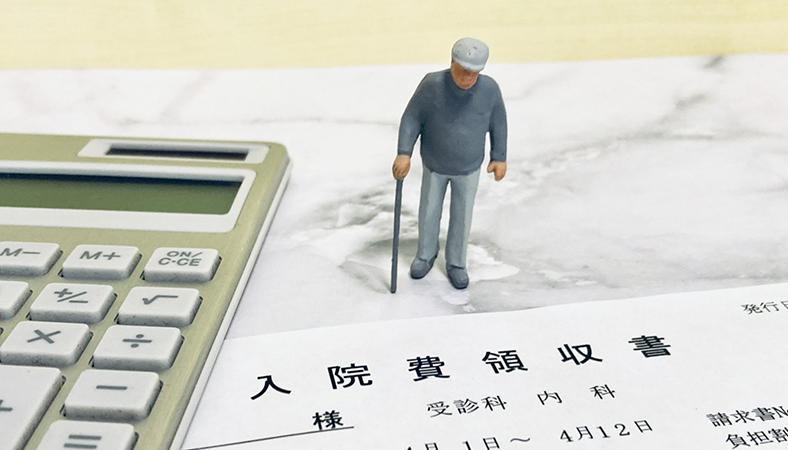社員持株会によるエンゲージメント向上と導入のポイントを解説

社員持株会制度は、福利厚生の一環としてさまざまな企業で導入されており、従業員エンゲージメントの向上にも寄与しています。
本記事では、社員持株会がエンゲージメント向上に果たす役割、基本設計とエンゲージメント効果を最大化する要素・導入プロセスや従業員への説明などについて解説します。
1. 社員持株会がエンゲージメント向上に果たす役割とメカニズム
社員持株会とは、従業員が自社の株式を購入し保有できる制度です。東京証券取引所の調査によると、東京証券取引所に上場する3,932社の中で、少なくても3,273社が社員持株会制度を採用しているのです。(2024年3月時点の情報に基づく)
社員持株会の導入には、従業員エンゲージメントを向上させる効果が期待されています。ここでは、従業員エンゲージメントの定義や測定方法、社員持株会がエンゲージメント向上に果たす役割とメカニズムを解説します。
従業員エンゲージメントの定義と測定方法
従業員エンゲージメントとは「企業と従業員のつながりの深さ」を表す指標で、企業に対する貢献意欲や愛着心に関する度合いを示します。
主な構成要素は、以下の3つです。
・企業理念やビジョンの理解度
・企業理念やビジョンに対する共感度
・業績向上への貢献意欲
従業員エンゲージメントが向上すると、結果的に生産性向上・離職率低下・顧客満足度アップなどにつながります。
従業員エンゲージメントの主な測定方法は、アンケートと面談です。
アンケートによる測定方法には、2種類あります。
・約5~10問を週に1回や月に1回の頻度で行う方法
・約50~100問を年に1回のように中長期的な視点で行う方法
アンケートでは、たとえば「仕事にやりがいを感じますか」といった質問に回答してもらい、エンゲージメントの状態を把握します。
面談による測定方法も2種類あり、定期面談と、退職時面談です。1対1で週に1回や月に1回行う定期面談では、従業員の本心や要望、課題を深く理解できます。退職者への面談では、企業に対する不満や退職の理由を明確にし改善に活かせます。
社員持株会が働く意識に与える心理的効果
社員持株会への参加によって、従業員に次のような心理的効果が生まれます。
・帰属意識の向上
・当事者意識の向上
・モチベーションの向上
・貢献意識の向上
社員持株会が与えるこれらの心理的効果は、生産性の向上や離職防止にも寄与し、結果的に長期的な企業価値向上につながります。
株主視点による経営参画意識の向上メカニズム
企業の業績は、株価や配当金に反映されます。従業員が株主である場合、業績の変動は資産に直接影響するため、企業の成長を自分ごととして捉えられます。
これにより、当事者意識やモチベーションが高まり、経営陣のビジョンと従業員の意識が一致していくのです。その結果、日常業務でも生産性やサービスの品質向上が期待できます。
2. 社員持株会制度の基本設計とエンゲージメント効果を最大化する要素
ここでは、社員持株会制度の基本設計と、エンゲージメント効果を最大化するために重要な要素について解説します。
制度の基本的な仕組みと運営体制
社員持株会とは、従業員から会員を募集し、あらかじめ希望した一定額を毎月の給与や賞与から天引きし、その資金で持株会が自社株を定期的に購入する制度です。従業員の拠出金に応じて持分が配分され、配当金も同様に分配されます。
社員持株会で購入した株式は、原則として従業員個人ではなく、理事長名義で一括保管する仕組みです。ただし、持分が売買単位相当に達し、会員が希望する場合には、従業員名義への書き換えや実質株主登録をします。非上場株式の場合は、名義書き換えに制限を設けることも可能です。
社員持株会は、企業から独立した組合として理事長(多くの場合は企業の代表)を中心に運営されます。株式の購入・保管・配当金管理といった実務は、社内で行う場合と、社外の証券会社や信託銀行に委託する場合があります。
奨励金設定によるエンゲージメント向上効果
奨励金とは、従業員が自社株を購入する際、拠出額に応じて企業が一定割合の金額を上乗せして支給する制度です。東京証券取引所の調査によると、持株会を導入している企業の96%以上が奨励金制度を採用しています。(2024年3月時点の情報に基づく)
積立額の5~10%を奨励金として負担する企業が多いとされています。これにより、従業員は自己負担額より多くの株式を取得できる点がメリットです。
東京証券取引所が実施した調査によると、社員持株会の加入者数は1989年の約162万人から、2023年には約311万人へと増加しています。一方で、社員持株会による株式保有比率(保有単元数)は1989年〜2023年まで1%前後の低位で推移しています。
さらに、持株会加入率は1989年が約47%から、2023年には約38%へ低下しているのです。これは、奨励金水準が低く持株会の魅力を感じにくかった可能性や、NISAの普及によって資産形成手段が多様化したことなどが要因と考えられています。
そこで、持株会へ参加を促すための施策として奨励金を引き上げると、従業員1人当たりの株式保有額、持株会参加率、持株会による保有比率が上昇すると報告されています。持株会への参加が促進されると、従業員の当事者意識・貢献意識・帰属意識などが高まり、結果的にエンゲージメント向上にも寄与するといえるでしょう。
加入促進と継続参加を高める制度設計のポイント
社員持株会は、長期的な運用を前提としているため、導入時の設計が重要です。
制度設計における主なポイントは次の通りです。
・目的を明確にする:従業員のエンゲージメント向上、資産形成支援など
・規則を具体的に設定する:対象者、拠出金の上限・下限、奨励金支給の有無・支給率、買付日、入退会や株式引き出し手続きなど
運用体制の構築は、専門家や、運用を委託する証券会社・信託銀行に相談しながら進めると安心してスムーズに進められます。
また、制度を導入する際は、従業員への丁寧な説明も欠かせません。制度の仕組みだけでなく、メリット・デメリットを含めて説明することで、安心感と納得感を持って参加してもらえるようになってきます。
3. 導入プロセスと従業員への効果的な説明・浸透方法
ここでは、社員持株会設立の手順、従業員に対する制度説明と参加促進のコミュニケーション戦略、さらに社内IR強化による経営参画意識醸成について解説します。
社員持株会設立の手順と必要な準備
社員持株会は、以下のような手順で準備を進めることで設立・運営を開始できます。
1.発起人・理事長・監事の選任
2.規約および運用細則の作成
3.取締役会で社員持株会設立の承認を得る
4.社員持株会発起人会の開催
5.銀行口座の開設
6.覚書の締結
7.従業員への説明および会員募集
8.運用開始
原則として、企業の取締役は、発起人や理事長といった持株会の役職に就任できないため、従業員から選任する必要があります。
従業員への制度説明と参加促進のコミュニケーション戦略
コミュニケーション戦略とは、情報を効果的かつ効率的に伝えるための施策です。企業内で行われる「インナーコミュニケーション」は、従業員との信頼関係構築、組織の一体感向上、満足度や意欲向上を目的としています。主な手段は、社内報、社内SNS、研修・説明会・イベントなどです。
コミュニケーション戦略において、重要なポイントには以下のようなものがあります。
・目的を明確にする
・デジタルとアナログのツールを併用する
・従業員にとって有益な情報を提供する
・現状を把握し、課題に応じた内容を発信する
持株会に関する説明においても「自社の株主になることで、企業の成長や資産形成に主体的に関与できる」メリットを伝え、モチベーション向上につなげることが重要です。社内報・社内SNS・動画配信・説明会など、複数の方法を組み合わせると効果的です。
社内IR強化による経営参画意識の醸成
社員持株会と社内IRを連携し、従業員が株主としての視点を養うことで、経営に対する参画意識の向上を促している企業があります。
具体的には、以下のような取り組みがあります。
・経営陣による持株会会員を対象とした説明会
・社内版IRレポートの発行
・金融や経営知識に関する研修会の実施
業績報告、経営計画、成長戦略、株価・配当金動向、金融・経営に関する基礎知識などをわかりやすく伝えることで、従業員が企業の成長を自分ごととして捉えるようになるのです。これにより、モチベーションや貢献意欲が高まり、エンゲージメント向上にもつながります。
4. エンゲージメント効果の測定と制度運用の継続的改善
ここでは、エンゲージメント効果の測定と、制度を継続的に改善していくためのポイントについて解説します。
社員持株会導入前後のエンゲージメント測定手法
従業員エンゲージメントを測定する際には、目的を明確にし、従業員にも共有することが重要です。測定方法として多くの企業で活用されているのは、アンケート調査です。
アンケートでは、以下の2つの観点から質問を設定します。
・エンゲージメントの現状を測る質問(帰属意識、やりがいなど)
・エンゲージメント向上のために必要な要因を把握する質問(主体性、満足度、企業風土など)
アンケートは、半年〜1年に1回など、定期的に実施することで、スコアの変化や新たな課題を可視化できます。結果は、分析して改善策の実行や、フィードバックにつなげることが重要であり、従業員のモチベーション維持にも効果が期待できるでしょう。
制度運用の透明性確保と従業員満足度向上
透明性の高い制度運用は、従業員の納得感・信頼感を生み、満足度向上につながります。
具体的には、以下のような情報を定期的に開示することが重要です。
・拠出金の管理状況
・株価や配当金の動向
・制度改正や運用ルールの変更内容
さらに、従業員からの意見や要望を取り入れることも、制度改善や信頼関係の構築に有効です。また、株式・配当金の配分ルールや、奨励金制度を明確かつ公平に設計することで、従業員満足度とエンゲージメント向上につながります。
他社事例から学ぶエンゲージメント向上の成功要因
アクセンチュアの調査(2017年11月)によると、社員持株制度を実際に導入している中小企業が感じているメリット(複数回答)は、以下の通りです。
・経営参画意識の向上:74.1%
・業績向上意欲の上昇:62.6%
・安定株主の確保:37.9%
・福利厚生として有効:29.6%
・離職率の低下:11.8%
エンゲージメントに関する効果が上位に入っていることがわかります。なお、デメリットは「とくにない」が66.1%ともっとも多く、次いで「事務手続きの煩雑化」が20.7%でした。
持株制度の導入を成功させるために、重要とされているポイントは以下の通りです。
・運営情報の透明性
・奨励金の支給
・手軽に参加できる制度設計
・従業員の意見を反映する仕組み
・定期的な制度の見直し
・成功事例の共有
このような要因が備わることで、従業員の信頼感や満足感を高め、エンゲージメント向上にも寄与します。
まとめ
社員持株会とは、従業員が自社の株式を購入し保有できる制度です。社員持株会の導入によって、従業員エンゲージメントの向上が期待されています。
従業員エンゲージメントとは「企業と従業員のつながりの深さ」を示す指標で、企業に対する貢献意欲や愛着心に関する度合いを表します。従業員エンゲージメントが向上すると、結果的に生産性向上・離職率低下・顧客満足度アップなどにもつながるのです。
社員持株会は、長期的な運用を前提とした制度であるため、導入時の設計が重要とされています。主なポイントは「目的を明確にする」「規則を具体的に設定する」ことです。制度を導入する際は、従業員への丁寧な説明も欠かせません。
制度の仕組みだけでなく、メリット・デメリットを含めて説明することで、安心感と納得感を持って参加してもらえるようになり、エンゲージメントの向上にもつながります。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
税金・公共料金をスマホで簡単支払い!キャッシュレス納付の方法とお得な使い方
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説