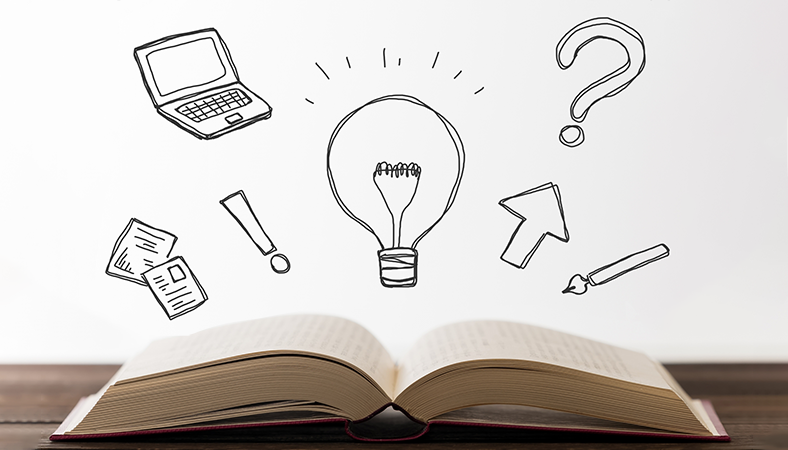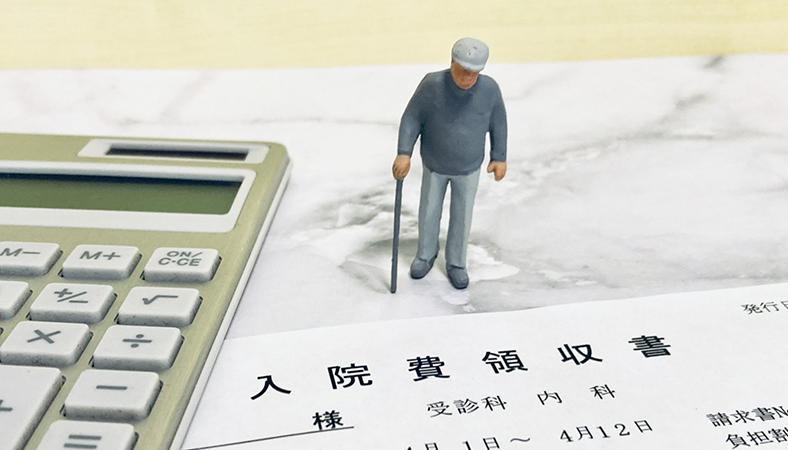老後資金はどう変わる?2025年改正の変更点と私たちにできる備えをわかりやすく解説

少子高齢化や働き方の多様化といった時代背景を受け、年金制度にもこれまで以上に柔軟性と公平性が強く求められるようになり、2025年6月に「年金制度改正法」が成立しました。
今回の改正では、短時間労働者や中小企業で働く人々、共働き家庭、自営業者など、多様な立場の人にとって重要な変更点が含まれており、将来の老後生活設計にも大きな影響を与えます。
今回の改正には、遺族年金の男女格差是正や育児期間の保険料免除など、家族のかたちや働き方の変化に対応した内容も盛り込まれました。この記事では、改正の背景とポイントをわかりやすく整理し、私たち一人ひとりが取るべき備えや、企業に求められる対応までを詳しく解説します。
1. 年金制度改正法とは?2025年6月成立の背景
2025年6月、「年金制度改正法」が成立した裏側には、少子高齢化が進み、働き方も多様化する中で、年金制度の柔軟性と公平性がこれまで以上に求められている背景があります。今回の改正は、現役世代と高齢世代における負担と給付のバランスを見直し、すべての人にとって持続可能な年金制度を目指すものです。
短時間労働者や中小事業者、遺族年金のあり方など、私たち一人ひとりの働き方や暮らしにも影響を与えるポイントが多く含まれています。ここでは、改正の背景と主な変更点、今後のスケジュールについて、わかりやすく解説していきます。
2025年改正法の成立概要とスケジュール
2025年6月、年金制度の見直しを盛り込んだ「年金制度改正法」が成立しました。今回の改正のポイントは、少子高齢化や働き方の多様化といった時代の変化を踏まえ、「より柔軟で公平な制度」にアップデートすることです。
特に注目されるのは以下のような改正点です。
・短時間労働者の厚生年金適用拡大
・個人事業所(5人以上の従業員)の非適用業種を解消
・在職老齢年金の見直し
・遺族年金の男女格差の解消
・厚生年金保険料上限の引き上げ
・将来の基礎年金給付水準の底上げ
それぞれの施策には段階的な実施スケジュールが設けられており、早いもので2026年4月からの実施が予定されています。今後も最新の情報をしっかり確認し、自分自身の年金プランを見直すことが大切です。(2025年6月13日時点の情報に基づく)
少子高齢化と財源確保に向けた再構築
なぜ、今このタイミングで制度改正が必要だったのでしょうか。その背景にあるのは、少子高齢化と人口減少の加速です。現役世代の負担が増え、高齢者の割合が増え続ける中、年金制度がこのままでは立ち行かなくなるという強い危機感があります。
2024年7月に発表された5年に一度の年金財政検証では、今後100年間の年金給付の見通しと、試算が公表されました。その中で、今後の年金給付水準について、所得代替率は50%を上回る結果が出ています。
今回の改正は、社会の流れにあわせて年金制度を「再構築」する一歩です。企業や個人の負担も軽くはありませんが、より公平で持続可能な仕組みに向けた土台づくりといえるでしょう。
2. 今回の年金制度改正で何が変わるのか?
2025年の年金制度改正では、時代の変化に合わせて、さまざまな制度が見直されました。特に注目されているのは、男女間の不公平の是正や、出産・育児と年金制度とのつながりの強化です。
共働きや多様な家族のかたちが当たり前となった今、年金制度も従来の前提を見直し、より柔軟で公平な仕組みへと進化しています。ここでは、今回の改正で私たちの暮らしに直接関わる主な変更点を見ていきましょう。
① 遺族年金の男女間格差の是正
遺族年金は、家庭の大黒柱を失った家族を経済的に支える重要な制度です。これまでの制度では、子どもがいない55歳未満の男性配偶者には遺族厚生年金が支給されないなど、男女間に不公平な点がありました。
しかし、現代では共働き世帯が増え、夫婦双方が経済的な支えとなるケースが多くなっています。こうした社会の変化を受けて、今回の改正では男女間の格差を解消し、男性にも遺族年金が支給されるよう制度が見直されました。
たとえば次のようなケースでの支給停止措置が見直されます。
-
離婚後に父(母)が死亡し、子どもが母(父)に引き取られた場合に子どもへの遺族基礎年金が停止される
-
父(母)が死亡して子どもが母(父)に引き取られ、再婚してその新しい家族と同居すると子どもの遺族基礎年金が止まる
-
親が死亡し、祖父母と養子縁組した場合の子どもの遺族基礎年金停止
-
片親が死亡し、配偶者の収入が一定以上(850万円)ある場合の子どもの遺族基礎年金停止
これらの見直しにより、実際の生活状況に即した柔軟な支援が期待できます。加えて、厚生年金に加入していた妻が亡くなった場合でも、夫が遺族厚生年金を受け取れるようになるなど、男女を問わず公平な支給が進みます。
このように、今回の改正によって遺族年金は性別に関係なく、現代の家族のかたちに合わせた支援が強化されました。これにより、さまざまな家庭環境でも安心して生活できる制度となり、社会全体のセーフティーネットとしての役割が一層充実すると期待されています。
② 出産・育児と年金の接続強化(育児期間の年金保険料免除等)
今回の改正では、出産や育児と年金制度のつながりを強化し、育児休業中の年金保険料免除など、支援が充実されました。具体的には、育児期間の保険料が免除されるとともに、将来の年金受給にマイナスの影響が出ないよう保険料納付済みとして扱われます。
さらに、配偶者も育児休業を取得している場合は、これを合わせて育休取得期間としてカウントできるため、育児参加の促進が見込まれます。このような見直しにより、男性も育児に積極的に参加しやすくなり、仕事と育児の両立を支える制度が公的年金制度の面からも強化されたのです。
3. 自営業・フリーランスに影響ある?
年金制度の見直しは、会社員や公務員など厚生年金加入者にとって大きな影響がありますが、自営業者やフリーランスはどうなるのか、気になる方も多いでしょう。実は今回の改正では、国民年金や基礎年金に対する大きな変更はなく、自営業やフリーランスに直接的な影響は限定的です。
ただし、配偶者が厚生年金に加入している場合は、遺族年金や扶養制度の見直しによって間接的に影響を受ける可能性もあります。ここでは、自営業・フリーランスの立場から見た改正のポイントを整理してみましょう。
国民年金と基礎年金への影響は限定的
今回の年金制度改正は、主に厚生年金加入者を対象としており、自営業やフリーランスが加入する国民年金や基礎年金に対する影響は比較的限定的です。国民年金の支給額は物価や賃金変動に連動した調整が行われ、2025年度も一定の増額が見込まれていますが、大きな制度変更はありません。
したがって、自営業者やフリーランスの方にとっては、基本的な受給資格や給付水準が大きく変わるわけではなく、現行の制度が微調整されるかたちとなります。ただし、今後の年金財政や社会情勢の変化に伴い、将来的には基礎年金の給付水準や支給条件について見直しが検討される可能性もあるため、最新の情報を注視しておくことが大切です。
遺族年金・扶養制度における取り扱いの再確認を
一方で、遺族年金や扶養制度に関しては、今回の改正により一定の見直しが進んでいます。特に遺族厚生年金の支給対象が拡大され、40歳未満の女性や60歳未満の男性で18歳以下の子どもがいない場合でも、一定期間の有期給付が受けられるようになる点は注目すべき大きな変化と言えるでしょう。
ただし、以下の人はこれまで通り制度が継続されます。
・すでに遺族厚生年金を受け取っている人
・60歳以降に受給が始まる人
・年度末時点で子ども(18歳以下)がいる人
・令和10年度に40歳以上になる女性
新たに対象となる人は、まず5年間の有期給付を受け、その後も障害がある人や収入が少ない人(単身で月の就労収入が約10万円以下)は継続して受給できます。年金額は、収入に応じて段階的に調整される設計です。
子どもがいる家庭では、18歳まではこれまで通り、さらに18歳を超えた後も5年間は増額支給の対象とされます。加算額も引き上げられ、1人あたり年間約28万円に増額され、3人目以降も同様です。これは既存の受給者も対象となっています。
4. 年金制度の今後と、私たちができる備え
今回の年金制度改正はゴールではなく、将来に向けた第一歩です。少子高齢化が進み、社会の構造が変わっていく中で、私たち一人ひとりがどのように備えるかが、これからますます重要になります。
年金の受け取り方には柔軟な選択肢が用意されており、繰上げ・繰下げ受給やiDeCoとの併用によって、ライフプランに合わせた資産形成も可能です。企業側にも、制度改正への対応や従業員への情報提供といった役割が求められています。
ここでは、改正後の制度を踏まえて、個人と企業がどのような準備や工夫をすべきかを整理していきます。
繰上げ・繰下げ受給の柔軟性やiDeCoとの組み合わせ
年金は通常であれば65歳から受け取れますが、66歳〜75歳まで繰り下げ可能で、繰り下げると月0.7%ずつ増額されます。70歳までなら約42%増、75歳までなら約84%増です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り下げることも、別々に繰り下げることも可能です。ライフプランに合わせて柔軟に選択できるのが、年金の魅力です。ただし、働きながら老齢厚生年金を受給すると支給停止になる場合があるため注意しましょう。
自営業の方は、付加保険料の納付や国民年金基金の加入により将来の年金額を増やせます。厚生年金加入者は加入期間を延ばすことで年金額アップも可能です。
さらに、iDeCoを活用することで、老後資金を自分で計画的に積み立てる選択肢もあります。税制優遇もあるため、年金制度と組み合わせて検討するとよいでしょう。
企業側は年金制度の説明責任が求められる
年金制度の改正は、企業にとっても大きな影響を及ぼします。そのため、就業規則や福利厚生規程の見直しが必要となり、社員への周知や説明会の開催など、丁寧な対応が求められます。
今回の改正は、改正内容が複雑なため、専門的な情報提供や相談窓口の設置も重要です。社員一人ひとりが年金制度を正しく理解し、不安なく働き続けられる職場づくりを推進していくことが、企業の持続的な成長にもつながるでしょう。
まとめ
2025年の年金制度改正は、少子高齢化や多様な働き方を背景に、大きく見直された重要な一歩です。短時間労働者の適用拡大や遺族年金の男女格差是正、育児との接続強化、そしてiDeCoとの組み合わせによる柔軟な備えなど、私たちの生活に直結するものです。
個人にとっては、制度の詳細をしっかり理解し、ライフプランに応じた年金受給のタイミングや資産形成の方法を選ぶことが、これまで以上に重要となるでしょう。一方、企業には、従業員への正確な情報提供や研修の実施など、幅広い対応が求められています。
年金制度は社会全体の安心に直結するため、今後も改正の動向を注視し、早めの準備を進めていくことが大切です。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
税金・公共料金をスマホで簡単支払い!キャッシュレス納付の方法とお得な使い方
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説