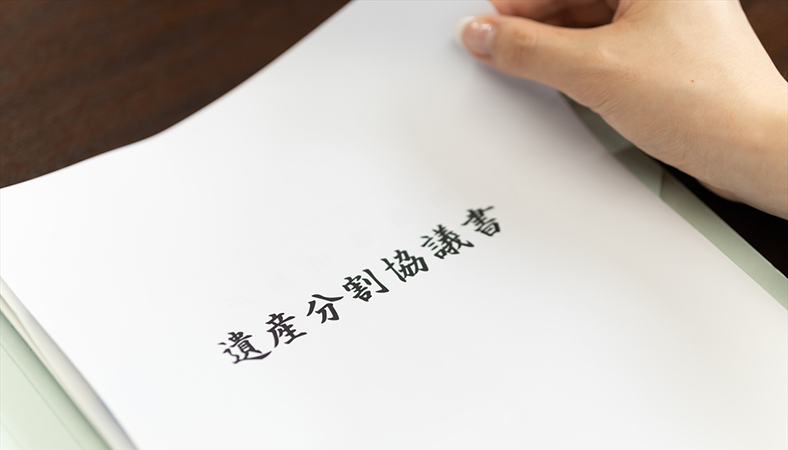出産育児一時金の財源に確定!後期高齢者医療制度の保険料を所得に応じて引き上げへ

75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の保険料の上限額引き上げなどを盛り込んだ改正健康保険法が、5月12日に行われた参議院本会議で賛成多数で可決、成立しました。これにより、出産育児一時金の財源の一部を75歳以上も新たに負担することになります。
後期高齢者医療制度の仕組みとは
後期高齢者医療制度は、平成20年(2008年)に高齢化による医療費増加を社会全体で支える仕組みとして75歳以上を対象に創設されました。以来、74歳以下の現役世代が負担する後期高齢者支援金は大きく増加し、現役世代は制度創設時に比べ、負担が1.7倍になりました。
加えて、令和7年(2025年)までに、戦後の昭和22年〜24年(1947年〜1949年)に生まれた世代である「団塊の世代」が後期高齢者となります。ますます74歳以下の現役世代の負担が大きくなることは避けられないと言われています。
令和4年(2022年)10月には、現役並みに一定以上の所得がある後期高齢者に限り、医療費の窓口負担が1割から2割へと引き上げられました。
後期高齢者医療制度については、「75歳以上は2割に!?後期高齢者の医療費自己負担はどう変わる?」をご覧ください。
保険料引き上げは2024年度から2年かけて段階的に実施
4月1日より50万円に増額された出産育児一時金の財源に充てるため、政府は後期高齢者医療制度の保険料の上限額引き上げなどを盛り込んだ改正健康保険法が5月12日に行われた参議院本会議で成立しました。
法改正により、今後、高齢者の負担は段階的に増える見込みで、2024年度に年金収入211万円を超える人、2025年度には153万円を超える人と高齢者全体約4割の方の保険料が増えるとされています。また年収約1,000万円を超える高所得者の保険料上限額が、今の年66万円から2024年度に73万円、2025年度からは80万円へと大幅に引き上げられる予定です。
今回の改正は、これまで74歳以下の現役世代が負担していた出産育児一時金の財源を、後期高齢者医療制度からも捻出するため、所得などに応じて支払う保険料の上限額を段階的に引き上げるとしています。
少子高齢化が進むなか、高齢者の医療費財源の半分弱を賄っている現役世代の負担を軽減する狙いがあるとしています。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025参院選】選挙公報・政見放送の見方と政策比較のポイントを徹底解説
-
【2025参院選】参院選で私たちの生活はどう変わる?各政党の政策を徹底比較・完全解説
-
米国向け輸出入企業必見!トランプ関税が導入されたら?国別影響と対応策を仮想シナリオで徹底解説
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ
-
トランプ政権の“品目別関税”とは?業界別影響と企業がとるべき対策を解説