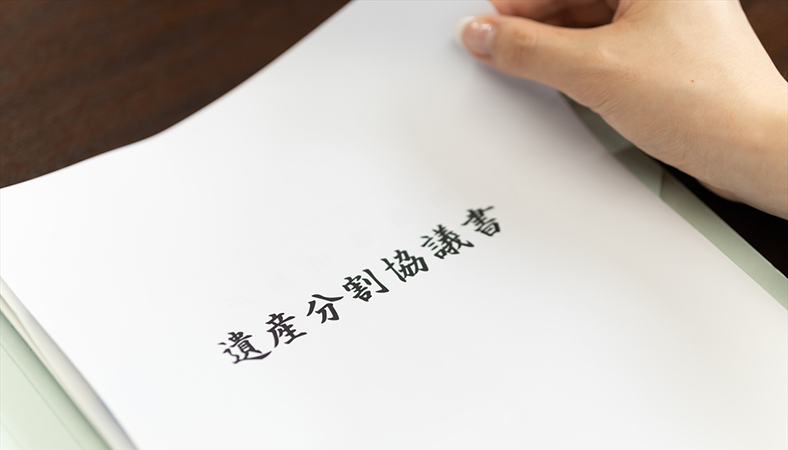2065年から2115年へ料金徴収期限が50年延長高速道路無料化は半永久的に先送り?

全国の高速道路を最長2115年まで有料とする道路整備特別措置法などの関連法案が5月31日の参院本会議で、賛成多数で可決・成立したことがわかりました。これにより2065年までとしていた高速道路の有料期限を50年延長し、半永久的に料金徴収が続くことになるようです。
期限延長は老朽化した橋やトンネルの改修費用を確保か
政府は、いままで高速道路の有料化期間を2065年までとし、その後無料化するとしていた道路整備特別措置法と日本高速道路保有・債務返済機構法を2月の閣議でそれぞれ一部改正、最大で50年延期することなどを盛り込んだ法律案を決定。今回の法改正で期間が2115年までとなり、事実上、料金徴収が半永久的に続くことがわかりました。
料金徴収期限については、2012年に発生した中央自動車道の笹子トンネルの崩落事故でインフラの老朽化が発覚し、設備更新費用を捻出するため2014年の法改正で有料期間を65年まで延長。今回、さらに期間が延長されることで無料化の実現は一段と厳しくなってきました。政府が当初設定していた「将来の高速道路無料化」は事実上、棚上げされる形となりそうです。
全国の高速道路は、建設費を賄うための借り入れを料金徴収で返す仕組みとなっていますが、政府はこれらの借金完済後に無料化する考えだったようです。
しかし、高速道路を管理する「NEXCO」各社は、橋梁やトンネルなどの設備で深刻な老朽化が進んでおり、対策に要する費用が膨張することが避けられないなどもあり、整備や点検、補修、設備更新のための財源を確保する必要があると判断。
政府は、現在は健全でも2115年までに老朽化して工事が必要になるとみられる箇所を含め、改修費は総額8兆3千億円必要だと試算。
法改正に伴い、国土交通省は設備補強などの計画については一定期間ごとに見直しながら対策を進めるとし、2115年まで料金徴収期間を順次延長するとみられています。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025参院選】選挙公報・政見放送の見方と政策比較のポイントを徹底解説
-
米国向け輸出入企業必見!トランプ関税が導入されたら?国別影響と対応策を仮想シナリオで徹底解説
-
【2025参院選】参院選で私たちの生活はどう変わる?各政党の政策を徹底比較・完全解説
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ
-
トランプ政権の“品目別関税”とは?業界別影響と企業がとるべき対策を解説