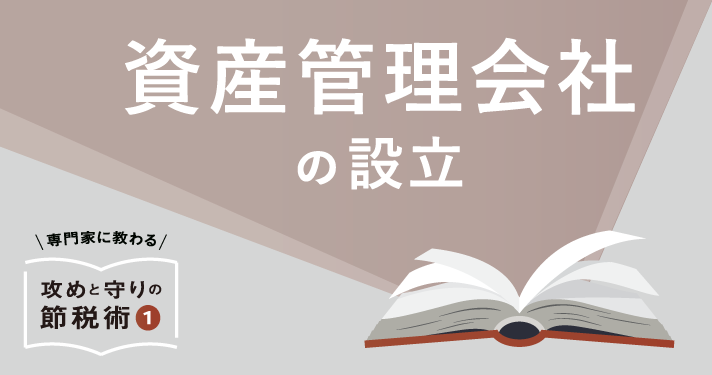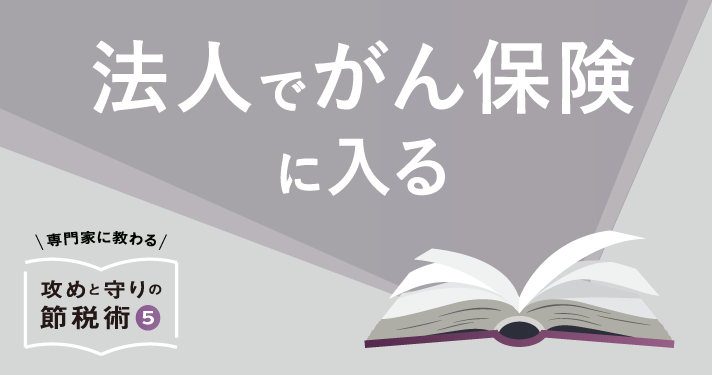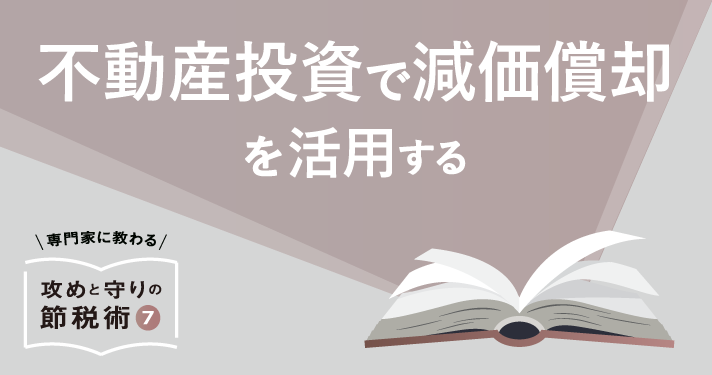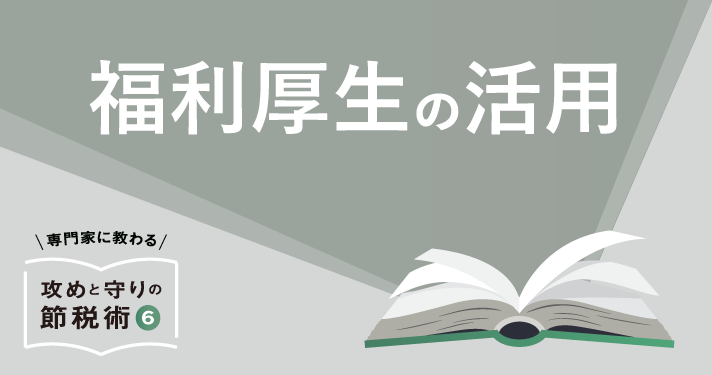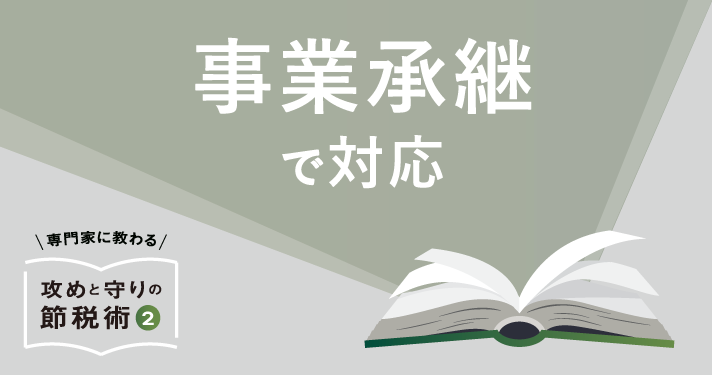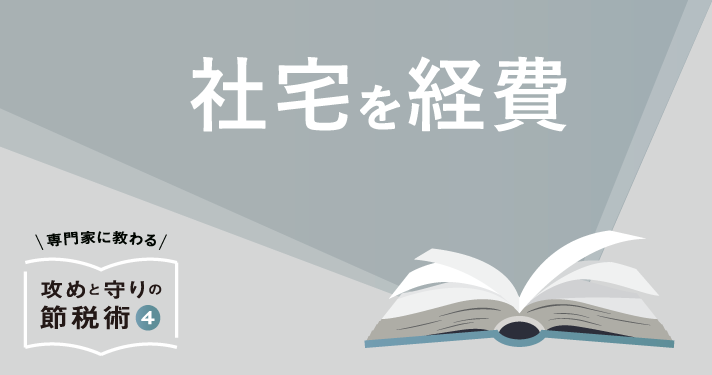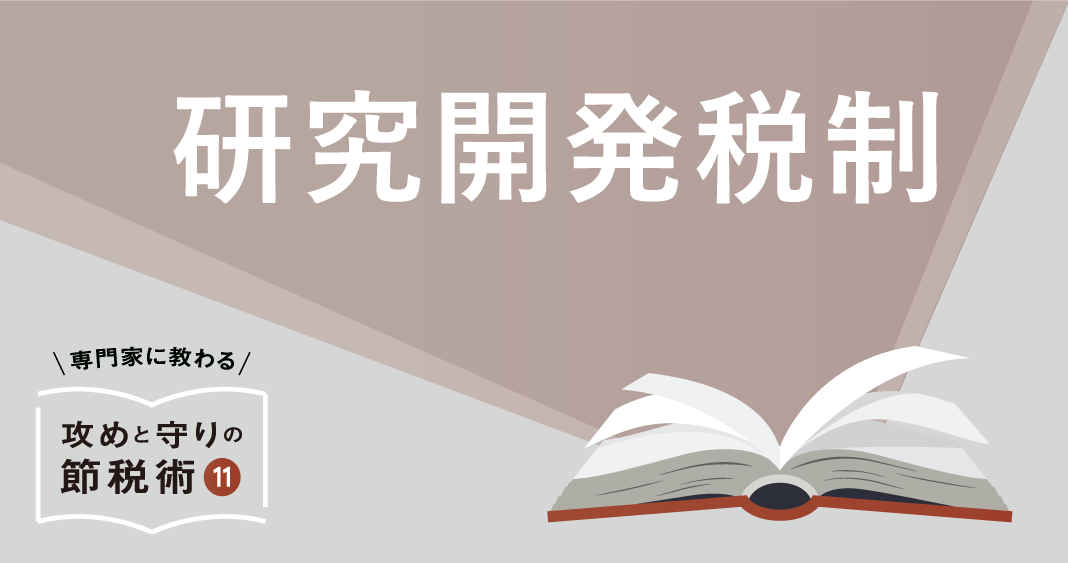
「研究開発税制」という節税術
研究開発費とは自社のシステムやサービスを開発・改善し、事業を拡大したり経営方針を転換したりする際にかかる経費を指します。
しかし、研究開発費を単なる費用計上で終わらせるのはもったいないかもしれません。
実は一定の要件を満たすことで、法人税などの税負担を軽減できる「研究開発税制」を活用できる可能性があるのです。
この記事では、節税につながる「研究開発税制」の仕組みや適用する際の注意点について、わかりやすく解説します。
研究開発費とは
研究開発費とは、企業が新しい技術やサービスを創出したり、既存のものを改良したりするためにかかる費用のことです。
企業会計審議会が公表している「研究開発費等に係る会計基準」によると、「研究」と「開発」は以下のように定義されています。
新しい知識の発見を目的とした、計画的な調査及び探究
新しい製品・サービス・生産方法などの計画や設計、または既存の製品等を改良するための計画や設計といった、研究の成果や知識を具体化する活動
具体的な例として、企業会計基準委員会が発表している「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」では、以下のような事例を「研究・開発の範囲」としてあげています。
- 従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査や探究
- 新しい知識の調査や探究の結果を受け、製品化または業務化を行うための活動
- 従来の製品と比べて顕著な相違を作り出す製造方法を具体化
- 従来と異なる原材料の使用方法や部品の製造方法を具体化
- 既存の製品、部品について、従来と異なる使用方法を具体化
- 工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法を具体化
- 新製品の試作品の設計や製作の実験
- 商業を生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画
- 取得した特許をベースとして、販売可能な製品を製造する技術的活動
出典:企業会計基準委員会「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」
これらの研究開発の範囲からわかるように、新しい技術やサービスを一から開発したものだけでなく、既存のサービスを改良し、よりよくするための調査や試行錯誤なども研究、開発に含まれます。
研究開発費に含まれる費用
研究開発費には、研究開発活動のために直接的または間接的に使用された以下のような原価が含まれます。
- 人件費
- 原材料費
- 固定資産の減価償却費
- 間接費の配賦
重要なのは、これらの費用が「研究・開発の範囲」、つまり「新しい知識の発見」や「研究成果の製品・サービスへの応用」などに該当する業務に使われているかどうかです。
たとえば、研究開発部門の業務であっても、市場調査や一般的な事務作業など、「研究・開発の範囲」に該当しない活動にかかった費用は、研究開発費としては計上できません。
一方で、研究開発を専門としない部門、たとえば製造部門や営業部門であっても、新しい生産方法の試験的な導入や製品改良のための実験など、「研究・開発の範囲」に含まれる活動に要した費用は、研究開発費として認められます。
研究開発費に含まれない費用
「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」では、研究開発費に含まれない業務として以下のような典型例を挙げています。
- 製品を量産化するための試作
- 品質管理活動や完成品の製品検査に関する活動
- 仕損品の手直し、再加工など
- 製品の品質改良、製造工程における改善活動
- 既存製品の不具合などの修正についての設計変更や仕様変更
- 客先の要望等による設計変更や仕様変更
- 通常の製造工程の維持活動
- 機械設備の移転や製造ラインの変更
- 特許権や実用新案権の出願などの費用
- 外国などからの技術導入により製品を製造することに関する活動
出典:企業会計基準委員会「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」
典型例を見ると、設計変更・仕様変更・検査・量産化のための試作などにかかる費用は「研究開発費」に含まれないことがわかります。これらの業務は、研究開発を専門とする部門でも行われるため、会計処理の際の区別には一層の注意を施しましょう。
研究開発費の会計処理
会計処理するタイミングは大きく分けて、一般管理費として計上する場合と製造原価費用として計上する場合の2種類があります。
- 一般管理費として計上する場合
「研究・開発の範囲」に含まれる活動から生じる費用は、当期の製造費用ではなく、基本的に一般管理費として処理します。これは、これらの活動が特定の製品やサービスの製造に直接的に結びつかないためです。
なお、研究開発費を一般管理費として処理する際は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第86条第1項」により、その総額を財務諸表に注記することが義務付けられています。
会計処理の際は、費用の記録だけでなく、期末における研究開発費の総額の把握と注記を忘れないようにしましょう。 - 製造原価として計上する場合(限定的なケース)
一部の例外として、研究開発活動が製造プロセスの改善や効率化に直接関連する場合、その費用を製造原価として処理できるケースがあります。ただしこの場合は、他の製造原価と明確に区別することが難しいことが前提です。
例:新製品の量産体制を確立するための、試験的な製造ラインの構築・改良にかかる費用 など
こうしたケースでも、研究開発費の内容を適切に管理し、財務諸表上でもその処理の根拠を明確にする必要があります。
会計処理時に注意すべきポイント
研究開発費の会計処理は、費用の発生時点で行うのが原則です。将来の見積もりや発生予定に基づいて処理することはできません。一般管理費として計上する場合は、財務諸表への注記を忘れずに行いましょう。
製造原価として処理する場合も、内訳を適切に記録・管理し、必要に応じて注記することが重要です。会計処理に迷った場合は、税理士や会計士などの専門家に相談することをおすすめします。
「研究開発税制」の節税メリット
「研究開発税制」を活用すれば、法人税の一部を直接控除でき、中小企業でも大きな節税メリットが得られます。
ここでは、その仕組みと具体的なメリットをわかりやすくご紹介します。
節税メリット1 法人税の税額控除が受けられる(最大25%)
研究開発税制の最大のメリットは、法人税額から一定額を直接控除できる点です。通常の経費のように損金算入されるだけでなく、実際の税額から減額されるため、非常に大きな節税効果が得られます。えるでしょう。
節税メリット2 控除対象となる費用の範囲が広い
研究開発税制は幅広い業種・業態で対象になることが多く、ITシステム開発や製造業以外でも活用できる場合があります。たとえば、以下のような費用も要件を満たせば控除の対象となります。
- 研究者・開発者の人件費
- 材料費や機械装置の減価償却費
- 外部委託した開発費用
- 間接費の一部 など
節税メリット3 中小企業向けの優遇措置が充実している
中小企業の場合、以下のような優遇措置も受けられます。
- 控除率が大企業より高い
- 税額控除の上限が法人税額の25%まで可能
- 赤字企業でも一部のケースで税額控除を繰越しできる
黒字・赤字を問わず、中小企業にとっては特に使いやすい制度になっているのが特徴です。
節税メリット4 節税しながら将来の売上・利益の源泉を育てられる
節税による直接的な効果だけでなく、研究開発税制の活用をきっかけに、企業の成長に直結するさまざまな副次的メリットも期待できます。たとえば次のような効果があります。
- 製品やサービスの革新につながる
- 競争力の強化、差別化が図れる
- 研究体制・社内技術の再評価・再構築が進む
研究開発税制の注意点
大きな節税効果が期待できる研究開発税制ですが、活用する際にはいくつか注意すべきポイントがあります。制度の複雑さから誤解されやすい点もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
注意点1 対象となる費用の範囲を誤認しやすい
一見、研究に関連していそうな費用でも、「研究・開発の範囲」に該当しないと認められないことがあります。
たとえば、市場調査や宣伝活動、教育研修費などは対象外です。判断が難しい場合は、税理士や会計士などの専門家に相談しましょう。
注意点2 税制適用の要件を満たしていないと否認されるリスクがある
税額控除を受けるには、「技術の新規性」や「不確実性」「体系的な計画」などが要件になることが多く、これらを文書で証明する必要があります。
税務調査で否認されるケースもあるため、根拠資料(研究報告書・開発計画・実験記録など)を残しておくことが大切です。
注意点3 制度が複雑で毎年見直される
「研究開発税制」は頻繁に改正されるため、最新の要件や控除率を把握しておく必要があります。
特に中小企業向けの特例や繰越控除の条件などは年度ごとに変わることがあるため、注意が必要です。
注意点4 他の税額控除と併用できない場合がある
たとえば、「賃上げ促進税制」や「投資促進税制」など、他の制度と併用する際には、控除上限の調整が必要になる場合があります。
併用による影響を十分に確認したうえで、税理士や会計士などの専門家と連携し、節税効果を最大限に引き出しましょう。
注意点5 過度な節税目的の利用はリスクがある
実体のない研究活動や、形式的に研究費として計上した費用に対しては、税務当局から否認される可能性があります。
あくまでも「事実に基づいた実態のある研究開発活動」が前提となります。
この節税術に必要な心構えとは
研究開発税制は企業にとって節税につながる制度ですが、適用には注意すべき点も多くあります。制度を正しく理解し、必要な準備や書類を整えることが大切です。
研究開発税制を活用する際は、税理士などの専門家の助言を得ることで、より効果的に節税を実現でき、企業の成長をサポートできます。専門家のアドバイスを受けることで、複雑な手続きや申請をスムーズに進められ、企業にとってのメリットを最大限に引き出せるでしょう。
顧問税理士を持つことは特に有効であり、企業にとって大きなサポートとなります。専門家の力も借りながら、節税と成長の両方を実現できる研究開発税制を活用してみてください。