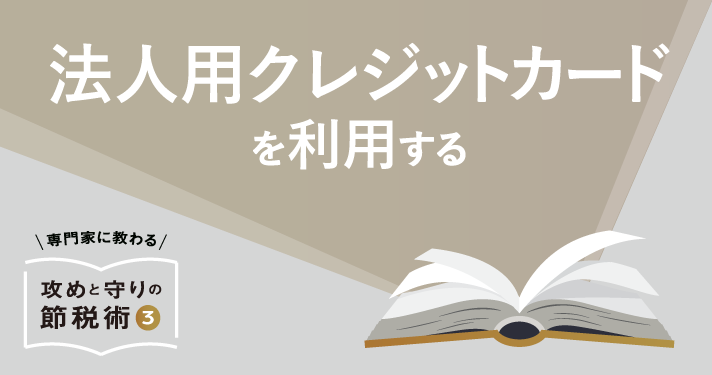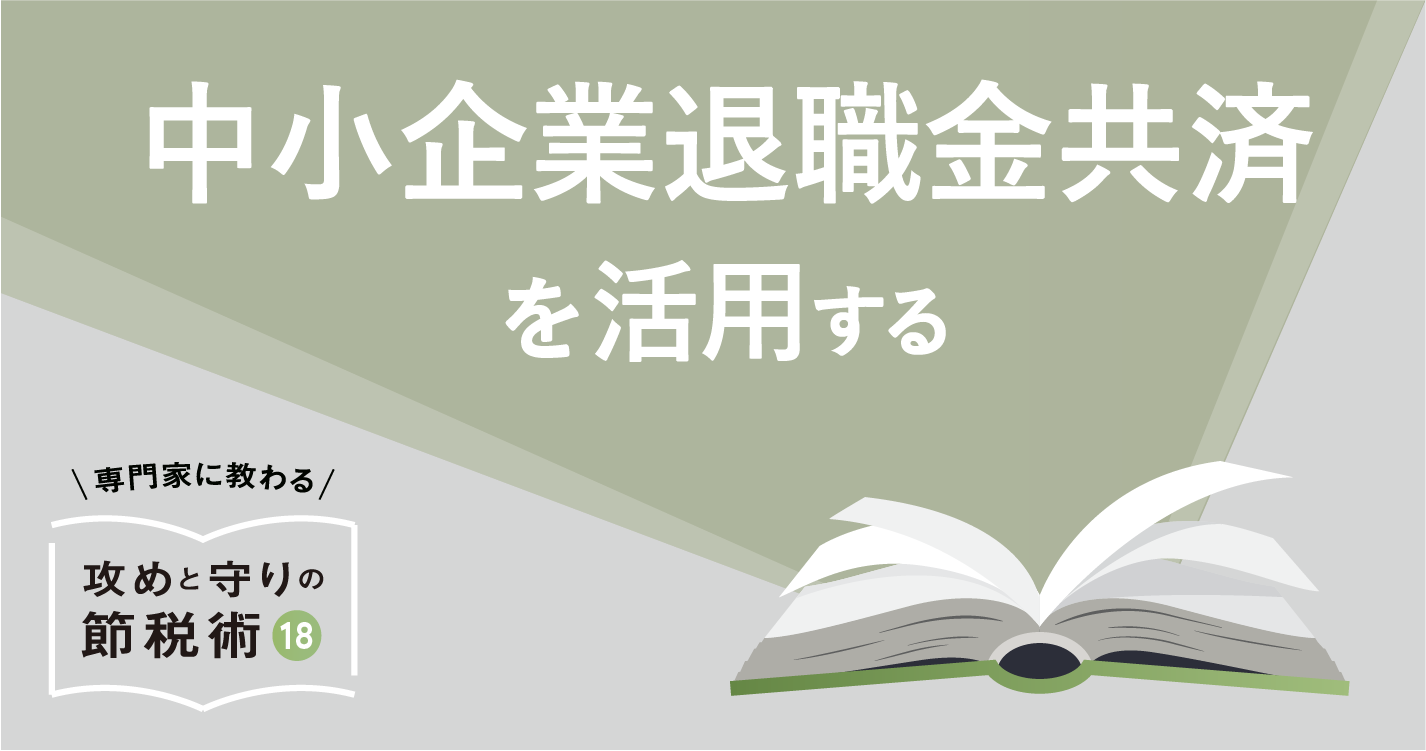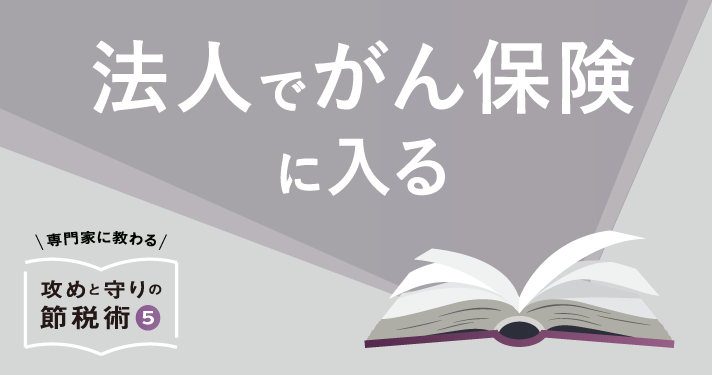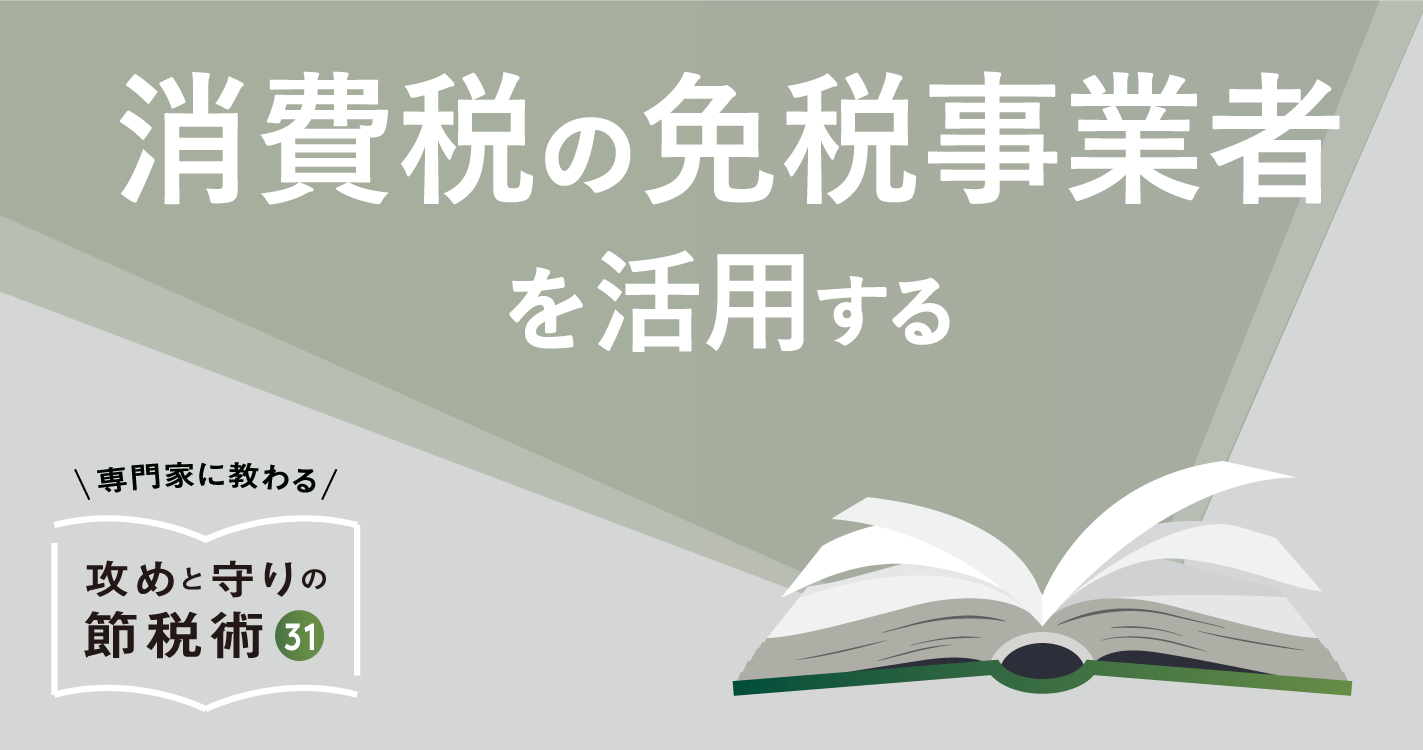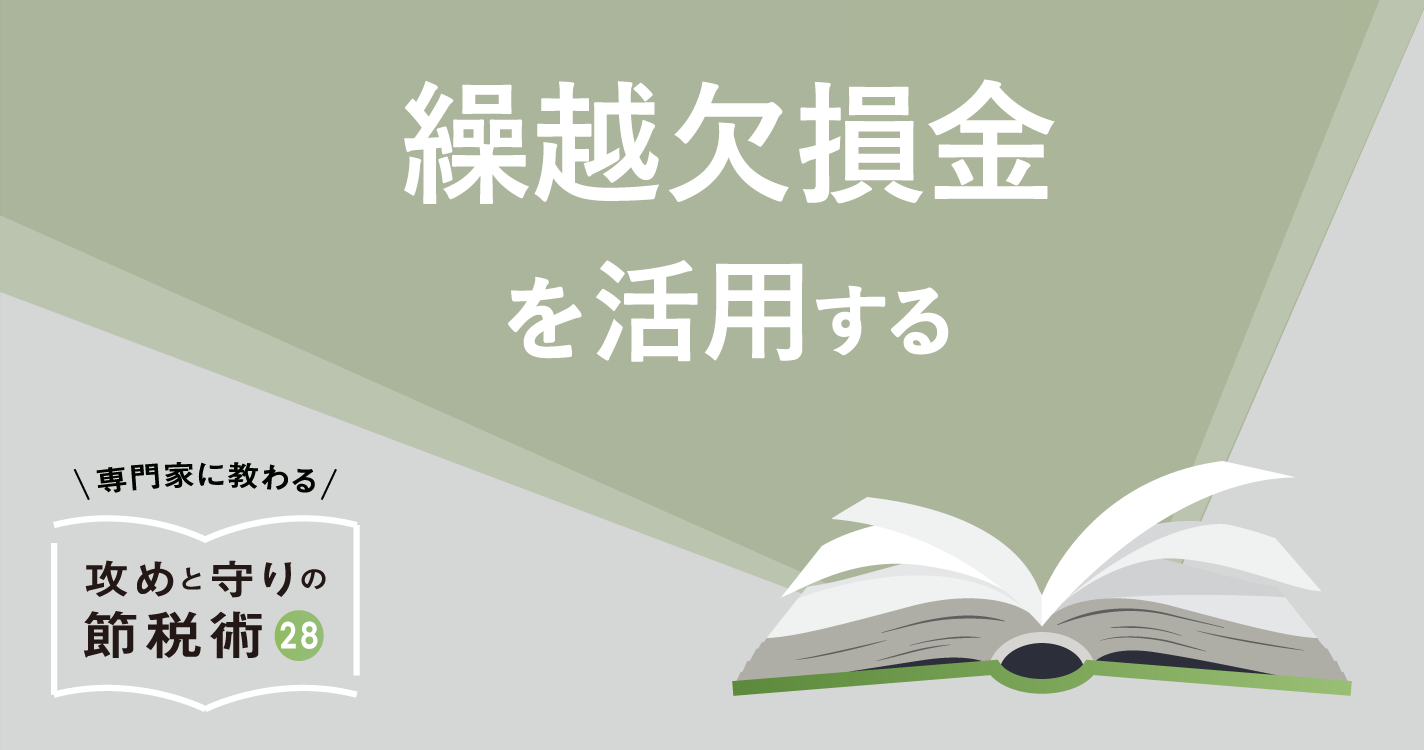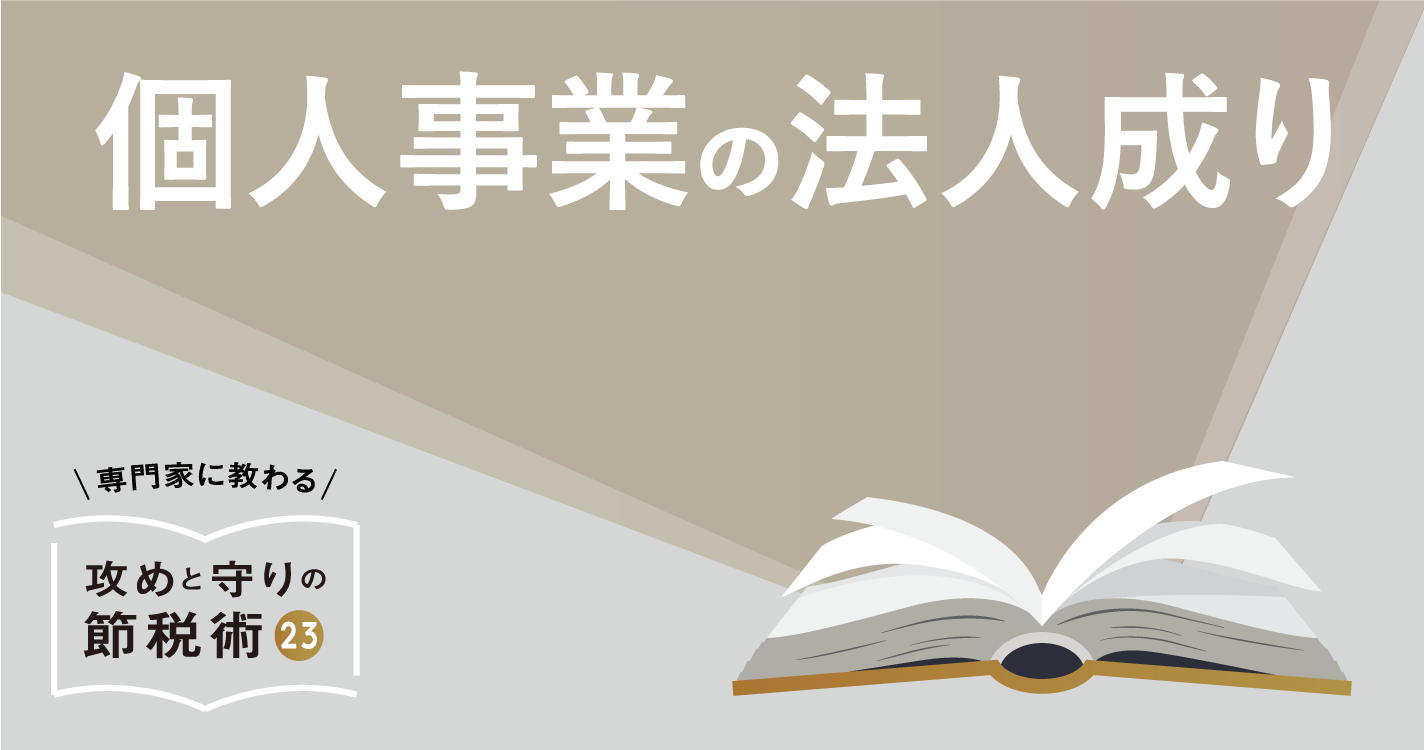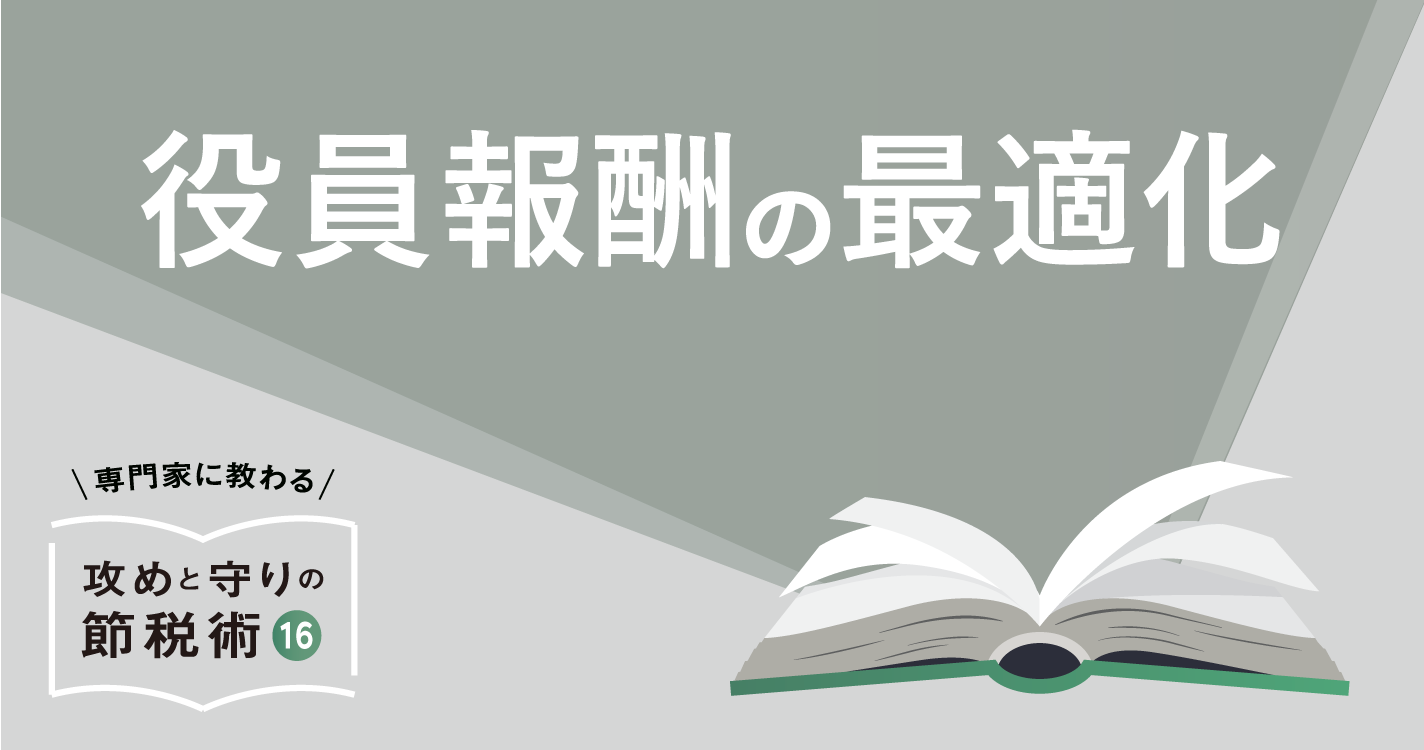
「役員報酬の最適化」という節税術
中小企業が節税対策を考える際に、ぜひ見直したいのが「役員報酬の設定」です。役員報酬は単なる「給料」ではなく、法人税や所得税、社会保険料の負担を減らすための有効な節税手段でもあります。
本記事では、役員報酬による節税の仕組みや設定時の注意点、押さえておくべき税務上のルールを、初心者の方にもわかりやすく解説します。中小企業の経営における税金対策として、ぜひご一読ください。
役員報酬の最適化による節税効果
役員報酬を最適化することで、法人税や所得税の軽減につながります。ここでは、役員報酬の定義と最適化による節税効果をわかりやすく解説します。
役員報酬とは?
役員報酬とは、取締役や監査役など会社の役員に対して支払われる報酬を指します。役員報酬は一般の従業員に支払われる「給与」とは異なり、株主総会などで決定され、会社の経営を担う立場の人に対して支給されます。
役員報酬の主な特徴は以下の通りです。
- ・労働基準法の対象外であり、残業代や労災保険といった制度は原則として適用されない
- ・税務上は「給与所得」として扱われるが、独自の税務ルールや社会保険の計算方法がある
- ・支給方法には「定期同額給与」(毎月同額)や「事前確定届出給与」(賞与)などがある
役員報酬は経費(損金)にできる
役員報酬が節税につながる最大の理由は、法人の経費(損金)として認められるためです。損金とは、法人税を計算する際に会社の利益から差し引ける費用のことで、課税所得が減るため、結果として法人税の負担を軽減できます。
たとえば、役員報酬を月50万円に設定した場合、年間で600万円(50万円×12ヵ月)が会社の損金として計上されます。この金額が法人の利益から差し引かれることで、法人税の対象となる所得をその分減らせるわけです。
一方で、配当金は損金にならないため、同じ金額を役員に支払う場合でも、役員報酬の方が節税効果は高いといえるでしょう。
ただし、すべての役員報酬が自動的に損金になるわけではありません。税務上、以下の要件を満たす必要があります。
- 定期同額給与:
毎月、同じ金額を継続して支給する必要があります。これは、税務署に「利益操作」や「恣意的な税負担の調整」とみなされないようにするための重要なルールです。 - 事前確定届出給与:
賞与(ボーナス)を支給する場合に適用され、事前に税務署へ金額と支給日を届け出る必要があります。 - 業績連動給与:
企業の業績に連動して支給額が決まる給与制度です。主に上場企業など非同族会社の役員報酬で導入される制度で、多くの中小企業では適用できません。
もしこれらのルールを守らなければ、役員報酬が損金として認められず、かえって税負担が増えてしまうこともあります。
そのため、役員報酬を設定する際は、税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。 (税理士法人岡本会計事務所 副所長 田邉哲弥)
役員報酬の節税メリット
役員報酬を適切に設定すれば、会社と役員個人の税負担を大幅に軽減することが可能です。特に中小企業や法人化したばかりのスタートアップ企業にとって、役員報酬の最適化は非常に強力な節税対策となります。
ここでは、5つの代表的な節税メリットを、具体的なシミュレーションとともにわかりやすく解説します。
節税メリット1 法人税の節税につながる
役員報酬は、法人の経費(損金)として計上できるため、法人税の対象となる課税所得を減らせます。
シミュレーション
たとえば、会社の年間利益が1,000万円だとしましょう。このとき、役員報酬を月50万円(年間600万円)に設定し、法人税の実効税率を30%と仮定した場合、法人の課税所得は次のように減少します。
利益1,000万円 × 法人税率30% = 法人税300万円
(利益1,000万円 − 役員報酬600万円)× 法人税率30% = 法人税120万円
300万円 − 120万円 = 180万円(節税額)
このように、役員報酬を適切に設定することで、法人税の負担を大きく軽減できることがわかります。ただし、役員報酬額は会社の事業規模や利益に応じて適切に設定する必要があります。
税務上のルールを守りながら最大の節税効果を得るためには、税理士に相談するのがおすすめです。
節税メリット2 中小企業向け「法人税軽減税率」を活用できる
中小企業の場合、課税所得のうち年800万円以下の部分に対して、通常よりも低い税率で法人税が計算される優遇措置があります。これは「法人税の軽減税率」と呼ばれ、現在の適用税率は15%です(通常の本則税率は約19〜23.2%)。
たとえば、課税所得が800万円だった場合、通常よりも約4〜8%分も税金が安くなります。この特例の適用は2027年3月31日まで延長されており、当面の間は継続して利用できます。
この有利な税制を最大限に活かすためには、役員報酬を適切に調整し、会社の課税所得全体を800万円以下に抑える戦略が効果的です。
法人税軽減税率15%の対象は資本金1億円以下などの条件があり、同族会社の特定要件や大法人の100%子会社などは対象外になるため注意が必要です。 (税理士法人岡本会計事務所 副所長 田邉哲弥)
節税メリット3 役員の所得税・住民税の節税につながる
役員報酬を戦略的に設定すると、役員個人にかかる所得税や住民税の負担を減らせます。日本の所得税は超過累進課税制度を採用しているため、所得が高くなればなるほど税率も上がっていくのが特徴です。
たとえば、個人の課税所得が900万円を超えると所得税率は33%、1,800万円を超えると40%にも達します。
つまり、役員報酬をあまり高く設定しすぎないよう調整することで、高い税率がかかるゾーンを避けられ、手取りを多く残せる可能性があるのです。
さらに効果的なのが、家族を役員にして報酬を分散させる「所得分散」という手法です。
家族それぞれが会社の業務に携わり、その対価として適正な役員報酬を受け取ることで、所得が複数に分散されます。これにより、所得税の累進課税が緩和され、世帯全体の所得税負担を大きく軽減することが可能です。
節税メリット4 社会保険料の負担軽減につながる
役員報酬は、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)を計算する際の基礎となります。つまり、役員報酬の金額を調整することで、会社と役員個人が支払う社会保険料の総額に大きな影響が出るわけです。
たとえば、役員報酬を高く設定すると、その報酬額に連動して健康保険や厚生年金の保険料も高くなります。これは会社と個人の双方にとって、無視できない大きな負担となるでしょう。
一方で、一定の範囲で報酬を適正に調整すれば、社会保険料の負担を抑えつつ、将来受け取る年金額も維持しやすくなります。この「適正なバランス」が重要なポイントです。
特に、会社を立ち上げたばかりの創業期や資金繰りが厳しい時期には、社会保険料の負担が大きな固定費になることがあります。こうした場合に、役員報酬の最適化は非常に有効な戦略となります。
ただし、社会保険料を減らす目的で不当に低い報酬を設定するのは注意が必要です。将来の厚生年金受給額に悪影響を及ぼすだけでなく、税務署や年金事務所の調査対象となる可能性もあるため、専門家と相談しながら慎重に検討しましょう。
厚生年金は在職中で一定以上の賃金や年金額があると支給停止になります。基準額超過に注意が必要です。 (税理士法人岡本会計事務所 副所長 田邉哲弥)
節税メリット5 退職金の活用で長期的な節税につながる
役員退職金は、会社と役員個人の双方にとって、非常に大きな節税メリットをもたらします。
まず、会社側にとっては、適正な算定方法に基づいた役員退職金を一括で支払えば、その全額を損金として計上できます。これにより、退職金を支払った事業年度の法人税を大きく圧縮することが可能です。会社の利益が大きい年に退職金を支給することで、効果的に法人税の負担を軽減できるわけです。
一方、役員個人が退職金を受け取る際は、税制上の大きな優遇を受けられます。勤続年数が5年を超えると1/2課税(課税所得が半分になる)が適用され、さらに勤続年数が20年を超えると退職所得控除額が大きくなるため、同じ金額を通常の役員報酬(給与)として受け取るよりも、手元に残るお金(手取り)が大幅に多くなります。
たとえば、退職金2,000万円を勤続21年で受け取る場合、退職所得控除額は870万円となり、残額の1/2にあたる約565万円が課税対象となります。
2,000万円 – (800万円 + 70万円 ×(21年 – 20年))= 1,130万円
1,130万円 × 1/2 = 565万円
これにより、適用される税率も低く抑えられ、以下のように、最終的な手取り額は同額の役員報酬(給与)と比べて大幅に増加します。
シミュレーション
課税所得565万円、税率20%(課税所得330万円〜695万円の範囲)として計算
565万円 × 20% − 427,500円(控除額)= 約702,500円
給与所得控除上限(195万円)を引いた1,805万円が課税所得と仮定、税率40%(課税所得1,800万円〜39,999,000円の範囲)として計算
1,805万円 × 40% − 2,796,000円(控除額)= 約4,424,000円
住民税も課税されますが、退職金に対する1/2課税の効果は住民税にも適用されるため、所得税と同様に手取り額に有利に働きます。
退職金制度を効果的に活用した節税は、専門的な知識が必須となるため、税理士などの専門家と相談しながら設計を進めることを強くおすすめします。
役員退職金は適正額算定と支給時期が重要。税務要件を守り、過大・不当支給は避けるために専門家に相談しましょう。 (税理士法人岡本会計事務所 副所長 田邉哲弥)
役員報酬を設定する際の注意点
役員報酬を設定する際は、以下の点に注意が必要です。
注意点1 定期同額給与のルールを守る
役員報酬は、原則として毎月同じ金額を支給する「定期同額給与」でなければ、損金算入が認められません。期中で金額を変更すると経費として扱われなくなるため、注意が必要です。
注意点2 過度な報酬設定は税務調査の対象に
会社の利益に見合わない高額な報酬は、税務署から「不当に高すぎる」と判断される可能性があります。適正な金額を意識することが大切です。
注意点3 社会保険料の増加に注意
報酬額が高くなると、それに比例して健康保険や年金などの社会保険料も上がります。法人・個人ともに負担が増えるため、全体のバランスを見て設定しましょう。
注意点4 税理士や専門家への相談を怠らない
税務や社会保険の制度は複雑で、判断を誤ると損金不算入や追徴課税のリスクがあります。役員報酬の設定は、必ず専門家に相談しながら進めていきましょう。
この節税術に必要な心構えとは
役員報酬は、法人税・所得税・社会保険料など、さまざまな税負担を軽減できる強力な節税ツールです。ただし、税務上のルールや社会保険の制度は複雑で、設定を誤ると、かえって税負担が増えてしまうリスクもあります。
節税効果を最大限に活かし、安心して活用するためにも、税理士など専門家に相談しながら進めることを強くおすすめします。
会社の実情に合った最適な役員報酬を設定し、税金対策を確かなものにしていきましょう。
役員報酬の最適化は、中小企業にとって法人税・所得税・社会保険料の負担を減らす有効な節税策の一つです。
ただし、支払方法や支払金額などについての損金算入要件や軽減税率の適用条件、社会保険制度の影響など、税務のみならず複数の法的ルールが絡み合います。誤った設計は追徴課税や将来の年金額減少などのリスクを伴うため、会社の利益規模や資金繰り、将来計画を踏まえた総合的な判断が不可欠です。
最も効果的かつ安全に制度を活用するためには、税理士などの専門家と綿密に相談しながら進めることが重要です。
(税理士法人岡本会計事務所 副所長 田邉哲弥)