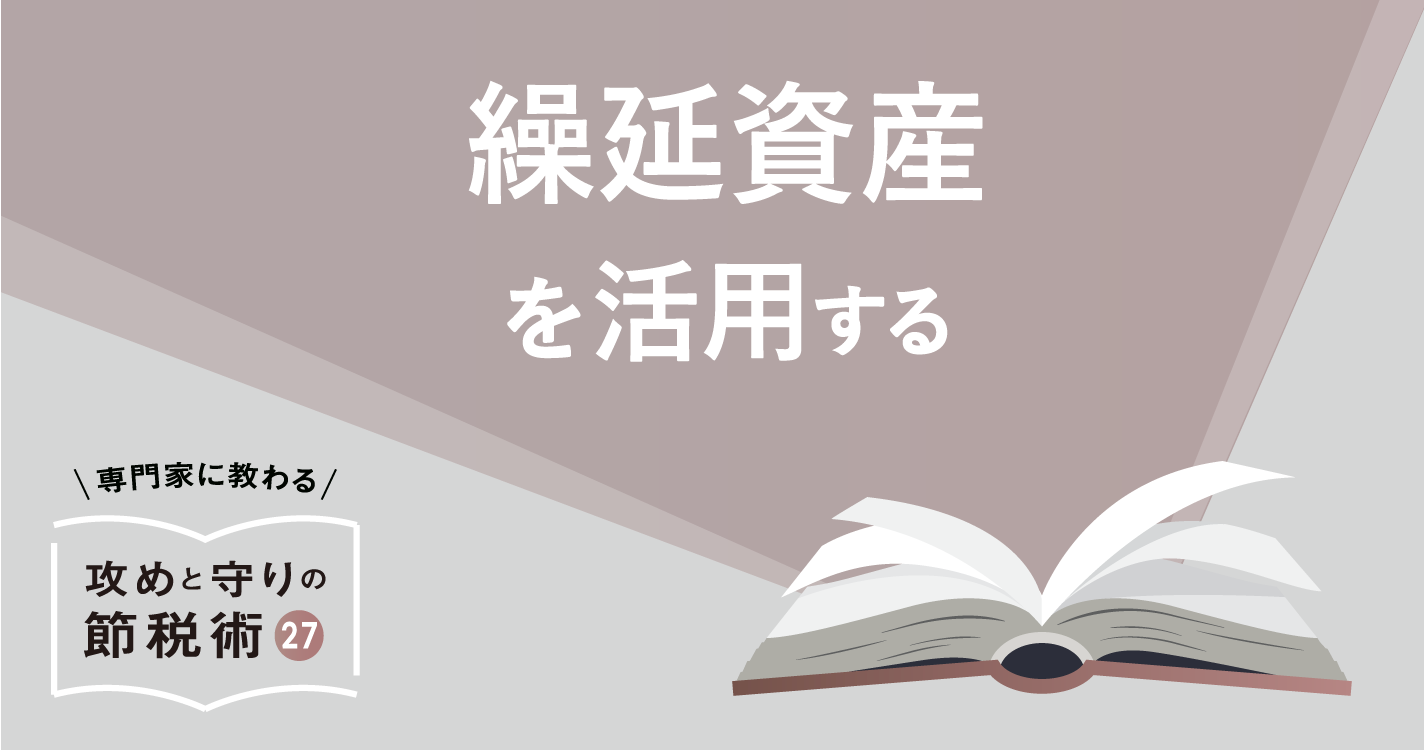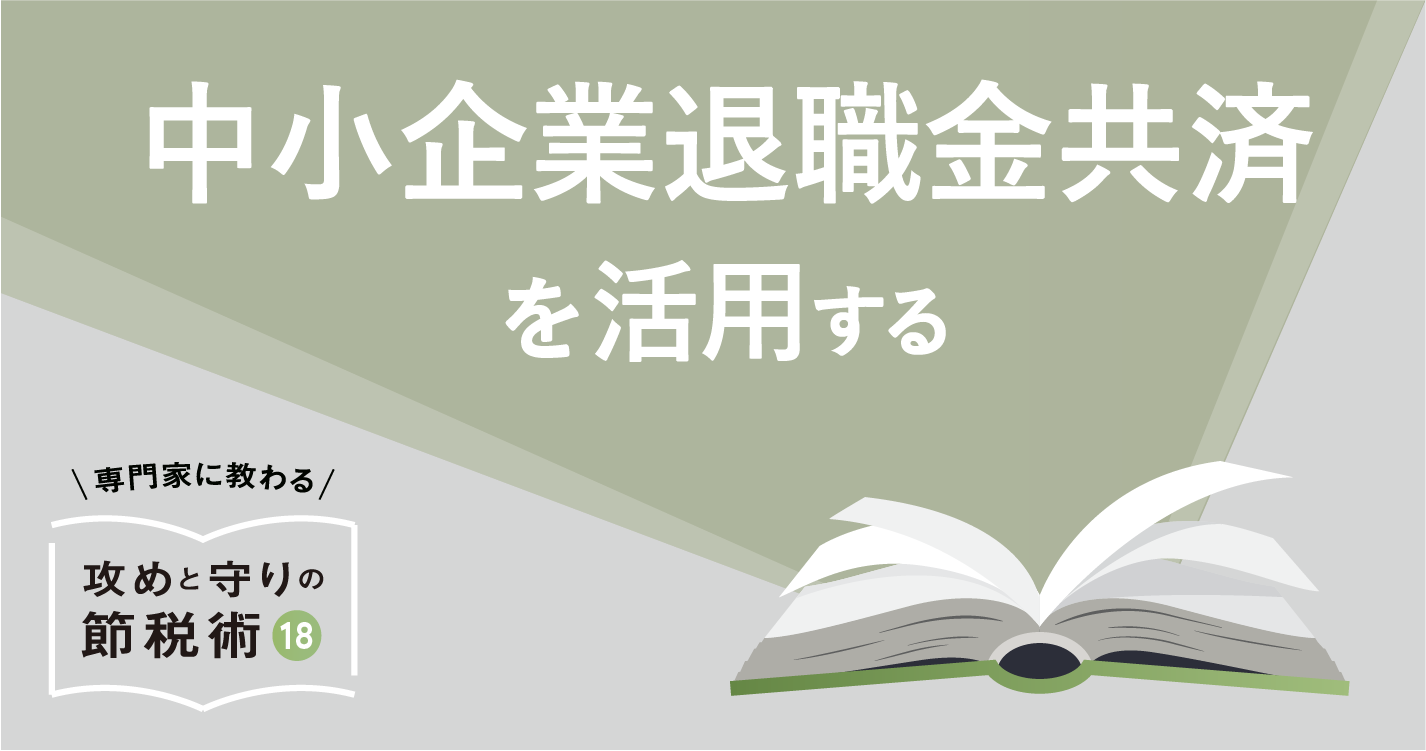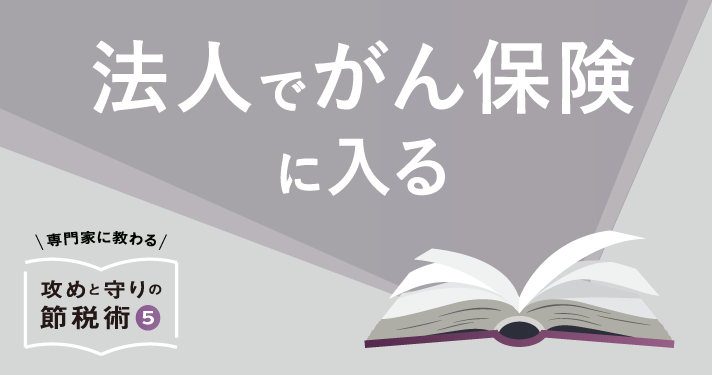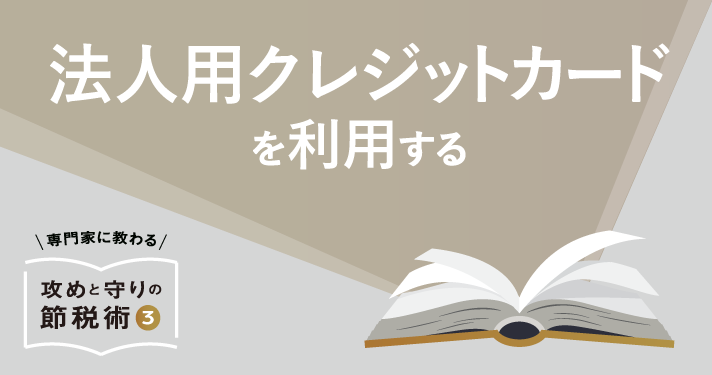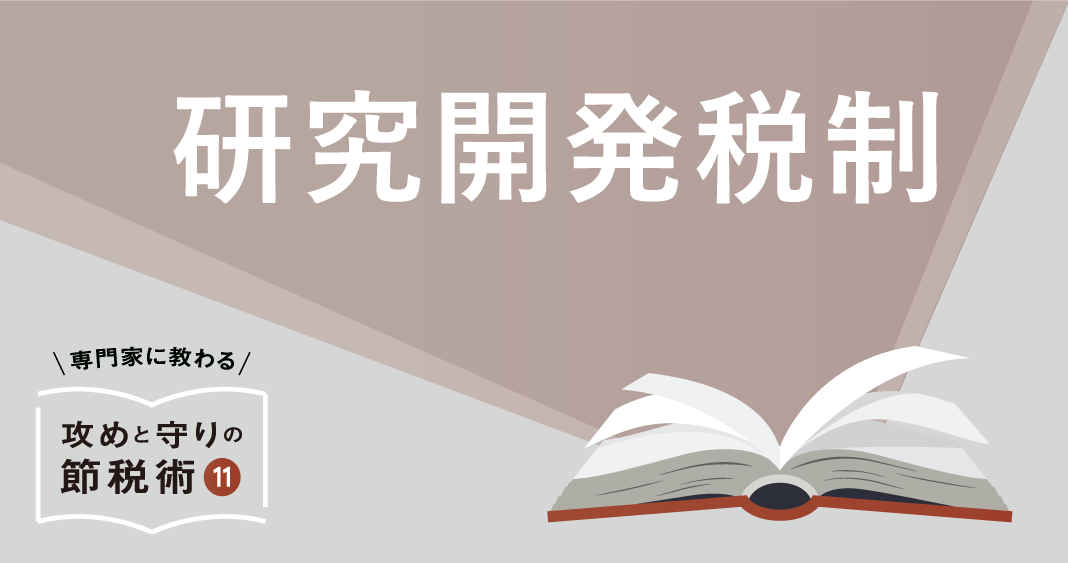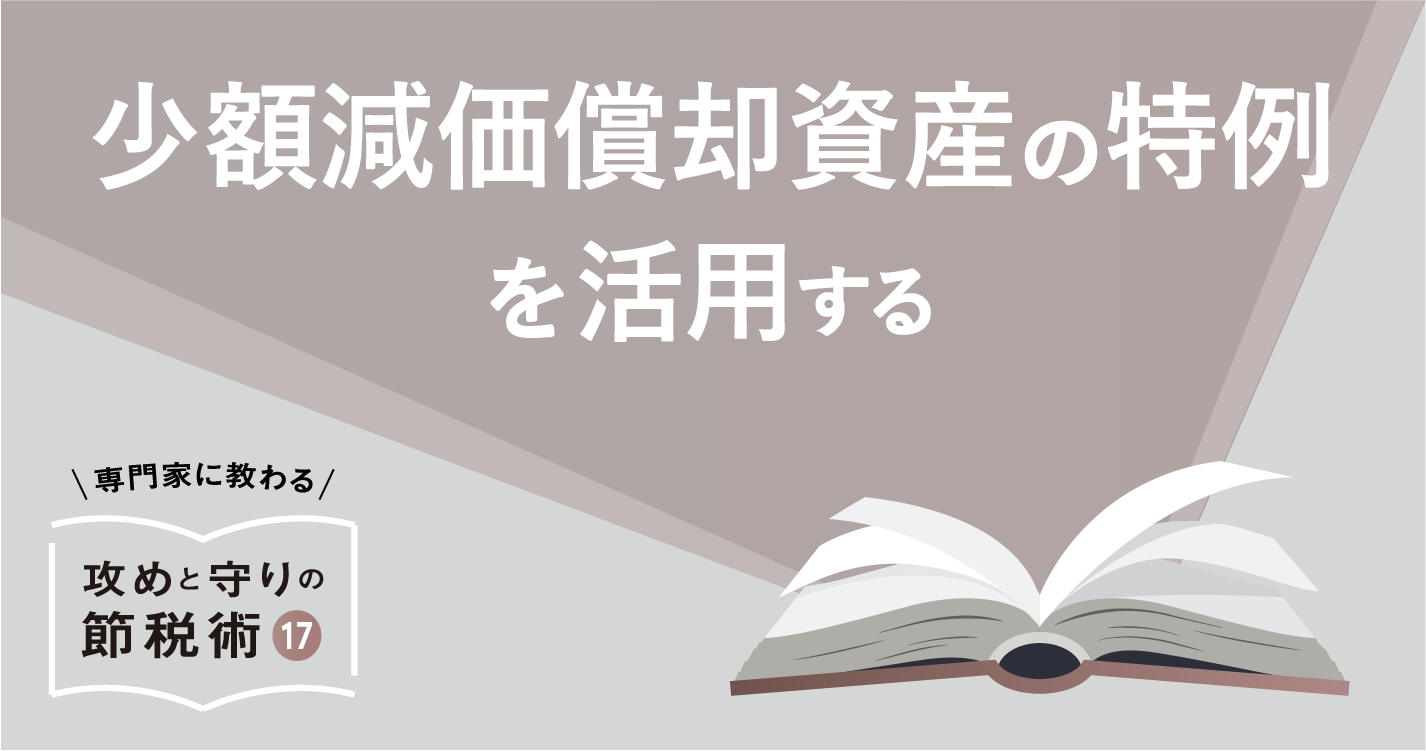
「少額減価償却資産の特例を活用する」
という節税術
「利益が出ても税金で手元資金が減ってしまう」「経理の手間を減らしたい」といった悩みを抱える中小企業経営者や個人事業主は少なくありません。
このような課題を解決する手段として、30万円未満の資産を即時費用化できる「少額減価償却資産の特例」があります。この特例を使えば、節税と資金繰りの改善を同時に実現できるでしょう。
本記事では、特例の仕組みからメリット、注意点までをわかりやすく解説します。中小企業や個人事業主の皆さまの節税対策や資金繰り改善に、ぜひお役立てください。
少額減価償却資産の特例の仕組み
少額減価償却資産の特例とは、青色申告者が購入価格が30万円に満たない減価償却資産を取得した際、即時に全額経費にできる制度です。ここでは、特例の仕組みをわかりやすく解説します。
減価償却資産とは?
減価償却資産とは、時の経過に伴って価値が減っていく固定資産を指します。たとえば、業務に使用するパソコンや車、機械装置、建物などが減価償却資産に該当します。
減価償却資産の税務処理では、減価償却資産を耐用年数に応じて、分割して必要経費として計上するのが原則です。たとえば、パソコンの場合だと法定耐用年数は4年であり、4年間にわたって分割して経費計上することになります。
- 主な減価償却資産と法定耐用年数は以下のとおりです。
- サーバー機器:5年
- 複合機:5年
- 事務机(金属製):15年
- 事務机(金属製以外):8年
- 普通自動車:6年
- 軽自動車:4年
中古資産(中古で購入した減価償却資産)については、通常の法定耐用年数ではなく、短縮された耐用年数で減価償却を行う特例が認められています。取得時点での使用状況や経過年数に応じて、所定の方法で耐用年数を算出することができます。(税理士法人岡本会計事務所 副所長 田邉哲弥)
「10万円未満の少額資産」「一括償却資産」「少額減価償却資産の特例」の違い
減価償却資産は、「10万円未満の少額資産」「一括償却資産」「少額減価償却資産の特例」の3つに分類でき、それぞれ税務処理の方法が異なります。
10万円未満の少額資産
減価償却資産のうち、取得費用が10万円に満たない少額資産は減価償却が不要です。耐用年数に関係なく、取得した年度に全額を必要経費として計上できます。
たとえば、9万円で購入したパソコンの場合だと、その年に9万円全額を消耗品費として経費化できます。(税理士法人岡本会計事務所 副所長 田邉哲弥)
一括償却資産
減価償却資産のうち、10万円以上20万円未満で購入した資産は、使用を始めた年から3年間にわたって、取得価額の3分の1ずつを必要経費として計上できます。
たとえば、15万円で購入したパソコンの場合だと、毎年5万円ずつ3年間にわたって経費計上することになります。
なお、一括償却資産の適用は「選択適用」であり、必ず一括償却を選択しなければならないわけではありません。
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の特例を受けると、取得価額が30万円未満の資産を、購入した年に全額経費として計上できます。
たとえば、25万円で購入したパソコンの場合だと、購入した年に25万円全額を経費として計上可能です。
ただし、少額減価償却資産の特例を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 青色申告が必要(白色申告者は不可)
- 従業員数500人以下の個人事業主または法人
- 資本金または出資金の総額が1億円以下の法人
- 確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告する
なお、少額減価償却資産の特例の適用には、1年間でその特例を適用できる資産の合計額は300万円までという上限があります。
10万円未満の少額資産については、少額減価償却資産の特例と異なり、合計額の限度額はありません。(税理士法人岡本会計事務所 副所長 田邉哲弥)
少額減価償却資産の特例を活用する節税メリット
ここでは、少額減価償却資産の特例を活用すると、どのような節税メリットが得られるのかを具体的に解説します。
節税メリット1 その年の利益を圧縮できる
少額減価償却資産の特例を活用すると、30万円未満の資産を購入した年に全額経費にでき、利益を減らすことで節税につながります。
たとえば、20万円のパソコンを購入した場合、特例で20万円をその年に丸ごと経費にすることが可能です。利益が20万円減るため、税率30%であれば以下のように6万円の税金を節約できます。
購入金額:20万円(税抜)
法人税等の実効税率:30%(中小企業の一般的な目安)
通常の減価償却:耐用年数4年、定額法(パソコンの場合)
①少額減価償却資産の特例を使った場合
- 購入した年に20万円全額を必要経費に計上
- 課税所得が20万円減少
- 節税効果:20万円 × 30% = 6万円
(税金の支払額が6万円減るという意味です)
②通常の減価償却の場合
- パソコンの法定耐用年数は4年
- 毎年の減価償却費:20万円 ÷ 4 = 5万円
- 購入初年度の節税効果:5万円 × 30% = 1.5万円
このように、少額減価償却資産の特例を利用することで、固定資産を購入した年の利益を大幅に圧縮でき、その分の税金の支払額をまとめて軽減できます。
※実際の税率は法人の規模や所在地によって異なります。正確な税額や適用可否については、税理士等の専門家にご確認ください。
節税メリット2 キャッシュフローが改善する
少額減価償却資産の特例を使えば、30万円未満の資産をその年に全額経費にできます。これにより課税所得が減り、税金の支払いを抑えられるため、手元に残る現金(キャッシュフロー)が増加します。結果として、資金繰りの安定に大きく貢献するでしょう。
一方、通常の減価償却では節税効果が数年に分散されるため、その年のキャッシュフローへの即効性は小さくなります。
「手元資金を厚くして資金繰りを楽にしたい」と考える経営者にとって、少額減価償却資産の特例は非常に有効な制度といえるでしょう。
なお、利益が出ていても資金不足により事業が立ち行かなくなる「黒字倒産」は中小企業にとって現実的なリスクです。こうしたリスクを避けるためにも、キャッシュフローの確保は極めて重要になってきます。
節税メリット3 会計処理がシンプルになる
少額減価償却資産の特例を適用すると、30万円未満の資産を1年で全額経費化でき、複雑な計算が不要で、会計処理がシンプルになります。通常の減価償却では、耐用年数に基づく計算や残存価額の管理が必要で、手間と労力がかかります。
厳密には「節税メリット」そのものではありませんが、経理の手間が減ることで、経営者は本業に集中できるようになることは大きなメリットです。
明細書の添付が必要(法人税・所得税)
特例の適用にあたっては、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付することが義務づけられています(措法67の5第1項)。
(税理士法人岡本会計事務所 副所長 田邉哲弥)
節税メリット4 投資判断の自由度が高まる
特例を適用することで、30万円未満の資産を即時全額経費化できるため、利益が多い年に資産購入を計画し、税負担を抑えつつ必要な設備投資を行えます。
たとえば、利益が大きく出た年に業務用のパソコンや事務机などをまとめて購入することで、設備投資と節税を同時に実現できます。
これは、事業の成長を図りたい経営者にとって、大きなメリットになるでしょう。
少額減価償却資産の特例を活用する際の注意点
少額減価償却資産の特例は、節税しながら事業の成長にも貢献する制度ですが、使い方を誤ると思わぬ不利益を招くことがあります。ここでは活用にあたって注意すべきポイントを解説します。
注意点1 翌期以降の費用計上がなくなる
特例を使うと、資産を購入した年に全額を経費化するため、翌期以降に費用計上できる分がなくなります。たとえば、通常の減価償却なら数年に分けて費用化できたものが、翌年以降は利益を圧縮する効果がなくなる点に注意が必要です。
特に、翌期以降に利益が増加する見込みがある場合は、税負担が相対的に重くなる可能性も考慮に入れる必要があるでしょう。
複数年にわたって安定的に経費を計上したい場合は、一括償却資産の活用も検討するなど、税理士とも相談して柔軟な対応が求められます。
注意点2 特例の年間適用限度額に注意
少額減価償却資産の特例は、1年間に適用できる合計額が300万円までという上限があります。上限を超える部分については通常の減価償却などで処理する必要があります。特例を前提に設備投資を計画する際は、限度額を把握したうえで計画的に進めることが大切です。
なお、この特例の適用期限は2025年度末(2026年3月31日)までとなっているため、この点もあわせて留意しましょう。
注意点3 税務調査で確認されることがある
少額減価償却資産の特例を使った資産購入は、税務調査で確認されやすい項目です。対象資産の使用実態や取得価額、帳簿記載が適正であるかがチェックされることがあります。
たとえば、パソコンを購入した場合、取得価額には本体価格だけでなく、配送料や設置費用なども含める必要があります。
不適切な処理があると、否認され追徴課税のリスクも生じるため、明細書の添付や証拠資料の保管を徹底しましょう。
注意点4 事業年度の利益計画に影響を与える
特例によって利益が大きく圧縮されると、銀行融資や補助金審査などで利益額を基準とする際に不利に働く場合があります。単年度の節税だけでなく、数年間の利益計画や資金調達の見通しを含めた判断が必要です。
この節税術に必要な心構えとは
少額減価償却資産の特例は、30万円未満の資産について購入した年に全額を経費化できる便利な制度です。この特例を上手に活用することで、その年の利益を圧縮し、税負担の軽減やキャッシュフローの改善、経理業務の簡便化が図れます。
一方で、翌期以降の利益圧縮効果がなくなることや、適用限度額、税務調査での確認ポイントなどに注意が必要です。単年度の節税メリットだけにとらわれず、将来の事業計画や資金繰り全体を見据えて活用しましょう。
なお、特例の適用期限は2025年度末(2026年3月31日)までとなっていますが、延長される可能性もあるため、最新情報のチェックも大切です。
特例の適用可否や具体的な効果、適正な処理については、税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
少額減価償却資産の特例は、30万円未満の資産を全額即時経費化できる中小企業向けの優遇措置です。税負担の軽減だけでなく、キャッシュフローの改善や会計処理の簡素化にもつながり、資金繰りや経営の安定にも寄与します。
一方、適用限度額や翌年度以降の費用化への影響など、制度運用には慎重な計画が必要です。特例の有効活用には、単年度の節税効果だけでなく、長期的な経営戦略や資金調達面への影響も踏まえた判断が求められます。制度の詳細や実際の適用については、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
(税理士法人岡本会計事務所 副所長 田邉哲弥)