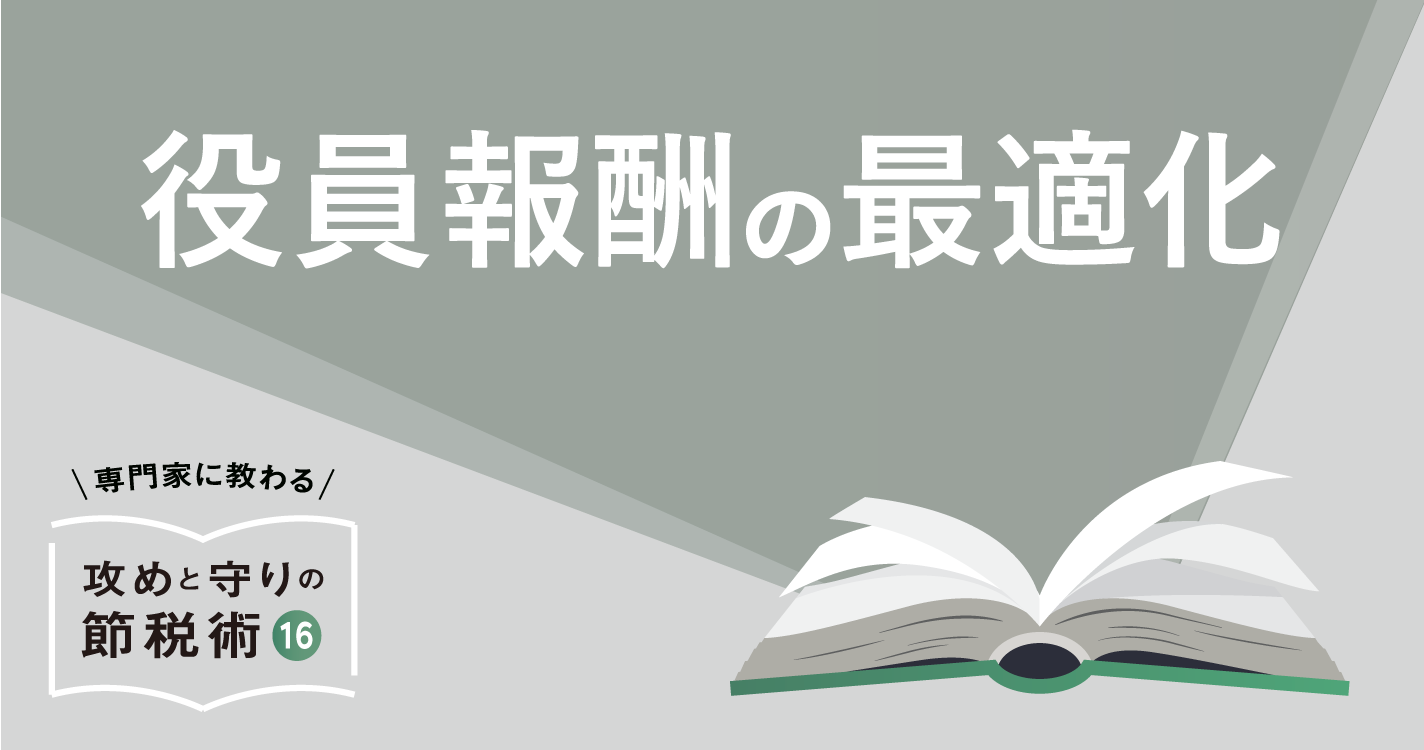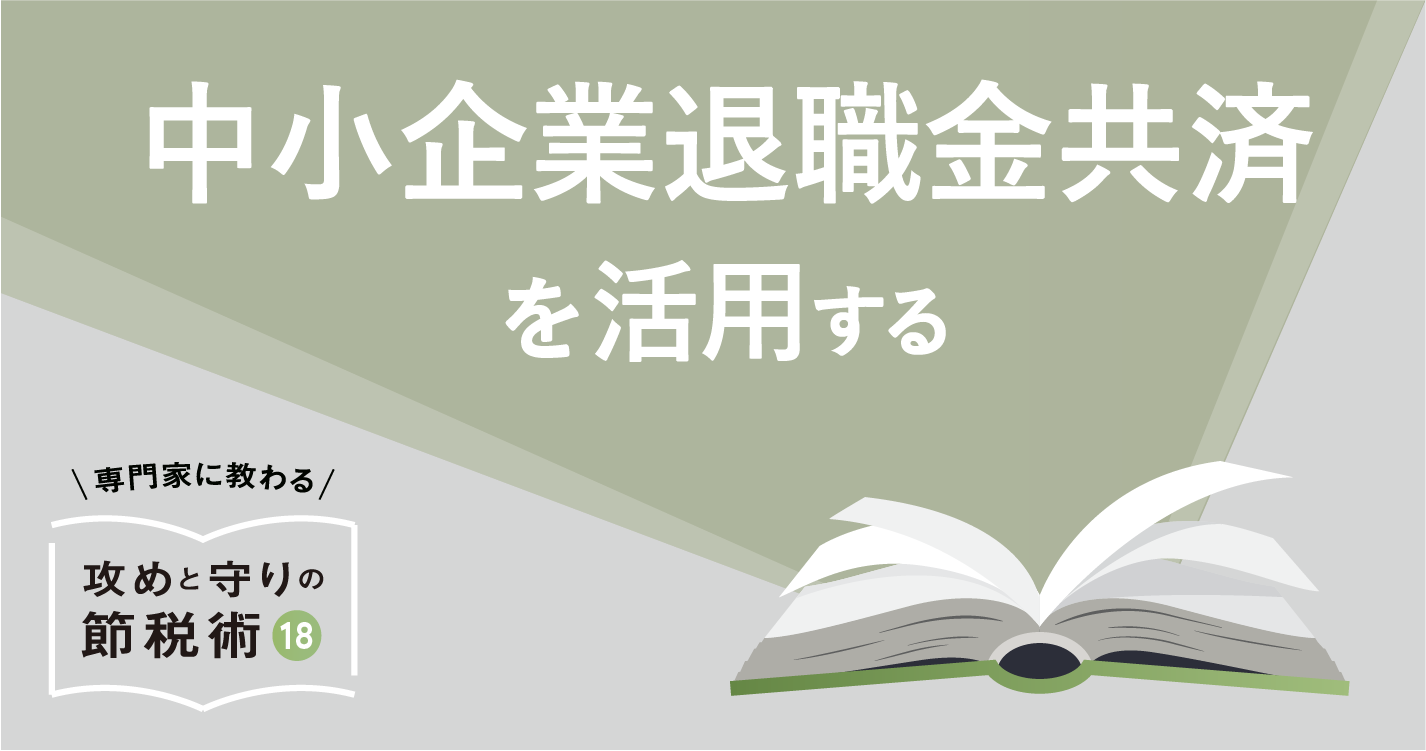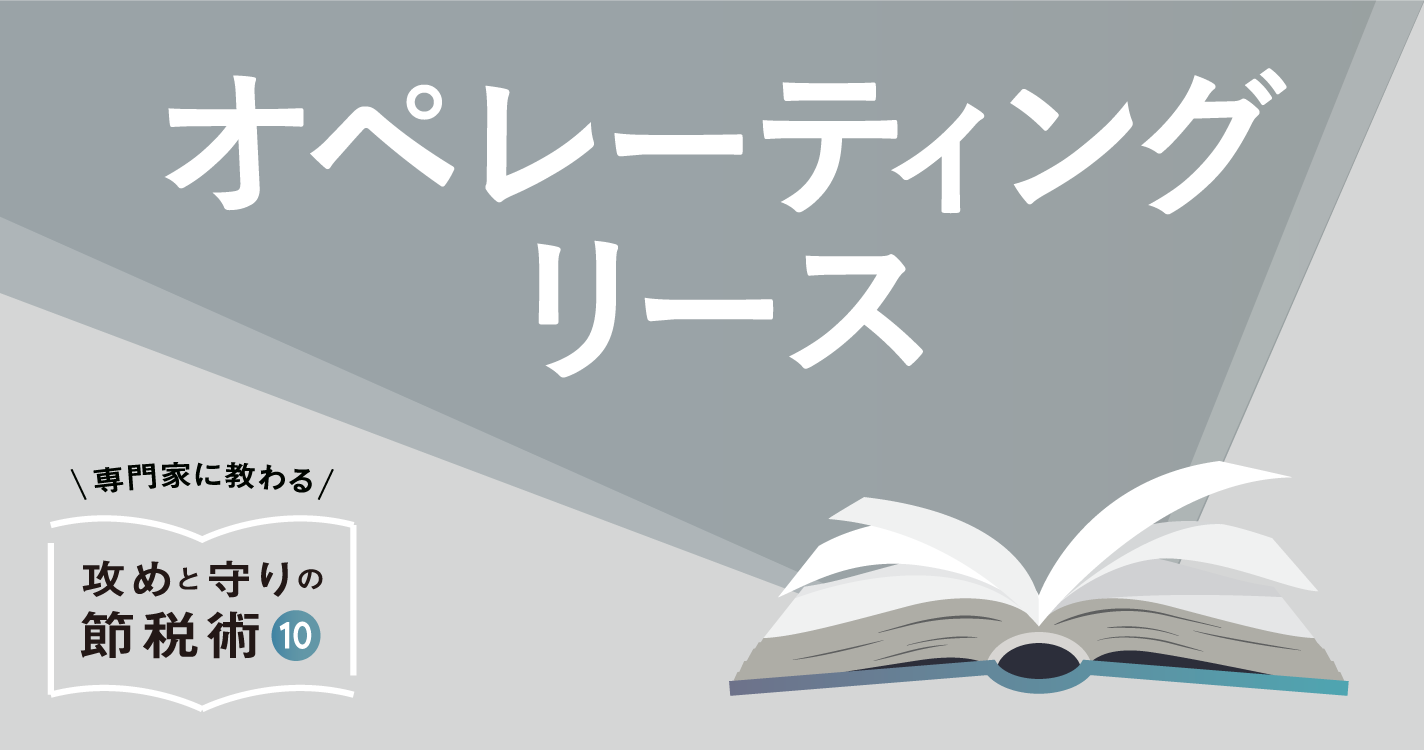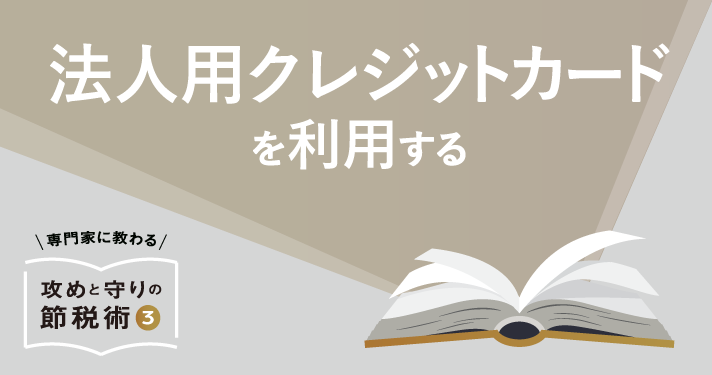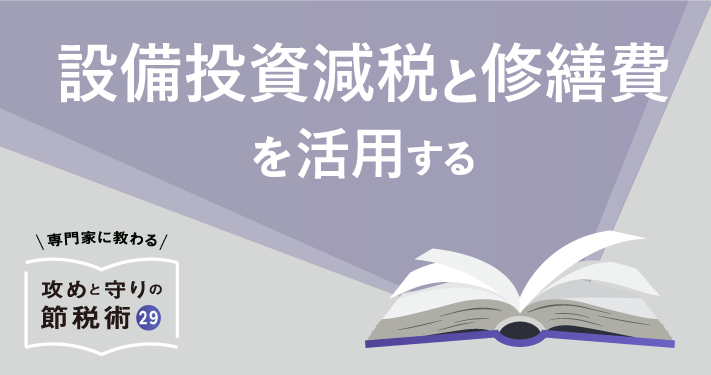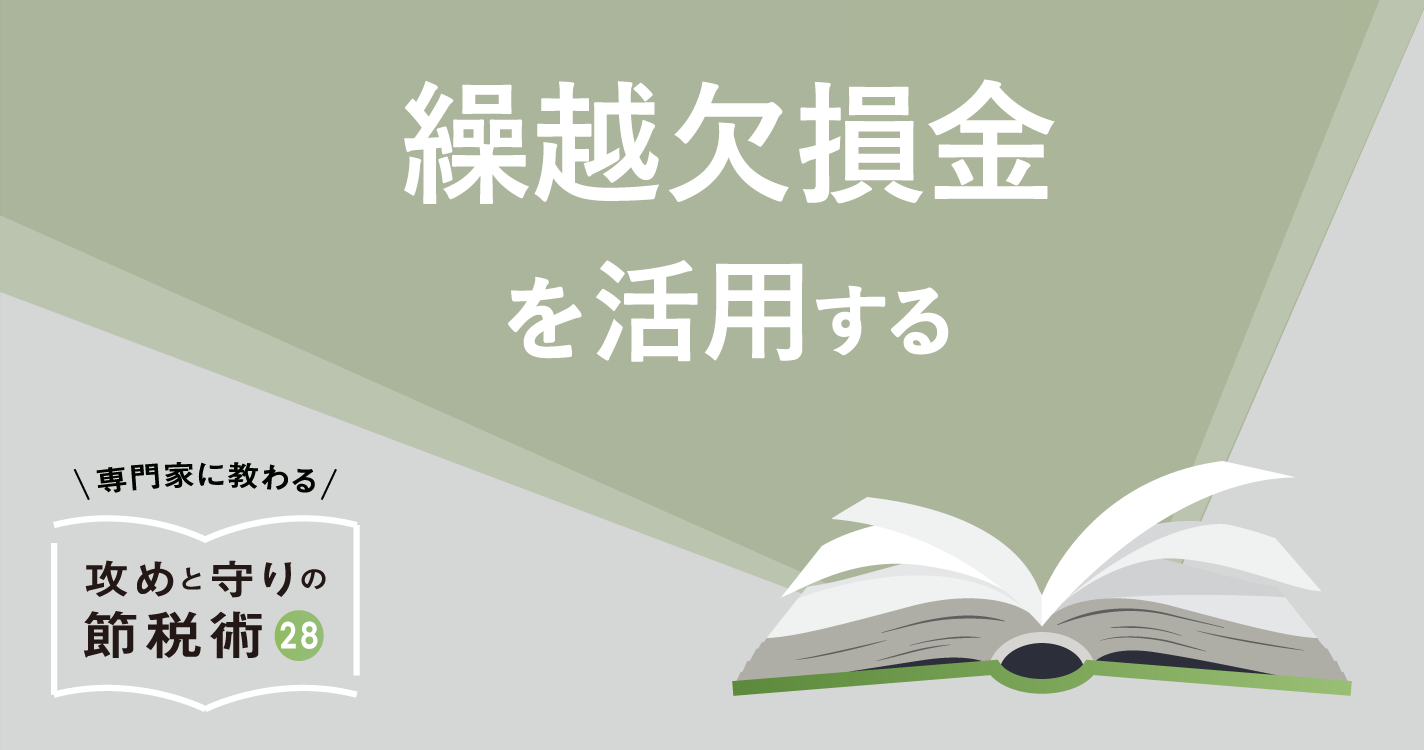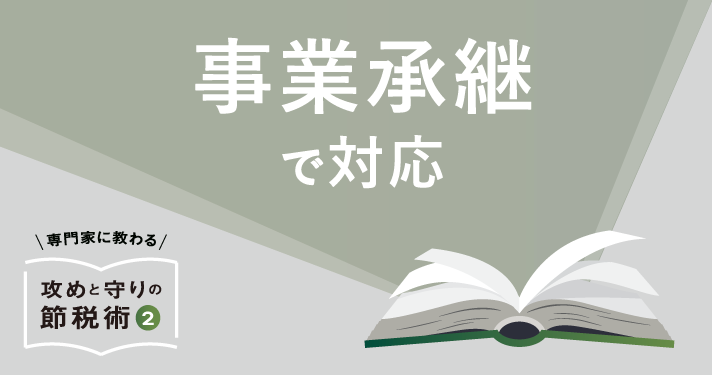
「事業承継で対応」
という節税術
経営者の高齢化に伴って、中小企業、家族経営などの小規模事業者の事業承継が大きな課題になっています。多くの経営者の悩みの種は、「後継者」と「資金」です。課題を乗り越えて、会社を引き継いでいくためにはどうしたらいいのか、ポイントを解説します。
事業承継の課題と
対応策
経営者として育成する
子どもに事業を継がせる場合、“親の七光り”の状況では、従業員にも取引先にもそっぽを向かれてしまう公算大です。社長としての能力、資質を身につけてもらうためには、育成のための教育や経験が不可欠です。
後継者には、できるだけ早い時期から会社に入ってもらい、営業などの現場や、総務などのバックオフィスを一通り経験できるようなローテーションを組んで、経験を積ませるべきでしょう。加えて、経営企画などの経営の中枢を担当させることにより、経営者としての自覚を育てることが重要になります。
こうした社内での教育には、従業員との信頼関係や一体感を築くことができるほか、現経営者の目の届く場所で、経営者としての振る舞いや働き方を直接受け継ぐことができる、というメリットがあります。 従業員承継においても、同様の意識的な社内教育が必要になります。早めに後継者を明確にし、社内外からの理解を得られる環境をつくることが大切です。
事業承継で一番大切なのは後継者の育成。先代経営者と後継者の対話、二人三脚で歩んでいく姿勢です。簡単なことのようですが、意外にも親子の場合、これが上手く行かないケースが少なくありません。「息子なんだから、言わなくてもわかってほしい…。」「親だから言えない…。」親子の間を専門家が取り持つことにより問題が解決することもあります。(塩見明税理士事務所 所長 塩見 明)
税負担への対応が必要
親族内承継においては、先代経営者から後継者に対し、株式や事業用資産を贈与、相続により移転するのが一般的です。ただし、そのため後継者に発生する贈与税、相続税の負担が、事業承継の大きな障害となる場合が少なくありません。できるだけ負担が少ない形で、移転を進める必要があります。 そのために多く用いられるのが、次のような方法です。
税負担への対応① 暦年贈与
贈与税は、もらった金額が多くなるほど税率も上がる累進課税になっています。年間110万円という基礎控除(贈与税が課税されない金額)も使いながら、自社株や財産を少額ずつ生前贈与(暦年課税)していけば、節税は可能です。
ただし、節税を意識しながら高額の資産を渡すためには、長い期間が必要になります。また、24年1月からは、相続税への「生前贈与加算」が、従来の相続開始前3年から7年に順次延長されています。この期間に生前贈与した財産は、基礎控除分も含めて全額が相続財産に加算されて、相続税計算のベースに含まれます。
税負担への対応② 相続時精算課税制度の利用
一方、税務署への届け出をすることで、2,500万円までの財産を贈与税ゼロで贈与できる相続時精算課税という制度があり、60歳以上の父母や祖父母(贈与者)から18歳以上の子や孫(受贈者)に対して財産を贈与した場合に選択することができます。税金は相続発生時に、贈与された金額を相続財産に加えることで、相続税として納めます。
24年から、この制度には従来なかった基礎控除(年間110万円)が新設されました。こちらには生前贈与加算はなく、相続発生時に基礎控除の110万円が相続財産に加算されることはありません。相続税の財産評価は贈与時のものになるので、例えば自社株が将来値上がりしそうな場合には、この制度を使って贈与しておけば、節税効果が大きくなります。
相続時精算課税は税務署へ届出書を提出することで選択できますが、一度選択すると撤回できません。安易に選ばずにどんな制度なのか、確認したうえで届出書を提出して下さい。(塩見明税理士事務所 所長 塩見 明)
税負担への対応③ 事業承継税制の利用
贈与や相続で自社株に課税される高額の税金が事業承継の障害になっている、という状況を打開するために設けられたのが、事業承継税制です。事業の後継者が自社株を贈与ないし相続で取得した場合、一定の要件を満たせば税金の支払いが猶予される、という制度です。
後継者が税の負担なく、経営に必要な自社株を譲り受けることができるのは大きなメリットですが、あくまでも納税猶予で、承継後に必要な要件を満たさなくなった場合などには、納税が必要になることもあります。
こうした対策には、一長一短があり、最も自社に見合ったやり方を選択する必要があります。早めに税理士などの専門家に相談し、助言を仰ぐべきでしょう。
事業承継税制を使えば、贈与税や相続税の支払いが免除される可能性がありますが、免除されるには、株を引き継いでから次の後継者へ株を渡す数十年もの間、一定の要件を満たし続けなければなりません。この間に要件を満たせなくなった場合は、猶予してもらっていた贈与税や相続税を利子税を含めて納付しなければならないのです。メリットもありますが、大きなリスクもあります。また、令和9年12月31日までに株を引き継ぐ予定がある場合、通常の事業承継税制よりも遥かに有利な特例措置を使える可能性があります。詳しくは事業承継を得意とする専門家へご相談ください。(塩見明税理士事務所 所長 塩見 明)
自社株の分散を避ける
事業承継が絡む相続で避けなければならないのは、自社株の多くが後継者以外の相続人に分散してしまう事態です。中小企業では、経営者が自社株を100%保有するのが理想で、その比率が下がると、安定的な経営の足かせになったり、他の相続人から買い取りを請求されて、会社の資金が流出したり、といったトラブルになりかねません。
先代経営者が計画的な贈与を行っておく、後継者に確実に株を渡せる遺言書を作成しておく、といった事前の対策を講じておくことが重要になるでしょう。
長男に半分、次男に半分、兄弟で株を分け合った場合、数十年後、長男の株は長男の子、次男の株は次男の子へ相続されます。いとこ同士で株を持ち合うことになるのです。さらに数十年後、それぞれの子へと株が相続されていくので、はとこ同士で株を持ち合うことになります。こうなると、分散してしまった株を買い集めるのは容易ではありません。実際、このような状態で苦労している経営者から相談を受けることは少なくありません。(塩見明税理士事務所 所長 塩見 明)
従業員承継の後継者の資金調達
従業員承継の場合は、前にも述べたように、自社株の買い取り資金をどう確保するのかが、大きな壁になります。一般的には、金融機関からの借り入れや、後継者候補の役員報酬の引き上げ、会社からの借り入れなどが選択肢となります。また、さきほどの事業承継税制は、従業員承継でも利用可能です。
近年、ファンドやベンチャーキャピタルなどの投資によって、株の買い取り資金を調達する事例がみられるようになりましたが、当然、事業の将来性などの条件を満たす必要があります。資金調達の可能性については、やはり専門家のアドバイスを受けるべきでしょう。
「60歳には準備に着手」が
望ましい
中小企業庁の「事業承継ガイドライン」(第3版、2022年3月)は、「後継者を決めてから事業承継が完了するまでの後継者への移行期間(後継者の育成期間を含む)は、3年以上を要する割合が半数を上回り、10年以上を要する割合も少なくない」と述べたうえで、「平均引退年齢が70歳前後であることを踏まえると、概ね60歳頃には事業承継に向けた準備に着手することが望ましい」と指摘しています。
実際には、経営者や会社の置かれた状況は千差万別で、事業承継に必要な時間もさまざまでしょう。ただし、着手が遅くなるほど、選択肢が狭まるのは確か。事業承継が頭に浮かんだら、できるだけ早く行動に移すべきだといえます。
この節税術に必要な
心構えとは
事業承継には、親族内承継、従業員承継、M&Aの3つの手法があります。どれを選択するのかを含め、早めの着手が成功の第一歩。まずは顧問税理士などの専門家に相談してみることをお勧めします。
事業承継は会社の一大イベントです。世代交代により会社が更なる成長を遂げられるよう、万全の準備をして臨まなければなりません。しかし、事業承継を行う当のご本人、先代経営者と後継者には事業承継の経験がありません。仮に先代経営者が2代目もしくは3代目であったとしても、経験したのは数十年前。時代も違えば、「引き継ぐ者」から「引き継がれる者」へと立場も逆転しています。ましてや、後継者には経験がある筈がありません。2人とも経営のプロではありますが、事業承継は初体験、人生に一度の経験なのです。ぜひ専門家のアドバイスを受け、まずは事業承継の計画を立てることをお勧めします。
また、事業承継における後継者への株式の移転は、先代経営者に万一のことがあった場合の相続を見据えて対策を立てなければなりません。株価の引き下げによる節税対策はもちろんですが、納税資金の確保、後継者以外の子へどんな財産を残すのか、といった相続全体を考えて対策を立てる必要があります。ぜひ、信頼できる専門家を見つけてください。
(塩見明税理士事務所 所長 塩見 明)