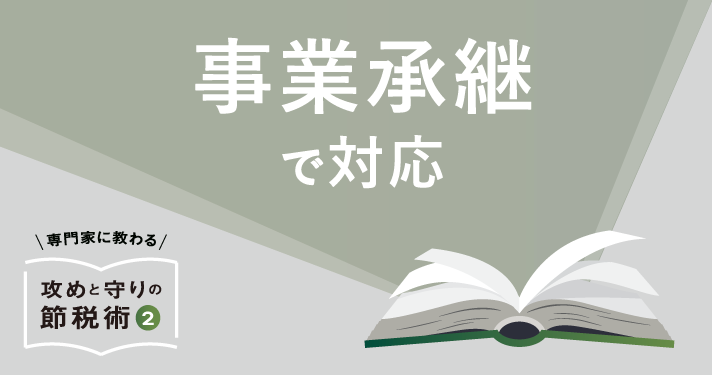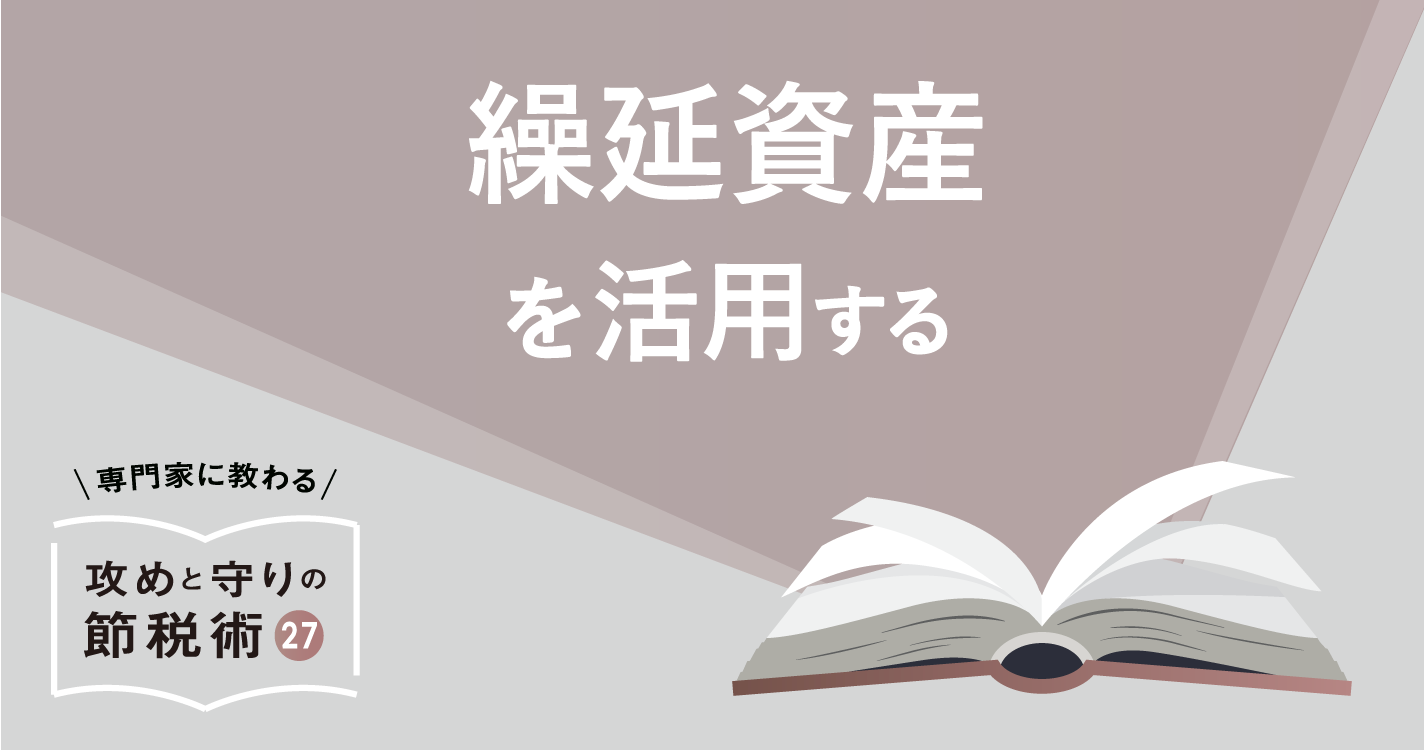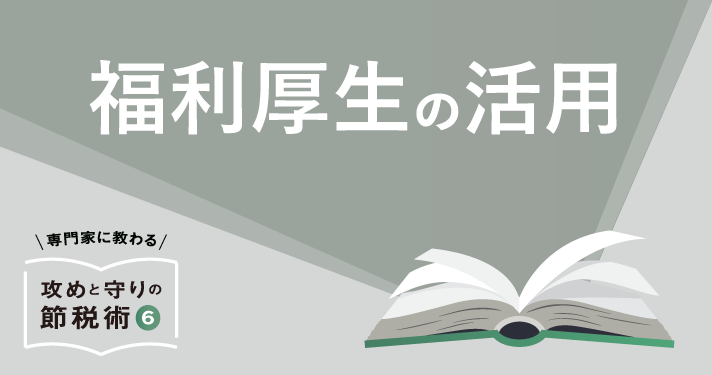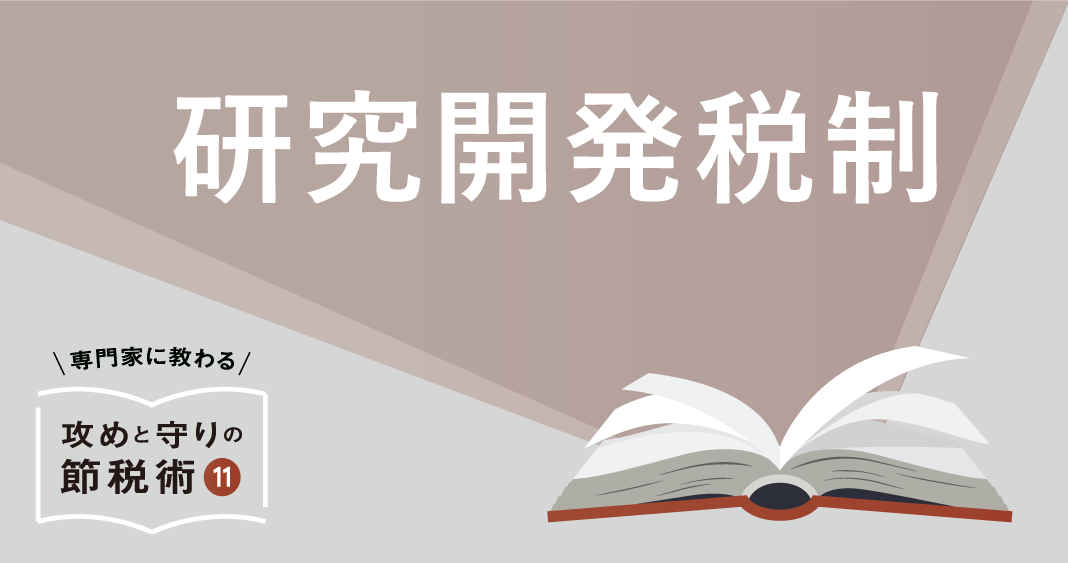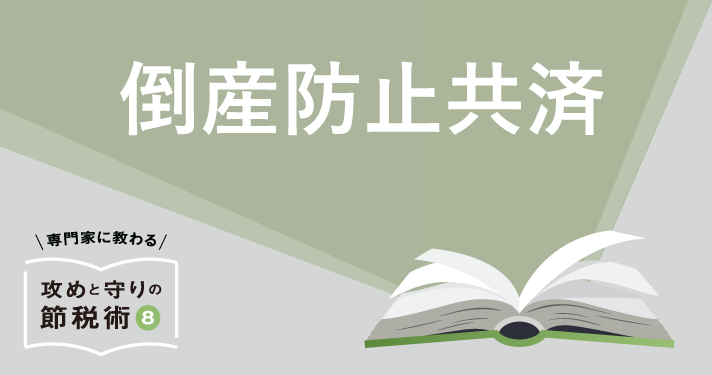「iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用する」
という節税術
個人事業主や小規模企業の経営者にとって、老後資金の準備は大きな課題です。国民年金や国民年金基金だけでは不安を感じる方も多いでしょう。
iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)とは、老後の資産形成をしながら、現在の所得税や住民税を大幅に軽減できる、一石二鳥の私的年金制度です。
iDeCoの最大の魅力は、掛金が全額所得控除になり、高い節税効果を得られることです。iDeCoを活用する節税術をマスターすれば、老後資金を積み立てながら、手元に残るお金を増やし、経営の安定にもつながります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?
まずは、iDeCoの仕組みと企業型DCの基本的な違いを整理して理解しておきましょう。特に個人事業主の場合、iDeCoは国民年金に上乗せして老後資金を準備しつつ、高い節税効果を得られる強力な手段となります。
iDeCoとは?基本の仕組みをわかりやすく
iDeCo(イデコ)は、個人が任意で加入する「私的年金制度」の一つです。正式名称を「個人型確定拠出年金」といいます。
iDeCoの仕組みは、加入者(個人事業主・経営者)が毎月掛金を拠出し、自ら選んだ金融商品(定期預金、保険、投資信託など)で運用します。そして、原則60歳以降に、それまでに積み立ててきた元本と運用益の合計額を受け取れるというものです。受取開始は原則60歳からですが、加入期間により60〜65歳の間で変動します。
個人事業主や小規模企業経営者など国民年金の第1号被保険者の方は月6.8万円(年81.6万円)まで拠出可能で、この金額が全額所得控除になります。
iDeCoの最大の特徴は、以下の3段階すべてで税制優遇が受けられる「トリプル節税」になる点です。
- 積立時:掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
- 運用時:運用益が非課税(通常20.315%課税がゼロ)
- 受取時:公的年金等控除・退職所得控除が適用
2022年5月の法改正で、iDeCoの加入可能年齢は65歳未満に引き上げられ、60歳以上の国民年金任意加入者も加入可能になりました。
将来的には、加入可能年齢が70歳未満まで引き上げられる予定で、2027年の控除分からの実現を目指していますが、施行日は現時点で未定です。
iDeCoと企業型確定拠出年金(企業型DC)の違い
「確定拠出年金」には、個人が加入する「iDeCo(個人型DC)」と、企業が導入する「企業型確定拠出年金(企業型DC)」の2種類があります。両者の違いは以下のとおりです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 加入者 ー 個人(自営業者、会社員、公務員など)
- 掛金拠出者 ー 個人(加入者自身)
- 加入の任意性 ー 任意(希望者が加入)
- 運用商品 ー 加入者が選定
企業型確定拠出年金(企業型DC)
- 加入者 ー 導入企業の従業員
- 掛金拠出者 ー 原則として企業(事業主)
- 加入の任意性 ー 原則として企業の全従業員
- 運用商品 ー 企業が提示した商品から選定
小規模企業の経営者や個人事業主の場合、企業型DCを導入していないケースが多いため、iDeCoに加入することで、ご自身で老後資金と節税対策を積極的に進めることになります。
加入資格と拠出限度額をチェック
掛金を拠出できる上限額(拠出限度額)は、加入者の職業や他の年金制度の加入状況によって、以下のように異なります。
- 第1号被保険者(個人事業主、フリーランスなど):拠出限度額は最大6.8万円(月額)
- 第2号被保険者(企業年金のない企業の会社員など):拠出限度額は最大2.3万円(月額)
個人事業主・フリーランスの方(第1号被保険者)は、月額6.8万円、年額で81.6万円という非常に大きな金額を拠出できます。この全額が所得控除の対象となるため、高い節税効果が得られます。
iDeCo口座開設の流れと金融機関選びのポイント
iDeCoを始めるには、運営管理機関(証券会社や銀行など)を選んで口座を開設する必要があります。
手続きの基本的な流れは以下の通りです。
- 金融機関の選定:
運営管理手数料が無料であること、提示されている運用商品が豊富で低コストであることなどを基準に選定します。 - 必要書類の準備と提出:
金融機関から取り寄せた申込書に記入し、国民年金の加入状況に関する書類などを添えて提出します。 - 国民年金基金連合会の審査:
提出書類に基づき加入資格が審査されます。 - 運用商品の決定:
審査完了後、毎月の掛金で購入する商品(投資信託、定期預金など)を決定し、拠出がスタートします。審査完了から実際に拠出が始まるまでに1~2ヵ月程度かかる場合があります。
金融機関によって提示される運用商品や手数料体系が異なるため、「運営管理手数料が無料」で「低コストの運用商品」を揃えているなどを確認し、自分に合った金融機関を選びましょう。
iDeCoを活用する節税メリット
iDeCoの「3段階の税制優遇」は、税率の高い個人事業主や小規模企業の経営者にとって、非常に大きな節税メリットが得られます。
メリット1 掛金全額が所得控除に
iDeCoの最大のメリットは、毎月拠出した掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になることです。
- 課税所得が減る:
拠出額の分だけ、所得税や住民税が計算されるもとになる「課税所得」が減ります。 - 節税効果:
節税できる金額は「掛金合計額 ×(所得税率+住民税率)」で決まります。所得税率(5~45%)が高い方ほど、節税効果は大きくなります。
たとえば、所得税率33%、住民税率10%の個人事業主が上限いっぱいの月6.8万円(年間81.6万円)を拠出した場合、年間の節税額は35万円超になります。
| 81.6万円 × (33%+10%) = 約35.1万円 |
この節税効果を考慮すると、年間の実質負担は約46万円となり、拠出したお金の半分以上が戻ってくることになります。
メリット2 運用益が非課税で再投資
通常、株式や投資信託などで利益が出た場合、その利益に対して20.315%の税金(所得税および住民税、復興特別所得税)がかかります。
たとえば、年間10万円の運用益が出た場合、通常は約2万円(10万円 × 20.315%)が税金として差し引かれます。しかし、iDeCo口座内ではこの税金がかからないため、全額を再投資に回せます。
これにより、複利効果(雪だるま式に資産が増えていく効果)を最大限に活かして資産をより大きく増やすことが可能です。
メリット3 受取時も大きな税優遇
原則60歳以降にiDeCoの資産を受け取る際にも、以下のような税制優遇があります。
- 一時金で受け取る場合:
「退職所得控除」が適用されます。勤続年数(iDeCoの加入期間)に応じて大きな控除額が設けられているため、受け取り額がこの控除額内であれば、税金はかかりません。 - 年金で受け取る場合:
「公的年金等控除」が適用されます。
退職所得控除は非常に優遇されており、長期間加入しているほど非課税枠が広がるため、大きな節税メリットになります。
メリット4 個人事業主は最大年81.6万円節税も
個人事業主やフリーランスの方(第1号被保険者)は、月額上限6.8万円、年額で81.6万円を拠出できます。課税所得に応じた年間の節税効果の目安は次のとおりです(年81.6万円×(所得税率+住民税10%)で計算)。
- 課税所得が195万円超〜330万円以下の場合 ー 年間の節税額は約16.3万円
- 課税所得が330万円超〜695万円以下の場合 ー 年間の節税額は約24.4万円
- 課税所得が695万円超〜900万円未満の場合 ー 年間の節税額は約26.9万円
- 課税所得が900万円超〜1,800万円以下の場合 ー 年間の節税額は約35.9万円
所得が高い方ほど、年間数十万円単位で税負担を軽減でき、手元に残る現金を増やせます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用する際の注意点
iDeCoは非常に魅力的な制度ですが、「個人型確定拠出年金 デメリットしかない」と検索される方がいるように、利用にあたっては注意すべき点も存在します。制度の特性を理解して利用しましょう。
注意点1 60歳まで原則引き出せない
iDeCoはあくまで「老後のための年金制度」です。一度拠出した掛金は、原則として60歳になるまで途中で引き出せません(一部例外あり:障害や死亡時など)。
資金繰りに余裕がない個人事業主や経営者は、無理な掛金を設定すると急な出費に対応できなくなるリスクがあります。掛金は、生活費や事業資金に支障が出ない範囲で設定することが重要です。
注意点2 手数料がかかるので金融機関選びが重要
iDeCoを運用するには、以下のような各種手数料が発生します。
- 加入時・移換時手数料:国民年金基金連合会に支払う手数料(加入時のみ)
- 運営管理手数料:選択した金融機関に支払う手数料
- 事務委託先金融機関手数料:資産管理サービス信託銀行に支払う手数料
特に「運営管理手数料」は金融機関によって異なり、毎月数百円かかる場合もあります。運用期間が長くなると手数料総額は数万円〜十数万円になることもあります。
運営管理手数料が無料で、かつ運用商品が豊富な金融機関を選ぶことが、コストを抑えつつ効率的に資産を増やす基本です。
注意点3 元本割れリスクがある
iDeCoで運用する商品には、元本が保証されていない投資信託なども含まれます。運用状況によっては、拠出した元本を下回る元本割れのリスクがあります。
商品の選択は自己責任であり、長期的な視点でご自身のリスク許容度に合った商品を選ぶことが重要です。なお、元本保証型の商品(定期預金や保険商品)もあり、分散投資や低コスト商品の活用でリスクを抑えることも可能です。
注意点4 企業型DCとの併用制限に注意
小規模企業の経営者が、企業型DCを導入している企業で働く配偶者とともにiDeCoを活用する場合など、企業型確定拠出年金との併用には掛金上限額の制限があります。
たとえば、企業型DC加入者がiDeCoに加入する場合、掛金上限は月2万円または月1.2万円(※企業の企業年金制度の有無による)に制限されます。
ご自身の企業年金制度の加入状況や配偶者の加入状況によって上限額は変わるため、国民年金基金連合会や金融機関で正確な情報を確認することが重要です。
この節税術に必要な心構えとは
iDeCoは、節税効果、運用益の非課税、受取時の優遇という、3つの節税メリットを同時に享受できる、個人事業主・小規模企業の経営者にとって有効な節税対策の一つです。
一方で、「60歳まで引き出せない」「運用リスクがある」「掛金上限が加入資格によって異なる」といった複雑な側面もあります。
この節税術を成功させるために最も必要な心構えは、「長期的な視点を持つこと」と「正確な情報に基づき無理のない計画を立てること」です。
iDeCoの加入資格や拠出限度額、事業における節税効果の最大化については、税理士にご相談いただくことを強くおすすめします。