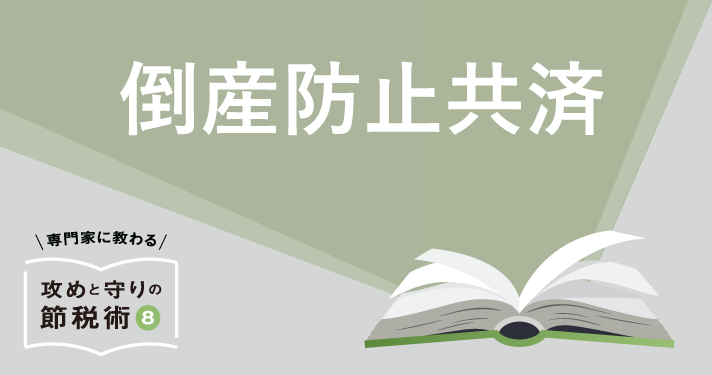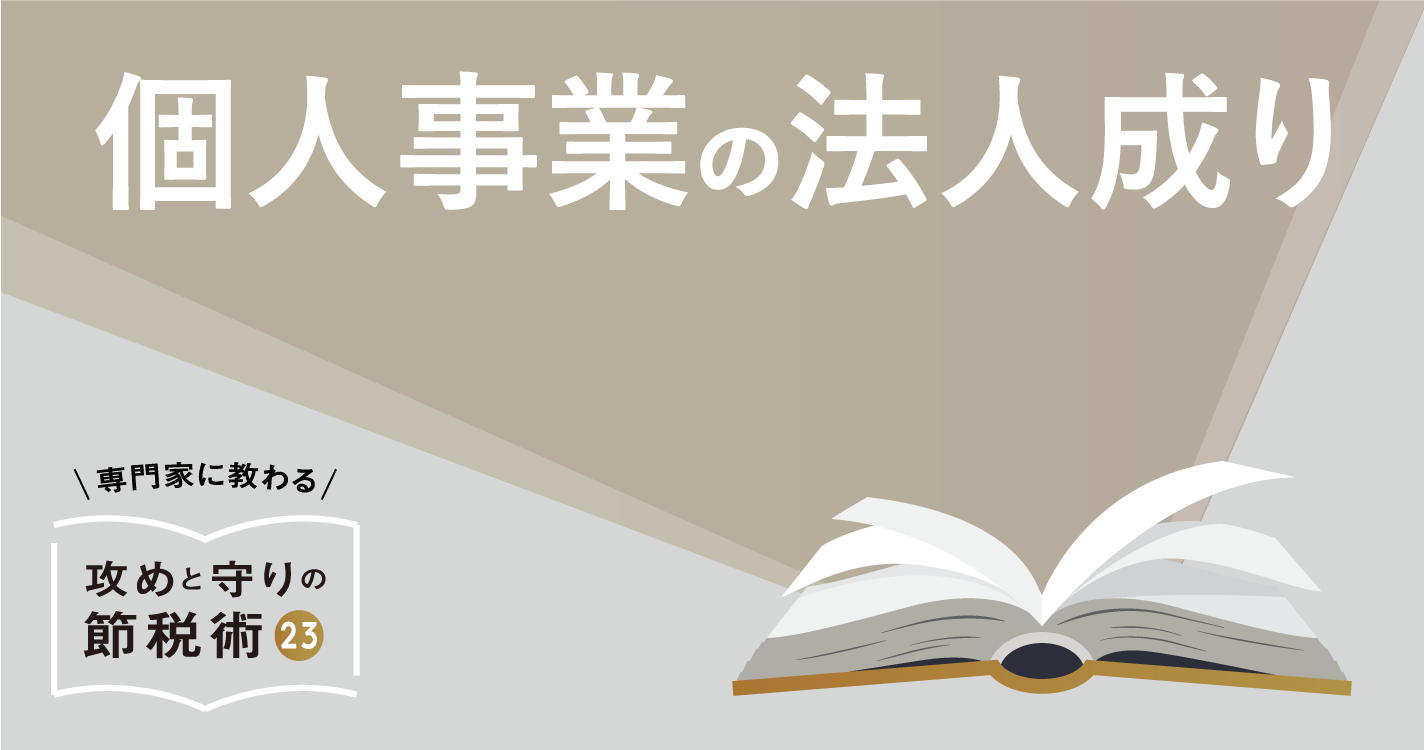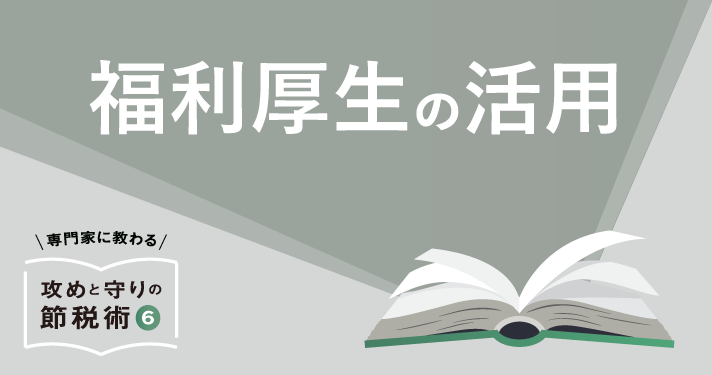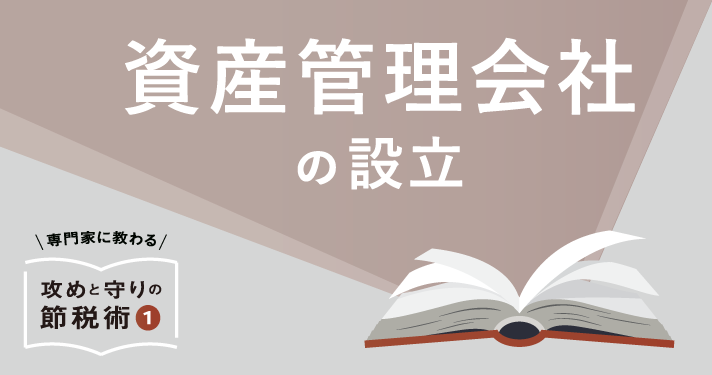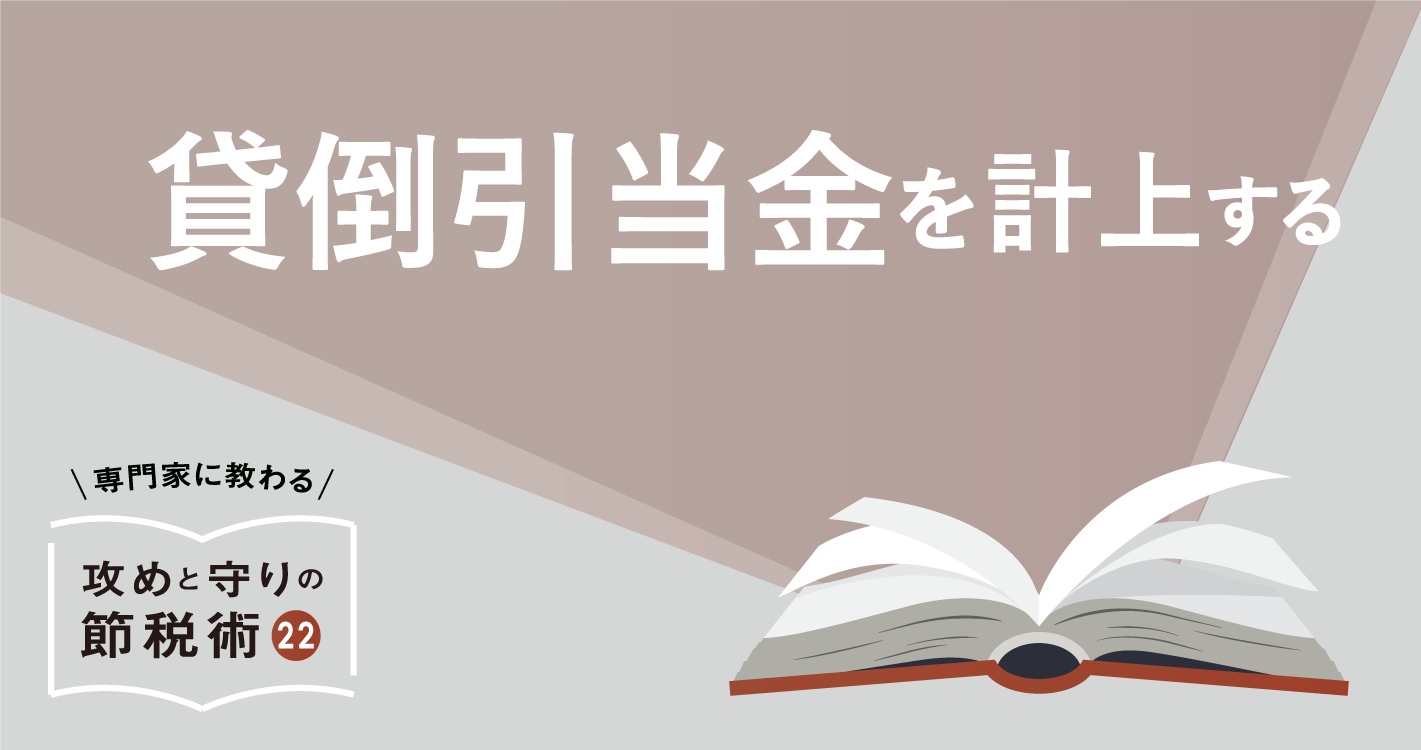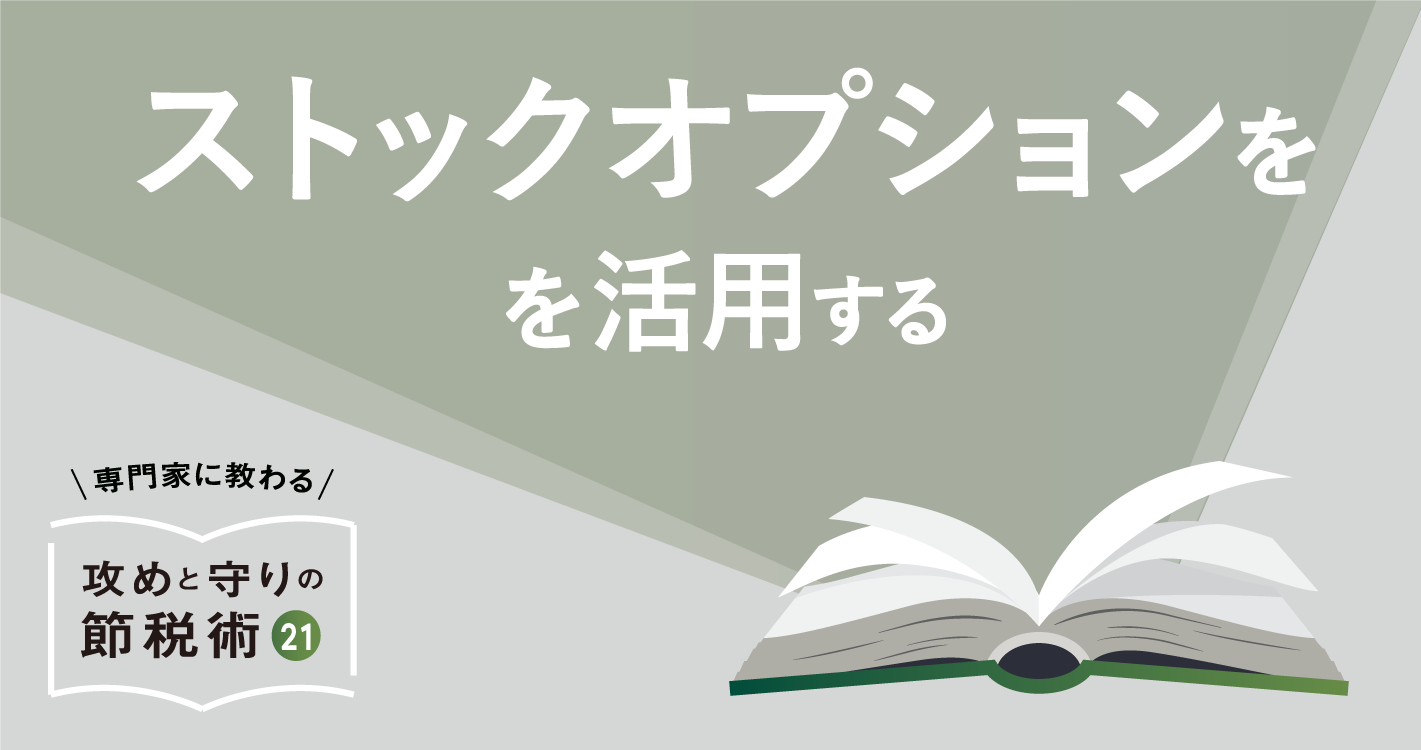
「ストックオプションを活用する」という節税術
企業の成長を支える役員や従業員にとって、自社株を取得できる「ストックオプション制度」は大きな魅力です。特にベンチャー企業や中堅企業では、今すぐの報酬ではなく、将来の株価上昇に期待するインセンティブとして活用されるケースが増えています。
しかし、ストックオプションには「税制優遇を活用した節税メリット」がある一方で、「要件を満たさなければ逆に大きな税負担になる」という落とし穴も存在するため、注意が必要です。
本記事では、ストックオプションの基本的な仕組みから節税メリット、注意点、そして失敗を避けるための心構えまでを解説します。
ストックオプションとは
ストックオプションという言葉を聞いたことはあっても、「一体どういう仕組みなの?」「会社や従業員にどんなメリットがあるの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
特にベンチャー企業や中堅企業の経営者・従業員にとっては、報酬設計や節税の観点から理解しておきたい重要な制度です。この章では、まずストックオプションの基本的な仕組みをわかりやすく解説します。
ストックオプション制度の基本(新株予約権の仕組み)
ストックオプションとは、役員や従業員が「将来、あらかじめ決められた価格で自社の株を購入できる権利」です。これは「新株予約権」と呼ばれ、企業が優秀な人材を引きつけ、モチベーションを高めるためのインセンティブとして活用されます。
この制度の肝は、付与時の株価に関わらず、将来の行使価格(株を買う時の価格)が事前に決まっていることです。
たとえば、現在株価が500円のときに、権利行使価格を500円に設定してストックオプションを付与されたとします。その後、企業の成長によって株価が1,500円に上昇した場合、従業員は権利を行使して1株あたり500円で株を購入できます。
この場合、「時価1,500円の株を500円で買える」ため、1株につき1,000円の利益が得られる仕組みです。
通常の報酬との違いと税金の扱い
通常の現金給与は、支給されたその時点で所得税や住民税が課税され、社会保険料の負担も発生します。
しかし、ストックオプションは付与された時点では税金はかからず、課税のタイミングは「権利を行使した時」、あるいは「株式を売却した時」まで先延ばしにできるのです。
また、税制の種類によって「給与所得として課税」されるのか「譲渡所得として分離課税」されるのかが変わるため、節税効果に大きな差が出ます。
ここがストックオプションを活用するうえでの重要なポイントであり、正しく制度設計すれば、税負担を大きく軽減できる可能性があります。
ストックオプションを活用する節税メリット
ストックオプションが単なる「将来の報酬」とは異なる最大の理由は、税制面での優遇措置によって大きな節税効果を得られることです。特にベンチャー企業や中堅企業では、経営者にとっても従業員にとっても有効な報酬戦略となります。
この章では、ストックオプションを活用することでどのように税負担を軽減し、手取り額を最大化できるのか、その具体的な節税メリットを4つに分けて解説します。
節税メリット1 権利行使まで課税を繰り延べできる
通常の給与と異なり、ストックオプションは付与された段階では課税されません。そのため「将来の利益が確定するまで課税を先送り」でき、現金支出のタイミングをコントロールできます。
たとえば、給与として100万円を支給する場合、支給時に所得税や社会保険料が発生しますが、ストックオプションなら権利行使まで課税を先送りでき、従業員の手元資金を増やせます。
企業としてはキャッシュアウトを抑えつつ人材を確保でき、従業員としては実際に利益を得るタイミングまで税負担を先延ばしできる点が魅力です。
ただし、これは「優遇税制が適用されるストックオプション(税制適格ストックオプション)」の場合に限られます。制度設計を誤ると、権利行使時や付与時に課税されてしまう可能性もあるため、詳細は専門家に確認することが大切です。
節税メリット2 税率の低い譲渡所得課税にできるケースがある
一定の要件を満たす「税制適格ストックオプション」であれば、株式を売却して得た利益は「譲渡所得」として扱われ、給与所得よりも圧倒的に低い税率で課税されます。
給与所得は稼げば稼ぐほど税率が上がる累進課税になっており、所得税の最高税率は45%にもなり、住民税と合わせると最大55%に達します。
一方、ストックオプションの売却益は譲渡所得として扱われ、利益の金額に関わらず、一律約20%(所得税15.315% + 住民税5%)と定められています。
たとえば、ストックオプションを行使して得た株式を売却し、500万円の利益を得たとしましょう。
通常の給与なら、所得水準によっては税率が30%程度となり、税金だけで約150万円が消えてしまいます。しかし、譲渡所得として課税されれば、税額は約100万円で済みます。
この仕組みにより、特に高額報酬を受ける従業員にとっては、手取りを大幅に増やすことが可能になります。
ただし、実際の課税状況は所得の総額や税制改正によって変動する可能性があります。制度の適用可否や最適な設計については、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
節税メリット3 キャッシュアウトを伴わないインセンティブ設計が可能
企業にとって、現金の支出を伴わずに従業員へ魅力的な報酬を提供できるのは大きなメリットです。
特に資金繰りが厳しいベンチャー企業では、高い給与を支払う代わりにストックオプションを活用することで、優秀な人材を引きつけ、離職を防ぐことに貢献します。これは、企業の成長と人件費のバランスを取り、安定した経営を続けるうえで非常に有効な戦略です。
つまり、キャッシュを温存しつつ優秀な人材を確保できる点が、他の報酬制度にはない大きな強みといえるでしょう。
節税メリット4 優遇税制適用で企業と従業員双方にメリットがある
ストックオプションは、役員・従業員と企業の双方にメリットがある理想的な制度です。
「税制適格ストックオプション」の優遇を受けられれば、従業員は税率軽減の恩恵を受けられ、企業は現金支出を抑えたインセンティブ設計が可能になります。制度をうまく設計することで、双方の利益を最大化できるのです。
制度設計を誤らなければ「企業と従業員のWin-Win」を実現できることが、ストックオプションの大きな魅力といえるでしょう。
ストックオプションを活用する際の注意点
ストックオプションは非常に魅力的な節税手段ですが、同時に多くの落とし穴が存在します。制度設計やタイミングを誤れば、期待した節税効果が得られないばかりか、むしろ想定以上の税負担や従業員の不満を生み出してしまう可能性もあるのです。
ここでは、特に注意すべき4つのポイントを解説します。これらを理解しておけば、「失敗しないストックオプション活用」に大きく近づけるでしょう。
注意点1 優遇税制の適用要件を満たさないと節税効果が消える
ストックオプションの最大の魅力は「税制適格ストックオプション」に認められる優遇措置です。しかし、これは自動的に適用されるものではなく、細かな要件をクリアする必要があります。
代表的な要件として、以下が挙げられます。
- 付与対象者は役員や従業員に限定され、社外の取締役などは対象外(ただし、高度人材に限り例外あり)
- 権利行使価格は付与時の時価以上であること(時価より低い価格では税制適格にならない)
- 行使可能期間は付与から2年超、かつ10年以内であること(非上場企業は最大15年まで延長可能)
これらの条件を一つでも満たさなければ「税制適格」とは認められず、行使益は給与所得として課税されてしまいます。つまり、累進課税の対象となり、最大で55%もの税率が適用される可能性があるのです。
制度導入の段階から税制要件を意識し、税理士などの専門家と連携して設計・確認を行うことが、節税成功の鍵となります。
注意点2 付与や行使のタイミング次第で税負担が重くなる
ストックオプションは、権利行使のタイミングを誤ると大きなリスクを伴います。具体的なリスクは以下のとおりです。
税負担の増大
税制非適格ストックオプションの場合、株価が急騰したタイミングで行使すると、多額の給与所得が一度に発生し、高額な税金が課される可能性があります。
たとえば、権利行使価格が1,000円のストックオプションを、株価が3,000円に急騰したタイミングで行使した場合、1株あたり2,000円の利益が給与所得として課税されます。
この給与所得は、給与や賞与に上乗せされるため、所得税率が大幅に上がり、最大55%の税率が適用される可能性があるのです。
価値の消失
株価が下落した場合、権利行使価格が現在の株価を上回ることがあり、その場合、権利行使による利益が得られません。これにより、ストックオプションの価値が実質的に失われる可能性もあります。
こうしたリスクを避けるためには、制度設計や付与・行使のタイミングを、専門家とともに慎重に検討することが不可欠です。
注意点3 株価下落リスクや行使不能リスクがある
ストックオプションは、将来の株価上昇を前提とした制度です。そのため、企業の成長が停滞したり、株価が想定以上に下落したりした場合には、その価値は実質的にゼロになるリスクを伴います。
権利行使価格が500円であるにもかかわらず、株価が400円になってしまえば、ストックオプションを行使する意味はありません。この場合、ストックオプションは報酬としての意味を失い、従業員は期待していた利益を得られない可能性があります。
上場企業の株価変動だけでなく、特にベンチャー企業では、M&AやIPO(新規株式公開)が実現しない場合、ストックオプションを行使する機会自体が失われる可能性もあります。
ストックオプションは「ハイリスク・ハイリターン」な金融商品の一種であることを理解し、期待通りにいかないリスクも念頭に置くことが重要です。
注意点4 制度設計を誤ると従業員への不公平感を生む
ストックオプションは、その設計を誤ると、従業員間の不公平感を生み、かえってモチベーションを低下させるリスクがあります。
たとえば、同じ部署や役職でも付与対象や行使条件に差があったり、付与対象者が経営陣や一部の古参社員に偏ったりすると、従業員は「自分たちは会社に貢献していない」と感じてしまいます。
こうした不公平感は、組織全体の結束力を弱め、優秀な人材の離職につながる可能性もあります。ストックオプション制度を導入する際は、単なる節税効果だけでなく、全従業員が納得できるような透明性の高いルール設定が不可欠です。
この節税術に必要な心構えとは
ストックオプションは、税制優遇を受けられれば大きな節税メリットが期待できる一方、要件を外すと高額課税のリスクを伴う制度でもあります。最大限に活用するためには、次の3つの心構えが欠かせません。
- 最新の税制要件を正しく把握すること
- 企業の成長戦略と従業員のモチベーション設計を両立させること
- 税理士など専門家の助言を受け、自社に最適な制度設計を行うこと
「節税」を入り口に、「企業の成長と従業員の利益が直結する仕組み」を構築することが、ストックオプションを活用する経営者が持つべき最も重要な心構えです。