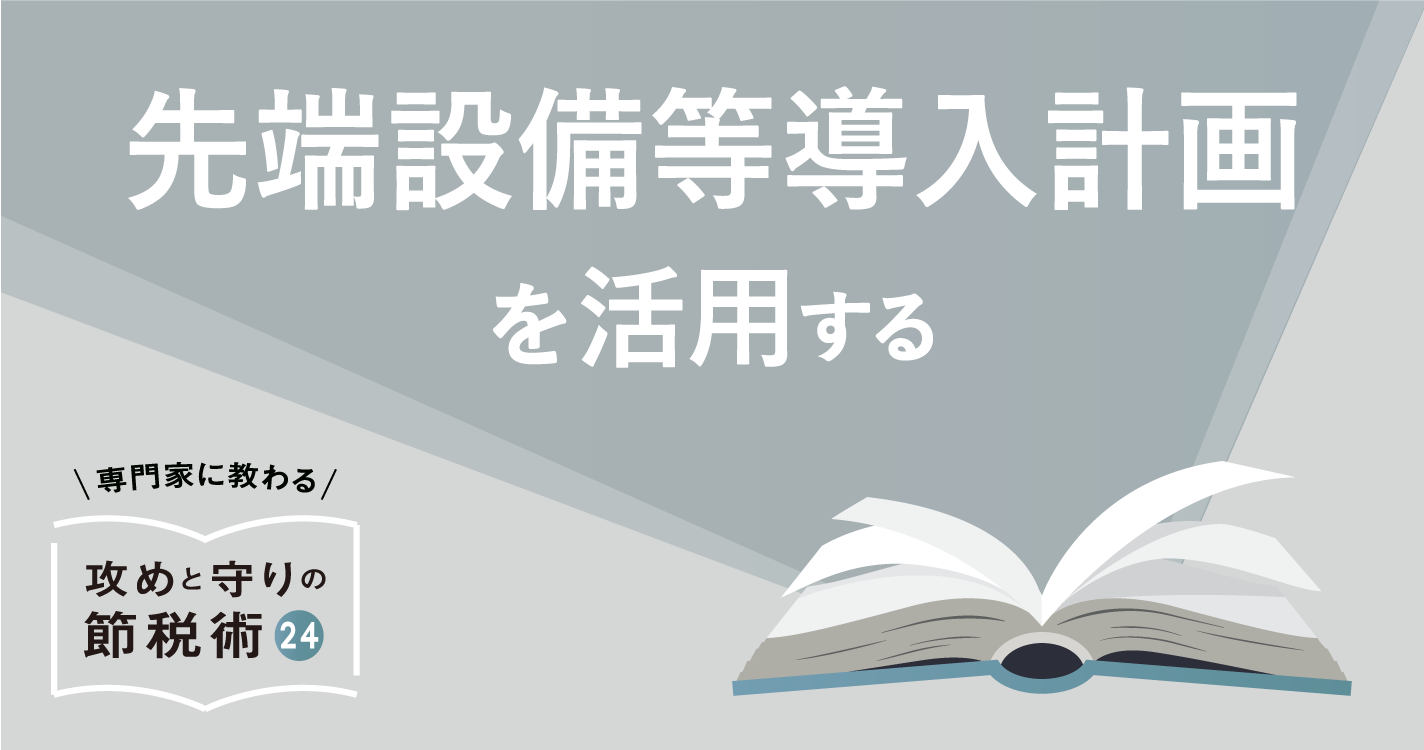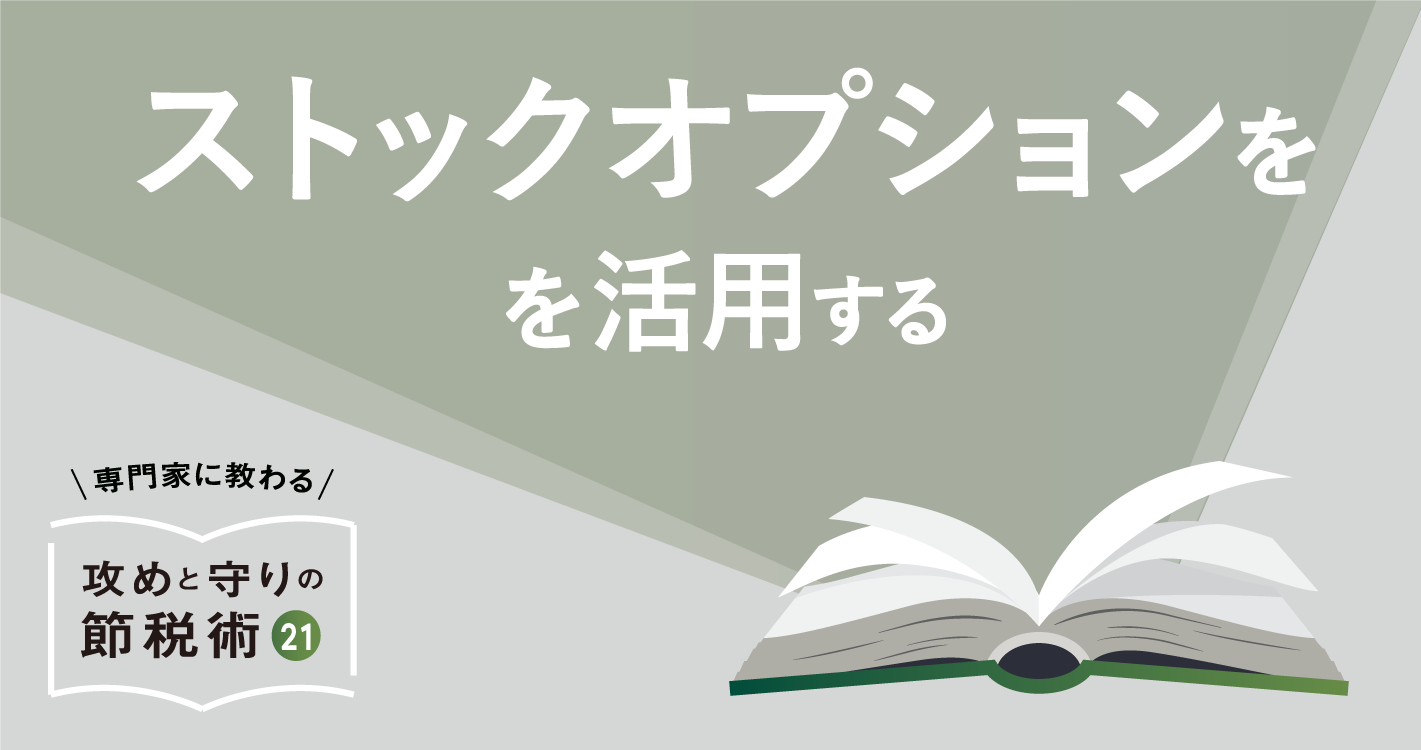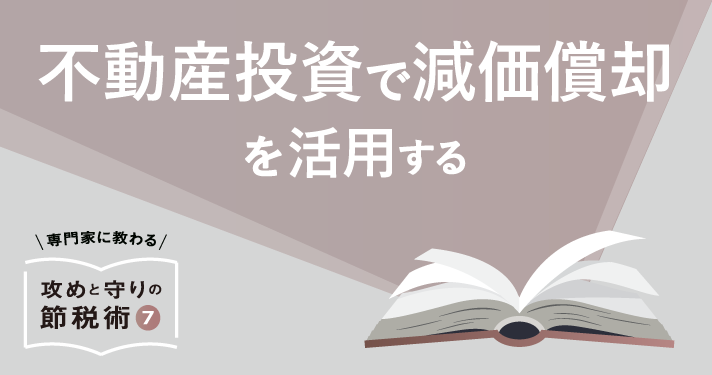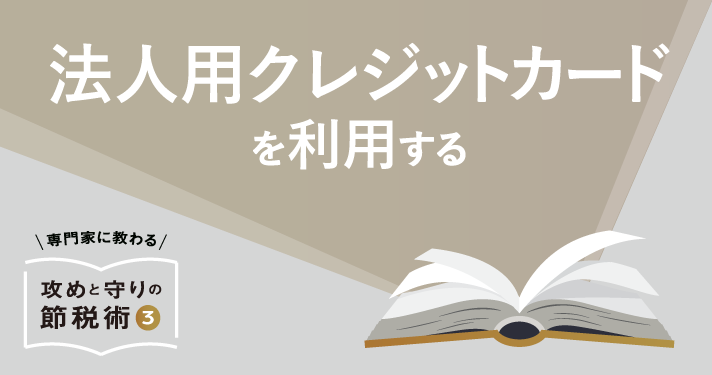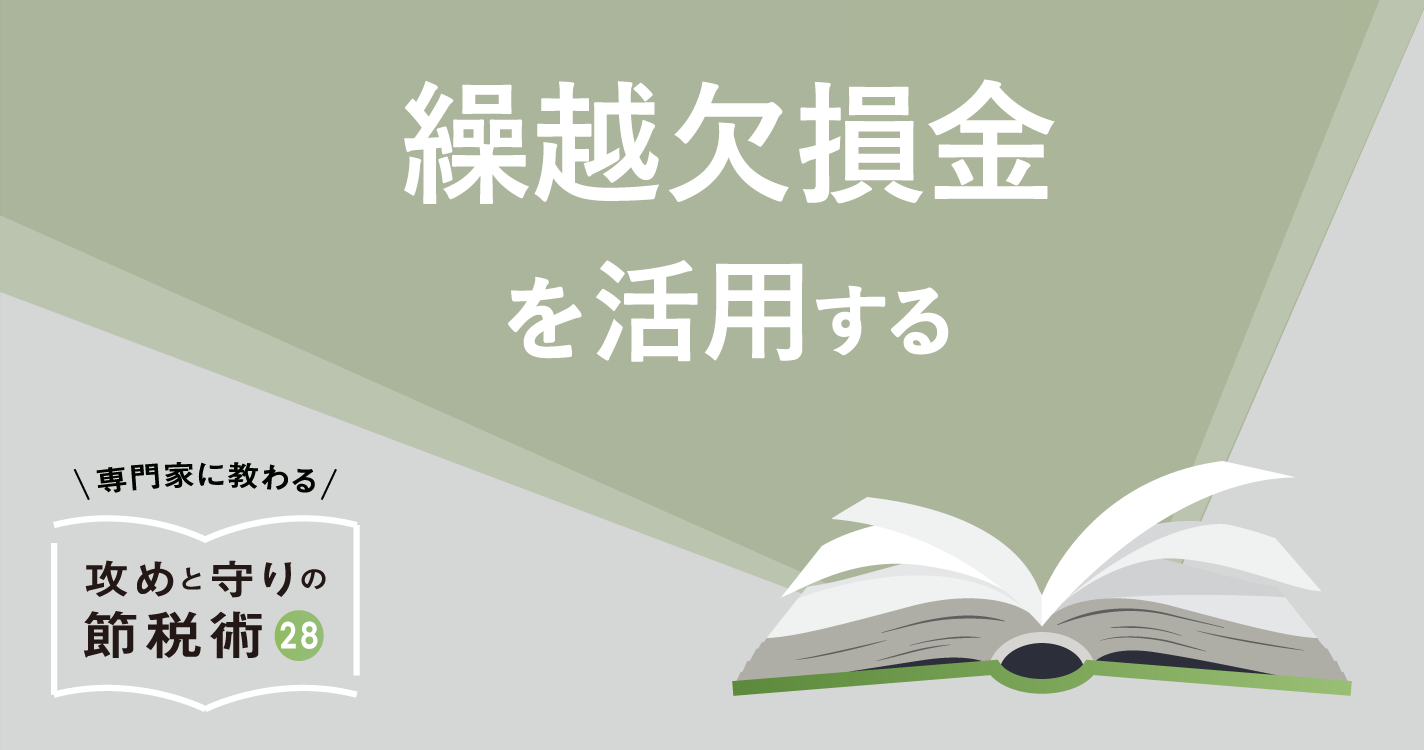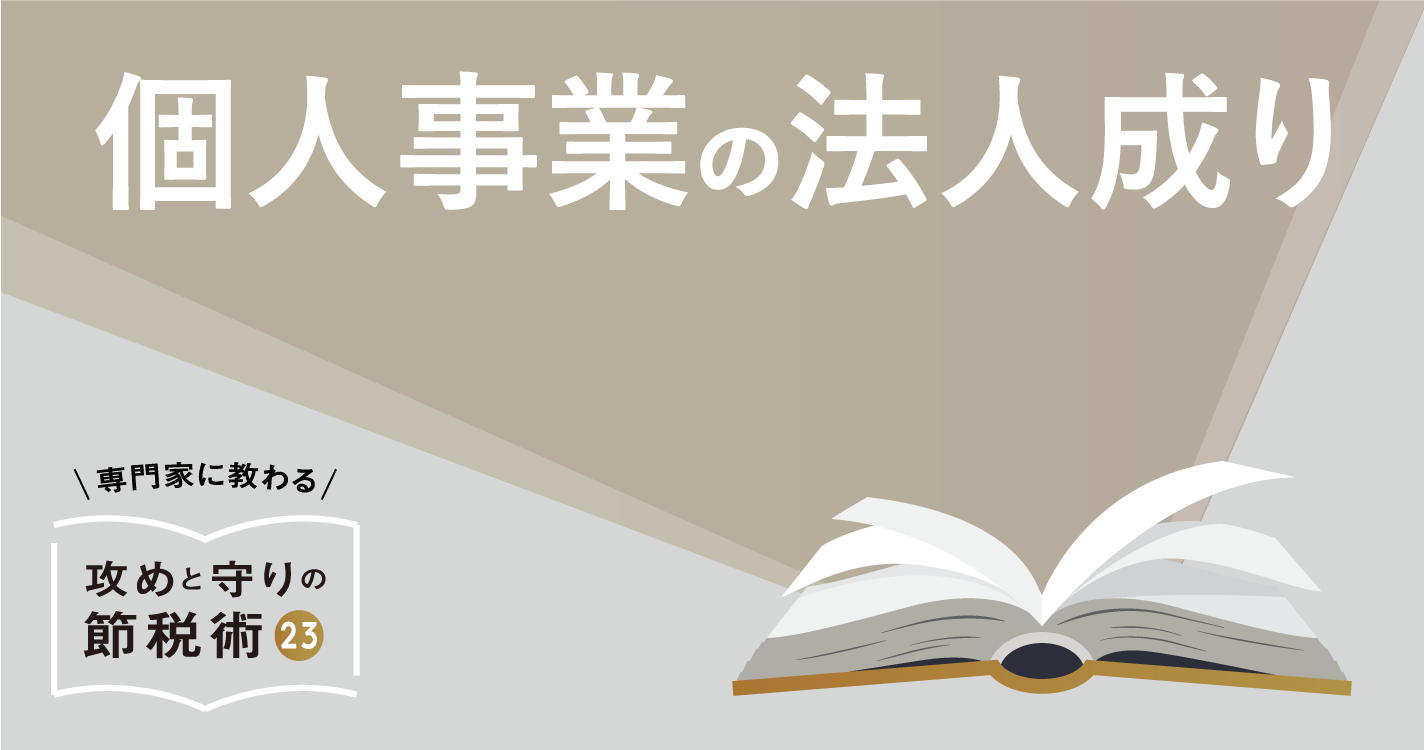
【節税術23】「個人事業の法人成り」という節税術
事業が軌道に乗り、売上が順調に伸びてくると、所得税の負担が重く感じられる方も多いのではないでしょうか。そんなときに検討されるのが「個人事業の法人成り」です。
法人成りとは、個人事業主が法人(株式会社や合同会社など)を設立し、事業を法人へ承継することです。個人の超過累進課税から法人の定率課税へ移行することで、ケースによっては全体の税負担を軽減できます。
一般的には、年間所得が500万円前後から検討を開始し、800万円を超えるあたりで法人化のメリットが明確になる傾向にあります。
ただし、法人税以外にも法人住民税や社会保険料、さらには2025年現在の消費税免除の特例(設立後2年間)などのトータル負担を考慮することが大切です。
本記事では、個人事業の法人成りの仕組みや節税メリット、注意点をわかりやすく解説します。法人化を検討されている方は、ぜひ最後までお読みいただき、判断の参考にしてください。
個人事業の法人成りとは?
個人事業の法人成りとは、個人事業主が法人(株式会社や合同会社など)を設立し、これまで営んでいた事業に関する資産・負債・契約などを法人に引き継ぎ、事業主体を法人へ移行する手続きを指します。
主な流れは、法人設立(定款作成・登記)から個人事業の廃業届出、資産移行までで、目安として2〜3週間程度で完了します。
この手続きを行う主な目的は、税制面でのメリットを享受すること、そして社会的な信用力を向上させることの2点です。
個人事業主の税金は所得税の超過累進課税が適用されますが、法人になると法人税の定率課税(2025年現在、中小企業の実効税率約23.2%)に切り替わります。
これにより、課税所得がおおよそ800万円前後を超える場合には、個人事業主のままでは税率が上がる一方で、法人として事業を継続することでトータルの税負担を軽減できる可能性があります。 さらに、設立後最大2年間の消費税免除特例も活用可能です。
ただし、法人化には設立費用(約10〜22万円)や法人住民税の均等割、社会保険への加入義務など、コストや手続き面で新たな負担が生じる点に注意が必要です。
次項からは、この「個人事業の法人成り」によって得られる具体的な節税メリットと、検討時に必ず把握しておくべき注意点について詳しく解説していきます。
個人事業の法人成りの節税メリット
個人事業の法人成りは、節税の観点から見て非常に魅力的な手法です。
主な理由は、税制の違いにあります。個人事業では所得に対して累進課税が適用されますが、法人は比例税率の法人税(2025年現在、中小企業の実効税率約23.2%)が基調となり、所得分散や経費拡大が可能で、節税に役立ちます。
次に、具体的な節税メリットを4つに分けて詳しく解説します。
節税メリット1 税率の軽減(法人税 vs 所得税)
個人事業の法人成りで得られる主なメリットの一つは、税率の軽減です。個人事業主の場合、課税所得が900万円超で所得税率が33%(住民税と合わせて実質43%)に跳ね上がり、1,800万円超では40%となります。
一方、法人は中小企業者(資本金1億円以下)であれば、所得800万円以下の部分に15%の軽減税率が適用され(2027年3月31日まで延長)、目安として全体の実効税率は約23.2%に抑えられます。
たとえば、個人事業で年収1,200万円の事業主の場合、所得税・住民税の合計は概ね300〜320万円程度となります。
法人化して役員報酬を適正額に設定すると、法人税・個人所得税の合計を概ね240〜260万円程度に抑えられる場合があります(※)。
※実際の税負担は控除(基礎控除・青色申告控除・社会保険料控除など)や経費、役員報酬の設定額により大きく変動します。詳細は税理士にご相談ください。
このように、個人事業の売上が増加し、所得が一定水準を超えたときに、この税率差が節税効果を最大化します。法人の個人成りとは異なり、成長期にある個人事業主に特に有効な節税メリットです。
節税メリット2 役員報酬の損金算入による所得分散
法人化すると、社長である個人事業主自身への役員報酬を、法人側の経費(損金)として計上することが可能となります。
個人事業では事業所得から直接課税されるため、このような所得の分散は行えません。しかし、法人は報酬額を調整することで、法人側の課税所得を減らし、個人側の所得税の税率を調整しやすくなるのが大きな特徴です。
ただし、役員報酬を経費として認めてもらうには「定期同額給与」(毎月一定額)であることなどの要件があります。具体的には、事業年度開始から3ヵ月以内に報酬額を決定し、株主総会で議決しておく必要があります(一人会社でも議事録作成は必須です)。
株主総会にて支給時期、支給額を確定し、税務署に届出書を提出することにより、役員賞与の支給をすることも可能です。但し、届出の提出期限がありますので注意が必要です。(水谷孝之税理士事務所 代表 水谷 孝之)
さらに、家族を役員に任命すれば、所得を複数の納税者に分散させることができ、扶養控除(配偶者の年収123万円以下で満額38万円、子38万円など)を最大限に活用した節税も期待できます。
ただし、業務内容に見合わない不相当に高額な報酬は、損金不算入のリスクが生じます。
たとえば、個人事業で900万円の所得がある場合、法人化して報酬500万円+法人留保400万円に分散することで、個人所得税を約140万円(低税率帯)に抑え、法人税も90万円程度に軽減され、総税負担を目安として約50万円節約できる可能性があります。
個人事業の法人成りの真価は、このような柔軟かつ合法的な所得管理が可能となる点にあります。
節税メリット3 消費税納税義務の2年間免除
個人事業を法人化すると、設立から最大2年間、消費税の納税義務が免除される特例を活用できます。
この特例が適用されるのは、法人設立時の資本金が1,000万円未満である場合です。法人の設立当初は、消費税の納税義務を判定する「基準期間」(前々事業年度)の売上がゼロとみなされるため、設立初年度とその翌年度の消費税の納付が免除されます。
これにより、法人化直後のキャッシュフローが改善され、事業資金の余裕を確保できるという大きなメリットがあります。
ただし、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では注意が必要です。この免税期間中であっても、適格請求書発行事業者として登録すると、その登録日から消費税の納税義務が発生します。
免税のメリットを最大限に享受したい場合は、登録のタイミングを慎重に検討する必要があります。
上記の他にも、特定期間の課税売上高が1,000万円超の場合などには、消費税の納税義務が発生することがあります。消費税の納税義務の判定は、近年改正が多くあり複雑化しております。消費税の納税義務が免除されるかは専門家に確認しましょう。
(水谷孝之税理士事務所 代表 水谷 孝之)
節税メリット4 経費計上の範囲拡大(退職金、生命保険など)
法人化により、経費として認められる項目が大幅に広がります。個人事業では退職金や生命保険料の計上が制限されますが、法人は役員退職金を損金算入可能(株主総会決議、事業年度内支払い)で、繰延べ節税ができます。
また、法人契約の生命保険料の一部を経費化を経費化でき、社宅家賃や出張手当の計上も柔軟です。赤字繰越期間も個人(青色申告3年)から法人(10年)へ延長され、事業リスクをカバーできます。
これにより、個人事業では課税所得が900万円超で税負担が急増する「壁」を回避でき、全体として20%以上の節税効果が期待されます。
個人事業の法人成りの注意点
法人成りは節税面で大きな魅力がありますが、同時に負担やコストも発生します。これらを事前に把握せずに進めると、かえって手元資金が減少するリスクもあるため注意が必要です。
ここでは、特に押さえておきたい4つの注意点を挙げ、それぞれの対策ポイントについて解説します。
なお、2025年現在のインボイス制度下では、登録義務により税務負担が増える可能性がある点にも留意してください。
注意点1 設立費用と手続きの負担
法人化を検討する際にまず理解しておきたいのが、初期費用の発生と手続きの負担です。個人事業は開業届だけで済みますが、株式会社を設立するには登録免許税や定款認証料などの法定費用が発生します。
これらの費用は目安として22万〜25万円程度で、司法書士など専門家に依頼する場合はさらに報酬が加わります。手続きは通常2〜3週間で完了しますが、書類不備があると遅延のリスクもあります。
また、法人化後は決算・税務処理が複雑化するため、税理士顧問料(月2〜3万円前後)が継続的に発生するケースが一般的です。
初期費用とランニングコストの両方を踏まえ、事業規模や利益水準に見合った資金計画を立てることが重要です。
注意点2 赤字時でも法人住民税の均等割
個人事業では赤字の場合、所得税や住民税は発生しません。しかし、法人は赤字であっても「法人住民税の均等割」として、資本金1,000万円以下の法人で年間約7万円(都道府県民税2万円+市町村民税5万円前後)が課税されます。
この均等割は、従業員数が増えると段階的に加算される仕組みです。初年度から固定費として発生するため、利益が不安定な時期はキャッシュフローを圧迫する可能性もあります。
特に、業績変動の大きい業種では法人化前にシミュレーションを行い、赤字リスクを十分に確認しておくことが大切です。
注意点3 社会保険加入義務と負担増
法人化すると、社長1人でも健康保険と厚生年金への加入が義務となり、保険料は法人と個人で折半します。たとえば月給30万円の場合、法人負担分はおおよそ月4万円が目安です。
個人事業主時代の国民健康保険・国民年金に比べると、社会保険料の総額は増えるケースが多く、家族を扶養に入れる際の条件も厳しくなります。
一方で、将来の年金受給額が増えるなどの保障面のメリットもあります。短期的にはキャッシュフローを圧迫するため、法人化前に保険料負担を試算し、資金計画に織り込んでおくことが重要です。
法人成りしたものの、税金の事ばかり考えていて、社会保険料の負担の事を失念していたというケースがよくありますので、ご注意ください。
(水谷孝之税理士事務所 代表 水谷 孝之)
注意点4 法人化のタイミングのミスマッチ
個人事業の法人成りは、タイミングを誤ると節税効果が薄れます。一般的な目安は課税所得900万円超や売上1,000万円超ですが、インボイス登録の有無や家族構成により最適時期は変動します。
早すぎると法人住民税の均等割が負担となり、遅すぎると所得税の高税率区分にとどまるリスクがあります。
赤字続きの事業や、短期的に売上拡大の見込みがない場合は法人化を控え、専門家に相談して3~5年後の売上予測を基に判断しましょう。
この節税術に必要な心構えとは
「個人事業の法人成り」は、事業の成長を次のステージへ押し上げるための、極めて有効な節税戦略です。
所得税の累進課税から法人税の定率課税へ移行することで、役員報酬の損金算入や消費税免除の特例、経費計上範囲の拡大など、多角的なメリットを得られます。
一方で、判断ミスは大きな追加コストにつながることもあります。必要なのは、事業拡大への覚悟と、専門家の力を柔軟に取り入れる姿勢です。
ぜひ、法人化の実績が豊富な税理士に相談し、2025年現在のインボイス制度を踏まえた最適なシミュレーションと手続きを進めましょう。それこそが、この節税戦略を成功へ導く、最初の確かな一歩となるでしょう。
個人事業の法人成りとは、個人事業主が法人を設立し事業を承継する手続きで、税制や信用力の面で大きなメリットがあります。
所得税の累進課税から法人税の定率課税へ移行することで、所得が増えるほど節税効果が期待でき、役員報酬による所得分散や設立後2年間の消費税免除、経費計上範囲の拡大なども可能です。
一方で、設立費用や法人住民税の均等割、社会保険料負担など新たなコストが発生するため、資金繰りや事業規模に応じた慎重な判断が必要です。
インボイス制度などの税制改正により、法人成りの最適なタイミングの考え方は変化していきますので、専門家と相談しながら進めることが成功の鍵となります。
(水谷孝之税理士事務所 代表 水谷 孝之)