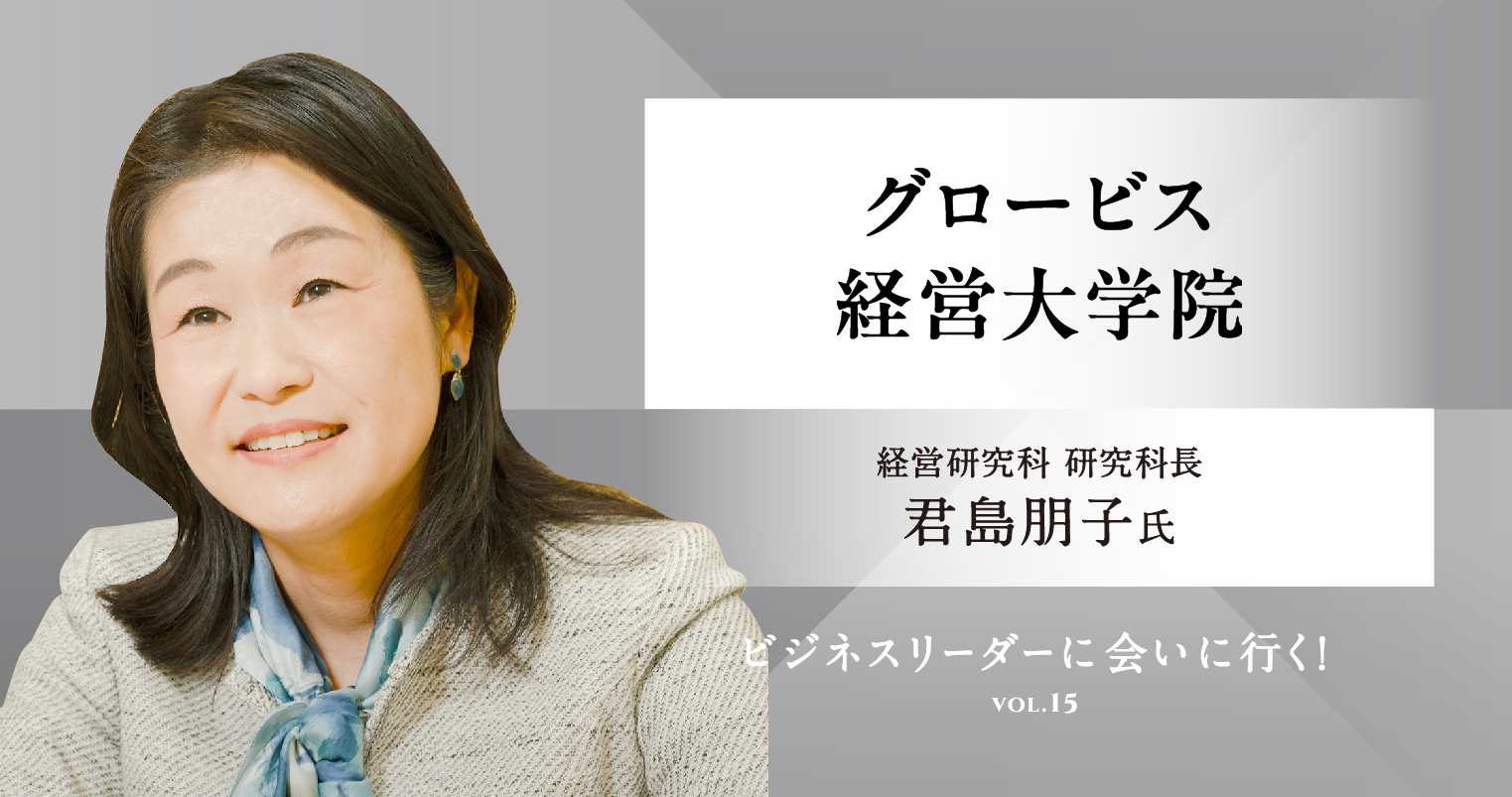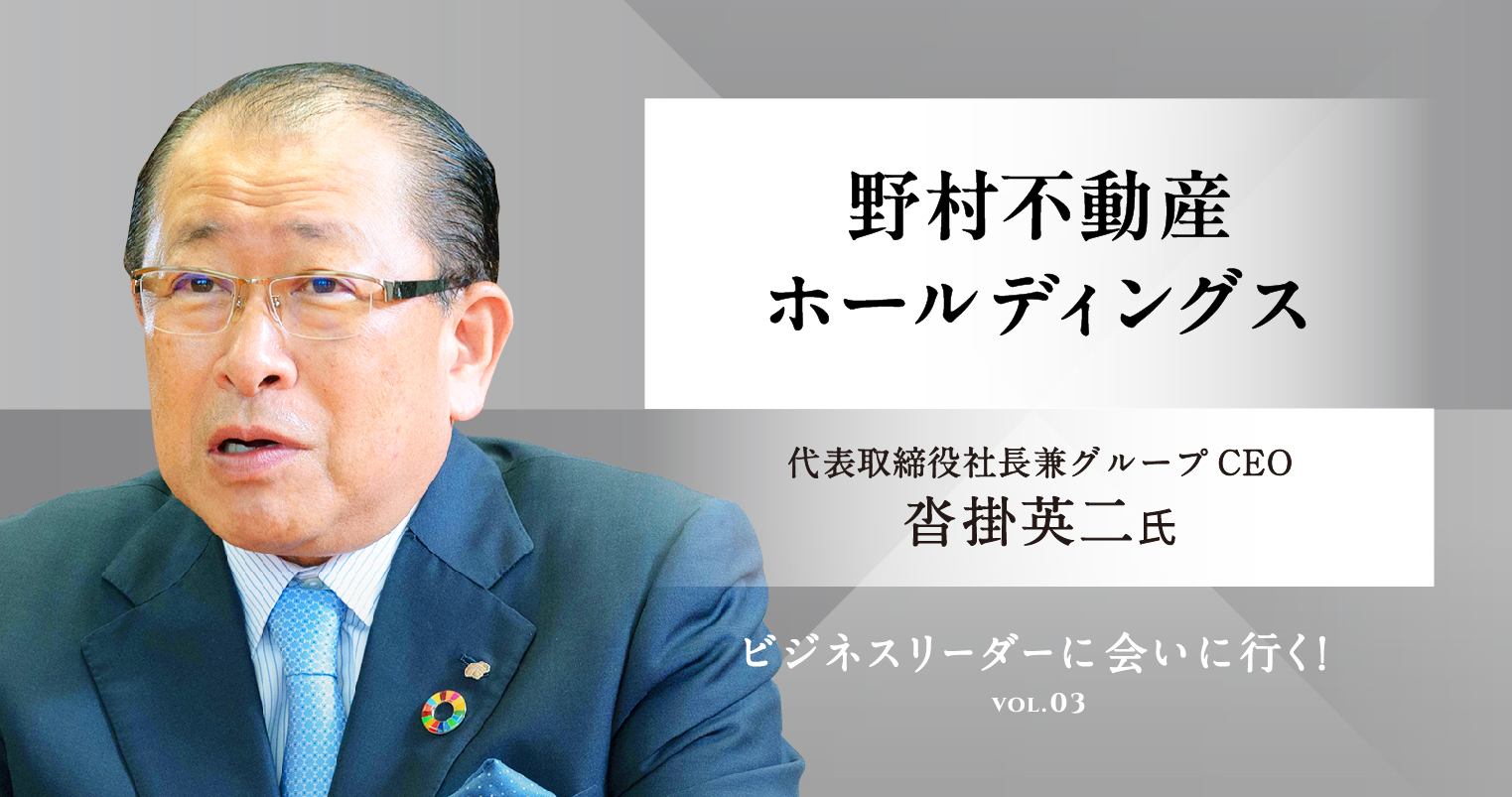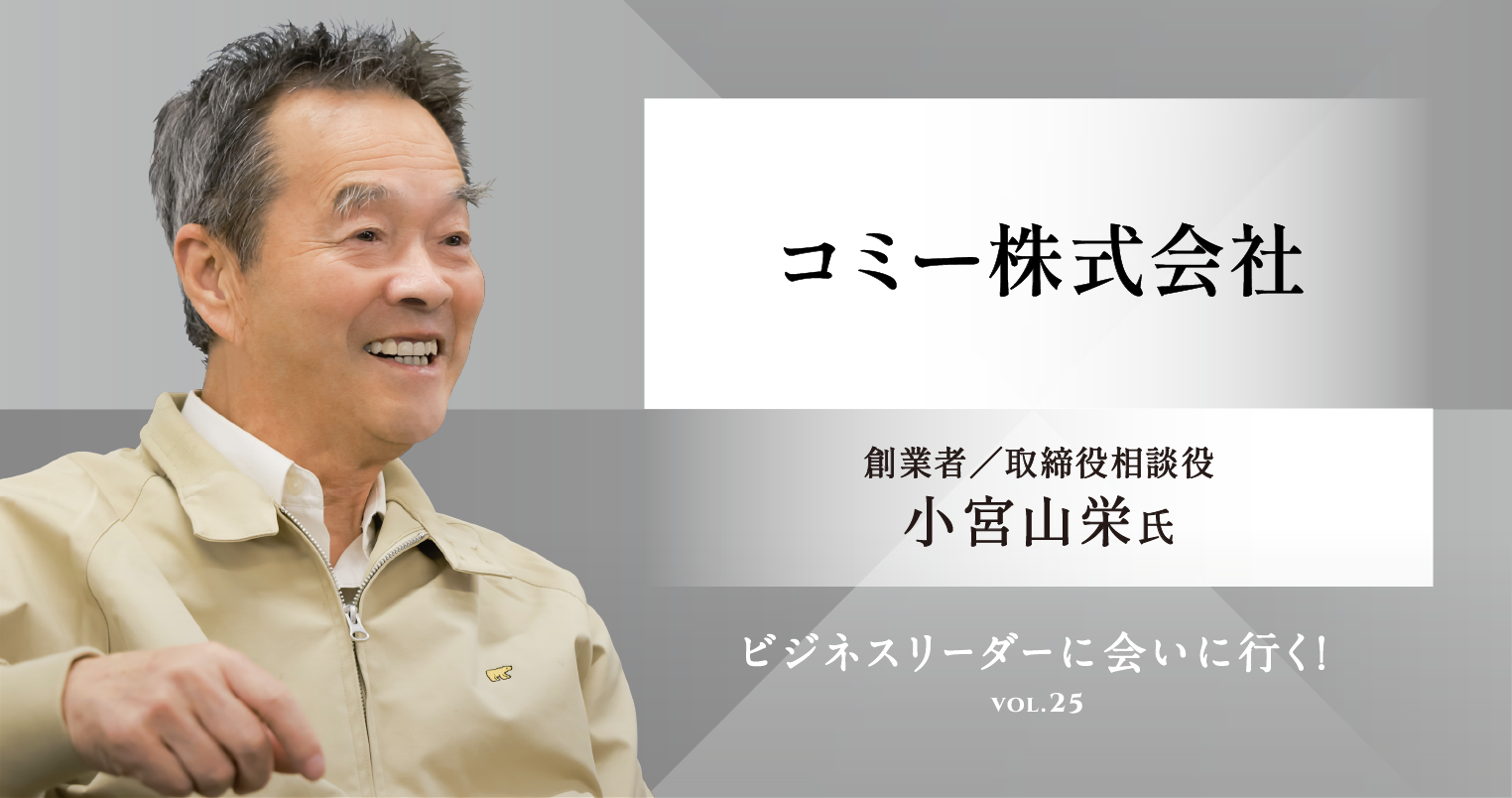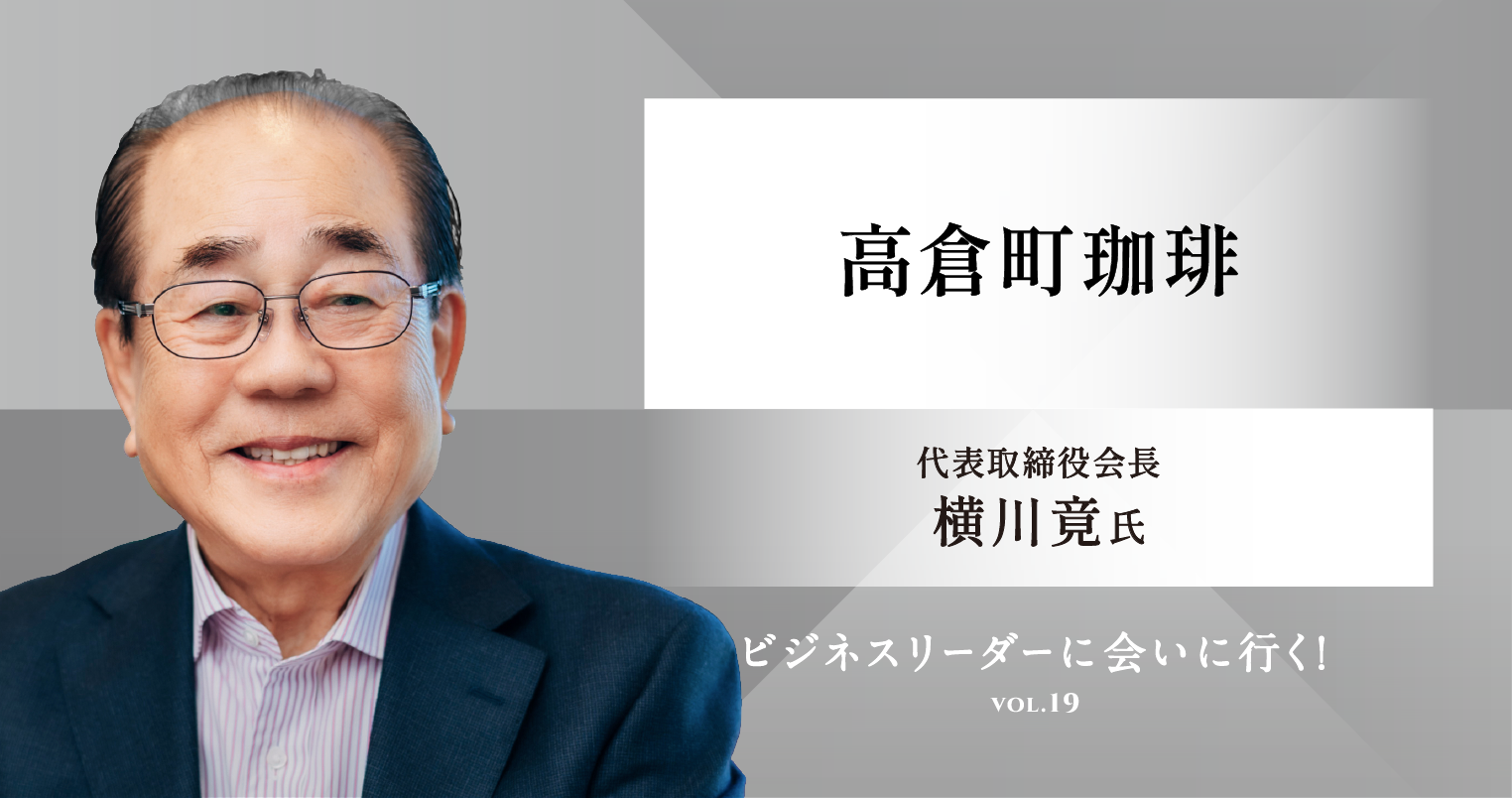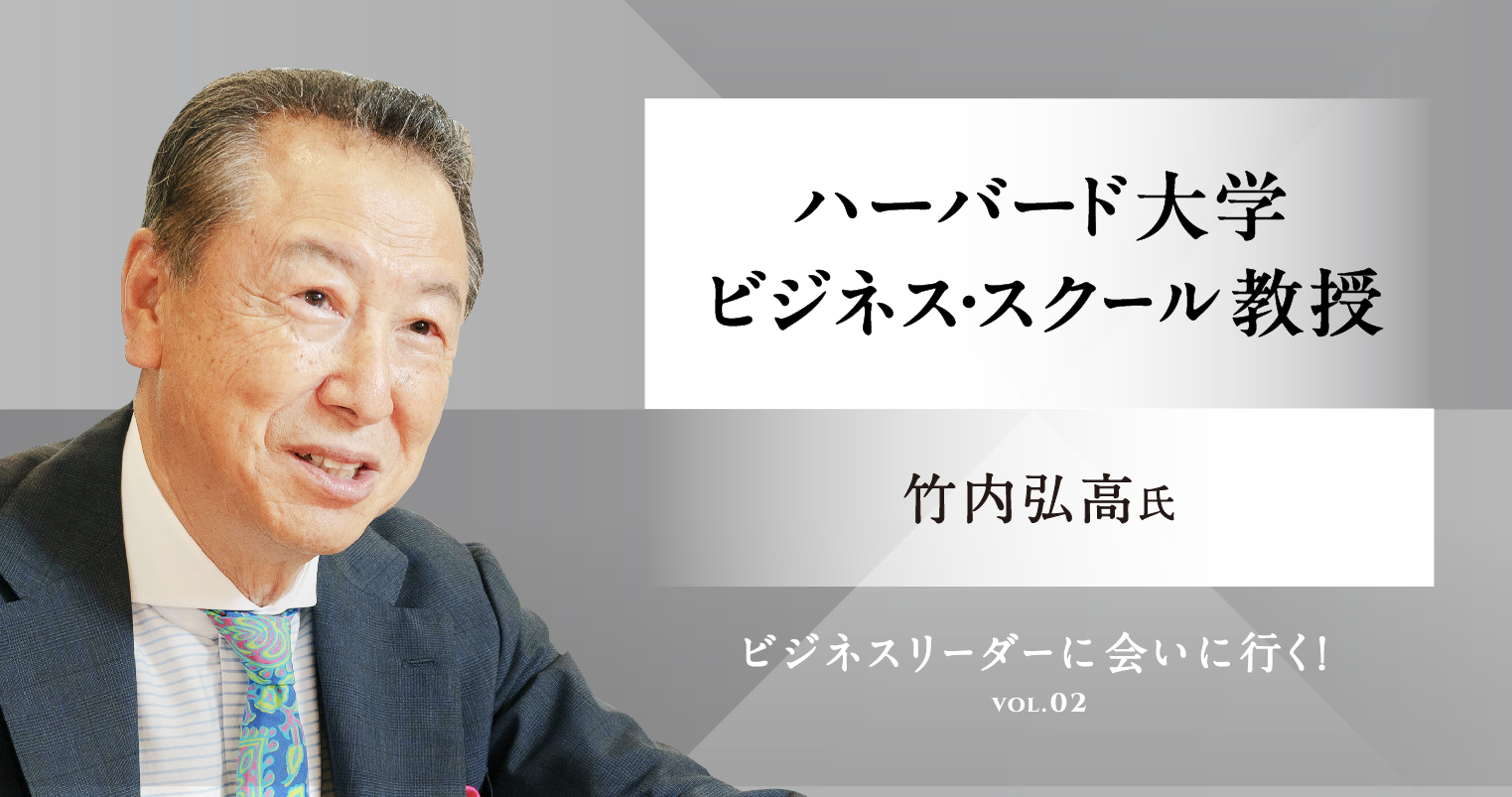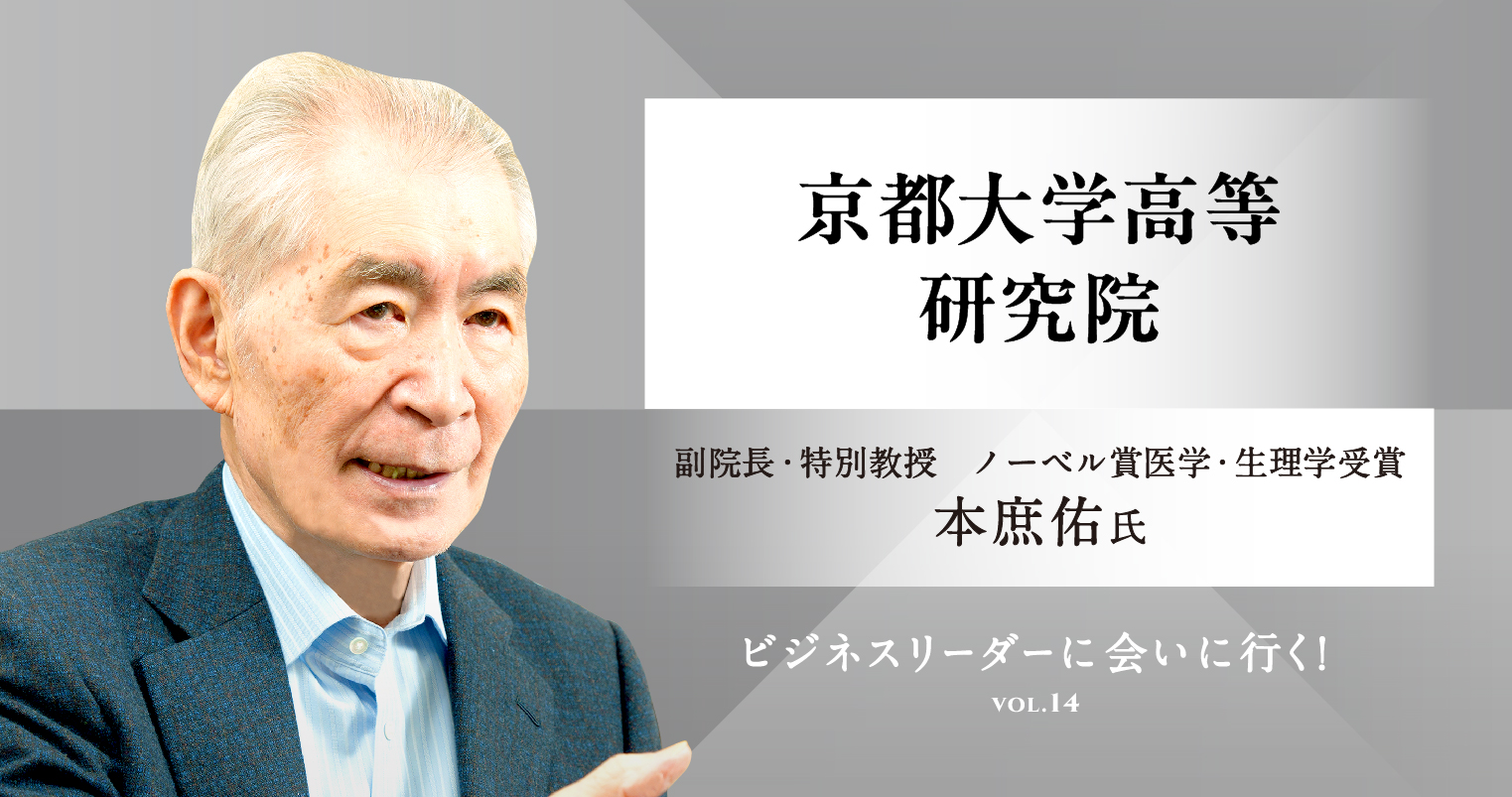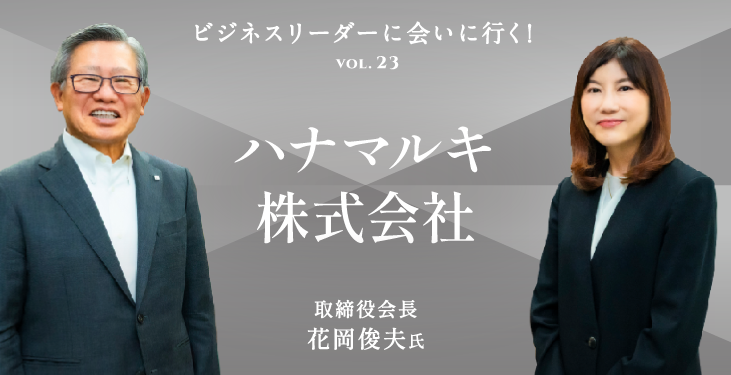
長寿企業だが、イノベーションを怠らない。
主力商品の味噌を支える「液体塩こうじ」を開発
素材とモノ作りを大切にすることが長寿企業の条件
1918年、大正7年に創業して100年以上続く長寿企業。「おみそならハナマルキ」など、斬新なCMでもお馴染みの企業だ。33年間社長業を務めた花岡俊夫取締役会長が、社長時代に生み出したヒット商品が「液体塩こうじ」だ。日本酒やビールの醸造技術からヒントを得て、粒状の塩こうじを搾った液体塩こうじを開発した。料理に使うだけではなく、欧州ではパンをふっくらにする材料としても利用されている。長寿企業の条件を、「素材を大事にして、モノ作りの基本を守ることだ」と語る。イノベーションはこれからも続く。
八木美代子社長(以下、八木) 本日はインタビューの時間をとってくださって、ありがとうございます。子どものころ、母が毎日お味噌汁を作ってくれていましたので、ハナマルキさんの味噌は欠かせませんでした。今でも海外に出かけるときはハナマルキのカップ入りの「即席みそ汁」を持参させてもらっています。
また、今は塩こうじの液体商品が発売されて、料理が簡単になりましたので、欠かさず使わせてもらっています。
もう一つ、ハナマルキさんと言えばCMですね。「おみそならハナマルキ」など一世を風靡されたCMを覚えています。
花岡俊夫(以下、花岡) そのようなお話を聞かせていただき、ありがとうございます。
世の中の動きに流されず、素材とモノ作りを大切にする
八木 ハナマルキさんと言えば、100年以上の歴史を有する長寿企業です。1918年、大正7年に初代社長が味噌と醤油の製造を始めておられます。ずばり核心の話をお伺いしますが、伝統ある老舗企業を経営されていくうえで、一番大事にされたことは何ですか。
花岡 私が社長になったのは1988年。2022年まで社長業を33年やりました。長く経営トップをやっていると、世の中の動きに流されてしまいそうになることがあるのです。「この商品は売れるのでとにかく作れ、作れ」みたいな気持ちにさせられてしまうことがありました。
そんな気持ちでいると会社を危うくします。味噌の場合は大豆、米、塩という素材を一番大事にしなければなりません。大豆などの原料を一番に考え、モノ作りの基本を守る、それが長寿企業として続けられる条件だと思います。

長年社長業をやっていると、
売るために世の中に
流される誘惑があるが、
そこは踏ん張る
八木 素材で妥協しないというのは、どういう意味ですか。
花岡 味噌の原料となる大豆は、国内産もありますが、アメリカやカナダの契約農家で栽培し、日本に輸入しているものが多いです。契約栽培するためには、大豆の種を決めて、「この種で栽培してください」とお願いするわけです。
大豆の種は1万種類もあります。イリノイ州やオハイオ州などが大豆の主産地ですが、その近くに農家に種を売る会社があります。そこへ行って、大豆を選定します。 いろんな種類の大豆のサンプルをもらって味噌を作ってみて、そのうえでハナマルキの味噌の味を出せる種を決めて、契約農家に育ててもらうのです。
人間が一人ひとりちょっと違うように、大豆もそれぞれに個性があります。例えば水につける時間、蒸したり煮たりする方法や条件で大豆の出来が変わります。いろいろな種類の大豆が入ってしまうと、こっちの大豆はうまく煮えても、あっちの大豆はうまく煮えないというアンバランスが生じます。
同じ種類の大豆を同じ地域で栽培すると、均一な原料になります。味噌の中心は大豆ですから、必然的に味噌の品質が安定します。ハナマルキにとって「素材にこだわる」というのは、種にこだわり、自分たちが決めた種を契約農家に育ててもらうことです。
食品安全のための国際規格ISOが伝統的な発酵技術を守ってくれる
八木 売れに売れて原料がなくなって何でもいいから使いたいという気持ちになりませんか。
花岡 とてもありがたいのは、ISOという製品、サービス、プロセスの品質や安全性に関する国際的な共通基準があることです。当社の場合、食品安全のための国際規格「FSSC 22000」を取得しています。ISOの審査は非常に厳しくて、伝票の1枚1枚をチェックされます。ISOの厳格なルールにもとづいて味噌などを作ってますから、モノ作りが安定しますし、品質の高い味噌が作れます。
八木 昔から伝統的に培ってきた発酵技術をISOというルールに照らし合わせることで、品質を安定させることができるという発想は、とてもおもしろいですね。
花岡 品質管理の責任者が目を光らせていて、基準が適合したものでないと出荷できません。生産効率ばかり重視すると、発酵が少し足りない原料でも使ってしまう誘惑にかられるかもしれませんが、それは許されません。
八木 100年長寿企業を続けられるのは偉業です。多くの経営者の方々にインタビューさせていただくと、「100年企業を目指しています」と言うオーナー経営者は結構いらっしゃいます。 しかし、実際に100年続く企業はとても少ないと思いますので、並大抵の努力ではないと思います。

海外に出かけるときは
ハナマルキのカップ入りの
「即席みそ汁」を
持参しています
味噌は長い時間をかけて日本人の食生活の中にしみ込んだ
花岡 味噌というゆっくりと進化した食文化のおかげもあります。最初は味噌とも醤油ともつかない調味料が、中国、朝鮮半島から入ってきました。 それが何百年の間に進化して味噌と醤油に分かれました。
味噌は長い時間をかけて、日本人の食生活の中に染み込んできましたので、ある一定のボリュームの市場は常にあるわけで、簡単に需要が激減することがないのです。全国の生産量はずっと右肩下がりですが、下がっても需要が大きく下がるわけではありません。減っても増えても上下2%を超えることはまずないです。
だからといって、伝統的な味噌だけを作って安住していていいわけがありません。需要が下がってきているわけですから、自分の会社のブランドを維持しながらマーケティングを展開して需要を喚起しなければなりません。そのため、父親が社長時代の1976年に高級即席味噌汁「おみおつけ」を開発し、販売しました。
父親の危機感は強かった。工場の設備まで更新して即席みそ汁の販売に全力を上げました。今は、即席味噌汁が売り上げの半分ぐらいになっています。どんな企業でも新しいものを生み出すことがとても大事です。

すぐ旨カップみそ汁 あげなす(提供:ハナマルキ)
八木 「液体塩こうじ」もイノベーションの成果ですね。
花岡 私たちにとって大きな存在である味噌を他の商品で支えてきた歴史です。塩こうじもそうですし、あまり知られていませんが、クレープも味噌を支える商品の一つです。
失敗から生まれたクレープがお菓子や寿司など別用途に利用
八木 クレープですか。
花岡 実はクレープは、失敗から生まれた商品です。以前、味噌の新商品として、赤味噌と白味噌を一つのカップに入れて売り出しました。当初は結構売れたのですが、そのうち売れなくなりました。流通経路を辿っている間に赤味噌と白味噌が混ざってしまったからです。
八木 消費者自らが赤味噌と白味噌を自分で混ぜて合わせ味噌にするって楽しいですね。
花岡 そこで、大豆たんぱく質を使ったシートを開発したのです。流通の途中で混ざるという問題は解決したのですが、それでも売れない。ちょうど経営を父親からバトンタッチしたので、この商品の発売をやめることにしました。
せっかく開発した大豆タンパク質のシートまであきらめるのはもったいない。どうするかと言われても、使い道がわからないので、ケーキ屋さんに相談したのです。 そうしたら、ロールケーキを巻くのに使えるってことになりました。
だったら、手巻き寿司にも使えるのではということになって、サンプルを持って行ったら採用してくれました。特に米国は寿司といってもロール巻きとかカリフォルニア巻きが人気ですから、そっちのほうで使えるというので輸出して売り上げを稼ぎました。
八木 味噌の海外での需要はどうですか。海外での売り上げが4倍くらいになったという記事を読んだことがあります。ハワイでも味噌スープを飲んでいる人が結構いました。
花岡 即席の味噌汁、味噌スープを飲む外国人はいますが、味噌を常時食べる民族はそれほど多くはありません。日本以外にスープとして味噌を飲んでいるのは、朝鮮半島の一部と台湾、中国東北部一部の人たちです。ですので、海外での味噌需要は、主に日本式レストランが主です。
当社は海外営業を強化して、積極的に展示会にも出展しています。その商材は味噌よりも塩こうじです。海外では味噌を売り込むよりも塩こうじの需要を拡大するほうが手ごたえを感じます。
八木 塩こうじは海外ではどの地域で需要がありますか。
花岡 主に欧州、米国、アジアで展開していますが、最近注目しているのが、欧州のパンメーカーで液体塩こうじが採用になっていることです。
パンに液体塩こうじを使用することで、生地がふっくらし、質感が出ます。液体塩こうじを使用しているパンは売れているようで、受注量が増えています。パンはグローバルでは主食ですから、広がっていくとおもしろいですね。
日々読む営業レポートが液体塩こうじを生み出すヒントに
八木 液体塩こうじの開発の話を伺いたいのですが、日本酒造りやビールの醸造をヒントにされたのですか。
花岡 日々の営業レポートを丹念に読みますと、取引先が何を欲しているか、どんなことで困っているかがよくわかります。例えば、粒タイプの塩こうじを魚の加工メーカーに持って行った時です。「魚を漬け込むときに塩こうじを使ってみてください」と売り込むわけです。それに対して「魚に粒状の塩こうじがついていると、焼くときに焦げができるので、使えない」という返事が返ってきたのです。
営業レポートを読んでいると、取引先でそういうことをおっしゃるところが多い。だったら、違う方法を考えなきゃいけないとなるわけです。

液体塩こうじ(提供:ハナマルキ)
灘の日本酒メーカーにお邪魔したとき、そこの会長さんが酒蔵を案内してくれました。日本酒の元になるもろみのタンクのところで、そこの経営者の方が「花岡さん、このタンクに首を突っ込んでご覧なさい」とおっしゃるわけです。タンクの上にのぼってタンクの中を見ると、酒のもろみと塩こうじのもろみはまったく同じに見えるわけです。「塩こうじのもろみを絞ったらどうだろうか」と気づかされたのです。
八木 その時にひらめいたんですね。

塩こうじの液体商品が
発売されて、
料理が簡単になりました
花岡 それで、一緒に見学に行った当社の技術者に、塩こうじのもろみを搾ってみてくれと指示したわけです。搾ってみた液体を調べたら、粒状の塩こうじと成分がまったく変わらない。
八木 すんなり製品化できましたか。
花岡 いやいや。液体の塩こうじができて、魚や肉の加工メーカーと協議したわけです。そうしましたら、相手から「搾った塩こうじの中に微生物がいる。無菌にしたら使える」ということになったわけです。米こうじに水を入れて搾ると、とても微量なんですが微生物が入ってくるわけです。次はどうやって無菌にするかという課題が生まれました。
その時は、ビールは酵母を加えて発酵したものをろ過して無菌にしていることを知っていましたから、技術者にそのことを話して、ろ過して無菌にしました。なので、日本酒の技術とビールの技術を組み合わせて液体塩こうじが誕生したのです。
液体塩こうじをヒットさせるため自らスーパーの店頭販売に立つ
八木 液体塩こうじを2012年に発売されています。試行錯誤の末に販売されたのですか。
花岡 他社が出す前に当社が出しておかないと価格競争に陥るだろうというので、一番先に出そうと考えました。オーナー経営の良いところで、設備の準備にすぐに取りかかるように指示を出しました。
八木 発売してすぐに売れましたか。
花岡 2012年10月に新発売したときは、世の中が塩こうじブームだったので、結構売れました。ところがブームが去ってしまって、翌年、翌々年は厳しかったです。取引先から「ブームが終わった商品をハナマルキさんは売れと言うのか」と言われました。それでも、工場を除いた全員で営業に走りました。私もスーパーマーケットの店頭に立って、マネキンになって塩こうじの店頭販売を行ったほどです。
八木 当社は営業会社なので、花岡会長が先頭に立って営業をされたお気持ちはとてもよくわかりますが、花岡会長自らがスーパーの売り場に立ったというお話はビックリです。
花岡 液体塩こうじは必ずヒットすると思っていましたので、必死でした。

日本酒とビールの技術を
組み合わせて
「液体塩こうじ」が誕生
八木 最後に後継者のことについてお伺いします。2022年に長男の花岡周一郎専務に社長をバトンタッチされました。33年ぶりの交代です。多くのオーナー経営者が悩むのは、いつ社長業を息子、娘に継ぐべきかということです。交代のタイミングはどのようにお考えになったのですか。
花岡 父から私がバトンタッチを受けたのは、父が70歳ぐらいで、私が38歳の時でした。当社ぐらいの規模の企業は、アクティブに動くことが経営トップの条件だと思っています。活動的に動ける年齢は、人によって違いますが、私は70歳ぐらいが限界なのかなと思っています。
例えば取引先のお客さんを訪問するときに、「なんで俺が行かなきゃいけないんだ」と思うようになったら交代したほうがいいです。 若い社長だったら、どんどん前に進み、自分で販路を開拓する勢いがあります。「おっくうだな」と考えるようになったら、交代を考えたほうがいいと思っています。もちろん、自分の気力、体力だけではなく、後継者が育ってきたと確信できることが条件です。
八木 周一郎社長に託したことはありますか。
花岡 特にありません。私が社長になったときも、父親は長野県のほうに住んでいて、取締役会も株主総会も出てこない。たまに父親に電話して、ある案件についてアドバイスをもらおうとしました。すると、父親の返事は「おまえはどう思うのか」と問われ、自分の考えを説明すると、「それでいいじゃないか」ですからね。つまりは、先代はおまえに社長業を託したのだから、自分で考え自分で行動しろということです。それが当社の伝統です。だから、私も新社長にすべて任せています。

1951年長野県生まれ。1974年ハナマルキ味噌(現ハナマルキ)入社、1984年常務製造本部長、1987年専務営業本部長などを経て、1988年より社長。2012年「液体塩こうじ」を発売。2018年に創業100周年を記念して「みそ作り体験館」をオープン。2022年に長男の花岡周一郎専務に社長の座を譲り、現在は取締役会長。社外活動としては、2007年全国味噌工業協同組合連合会副会長。2014年に藍綬褒章受章。
各業界のトップと対談を通して企業経営を強くし、時代を勝ち抜くヒントをお伝えする連載「ビジネスリーダーに会いに行く!」。第23回目は、ハナマルキの花岡俊夫取締役会長です。私自身、海外に行くときに持参するのがハナマルキのカップ入り即席みそ汁です。今回のインタビューでは、「液体塩こうじ」の開発ストーリーを詳しくお聞きできましたが、最初から売れたわけではなかったと明かしてくれました。その時、工場を除く会社全員で販路拡大に走り、花岡会長自らがスーパーマーケットでマネキンとして店頭販売したとのこと。とても穏やかな口調で語っていただきましたが、迫力満点でした。