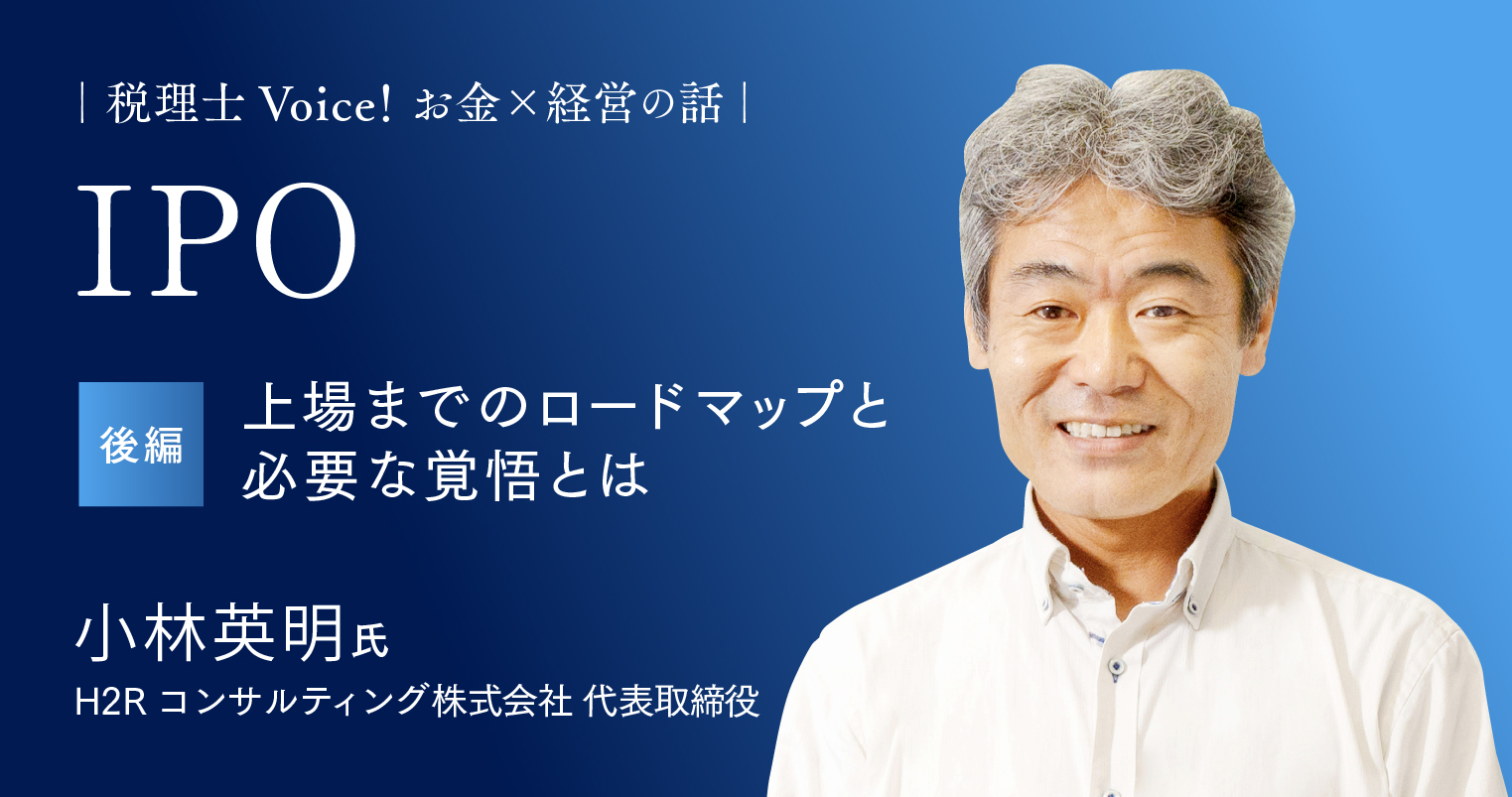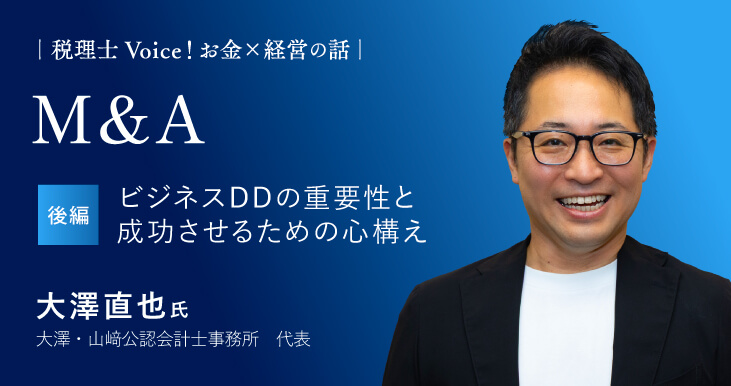【税務調査 後編】「我々の役割は“三方一両損”で収めること」 元国税の税理士が語る税務調査対応の極意とは
峰博行税理士事務所 代表 峰博行氏会社をやる気にさせる調査
――あえてうかがいますが、先生はかつてご自身が国税の職員として税務調査に入るとき、どんなスタンスで臨まれたのですか?
峰 そうですね。調査に関しては自分なりのポリシーがあって、税務署の理論を押し通せば申告漏れにできそうなものが100あったら、是正するのを80くらいにとどめるようにしていました。今回これだけ非違事項がありましたが、追徴課税するのはこの部分にします。以後、注意してください。と、あくまで、意図的な税逃れでない場合ですけど。
――そういう処理をしたのは、どうしてですか?
峰 多くの会社は、税に関しては真剣に取り組んでいます。また、一生懸命やっています。だが、人間のやることだから、勘違いやミスも起こる。そういうところを一切合切「ダメだ」と切り捨てたら、会社は「まじめにやるのが馬鹿らしい」という気持ちになるかもしれません。
そうではなく、「税務署は我々の姿勢を認めてくれた」となれば、「次からも指摘を受けないように、頑張ろう」ということになると思います。そういうふうにもっていくのが、本当の調査だと思っていました。
――まさに「さじ加減」の妙だと感じます。そんな調査官だけだったら、納税者としてはうれしいのですが(笑)。
峰 同じような気持ちを持っている人は、たくさんいると思います。ただ、国税の職員もサラリーマンですから、例えば厳格で実績を重視する上司の下では、それに抵抗するのは、なかなか難しい。そんなこともあり、現実には「厳しい」と感じる税務調査も少なくないわけです。
調査官も人間である
――では、ここまでのお話を踏まえて、税務調査になった場合の対処法に話を進めたいと思います。調査の当日は、どんなところに気をつけるべきでしょうか?
峰 今の話の裏返しでもあるのですが、経験的に申し上げたいのは、まず調査官に「いいイメージ」を持ってもらう、ということです。彼らも人の子なんで、そのときの気持ちのありようによって、処理の仕方が違ってくる可能性があることは、念頭に置くべきでしょう。

脱税が疑われるような特別調査を除き、一般の税務調査にやってくるのは、多くの場合、若い職員です。社長からすると、子ども世代くらいだったりする。一国一城の主としては、つい目上として対処したくなるかもしれませんが、そこで偉そうな態度をとったりして、プラスになることは何もありません。
この点は、調査官の立場になって、考えてみてほしいのです。若いとはいえ、彼らは適正、公平な課税を実現すべく、ある意味国の代表という気概と決意を持って調査にやって来ます。にもかかわらず、現場でぞんざいな扱いを受けたら、いやでも「絶対に問題点を見つけてやる」という発想になるのではないでしょうか。逆に父親世代の社長に尊重されれば、「自分も“紳士的”に振舞おう」という気持ちになると思います。
――よくわかります。調査官に「いいイメージ」を持ってもらうために必要なのは?
峰 なにより調査に協力的な姿勢です。聞かれたことには真摯に答える、要求された資料は速やかに出す、といったことです。
調査はだいたい2日間ですから、会社のすべてを見られるわけではないのです。協力的に対応していれば、普通はポイントを決めて調べて、それで終了です。ところが、何を聞いてもぶっきらぼうな答えしか返ってこない、書類の提出を求めても出し渋る、となると、「もう少し詳しく調べてみよう」「銀行照会をかけてみるか」ということになりやすい。
――帳簿の中身などもさることながら、そういう気持ちの部分を軽視してはいけない、ということですね。
峰 そうです。ただし、調査官を尊重するといっても、彼らの前で余分なことをしゃべったりするのは、やめておきましょう。税務調査では、初めに社長に対するヒアリングの時間があります。調査する側は、そのときに社長の趣味・嗜好や家族などのプライベートな話題に話を振ったりして、少しでも多くの情報を得ようとします。
――そこで語ったことが、調査の端緒になることもある。
峰 国税時代には、こんな経験もありました。社長が「私は、酒は飲まない。趣味はもっぱらゴルフです」と言うのです。それにしては、経費の中に同じバーの領収書がたくさんありました。そこで、そのバーに反面調査(※)に行ってみると、店の担当の女性が「社長がたまにいらっしゃったときに、日付、金額なしの領収書を2、3枚ずつ渡していました」と。よくあるパターンかもしれませんが、さすがにこうしたものを「次回から気をつけてください」と、見逃すわけにはいきません。
※反面調査 税務調査対象者の取引先や金融機関など関係先に対して、税務当局が行う調査。
“お墨付き”をもらうのもいい
峰 まあ、調査になれば、そうしたいろいろなことも起こるわけですが、反対に「税務署がいつ来るかわからない」とビクビクしながら、「安全第一」で申告を行うというのも、私はどうかと思います。節税が可能だと思ったらどんどん実行すべき。もちろん、白紙の領収書をもらったり(笑)、売上を隠したり、と言った脱税行為は絶対やってはいけませんが。
これも私はよく言うのですが、仮に継続的な出費について税務署と見解が異なり、調査でノーと判断されたとしても、追徴の対象になるのは、最長過去5年分です。調査が10年に1回なら、あと5年は経費で取れていましたので、トータルでは得したことになりますよね。
――なるほど(笑)。
峰 最終的に申告の誤りが確定した場合にしか、追徴課税は発生しません。大昔は、納税者を半ば恫喝するような形で修正を認めさせるようなことも、あったと聞いています。しかし、今は国税に審理担当という部署があり、個々の調査の判断が法に照らして合致しているかのチェックを行う仕組みになっています。その結果、「課税できない」という結論になることもあります。
ですから、よほどの「わるさ」をしていなければ、税務調査を過度に恐れたりする必要はありません。むしろ早めに1回来てもらって、正すべきところは正した上で、調査済みの“お墨付き”をもらう。税務調査に対しては、そのくらいの気持ちで構えるのがいいと思います。
――先生が税理士業を始めてから、印象に残る税務調査の事例があれば、教えてください。
峰 税務調査を受けて、会社が「儲かった」ことがありました。さきほどの「期ずれ」に関連するのですが、会社が役務を提供して相手に対価を請求したけれども、まだ入金されていない状態の売掛金も、その期の売上に計上しなくてはなりません。
この会社のケースは、単純なミスで担当者が請求書の控えを机の引き出しにしまい込んだままにしていました。調査でそれが出てきて、「帳簿にないこの請求は、何ですか?」と聞かれた経理の人間は、「わかりません」と答えるしかありませんでした。
それで、調査官がその相手先に確認したわけです。そうすると、「確かに請求は受けている」と。「ちなみに、いつ支払うのですか?」と聞いたら、「いや、そのうちに」というあいまいな返答だったそうです。業界の慣習もあって、督促があったら払う、というような雰囲気だったようです。
ですから、もし調査が入らなかったら、請求の事実は忘れられ、入金されないままの可能性が高かったでしょう。税務署が売掛金を見つけてくれたわけです。
――そういうことになりますね。
峰 また、こんな事例もありました。これも旧態依然の慣習なのですが、ある企業が取引先にいわゆるリベートを渡していたんですね。社長はやめたいのだけれど、そうすると仕事がもらえなくなるかもしれない。で、苦心惨憺して「裏金」を作り、銀行には預けられないから、自分の車のトランクに隠していました。
――それが税務調査で見つかった。
峰 税務署は、銀行口座の調査などを基に、簿外の資金を作っている証拠をある程度押さえていたようです。社長は、当然相手先を言えない訳ですから、追徴課税を受けました。でも、「それでよかった」と言うわけです。
――それはなぜでしょう?
峰 リベートをやめる、この上ない口実ができたからです。「リベート資金が税務署に見つかって、高い税金を支払った」という話をすれば、相手も納得せざるを得ないでしょう。「御社の名前は出していませんよ」と、恩を売ることも忘れませんでした(笑)。結果的には、その後も発注を切られることなく、それまで通りの仕事をしています。
顧客同士のネットワークを作りたい
――さきほど、先生の国税時代のスタンスについてうかがいました。税理士として、心掛けていることはありますか?
峰 “大岡裁き”をネタにした古典落語の「三方一両損」をご存じでしょうか。ある日、左官の金太郎が3両入った財布を拾い、持ち主である大工の吉五郎に渡しに行きます。ところが、吉五郎は「江戸っ子は一度落とした金はもらわない」とこれを突っぱねる。金太郎も「受け取れ」と譲らず、ついには奉行所に持ち込まれ、大岡越前の裁定に委ねることになりました。

両者の言い分を聞いた越前の守は、3両をいったん預かった後、自らそれに1両を加えて、「両者殊勝である」と、褒美として2人に2両ずつを渡し、事を収めました。3両を落とした吉五郎、拾った金太郎、ポケットマネーを出した越前の守それぞれが1両損をした計算になるので、三方一両損。
――でも、みんなが納得して、うれしい気持ちになった。
峰 大岡越前に例えるのもなんですが、私は税理士もこうありたいと思います。税務署と納税者の意見が対立する場面では、自分が知恵を絞って、両者が折り合える解決案を提示する。それが税理士としての私の理想です。
――よくわかりました。最後に、貴事務所の今後の展望をお聞かせください。
峰 最初に申し上げたように、国税の出身者を多く迎え入れ、規模と機能の強化を図りたいと思っています。それを見据えてお客さまを増やすと同時に、事務所を中心にそういう顧客同士をつなぐネットワークを作りたいと思います。税務に関する質問があれば、ネットワークを通じてやり取りする。他のお客さまも見られるようにすれば、他のお客さまにも参考になります。
さらには、そのネットワークを「商売のツール」として活用してもらうことも考えています。同業同士、「うちはこの日は手いっぱいだけれど、どこか受けられる会社はありますか?」と、お互いに仕事を融通しあうとか。顧客のSEさんの力を借りれば、システムの構築自体は、そんなに難しくないはずです。
――会計事務所としては、あまりない取り組みだと思いますので、形になるのが楽しみです。本日はありがとうございました。
税務署・国税局勤務の経験を活かし、税務・会計、税務調査、起業・開業支援、相続まで幅広く対応する。また、自ら不動産管理会社を経営しており、経験に基づいた節税策のアドバイスも行う。
URL:https://www.all-senmonka.jp/search/shousai/0ed492cb2d5b08b2/