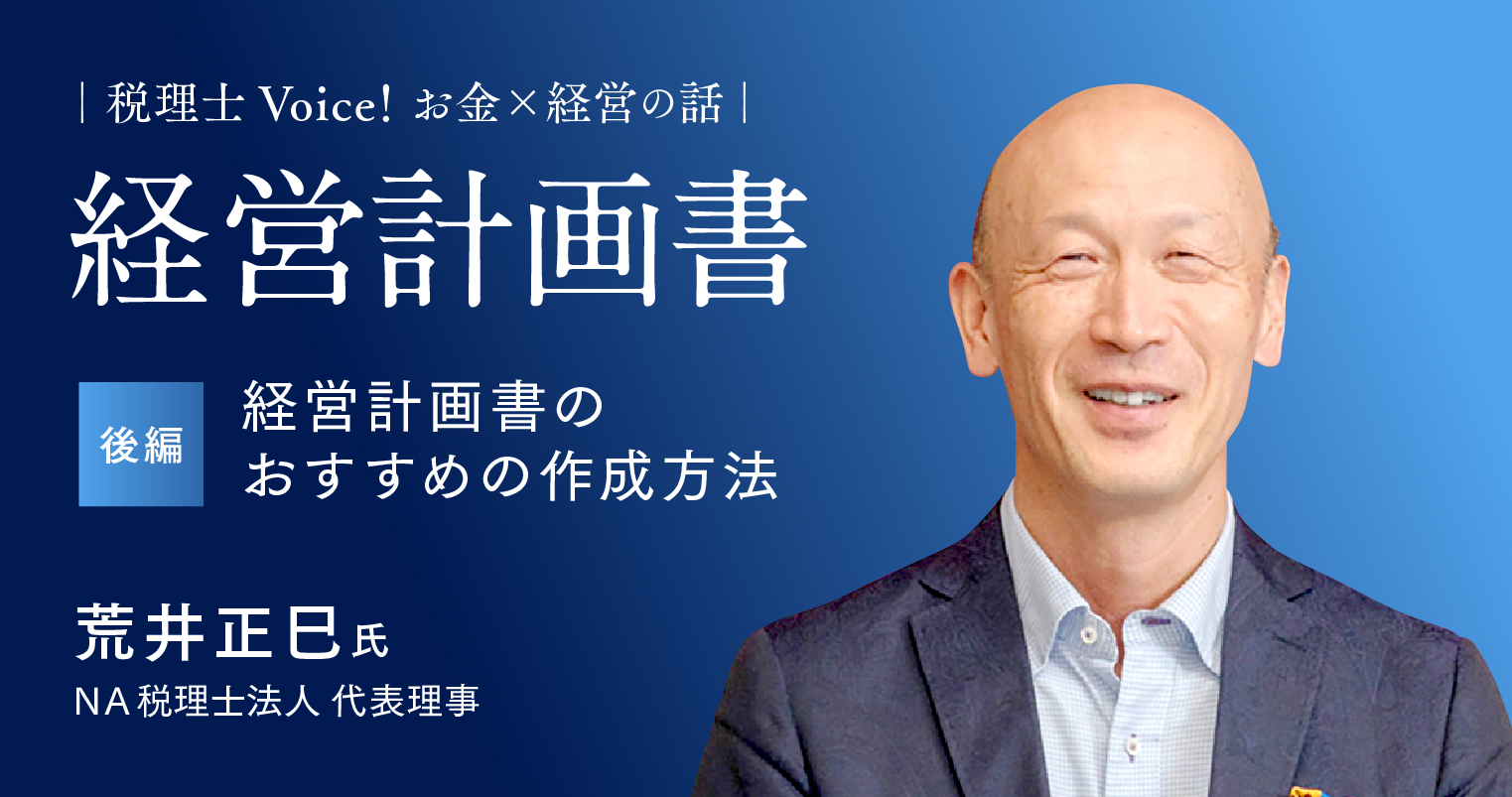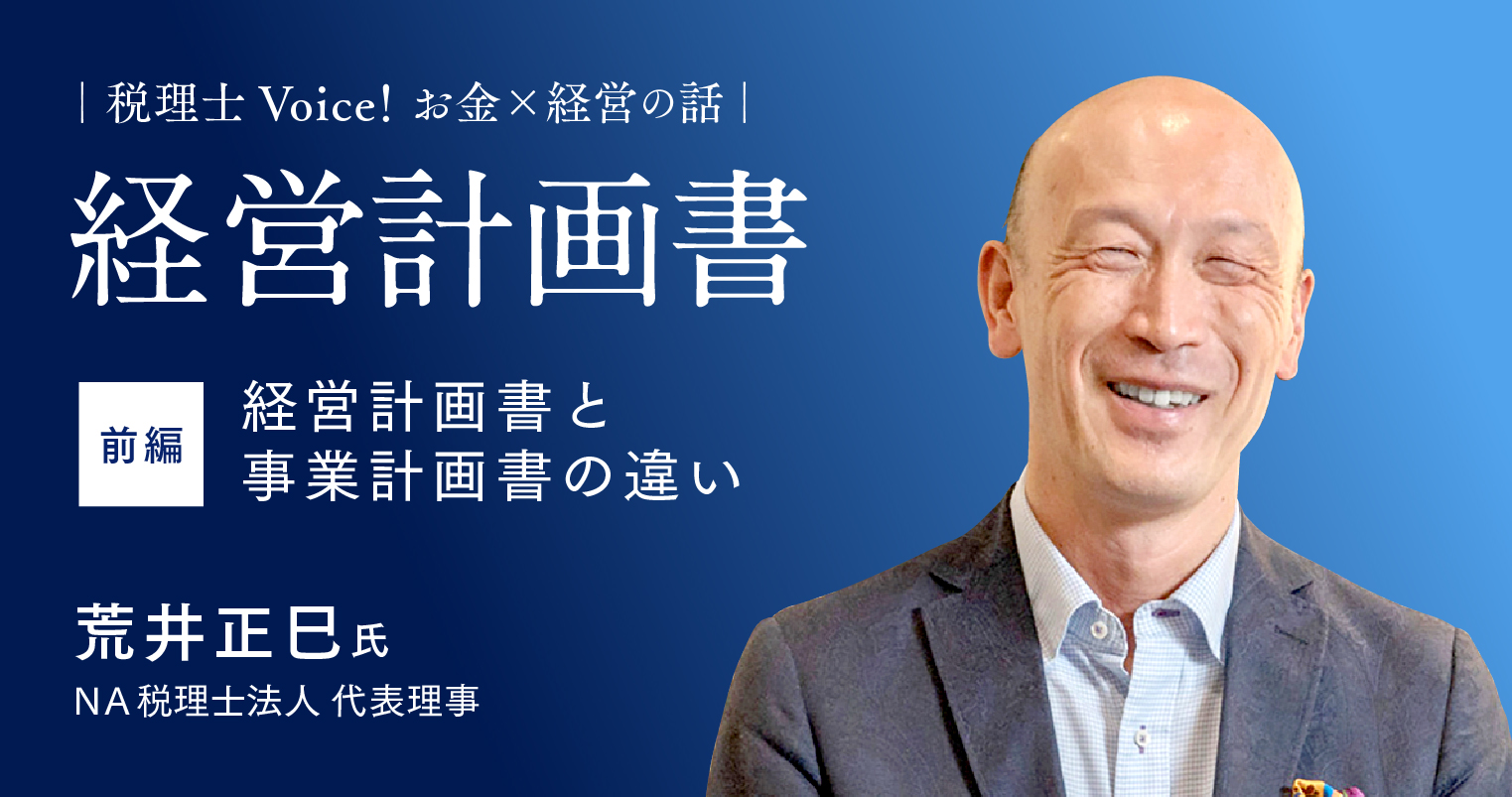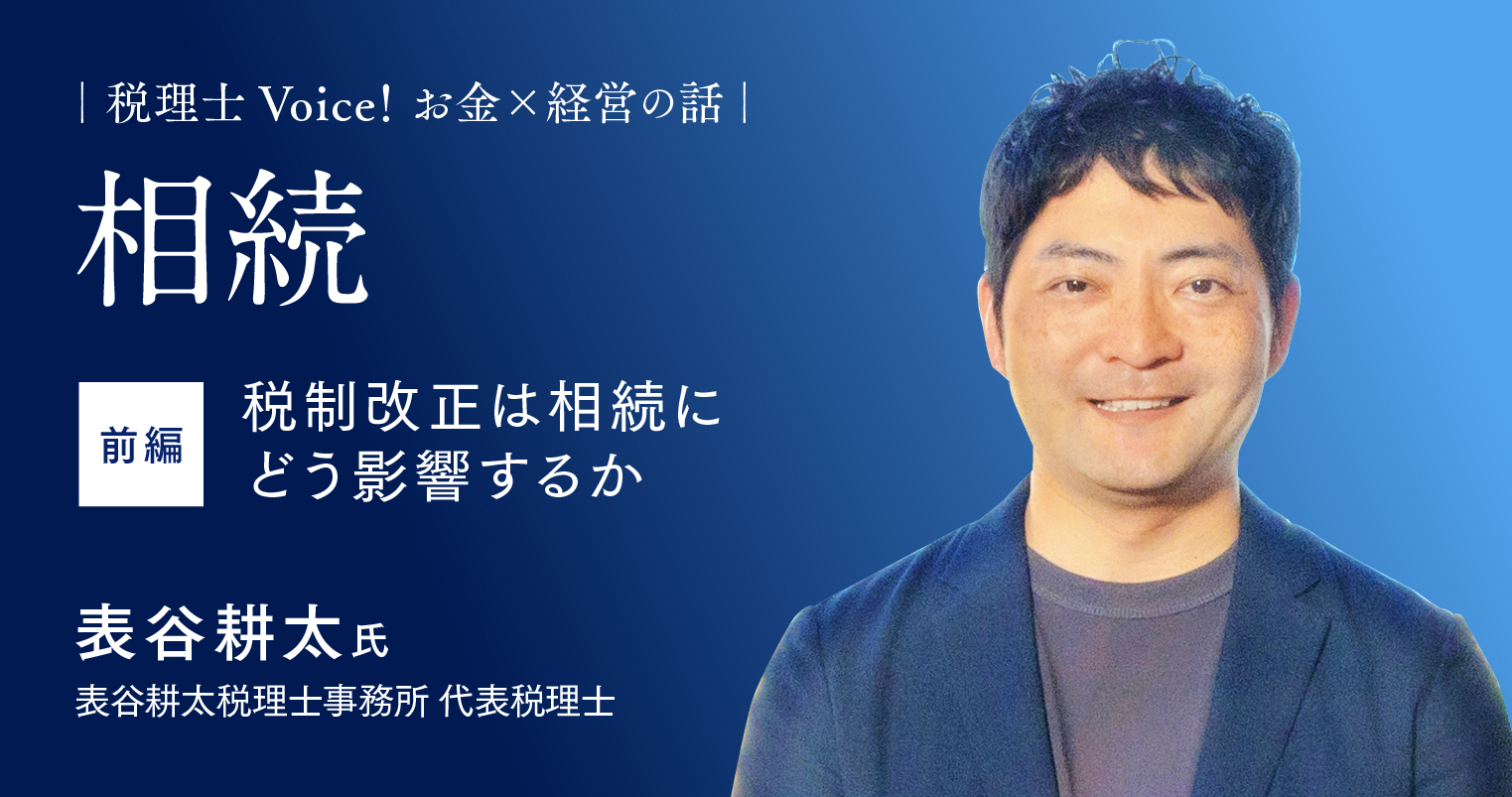【M&A 前編】M&Aは“人対人”のプロジェクト
単なる資本取引ではないことを心得るべき
大澤・山﨑公認会計士事務所 代表 大澤直也氏 事業規模の拡大を目的に会社を買収したり、あるいは後継者のいない自社の事業を承継してもらうために売却したりというかたちのM&Aが増えている。ただ、そこには当事者や利害関係者のさまざまな思惑も絡み、中にはトラブルに発展するようなケースもあるようだ。今回は、公認会計士としてM&Aのポイントでもあるデューデリジェンス業務などにも多数関わってきた大澤直也氏(大澤・山﨑公認会計士事務所代表 公認会計士/税理士)に、特に中小企業がM&Aを行う場合に、買い手・売り手双方が注意すべき点などをお話しいただいた。
記事では、「前編」でトラブルの事例などについて、「後編」でM&Aを成功させるための心構え、実行すべきことを中心にうかがった。
会計士の経験を生かして独立開業
――先生は、もともと会計士として監査業務に携わっていらっしゃいました。
大澤(敬称略) はい。大手監査法人で10年ほど上場企業の監査に加えて、財務デューデリジェンス(投資や買収の対象となる企業の価値、リスクなどを調査すること:以下DD)、公開(IPO)準備会社の監査・予備調査、民事再生の再生計画の策定支援などに従事しました。
その後、上場準備中のIT会社のCFOを2年ほど勤めて、2008年に独立して、財務DDなどのサービスを提供する事務所を設立し、翌年、税理士登録を行って税務業務を始めました。2013年に同じ公認会計士・税理士の肩書を持つ山﨑友揮をパートナーに迎えて今の形になった、というのが当事務所の略歴です。
体制としては、現在スタッフが8名いて、計10名の陣容となっています。お客さまは法人が150件ほど、個人は200件ほど。業種による特化はしていないのですが、私の家系に医師が多いということもあって、個人のお医者さんや医療法人、病院、クリニックといった医療関連のウエートが比較的高くなっているんですよ。あとは、上場会社の顧問先が結構あって、監査前の税金計算、税効果の計算、グループ通算制度や組織再編による節税もお手伝いしています。
従業員や取引先を守るためのM&A
――先生のキャリアだと、今回のテーマであるM&Aについての知見も多くお持ちだと思います。
大澤 そうですね。M&Aといってもいろんなパターンというか、買い手側と売り手側それぞれの目的があります。
例えば、当事務所のお客さまには上場企業もあるのですが、最近は本業の規模を拡大するために同業を買収するパターンに加えて、本業の成長性や収益性が落ちてきている中、新たな事業展開を模索するような買収も目立ちますね。単純にシナジーを追求するケースもあれば、企業価値のテコ入れのために成長企業を買うような場合もあります。彼らには、業績や株価を落とせないというプレッシャーもありますから。

――独立してから関わったM&A案件で、印象に残る事例を教えていただけますか。
大澤 今の目的という点では、従業員の雇用と取引先の経営を守ることを主眼に、「破産事業譲渡」というちょっと特殊な方法でM&Aに関与したことがありました。足元の業績はそこそこだけど、過剰債務の返済が難しく、このままだと資金ショートして倒産するしかない。そこで、破産申し立てを視野に、破産財団からの事業譲渡で、他社が事業と社員を引き継ぐかたちにしたのです。
買い手・売り手ともに売上数十億円程度の会社で、両社にはもともと取引関係がありました。実は私は買い手側の会社の税務顧問をしていて、買い手の社長の所に、売り手社長から資金スポンサーの依頼の話が来た流れで、買い手の社長から私に相談がありました。売り手側の情報を色々と精査した上で、このスキームを知り合いの大手弁護士法人の弁護士とともに提案したのですが、非常にうまくいった事例だと思っています。事業をほぼ従来通り継続させることが可能になりましたから。残念ながら、社長個人は破産したものの、事業も従業員の雇用もお客様にも迷惑にかける最悪の事態は避けられました。
――M&Aをしなければ、売り手側が経営破綻して、けっこう大変なことになっていた。
大澤 そう思います。ちなみにこのようなケースでは、民事再生(※)と事業譲渡と清算をプレパッケージにして検討されることが多いんですね。ただし、民事再生だと社会保険の滞納があったりした場合、その支払いを免れません。売り手企業には億に近い滞納があったので、それが破産事業譲渡を選択する決め手でした。
※民事再生:債務者が、破産を回避し、事業の継続、経営再建を目指すための法的手続き
――そのあたりは、ケースバイケースということですね。それにしても、その事例は、売り手側の社長に「自分は破産しても社員の雇用やお客様に迷惑をかけたくない」という気持ちがあったから成り立ったM&Aですよね。
大澤 通常のM&Aでは、売り手は利益を求めるわけですが、このケースでは、「それはいいから、とにかく従業員の雇用を守って、事業を存続させてもらいたい」というのが、社長の意思でした。そういう点では、しっかりした経営者だな、と感じましたね。
M&Aを急いだ結果、トラブル発生
――事業承継に絡むM&Aも増えています。子どもや幹部社員に継いでもらおうと思ったけれども、うまくいかずに売却を考える、というパターンです。
大澤 税務顧問先だった医療法人で、そういう事例がありました。医師であるお父さまは、経営する総合病院(医療法人)を継いでもらいたくて息子を医師にした。ところが、体調の衰えを感じるようになったし、そろそろバトンタッチしようかと話をしたら、意に反して「継ぎたくない」と言われてしまったわけです。

それで、売却を決心して、私に相談すると同時に、複数の大手M&A仲介業者にも依頼して、売り先を探し始めたんですね。これは経営者の方にはよくあるのですが、決断すると早い(笑)。ことM&Aなどに関しては、少なくとも3、4年はかけてじっくり準備したほうが絶対にいいのです。ところが、いったん「売る」というスイッチが入ると、止まらない。
医療法人自体は、とても優良な法人でしたので、仲介会社の紹介で買い手はすぐに見つかりました。でも、話を聞くと、売却の手順に重大な“穴”があることに気が付いたんですよ。それで、先生には「その方法で売るのは危険です」と申し上げたのです。
――忠告は聞いてもらえたのでしょうか?
大澤 いいえ。「そうはいっても、M&Aの専門家が紹介する相手だし、専門家のやり方だから大丈夫だろう」とおっしゃって、そのまま売却が実行されました。そして、案の定トラブルが発生。
――そうなんですか。指摘された“穴”とは、どのようなものだったのでしょう?
大澤 問題になったのは、先生の退職金でした。この医療法人は、「出資持分あり」の法人で、M&Aに伴う持分の譲渡対価に関しては、基本的に契約と同時に買い手から支払われます。同時に、社員権も社員総会で退任と選任で交代してしまいました。しかし、退職金については、いったん法人に入金された後に、そこから支払われるかたちになるわけですね。
私が申し上げたのは、契約前に買収側の法人にそのお金を入金させておく必要がある、同時に経営権を渡す前に法人の社員総会で退職金の金額などをしっかり決議して社員の退職(交代)と同時に退職金を受け取るべきだ、という2点でした。不動産の売買でも対価未払で登記変更するなんてことはあり得ないので、退職金の支給まで実行して着金まで完了と同時に社員を交代させるべきだと。
しかし、お話ししたような経緯で、その両方とも曖昧にしたまま持分譲渡契約を締結して、社員権も譲渡してしまったのです。
――それで、退職金は支払われなかった。
大澤 はい。それだけではなくて、譲った出資持分を別のところに再譲渡されてしまったんですよ。この状態で、間の法人が倒産したり、行方知れずになったりすれば、もうどうしようもなくなります。再譲渡先は、退職金の未払いなんて知らないわけですから。
これはもう詐欺に近いということで、裁判を起こして、最終的には多少金額は減ったものの、退職金についてはなんとか支払わせることができたのですが。
――M&Aでは、実際にそんなことが起こりうるということを、あらためて心にとどめるべきですね。
「仲介のプロ」に丸投げは、リスクもある
――今の事例では、高額の取引にもかかわらず、例えば社員総会での決議をスルーや退職金の受取前に社員交代してしまうというようなことがどうして起こるのか、不思議に思う人も多いのではないでしょうか。
大澤 依頼したM&A仲介会社が「問題ない、心配ない。」とアドバイスしたので、それに従ったのでしょう。私自身、M&Aの仲介をしたこともありますし、「すべての業者がいい加減だ」などというつもりは毛頭ありません。ただし、同時に「任せたからには全部お任せ」といった姿勢も問題だと思うのです。M&Aの相手がどんな会社なのか、仲介業者の言うことが本当に正しいのか、最低限の注意義務は払うべきでしょう。
特に売り手に関する情報がどうしても不足する買い手の側は、気をつけなくてはなりません。誤解してはならないのは、仲介業者は基本的に売り手企業の精緻なDDを行ったうえで買い手に紹介するわけではない、ということです。わかりやすく言えば、それをやって売り手の“粗”が露呈すれば、それだけ「商品価値」は下がってしまいますよね。
もちろん、問題だらけの会社を紹介するわけにはいきませんから、簡単なDDはやるでしょう。あとは、売り手からもらった決算や事業計画などを、きれいにまとめて提示する。でも、その内容に関しては、彼らは責任を負いません。
――なるほど。M&A仲介業者を活用する際には、そういうところまで理解しておく必要がありそうです。
「後編」では、M&Aを成功させるためのポイント、注意点について、引き続きお話をうかがいます。
大手監査法人・一般事業会社のCFOの経験を生かし、税務・会計・財務の専門家として幅広いサービスを提供。スタートアップから上場企業まで伴走できる幅広さ、税務調査対応、節税、医療関係に強い会計士事務所。
URL:https://www.ocpa.jp/