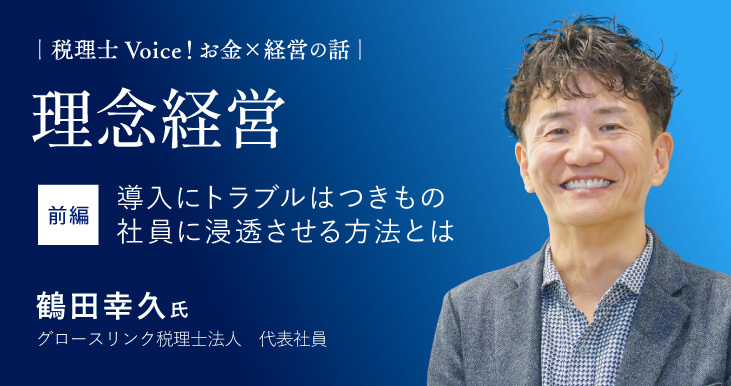【決算書 後編】決算書はなぜ大切か 自社の状況を知り経営判断に活かすには、「ここをこう読む」
田辺会計事務所 代表 田辺和史氏決算書を活用し、資金繰りを改善
――先生のお客さまには、実際にそうした決算書の読み方をアドバイスされていると思います。その結果、経営が改善された事例をご紹介いただけますか。
田辺 年商3億円程度の建設業のお客さまの事例をお話ししましょう。ヒアリングの際に聞かされたのが、やはり資金繰りの苦しさでした。利益は出て黒字なのに、月末になると預金がゼロに近い状態になっている、というよくあるパターンです。
そこで、あらためて決算書を見ながら、まず棚卸資産と売掛金の管理の改善を提案しました。
――そこに問題があったわけですね。
田辺 ひとことで言うと、資材などの仕入れが必要量を上回っていて、資金が滞留してしまう、という現状が見て取れたのです。
アドバイスしたのは、工事単位で、仕入・工期・入金のタイムラグを可視化して、「いつどれだけのキャッシュがどのように動くのか」を把握することでした。それに基づいて、仕入先には支払いサイトの延長を、一方、得意先には入金の前倒しの交渉を行って、資金がしっかり月末に残る形を整えたんですよ。
――なるほど。おっしゃるような可視化によって、そうした具体的な交渉も可能になった。
田辺 そういうことです。で、次にやったのが、「資金繰り表」の作成です。月次ベースでの支払と入金のタイミングを、キャッシュベースで把握する仕組みを構築しました。ただ表を作るだけではなく、月末には収支の計画と実績を検証し、差が出たらその要因を分析して、ギャップを埋めるための方策を検討するようにしました。
そして、最後に不要な支出の洗い出し。さきほど損益計算書のところで触れた販管費の精査を行ったところ、使用していないリース契約などが見つかりました。
――そういう「無駄遣い」もけっこうありますよね。
田辺 そうした契約は解除して、キャッシュを残す対応を取りました。
このように、資金繰りの可視化、そこに表れたアラートへの早期対応の体制を築いたことで、半年後には月末の預金が1,000万円を超えるまでに財務体質が改善されたんですよ。この点は金融機関も評価してくれて、追加融資を受けることもできました。
とはいえ、私自身一番大きな成果だと感じたのは、経営者が資金繰りの悩みから解放され、本業に集中できるようになったこと。いつまでもお金の問題に足を引っ張られているのか、そういう懸念を払拭して、事業の先行きを考えられるのかの差は、大きいと思うのです。
銀行は決算書のここに注目
――今も金融機関の話が出ましたが、必要なときに融資が受けられるかどうかは、経営にとって重要な意味を持ちます。彼らが決算書のどこに注目しているのか、経験を踏まえて解説いただけますか。
田辺 銀行は、「返済能力があるのか」という視点で会社を見ます。既存の融資先については、基本的に半年に1度、返済能力についての査定を行い、それを基に例えば貸倒引当金をどの程度積むのかを判断するんですね。決算書は隅々まで精査されると考えてください。
そのうえでポイントを挙げると、まず目を向けるのは利益です。さきほどの〈営業利益〉、〈経常利益〉が安定しているか。これらが赤字だったり、前年から大きなマイナスがあったりすると、「返済能力に問題あり」とみなされる可能性は高まるでしょう。

パターンとしては、一時期に多くの利益を計上しているよりも、コンスタントに稼いでいるほうが、高く評価される傾向にあります。
――安定的に利益が出ていれば、先行き返済が滞るリスクも小さいでしょう。
田辺 次に、〈自己資金〉の健全性ですね。これがプラスかどうかも決定的に重要です。負債が資産を上回る債務超過状態だと、金融機関の与信判断はかなり厳しいものになります。
さらに、借入を何年で返済できるかの目安である〈債務償還年数〉にも注目します。当然、短いほうが「貸し倒れリスク小」で、一般的には10年以内が望ましいとされます。業界によって差はありますが、これを大きく超えていると、やはり融資を受ける際に問題になるかもしれません。
これらが主なところですが、固定資産に関して、減価償却費(※)をちゃんと計上しているか、というところまで確認されることには、注意が必要です。なぜわざわざ費用を計上しないのか、と思われるかもしれませんが、いろんな事情で目先の決算を黒字にするために、そういう処理が行われることもあるわけです。
※減価償却 固定資産の購入費用を、耐用年数にわたって分割して費用計上する会計処理。
――ああ、なるほど。
田辺 費用計上しなくても、税務署的には「お咎めなし」。でも、会社の財務状況の正確な評価という点からは、大いに問題ありです。
このような場合、金融機関は、会社が保有している固定資産から概算の減価償却費を算出して、実態ベースに補正を行います。その結果、表向きは黒字だったはずが、実質的には赤字と判断されることも多々あるんですよ。
――そこまでやるのですね。銀行に嘘はつけない。
田辺 ええ、彼らはプロですから。あとは、役員報酬や経費が妥当な金額に収まっているのかどうかにも気をつけてください。金融機関が最も嫌がるのは、「不透明な支出」なのです。
決算書を活かす経営とは
――決算書を次年度以降の経営にどう活かしていくべきなのか、あらためてまとめていただけますか。
田辺 今までの話と重なる部分もありますが、次のようなことがポイントになると思います。わかりやすく箇条書きのメモにしてみました。
収益構造の見直し:売上高の推移や構成を分析し、どの商品、サービスが収益を支えているのかを把握します。販売戦略や商品開発の根拠とすることができるでしょう。
費用の適正化:各費目(人件費、材料費、外注費、家賃など)を前年と比較し、増減の理由とともに、無駄がないかをチェックし、改善すべき点があれば実行します。
利益とキャッシュの管理:税引後の最終利益だけでなく、さきほどの減価償却を含めたキャッシュフローを見ながら、内部留保や資金繰りの余裕を確認します。「黒字倒産」のリスクを回避する判断材料にもなります。
財務状態の改善:自己資本比率や借入金の比率をチェックすることで、財務の健全性を評価します。設備投資や借入返済計画を立てる根拠になるはずです。
目標設定の根拠:決算書の数字を基に、次年度以降の売上、利益、費用などの目標を設定します。例えば「前年度比売上5%アップ」「人件費比率を50%以内に抑える」といった具体的な経営目標に落とし込むことで、やるべきことはより明確になるでしょう。
.
金融機関など外部への説明資料:融資を受ける際や他社との事業提携などの局面で、自社についての信頼性のある数字として、決算書は説明資料の役割を果たします。決算書に基づいた合理的な経営計画は、資金調達の成功率も高めます。
――決算書を“武器”に、これだけのことができるということですね。何もしない場合との差は歴然だと感じます。
決算書を読むことは、経営者の「本業」

田辺 事業を安定的に成長させて、従業員の生活を守るのは、企業経営者の使命ですよね。そういう意味では、きちんと決算書を読むこと自体、社長の「本業」だと思うんですよ。繰り返しになりますが、決算書をただ税務署に提出するだけではなく、「読むもの」「活かすもの」にしてほしいですね。には多数派だと思います。
――そういう問題意識を持って、決算書の基本的なところを勉強したいと思ったら、どうすればいいでしょう?
田辺 まずは、会計、税務の専門家である顧問税理士に相談してみてはいかがでしょうか。決算書の見方をレクチャーするのも、税理士の仕事ですから。
決算書の読み方に関する入門書を読んだりセミナーに出かけたりするのもいいですが、活用すべきはインターネットです。今は、基礎的なことがらを説明するサイトがいくつもありますから、必要な知識を得ることができると思いますよ。
――本日は、決算書についてのためになるお話をありがとうございました。最後に、貴事務所の将来展望をお聞かせください。
田辺 当事務所は、「お客さまに喜ばれる事務所」をモットーにしています。税務にとどまらず、コンサルティング業務をはじめ、顧客のニーズに対応した付加価値の高いサービスを提供していきたいですね。
今後も業種などに関係なくサポートしていく考えですが、私自身が強みを持つ医療関係やスタートアップ企業の支援、相続・事業承継など資産税関連の業務も積極的に展開していきたいと思っています。
――事務所の今後のご発展を期待しています。
「お客様に寄り添うこと」をモットーに、中小企業や個人事業主のお客様を中心に、税務・会計・経営に関するアドバイスやサポートを行う。税務申告や節税対策だけでなく、事業計画の作成や資金繰りの支援、経理業務の改善提案など、経営に関するさまざまな相談にも対応する。
URL:https://tanabe-tax.com/