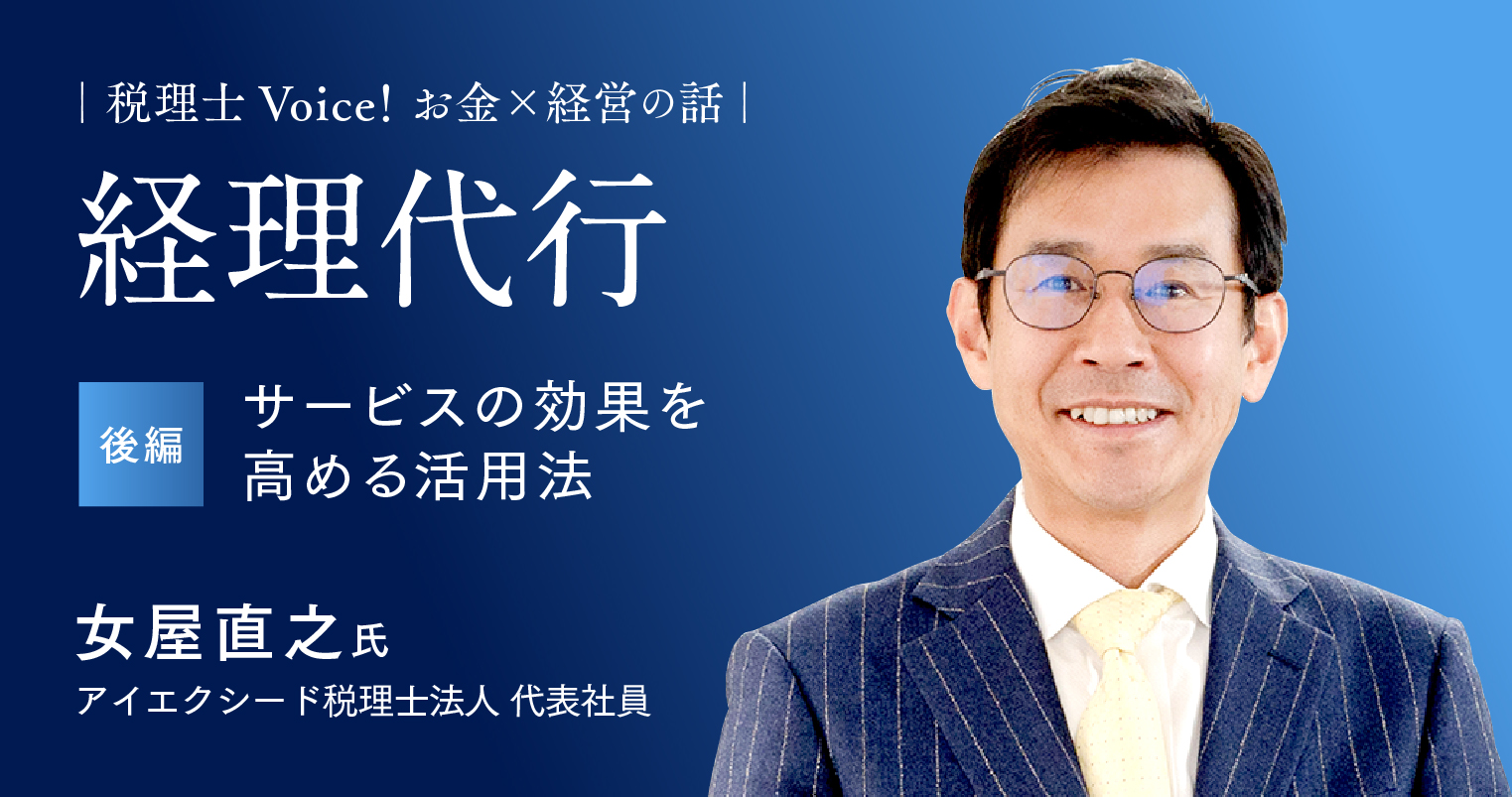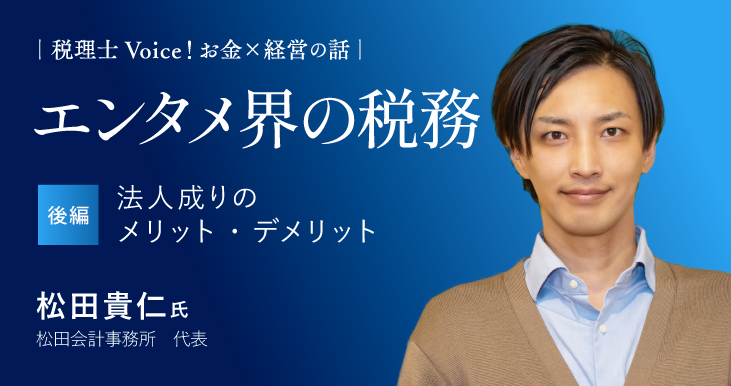【事業承継 前編】事業承継に必要なことはそれぞれ違う 後継者に「任せる覚悟」がカギに
名古屋総合税理士法人 代表税理士 細江貴之氏事業承継に悩む経営者、後継者は少なくない。業績が好調で株価の高い企業ほど、事業の承継に苦労する、という問題もある。加えて、親子のちょっとした気持ちの行き違いがスムーズな承継の妨げになることもあるから、注意が必要だ。今回は、相続、事業承継分野で多くの実績がある名古屋総合税理士法人の代表税理士 細江貴之氏に、中小・中堅企業の事業承継のポイントについて聞いた。
記事では、「前編」で事業承継において必要になる対策について、「後編」で承継を成功させるための心構え、実行すべきことを中心にうかがった。
高まる事業承継対策への関心
――貴社の概要からお聞かせください。
細江(敬称略) 当社は名古屋で創業して、54年になります。お客さまは、個人の方から上場企業までさまざまですが、比較的中堅といわれる企業が多いです。また、税務顧問のほか、相続や事業承継の分野も創業来の実績があって、売上の3割以上はその分野の案件が占めています。
社員は約50名で、11名の税理士がいます。グループに経営コンサルティングや不動産関連などの事業会社もあり、お客さまの幅広いニーズに的確にお応えする体制を築いているのも、当社の特徴です。
――本日は、事業承継をテーマにお話をうかがっていきたいと思います。事業承継では、親族に後継者が見つからず、苦労するケースも多いと聞きます。
細江 そうですね。親族後継者がいない場合、選択肢は親族外承継やM&Aということになります。近年、その比率が高まっているのは確かですが、当社の場合には、親族内承継に関する相談が依然として最も多く、件数自体も年々増えています。
――相談件数の増加は、事業承継自体が増えているからなのでしょうか?

細江 もちろんそれもあるのですが、「事業承継対策」に対する関心の高まりが背景にあるように、私は感じています。逆にいえば、かつてはとにかく毎年毎年、贈与税の非課税枠(基礎控除)を意識しながら株式を贈与していけばいいだろう、という程度のことしか行っていなかった会社が多かったと思います。
しかし、例えば同じ自社株の移動でも、できるだけ株価を下げたうえで渡したほうが有利ですし、それを実現できる方法があるという理解が、だんだん広まってきているんですね。それで、「うちもしっかり対策したい」というニーズが高まったように思います。
――なるほど。では、親族内の事業承継に有効な対策からお聞かせください。
細江 ポイントは大きく2つあって、1つは今も触れた株価対策です。どうやって後継者に課される税金を引き下げるのか、ということですね。もう1つは、有効というより必要な対策になるのですが、自社株・議決権を後継者にどう集約するか、という点です。
株価引き下げに有効な退職金と組織再編
細江 株価対策からみていきましょう。非上場会社の株価は、基本的に業績がいいほど、また、純資産額が大きいほど高くなります。先代経営者の持つ自社株も相続財産ですから、後継者である子どもなどがそうした高額の株式を相続や贈与で受け継げば、税負担が過大になり、納税資金の捻出に困難をきたしかねません。
――だから、渡す前にできるだけ株価を下げておくのが望ましい。
細江 そうです。最も一般的なのは、役員退職金の支給です。支給することにより、会社の利益及び純資産を圧縮し、株価を引き下げることができます。事業承継のタイミングで退職金を支給すれば、後継者の税負担を、減らすことができるでしょう。株式を渡す際は、2,500万円まで贈与税が非課税となり、相続時に相続税として支払う相続時精算課税を利用することもできます。
これは、比較的簡単に実行することができ、純資産がそれほど多くない会社であれば、有効な株価対策になります。ただし、それでもまだ株価が高い会社の場合には、当社ではさらに組織再編の提案を行います。
――具体的には、どのような対策になるのでしょう?
細江 会社の業種業態や規模、資産の内容などによって、“オーダーメード”に近いことになるのですが、例えば会社をホールディングス(持株会社)化することで、株価は半分近くに下げられることが多いです。また、例えば高収益部門を切り離すことができる場合には、それを子会社として親会社の評価から切り離すことで、さらに株価の引き下げが可能になるなど、様々なケースがあります。
このような組織再編節税スキームと、さきほどの退職金支給の「合わせ技」によって、株価は何もしない場合と比べて1/5~1/10くらいにできるケースが、多数あります。
――それは大きな違いになりますね。
細江 そうですね。また、組織再編により、株価を引き下げられるだけではなく、株価が上がりにくい会社にすることもできます。
安定経営に必要な株式の集約
――事業承継対策のもう1つのポイントとして、後継者への自社株・議決権の集約を挙げられました。
細江 株式を保有している割合は、会社の支配権である株主総会での議決権に直結します。最低でも議決権の過半数を持たないと、支配権を発揮できない「雇われ社長」になってしまいます。できる限り特別決議に必要な2/3以上を確保し、さらにはスクイーズアウト(※)が可能な90%以上を持つのが理想です。もちろん、100%持っているに越したことはありません。
※スクイーズアウト 株式を強制的に買い取るなどの方法により、少数株主を会社から追い出すこと。株主総会の開催を省略できる、経営の自由度が高まる、などのメリットがある。
先ほどの株価対策には、できるだけ株価を引き下げることにより後継者に株式(議決権)を集約しやすくすることで、株式の分散を防ぐという意味合いもあります。
一方、後継者が自社株の多くを取得する場合には、相続時にトラブルが生じやすいため、しっかりした準備が必要になります。自社株を相続すると、他の相続人との間に相続や贈与により取得する財産に大きな差が生じ、遺留分(一部の法定相続人に保障された遺産の最低取得割合)を侵害することもあります。特にその可能性があるときには、相続の生前対策が欠かせません。
――どのような対策を講じるのですか?
細江 相続の方法にはいくつかの種類があり、その一つに、ある相続人が特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に代償金を渡す「代償分割」という方法があります。代償金の支払いにより、遺留分を侵害しないように、その手当の仕方を検討したりすることもあります。また、ケースによっては、除外合意(※)や生前の遺留分放棄などの対策を提案し、生前対策を進めることもあります。
※除外合意 「遺留分に関する民法の特例」に基づき、後継者と推定相続人(先代経営者の死亡時に法定相続人になる人)の全員が、自社株を遺留分の対象となる財産から除外する、と合意する手続きのこと。
――後継者以外の相続人に「家業を継ぐ意味」に対する理解があれば、そういう合意も可能になりそうです。
ハードルの上がる「自社株の買戻し」

細江 ただ、当社が拠点を置く名古屋でも、すでに株式が分散してしまっているケースが、結構あります。社歴の浅い会社はそれほどでもないのですが、経営者が代を重ねている老舗と呼ばれる会社に、例えば創業者の長男家、二男家、三男家が1/3ずつ持っているなど、株式が分散している例は珍しくありません。
また、遠い親族や元役員、取引先などの少数株主がたくさんいる会社も案外多いものです。少数株主とはいえ軽視は禁物で、会社は株主代表訴訟や自社株の高額買取請求のリスクなどを抱えることになります。
――自社株を分散させてしまったのは、相続の際にそういうリスクをあまり認識していなかったからなのでしょうか?
細江 ひとことで言えば、そういうことだと思います。以前は、自社株の分け方をアドバイスできる専門家も少なかったですから。「どうしたらいいんでしょう?」と聞かれて、「子どもが3人いるなら、3等分しましょう」という感じの相続対策が珍しくなかったと思います。
ちなみに、相続対策として生前贈与を行う人は多いと思いますが、税金のことだけを考えるのならば、できるだけ贈与先を分散させたほうが有利なんですね。受贈者(贈与財産をもらう人)1人当たり年110万円まで非課税で贈与できるのだから、その人数が多いほど、たくさんの財産を税負担なしに移動させることができるということになります。
――なるほど。節税ばかりに目が行った結果、自社株の分散を招いたケースも少なくなさそうですね。
細江 いったん分散してしまった株式を集めようとしても、相手が贈与してくれる保障はなく、基本的には買い戻すことを考えなくてはなりません。その際のキャッシュアウトが馬鹿にならないのです。
ごく簡略化して、説明してみましょう。先代が220万円分の自社株を、110万円ずつ後継者である長男と経営には関わらない二男に贈与したとします。その際、長男にも二男にも税金(贈与税)はかかりません。仮に長男が二男に渡った110万円分を普通に相続していたら、相続税率(限界税率)が50%と仮定すると55万円の税負担が発生するので、一見節税になるように思えます。
さて、後日、長男が自社株の集約の必要性を感じて、二男から買い戻そうと考えたとします。その際、企業価値が変わっておらず、株価が上昇していなければ、110万円が買取交渉における1つの目安になります。ただし、業績が良く例えば株価が3倍になっていたら、330万円です。株価対策や自社株の集約が問題になるのは、多くの場合業績のいい会社ですから、よくある話です。長男からすると55万円の節税をしたことで、後日、330万円のキャッシュを失う結果になってしまいます。
――税負担と買い戻し価格とでは、金額の桁が違ってしまう、というイメージですね。
細江 実際、そういう理由により株式の集約に行き詰まってしまう会社は、たくさんあります。
地道な交渉で集約を目指す
――そうした状況の経営者から相談を受けた場合、先生はどう対処なさるのですか?
細江 その会社の置かれた実情に合わせて、個別の対策を講じるわけですが、基本的には株式の所有者と丁寧にお話しをして、納得していただいたうえで買い集めることが多いです。そういうお話しをしてもまったく気聞き耳を持たないという人も、中にはいらっしゃいますが…。
非上場株の相続税評価額はあくまで税務上の評価等に基づく「理論値」で、実際に市場で売れる金額ではありません。実際には、特に、配当を出していない会社の株式を持っていても、何も身入はなく、相続税だけがかかってしまう可能性があるので、所有者にとってはいいことはないのです。
――確かにそうです。
細江 そうした話をしつつ、お互いに納得できる金額を提案していきます。その際、その方がどういう経緯で株式を取得したのか、どんな経済状況にあるのか、といった情報も重要になります。
――そこまできめ細かく対応するのですね。
細江 1人1人、生活の状況も、考えていることも違いますから。現実的には、株式を集めたい経営者との仲がいいのかどうかでも、対応の仕方が変わってきたりするものです。
相続全般にいえることですが、単に税金やお金だけでは解決しない課題がたくさんあります。そうした部分にも目を配って対策を講じるのが、専門家としての私たちの仕事だと思っています。
「後編」では、スムーズな事業承継のために必要なことなどについて、引き続きお話しいただきます。
徹底した税務アドバイス・提案・スキームの構築を行う、会計・税のプロフェッショナル。50年以上にわたり、上場企業から中堅企業まで、様々な規模・形態の税務顧問実績を持つ。相続・事業承継の専門部門があり、円滑な事業承継をサポートする。
URL:https://hosoe-tax.com/