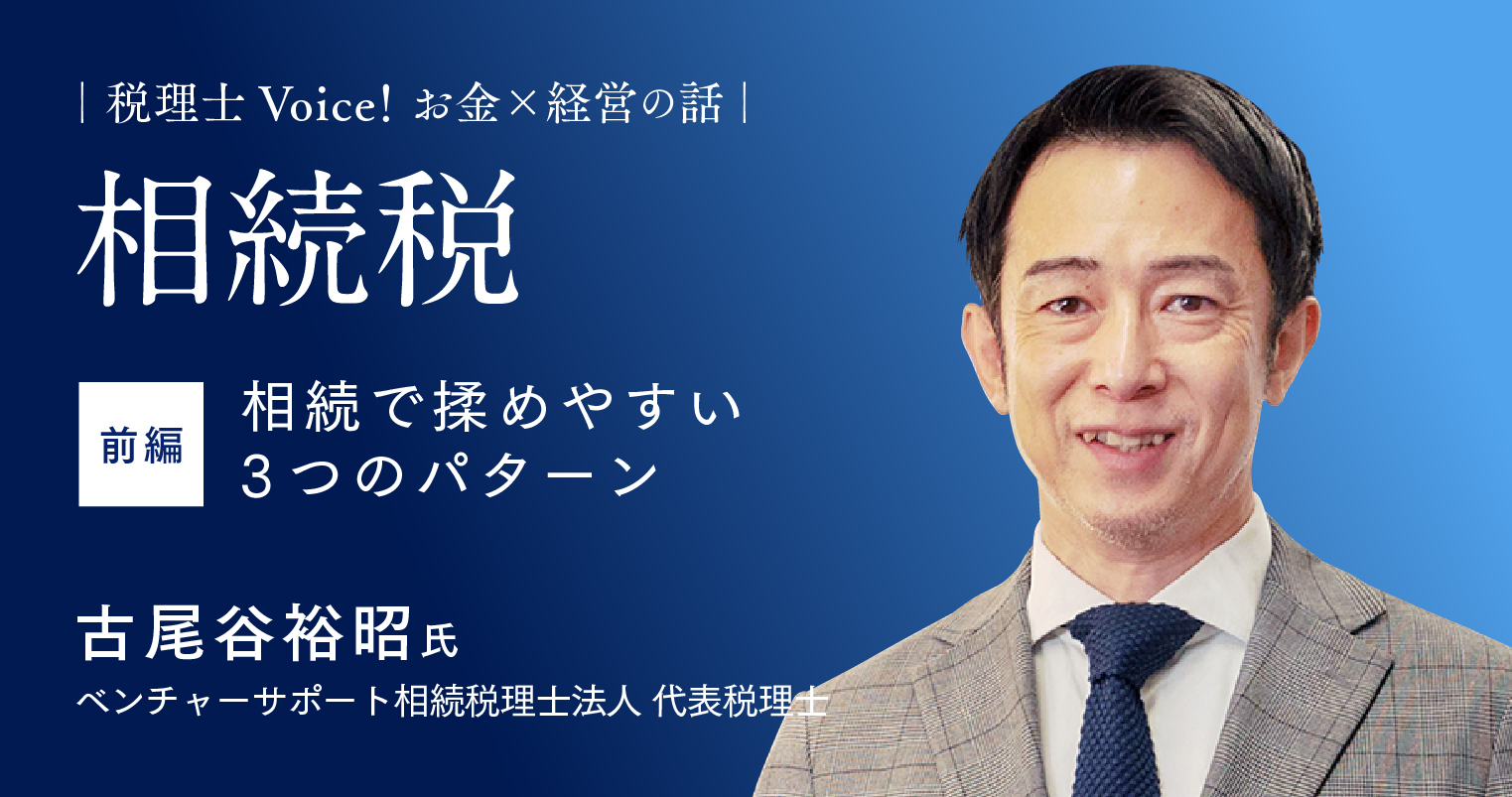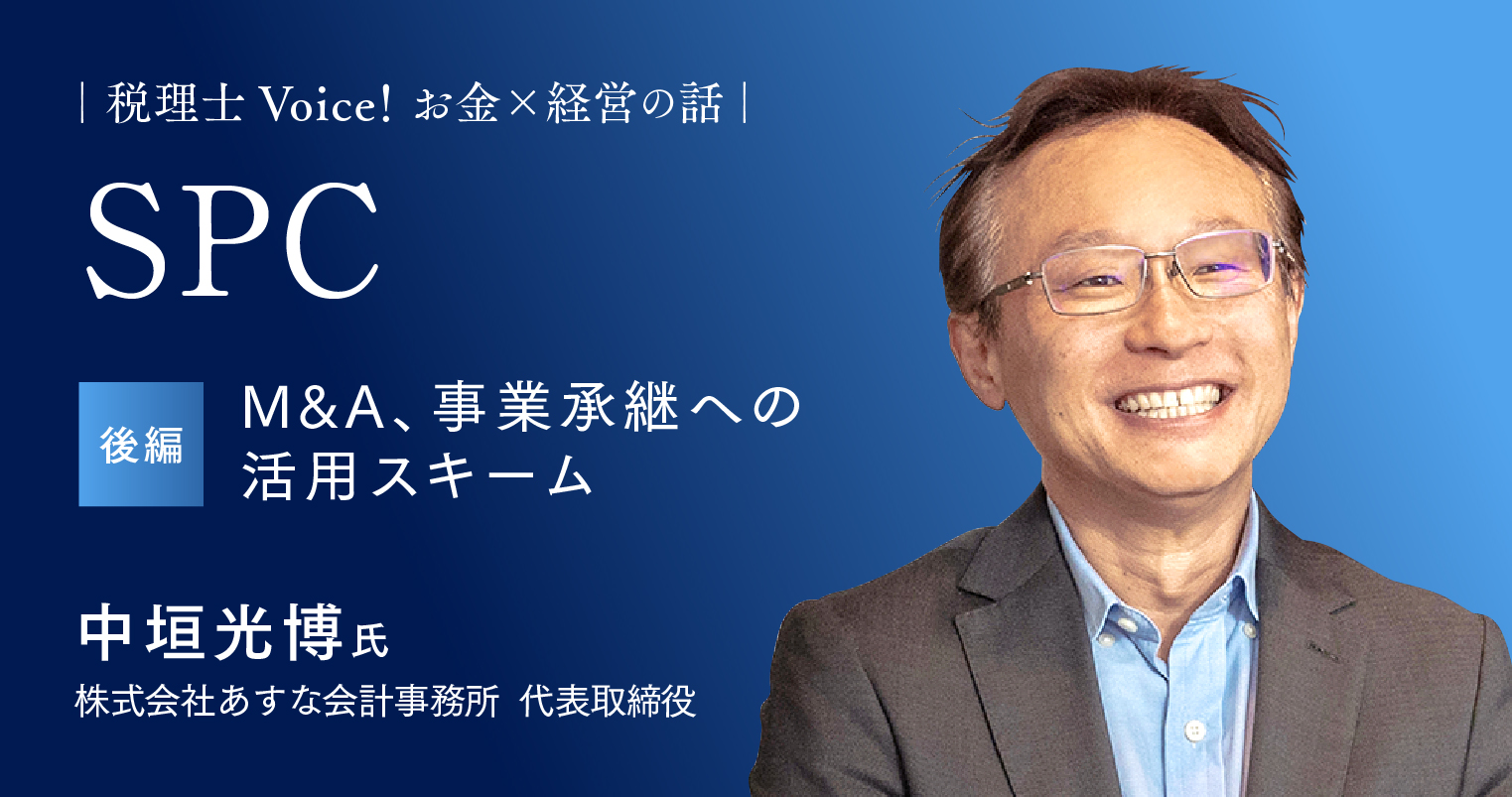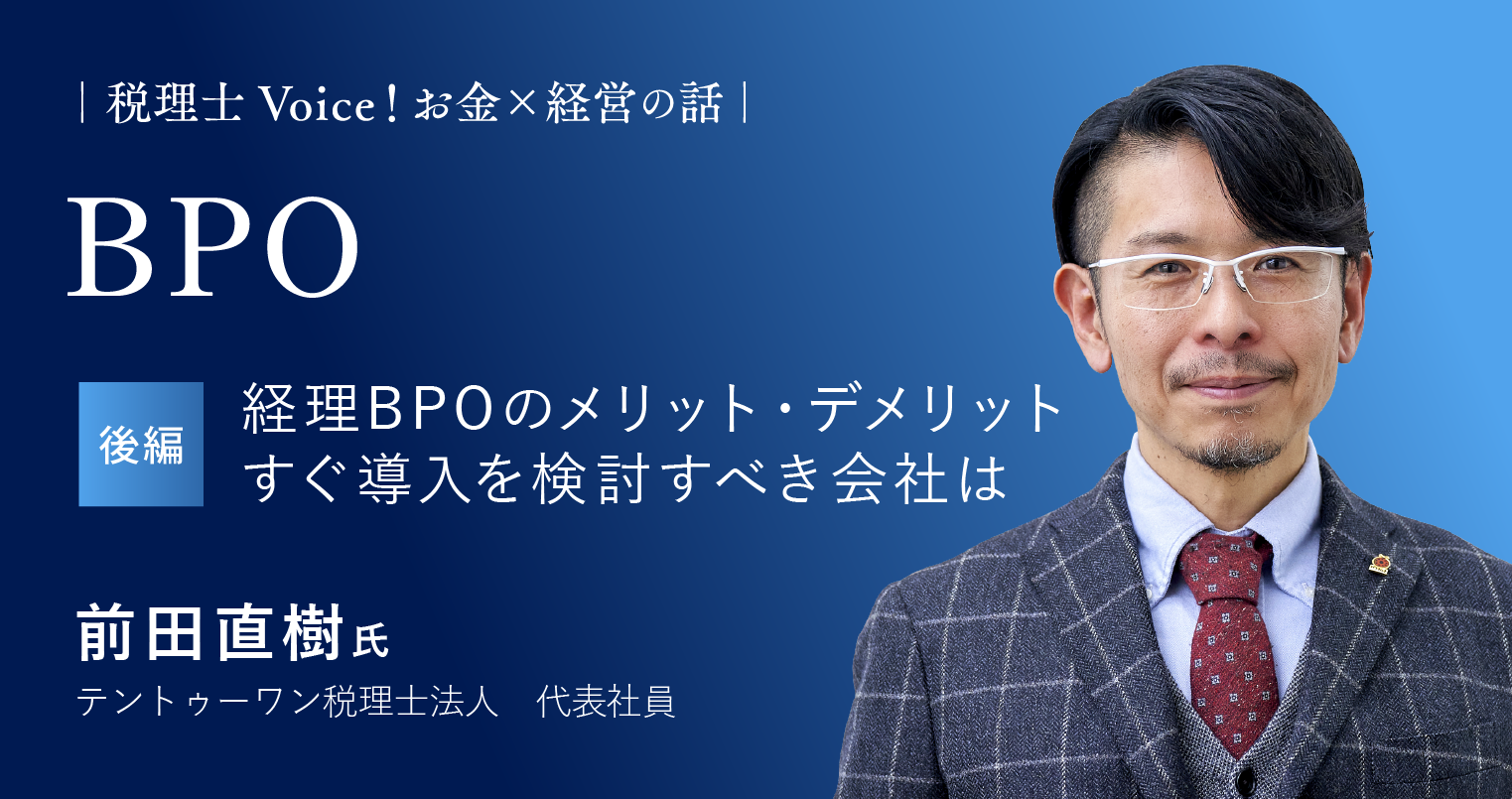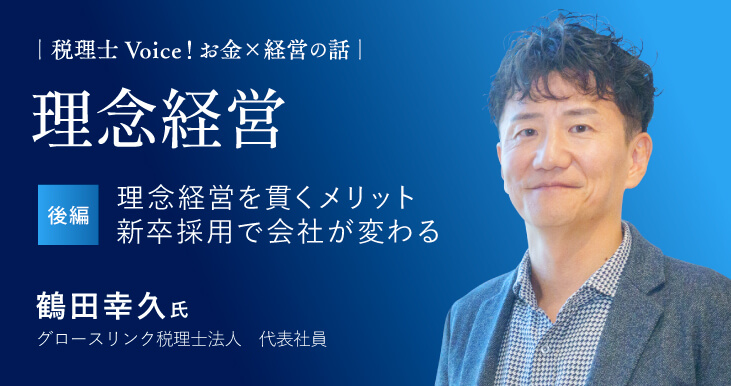【税務調査 前編】税務調査では「主張すべきことはする」 それをサポートするのが税理士の役目
菊地大輔税理士事務所 所長 菊地大輔氏法人でも個人でも、気になるのが税務調査だ。対象になった場合、税務署とどう向き合うべきか、税理士に頼めることとは? 今回は、「税務署に指摘を受けても、十分交渉の余地はある」「納税者が納得できる対応を行うのが我々の使命」と語る菊地大輔氏(菊地大輔税理士事務所、税理士)に、リアルな事例も含めて話をうかがった。
記事では、「前編」で最近の税務調査の動向や調査当日の注意点など、「後編」では個人を中心とした調査対策のポイント、税理士の活用法などについてまとめた。
インボイスで個人への調査が増加傾向
――貴事務所の概要をお聞かせください。
菊地(敬称略) 当事務所は、40年ほど前に元マルサ(国税局査察部)の肩書を持つ父親が開設しました。現在は、20年くらい前に加わった私と税理士2人、スタッフ4名の体制で運営しています。もともと東京・港区に拠点を置いていて、今の足立区北千住に移って2、3年になります。
お客さまは、法人が40件、個人が70件ほどでしょうか。以前は法人メインだったのですが、インボイスが始まってから、個人の方が急に増えたんですよ。
――そうなんですか。
菊地 インボイスを機に、個人事業の開業届を出す人が増えました。それに合わせて、税理士を頼もうという人が、けっこういます。それまで申告がおざなりだったり、無申告だったりするケースも少なくありません。
今日のテーマである税務調査に関して言うと、税務署がそのタイミングで調査に入ることも多くなっています。当事務所では、以前は法人の調査が年に1回あるかどうかという感じだったのが、昨年は個人の方の調査を4回ほど経験しました。

――インボイスをきっかけに、個人に対する税務調査も増えている、というわけですね。
菊地 その傾向はあると感じます。ただし、調査の中身は、今のところインボイスの運用そのものではないようです。ターゲットは、無申告などでそれまで曖昧になっていた所得ということになります。
調査の現場では、聞かれたことだけしゃべる
――対面の調査ができなかったコロナ禍が明けて以降、やはり税務調査の件数自体は増えていますよね。もし、経営する会社に調査が入った場合、当日はどのようなことに気をつけたらいいのでしょうか?
菊地 まず申し上げておけば、よほど悪質な脱税を当局に見抜かれていて、マルサが令状を持ってやってくるようなケースを除き、税務署が調査に入る場合には、まず顧問税理士のところに連絡が来ます。当日も税理士が同席し、受け応えすることも認められています。
もし、突然税務署の調査官がやってきたとしても、即日応じる義務はありません。彼らが無理やり立ち入ることもできないのです。「税理士と連絡を取るまで待ってほしい」と対応すればいいでしょう。
――基本的には、税理士を介して事前に日程調整したうえで、調査が行われる。
菊地 そうです。中小企業の調査は、だいたい2日間行われます。1日目の午前中に社長のヒアリングが行われ、その後、帳簿などについて個々の調査が行われる、というのが通常の流れになります。
ところで、私は社長に対して、「最初のヒアリングだけ同席してもらえればOKで、あとは普通に仕事をしていてもらって大丈夫です」という話をするんですよ。「必要に応じて顔を出してもらえればOKです」と。税理士には代理権限がありますから。
――調査になったら、期間中はずっと調査官の質問に答える必要があると思っている人も、多いのではないでしょうか。
菊地 個別のことがらについては私が対応しますから任せてください、というスタンスで調査に臨みます。それで、調査官から文句を言われることはありません。
そのように言うのは、調査にいたずらに振り回される必要はないというのもあるのですけど、税務署の調査官に対して「話しすぎる」リスクを減らすためでもあるのです。税務署は、調査に入った以上は、少しでも多くの税金を取って帰ろうと考えます。社長がふと漏らした一言が、その材料になることは、珍しくないんですよ。
――それは、気をつけなくてはいけませんね。
菊地 ですから、最初のヒアリングのときにも、率先してしゃべるのはやめて、聞かれたことだけに答えるようにするのが鉄則です。私の場合は、「直接受け答えするのではなく、一度私を介して話すくらいでいいです」と言います。
社長の性格にもよるのですが、緊張が解けると、つい「余計なこと」を語ってしまう方もいます。前にこんなことがありました。事務所のドアが壊れたので修理して、その費用を経費に計上していたんですね。ところが、調査官に「いいビルですね」と言われた社長が、「そのドアも修理のついでに金細工を施して……」と自慢を始めたわけです(笑)。この場合、単純な修理ではなく、前よりグレードアップしたと判断されると、資産とみなされて、その年に経費で落とすのはNGということになります。
――それは、調査官の誘導尋問だったかもしれません(笑)。
菊地 彼らもプロですから。いずれにしても、社長自身の口からそういう話をされてしまうと、我々も反論の余地はなくなってしまいます。もちろん、聞かれたことに答えなかったりするのは問題ですが、それ以外はしゃべらない、という姿勢でいるのがベストです。
税務調査は交渉でもある

――余計なことをしゃべらなくても、帳簿などを調べた結果、いろいろな指摘を受けることがあると思います。税務署の言うことには、そのまま従う必要があるのでしょうか?
菊地 いいえ、そんなことはありません。税務調査で指摘されたことについても、ケースバイケースで交渉の余地がある、というのが私の考えです。
これも過去に経験した事例をお話ししてみましょう。開業医のクライアントで、交際費がけっこう膨らんでいる方がいました。税務調査になって、調査官が飲食店関連の領収書を全部チェックして、カレンダーのようなものを作ってきたんですね。それを私に見せながら、「見てください。この方は、ほとんど毎日飲みに行ってますよ」「お医者さんは、患者を接待したりしないでしょう」と言うわけです。だから、「これらの領収書の経費計上は、一切認められない」というのが税務署の見解でした。
――一理ありますね。言い訳は厳しいかもしれません。
菊地 確かに職業柄、連日他人を接待しているというのは、不自然に思えます。しかし、逆にそういうことがまったくないのかといえば、そうとも言えないのです。お客さまに話を聞くと、「地域の有力者だとかの横の繋がりを大事にしないと、長くやっていくのは難しい」と言うんですね。
――中には、交際費として認められる接待もけっこうあった。
菊地 そうです。そこで私は、「交際費については、納税者が粗く計上していたものの、ゼロではないので、一定部分を認めてもらいたい」と主張しました。そうなると、税務署側も、納税者が申告したものを全否定するのは難しいわけですよ。そうした交渉を行って、最終的に計上しているものの割合で交際費として認めさせました。
こうしたケースで、具体的にどう判断するのかは、担当の税務署や税務官によって、違いもあります。ただ、大事なのは、見解の違いがあったら一度交渉の場に乗せる、主張すべきことは主張する、ということです。
――そのあたりは、税務署もまったく聞く耳を持たない、というわけではないのですね。
菊地 税務署を怖がる人もいるのですが、彼らの言うことをそのまま受け入れれば、納めなくてもいい税金を支払うことになるかもしれません。脱税しようというのではないのですから、堂々と意見を述べるべきです。
とはいえ、納税者自身が税務署と対峙するのは、現実には難しい面もあります。そこは、専門家である税理士の出番。私は、お客さまには、「代わって主張しますから、事実を正確にお話しいただいて、安心して任せてください」と話すようにしています。
「後編」では、税務調査に臨む心構え、税理士の活用法などについて、さらにお話をうかがいます。
北千住・東京エリアを中心に、法人・個人事業主・業種問わず、経営者を支える税理士事務所。特に税務調査立ち合いを得意とし、会社設立、相続まで幅広く対応する。「納税者ファースト」を掲げ、お客様の多様なニースに寄り添い、最適な解決策を提案する。