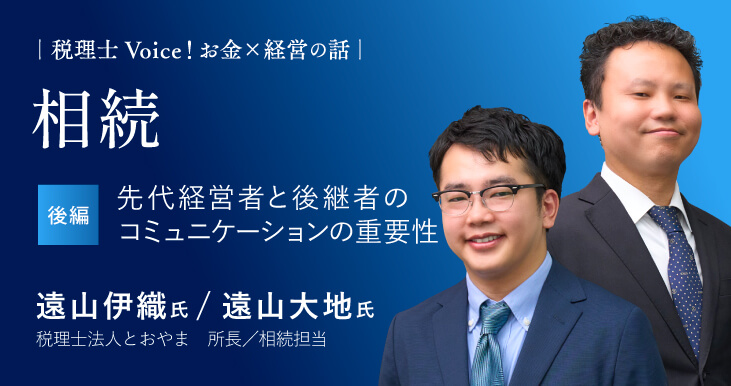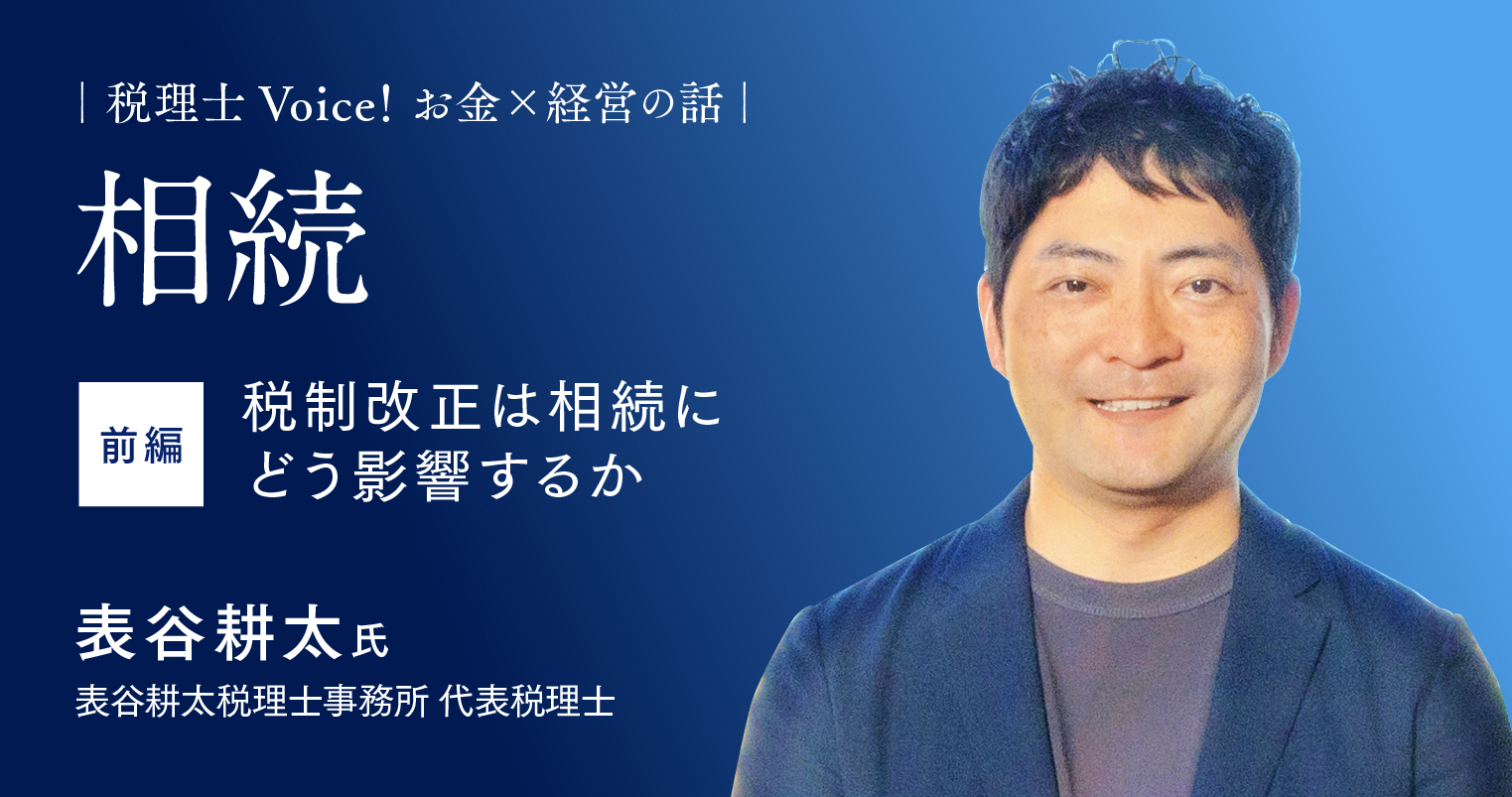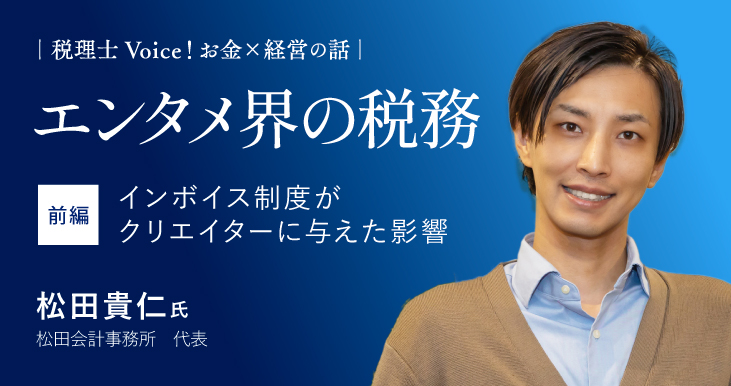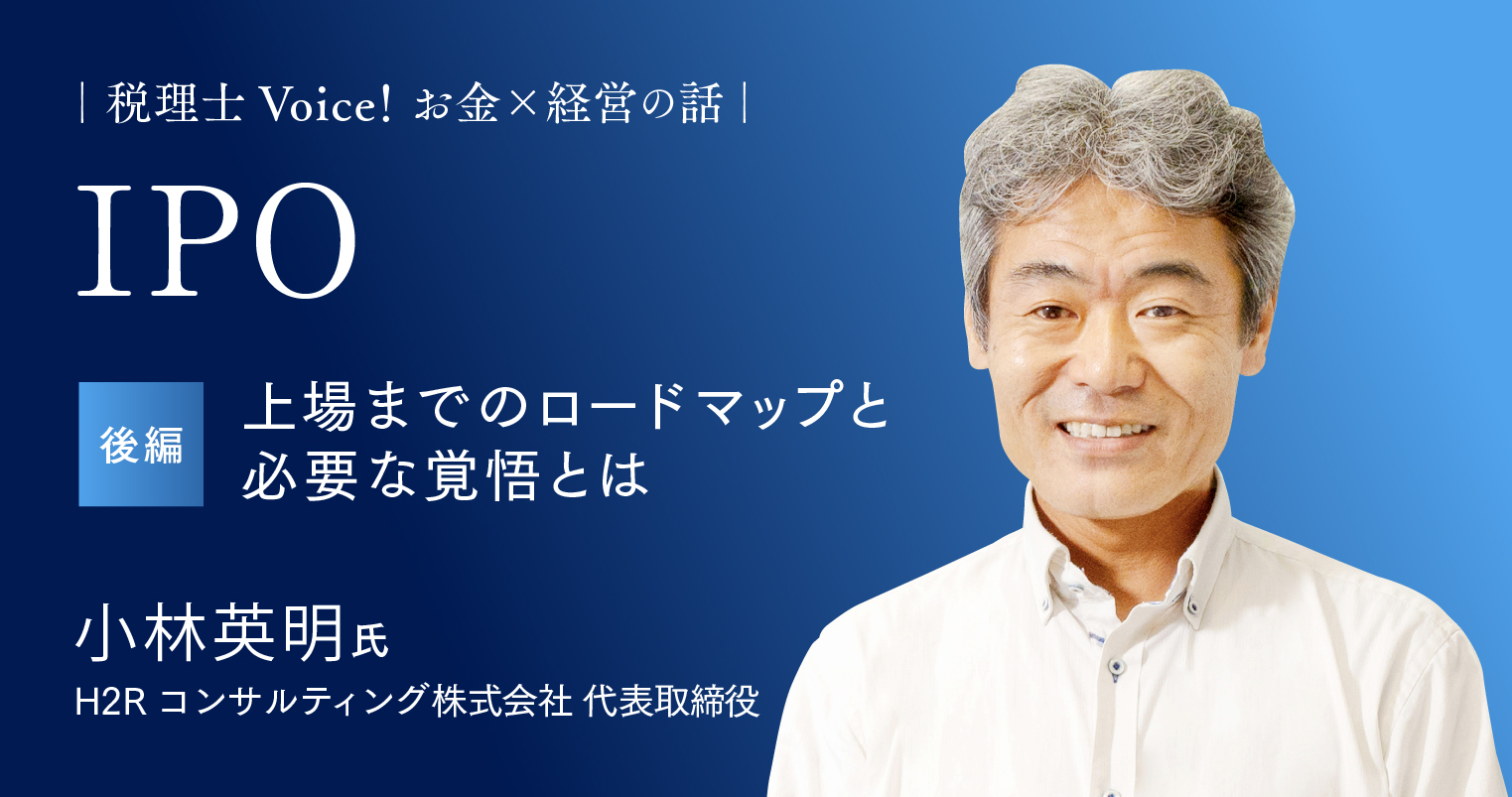【税務調査 後編】税務調査では「主張すべきことはする」 それをサポートするのが税理士の役目
菊地大輔税理士事務所 所長 菊地大輔氏個人は「所得と生活水準の落差」が問題になる
――税務調査といえば法人というイメージもあるのですが、前編では「個人に対する調査が増えている」というお話がありました。先生の目から見て、調査に入られやすいパターンには、どのようなものがありますか?
菊地 言わずもがなですが、まず収入があるのに確定申告していない「無申告」のケース。申告していても、所得(利益)が極端に少ない場合には、調査の対象にされやすいですね。個人は法人よりも、所得の「不自然さ」がわかりやすいのです。
法人の場合、儲けは法人に入り、社長はそこから決められた報酬をもらいます。一方、個人事業では、所得は直接事業主が受け取るかたちになりますよね。所得と個人の生活がストレートにつながっている。そうすると、その人の生活の状況から、実際の事業所得がある程度「逆算」できます。
例えば、月に20万円の生活をしていたら年240万円、30万円なら360万円のお金が必要です。貯金を切り崩しているとか、誰かの援助を受けているとかいうことがなければ、最低それだけの所得がないと、辻褄が合いません。
――確かにそうですね。
菊地 ところが、家賃15万円のアパートに住んでいるのに、申告所得が100万円、というような方が時々いらっしゃるのです。税務署ならずとも「どうやって生活費を捻出しているのですか?」ということになるでしょう。「とにかく税金を払いたくない」「他の人もやっているから」というような気持ちでそういう申告をするのだと思うのですが、外から見ると矛盾は明らかです。
――さきほどのような「交渉の余地がある」というのとは、状況が違いますね。税務調査でそうした問題が見つかると、大きな代償を払うことになるかもしれません。
菊地 調査に入られて痛い目に遭ったことが、実際にありました。何年か無申告のケースだったのですが、調べたら、合わせて1,000万円ほどの売上が見つかったんですね。
ちなみに、税務署は必要に応じて預貯金口座を調査する権限を持っています。相続税申告などでも問題になることがあるのですが、たとえ通帳を隠しても、預金の中身は筒抜けなのです。今は家族や関係する会社などの「名寄せ」も容易ですから、当局に嘘はつけません。
加えて、無申告を続けていたような人の場合、そうやって収入は明らかにされるのに、そこから差し引ける経費は、わからなくなっているケースが多いんですよ。経費については、現金を下ろして使っていることも多いですから。
――領収書を取っていなかったりすると、支出の証明は難しいですね。
菊地 経費が計上できないと、課税対象の所得が膨らみます。今の事例でも、可能な限りそれを認めてもらえるよう手を尽くしましたが、やれることには限界がありました。もう少し早く相談してもらえれば、というのが率直な気持ちでしたね。
付け加えれば、今のように無申告の場合は「無申告加算税」、申告所得が少なかったら「過少申告加算税」、さらに悪質な所得隠しが発覚すれば、「重加算税」といった加算税や延滞税というペナルティも避けられません。
――「税務調査は個人には来ない」という「通説」に惑わされず、後で困らないような申告を心掛けるべきですね。
「主張できる申告」を目指す
――当社(ビスカス)にも、「今までちゃんとした申告をしてこなかったので、これからはしっかり取り組みたいのですが」というかたちでの、個人の方からの税理士紹介の依頼が増えています。そうした顧客に対して、先生はどのように対処なさっていますか?

菊地 できるだけ節税したい気持ちはわかりますし、当然そのためのお手伝いをするわけですが、税の仕組みから言って、利益が出たらそのぶん課税されるのは仕方のないことなんですね。そうしたことを理解していただいたうえで、私は、まず「ここを『元年』と思って、税務申告に関しては、税務署に主張できるものを作っていきましょう」と話します。
今まで申告を曖昧にしてきたということは、修正申告の必要があるだけではなくて、さきほど説明したような税務署に対する主張をしてこなかったという点でも、納税者のデメリットなんですね。
――ああ、なるほど。
菊地 主張できるものにするためには、例えば「この経費は、こういう理由で事業に欠かせないのだ」といった“ストーリー”を、自分の中でしっかり持つ必要があります。もちろん自分勝手なものではなく、税務署を納得させることができる客観性を持った「理由付け」ですね。
そういう意識を持つことは、税務調査対策にとどまらず、事業そのものにもプラスの影響を与えるはずです。きちんと申告していれば、そこから事業の実態を把握できますし、損益分岐点のようなものも把握することが可能になるでしょう。個人の所得と生活の話をしましたが、それがバラバラになっていることで、知らずしらず無駄遣いが増えているかもしれません。正しい申告を出発点に、そういった問題点を洗い出し、改善を図ることもできると思いますよ。
税務調査を税理士に頼むべき理由
――実際には、顧問税理士がいないケースもあるでしょう。そういう人が税務調査になった場合、どうすればいいのでしょうか?
菊地 そうした場合でも、税理士に立ち合いを頼むことはできますし、ぜひそうすべきです。税務署は、納税者の側がしっかり主張すれば、それに耳は傾けます。ただし、相手が“素人”の場合、一方的に彼らの理屈を押し付けてくるようなことも、珍しくないのです。
――税の知識がなければ、言いなりになるしかありません。結果的に、高額の税金を支払う羽目になる危険性がありますね。
菊地 これも過去に経験した事例を紹介しましょう。宝石商を営んでいた方の顧問税理士をしていたのですが、業績が思わしくなく顧問料が負担だからという理由で、契約を解除することになりました。ところが、私が顧問をやめたとたんに税務調査が入ったんですよ。その際、宝石の留め金に使っていた金を売却した収入があることが発覚しました。はっきりしているのは十数万円程度でしたが、私は知らず、申告もされていなかったわけです。
金は、売れ残った宝石製品から外して売ったというパターンで、本人は小遣い稼ぎくらいの気持ちだったのでしょう。ところが、調査官は、手元にあった1ヵ月分の売上資料を基に、それに5年分の60を掛けて、無申告の所得を千数百万円と弾いたのです。
――税務調査では、原則として最長5年分の所得を対象にできるから、そんなことをしたのですね。その取引に関する過去の売上や利益は、明確にできなかったのでしょうか?
菊地 やはり、領収書などのちゃんとした資料が残っていませんでした。ならば、ずっと当月と同じ利益を上げていたと推測し課税する、というのが税務署の言い分です。
その方が、以前からそういうかたちの金の売却を行っていたのは、事実のようでした。しかし、経営や生活の状況からみても、そんなに多額の利益を上げていたとは、考えにくかった。
でも、悪いことに、私のところに「実は……」と相談にいらっしゃったのは、税務署の言う通りの修正申告書に判を押した後だったんですよ。そうなると、さすがにこちらから新たな主張をするのには、無理がありました。手は尽くしたのですが、税金の減額を認めてもらうことはできなかったですね。
――「加算税」なども含めて、税金は納期までに一括で納めなくてはなりませんから、その方もけっこう大変な思いをすることになったでしょう。
菊地 税務調査では、今のように「税務署主導」にされないこと、逆に言えば納税者側がイニシアチブを握って主張することが大事になります。そのために、プロの力を頼ってもらいたいと思うんですよ。
税理士の力を活用する

――ただし、税理士さんにも得意・不得意はあって、あまり税務調査の経験がない方もいます。
菊地 そうですね。話を聞くと、そもそも税務署の前に税理士を怖がっているような納税者の方もいます(笑)。「飲食店の領収書はあれこれ言われるので、仕事のために好きで飲んだわけではなくても、出しにくい」とか。
申告の前に税務署に目を付けられそうな領収書を「カット」しておけば、税務調査のリスクを減らすことはできます。その点で、納税者も安心できるかもしれません。しかし、それは調査で税務署の言いなりになるのと同じで、本末転倒ではないかと私は思います。そもそも税金を払い過ぎていては、事業にも影響してしまうでしょう。
――そうした点を考えて税理士を選び、大いにその力を活用すべきですね。
菊地 税理士を使う、という点から1つ補足しておくと、私は相続税の申告を請け負うこともあります。相続税についても、調査が入るとしたら申告から5年とか、かなり後のことになるのには、注意してください。
――その頃には、申告の内容などは、ほとんど覚えていないかもしれません。
菊地 その場合でも、税理士のところにまず連絡が入るのが普通なのですが、調査官によっては、直接調査をやろうとすることもあります。いきなり「税務署ですが」と電話が来れば、誰でも焦るはず。
そうしたケースに備えて、申告を担当した税理士の事務所や氏名は、しっかり控えておくべきです。私は、「わかりやすいところに、名刺を置いていてください」と言うようにしているんですよ。
さらに言えば、依然として特殊詐欺が横行しているのですが、相続でお金が入った高齢者が狙い撃ちされることもあるようです。彼らが税務署員を名乗ったりすることも、十分考えられるわけですね。
――税務署から連絡が来た、と焦って対応していると、大変なことになるかもしれません。
菊地 ですから、申告について何か困ったことがあったら、とにかく担当した税理士に一報を入れてほしい。ある意味、相談窓口のように使ってもらえばいいと思います。
――本日は、税務調査について、役立つお話をうかがうことができました。最後に、貴事務所の今後についてお聞かせください。
菊地 実は、私は大学で物理学を専攻しておりまして、難しい税務の専門用語は、今でも苦手なんですよ(笑)。お客さまにも、できるだけわかりやすい説明を心掛けて、これからもさきほど言ったような「納得できる納税」のお手伝いができれば、と考えています。
事務所の規模を拡大したいという気持ちはありますが、それ自体を目標にはしていません。当事務所の「イズム」を理解いただける専門家が見つかれば、タッグを組んでやっていきたい、というのが基本的なスタンスです。
――ますますのご活躍を期待します。本日はありがとうございました。
北千住・東京エリアを中心に、法人・個人事業主・業種問わず、経営者を支える税理士事務所。特に税務調査立ち合いを得意とし、会社設立、相続まで幅広く対応する。「納税者ファースト」を掲げ、お客様の多様なニースに寄り添い、最適な解決策を提案する。