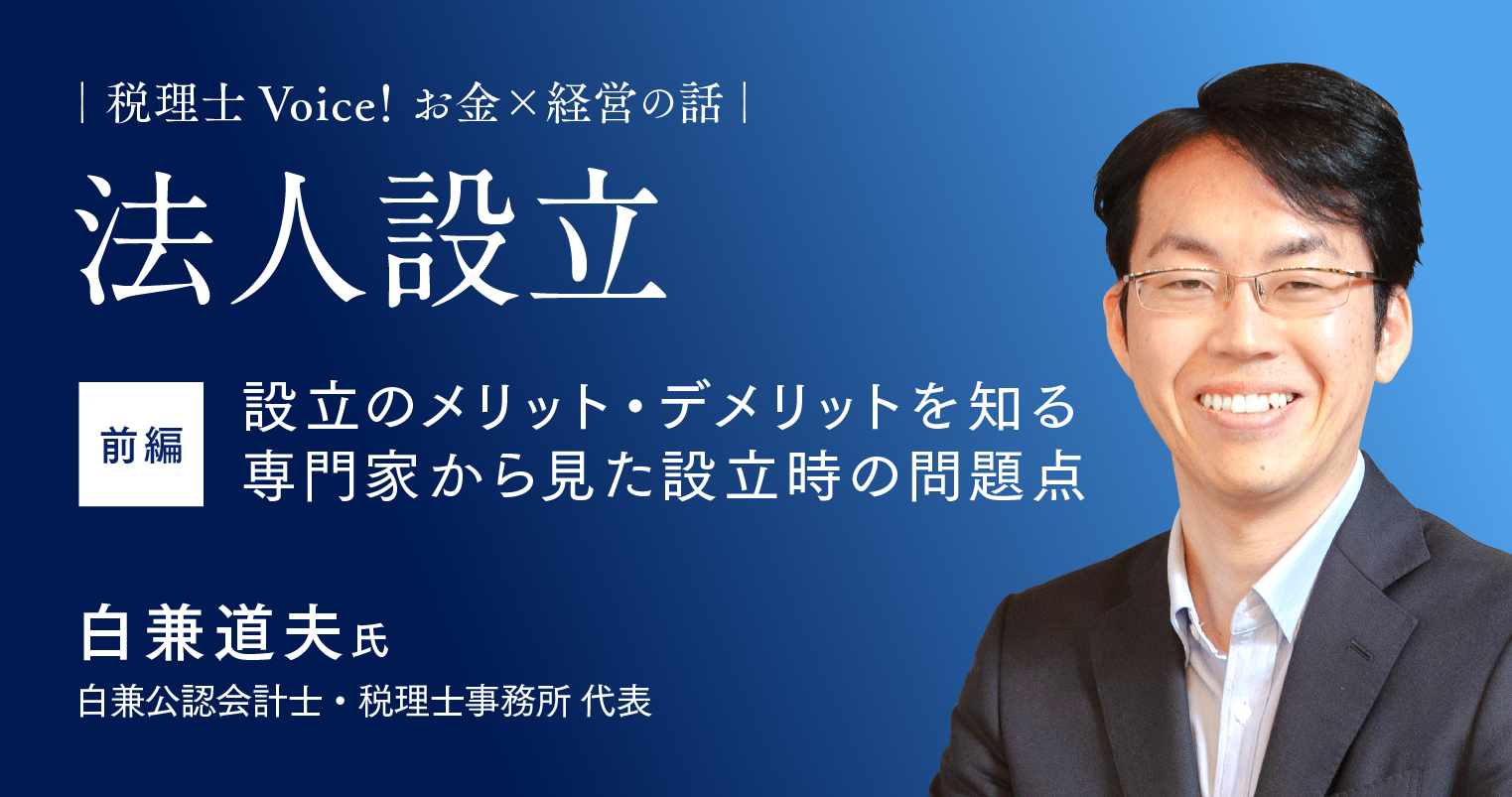【事業承継 前編】減る親族内承継、増える中小企業のM&A これからの事業承継に必要な準備とは
雨宮会計事務所 代表 雨宮英希氏事業承継には、いくつものハードルがある。後継者はいるのか? 親族か、従業員か? あるいはM&Aという選択か? いずれにしても、成功させるためには、しっかりした準備をしておくのが理想だ。先代経営者が急に倒れ、会社の行く末が見えなくなってしまった、といった事態を避けるためには、何を考えて、どんな備えを進めるべきなのか。コンサルティング会社で、多くの事業承継の案件に携わった経験も持つ雨宮英希氏(雨宮会計事務所代表、公認会計士・税理士)に、話をうかがった。
インタビューでは、「前編」で最近の事業承継の傾向や準備の進め方、「後編」で親族外承継、M&Aの注意点や相談相手の探し方などを中心に聞いた。
減りつつある「子どもへの承継」
――先生は公認会計士の資格をお持ちです。
雨宮(敬称略) はい。7年ほど監査法人で上場企業の監査に携わったのち、会計・税務関係のコンサルティング会社に転職し、そこでは事業承継、M&Aなどの業務も担当しました。その後、金融機関への出向も4年ほど経験しています。
独立して東京・日野市に事務所を構えたのは、2022年です。現在、私のほかにスタッフが3名という体制で、多摩地区のお客さまをメインに活動しています。顧客に多い業種は運送業、不動産業、介護事業、小売業などですが、特に偏りはありません。通常の顧問業務などに加え、キャリアを生かして事業承継、相続のコンサルティング、相続税申告などにもスポットで対応しています。
――今回は、その事業承継をテーマに、お話をうかがっていきたいと思います。件数は増えていると聞きますが、最近の動向についてお聞かせください。
雨宮 以前は、親の事業を子どもが継ぐ「親族内承継」というのが当たり前だったと思うのですが、そうした意識が徐々に薄れ、実数としても減っているのが一般的な傾向と言えるでしょう。そもそも、少子化で子どもがいない。いても、例えばサラリーマンをしていて、そちらでうまくいっているので、今さら家業を継ぐために戻る気はない。親の方が、「こんなきつい仕事を子どもに継がせたくない」というパターンもあります。

そうなると、会社の役員や従業員後継者に据える「親族外承継」や、他社に事業を売却する「M&A」が選択肢になります。かつては中小企業のM&Aというのは珍しかったのですが、親族内承継の減少とは裏腹に、年々増える傾向にありますね。
ただ、これも一般論ですが、地方の名門企業だったりすると、子どもが小さな頃から社長になるために鍛えるといった伝統が、都市部に比べると残っているようにも感じます。
承継には「事業」と「株」がある
――事業承継に関して、先生のところにはどんな相談が寄せられるのでしょう?
雨宮 相談に来られるのは、ほとんど後継者側の方です。中に、「事業は引き継いで社長になったものの、会社の株はまだ先代の父親が持っている。どうしたらいいでしょう?」というケースがありました。
――自社株の所有割合は総会の議決権に直結しますから、社長が株を持っていないと、経営はかなり不安定になってしまいます。
雨宮 この事例の場合は、先代が経営に影響力を行使したいとかいうことではなく、単純に今の話のような自社株の移動の意味や、その方法が十分理解されていない、という状況でした。そこで、株価の算定や、それを譲り受けるには贈与、あるいは有償の買い取りという方法があることなどから、説明させていただきました。
このように、経営者以外の親族などが一定の株を持つこと自体は、そんなに稀なことではないんですね。
――先代経営者の相続などの際に、「分散」することがあります。
雨宮 それでも、会社の業務がきちんと回っていると、株の問題は意識されにくい面があるのです。「株主」から特に横やりが入るわけでもなく、自分の報酬もちゃんと受け取れる状態であれば。実際、その状態で何十年もやってきました、という会社もありました。
ただ、そうした場合の経営者のジレンマは、自分が頑張って会社の業績が良くなるほど、基本的に株価も上昇していくことです。いざ株を買い取って自らの手元に集めたいと思ったときには、より多くの資金が必要になってしまいます。
一方、経営に参画しない人にとって、市場で売却できない非上場株式を持っている経済的なメリットは、基本的にありません。なので、ある時点で、経営者がそういう株主から、株の買い取りを迫られるかもしれません。業績のいい会社だったら、株が欲しいという第三者に売却される可能性もあるでしょう。そうやって、他者に多数の株を持たれた結果、経営を奪われる、という最悪のシナリオもありえます。そういう動きが出てきたときに、初めて株を持たないリスクに気づくことが多いのです。
――それは、先代経営者にとっても望ましい状況ではないですね。
雨宮 そうならないために、承継の相手が決まったら、なるべく早いタイミングで株を渡し、後継者が本業に集中できる基盤をつくっておくというのが理想なのは、いうまでもありません。
準備はどこから始めるか
――事業承継を成功させるためには、ある程度計画的な準備が必要になりそうです。
雨宮 一からお話しすれば、まずは後継者の選定、見極めです。株とか税金の話もあるのですが、ケースによっては、ここが最大の難問だったりもします。さきほども言ったように、子どもに継がせたいと思っても、本人にその能力や気持ちがなければ、うまくいきませんから。会社の従業員が候補になる場合も同じです。

後継者が決まってからも、やるべきことが多くあります。例えば、経営ノウハウや内部管理の方法の伝授、取引先へのあいさつなどですね。困るのは、そうしたことが済まないうちに先代社長が体調を崩したりすること。後継者は準備不足のまま経営を引き継ぐことになってしまいます。
――まして、後継のめども立っていない状態で先代が亡くなれば、会社の存続自体が危うくなるかもしれません。
雨宮 ですから、事業承継の準備は、社長が元気なうちに始めていく必要があるわけです。
税理士の視点からいうと、今の株の話があります。株価が安ければまだいいのですけど、高い会社、先々値上がりが予想されるケースでは、きちんとした対策を講じるべきでしょう。
非上場会社の株価には、税法上の算定ルールがあって、原則として業績が良かったり純資産が潤沢だったりするほど高くなり、逆だと安くなります。対策の一つは、このルールを活用して株価をコントロールすることです。
株式の承継は、親族であれば生前贈与か相続、親族外の場合には売買というのが一般的です。あらかじめ株価を下げておいて子どもに贈与したり、従業員に買ってもらったりすることで、後継者の経済的な負担を減らすことが可能になるのです。
――利益を抑えるには、どうするのでしょう?
雨宮 一般的には、自分自身に退職金を支給する、大型の設備投資を行い、投資減税を活用する、といった手法があります。
後継者が決まっていれば、「自社株を渡して大丈夫だ」と判断したタイミングで、こうした株価対策を実行し、渡すことができるでしょう。「先代が元気なうち」は、「このようなタイミングが図れる間」と言い換えることが可能です。
一方、先代社長が自社株を持ったまま亡くなった場合、今説明したような株価のコントロールはできません。後継者が株を取得するためには、その時点の株価を基にした相続税を支払い、相続することになります。
株の評価額が高ければ、納税資金が問題になるかもしれません。さきほど話に出た、他の相続人への株の分散が起こり、後継者が安定的な経営に必要な株を確保できない、という事態も考えられます。
――相続で自社株を渡すのには、リスクがあるのですね。
雨宮 事業の後を継いでくれる人のことを考えるなら、繰り返しになりますが、十分元気なうちに、事業承継の青写真を描いて、実行すべきでしょう。前職からの経験を踏まえていえば、事業承継の準備期間は、後継者が決まった時点から3年~5年は必要だと思います。
――そこから逆算して、行動を起こすのが理想だということになります。
「後編」では、M&Aも含めた事業承継の進め方などについて、引き続きお話をうかがいます。
注:記載の「事例」に関しては、情報保護の観点により、お話の内容を一般化したり、シチュエーションなどを一部改変したりしている場合があります。
監査法人、コンサルティング会社、金融機関での経験を活かし、中小企業のよきアドバイザーとして、経営者に寄り添う会計事務所。会計税務だけではなく事業承継・M&Aも得意としており、多摩エリアを中心にコンサルティングサービスを提供する。
URL:https://amemiya-cpa.com/