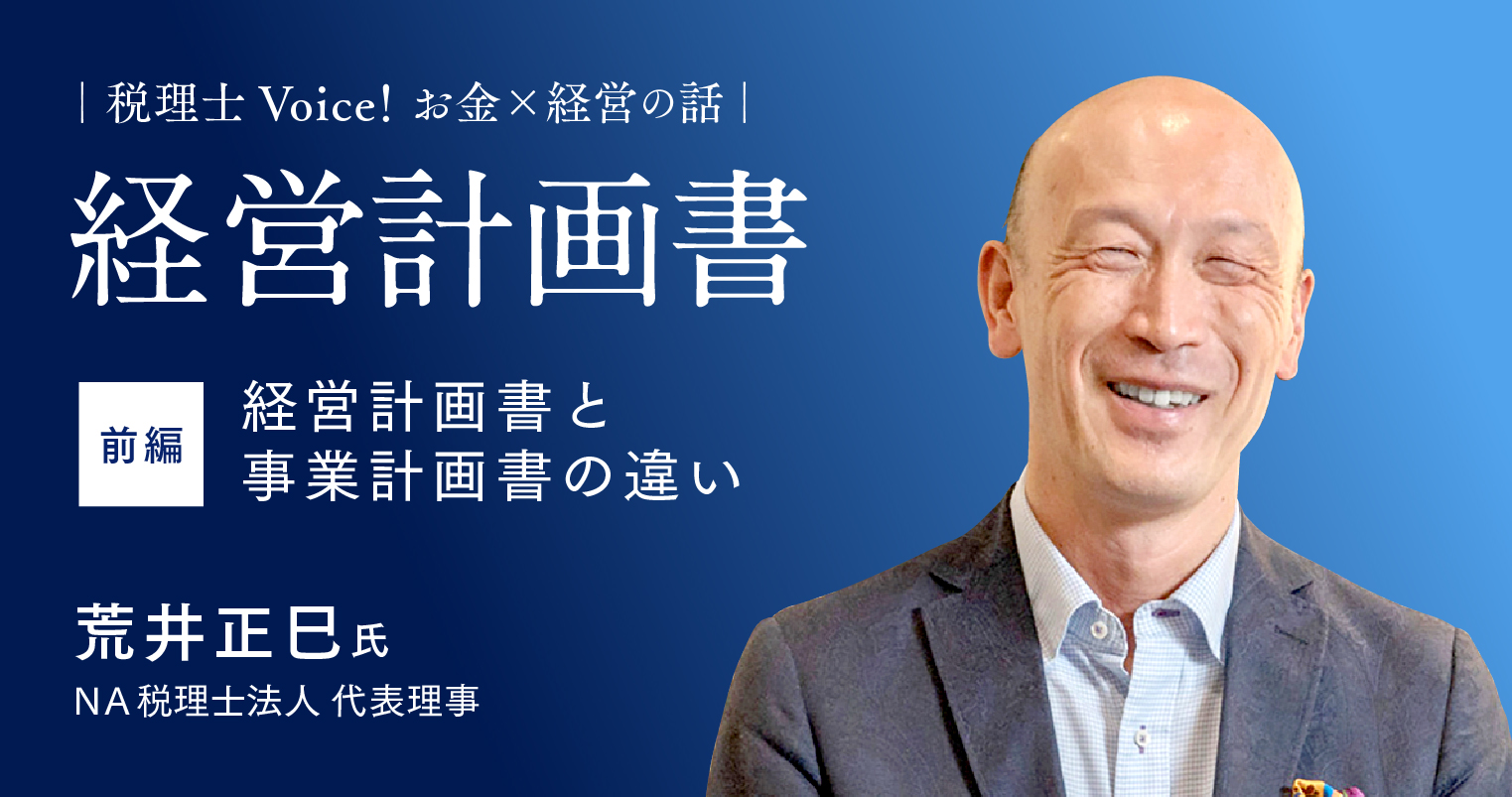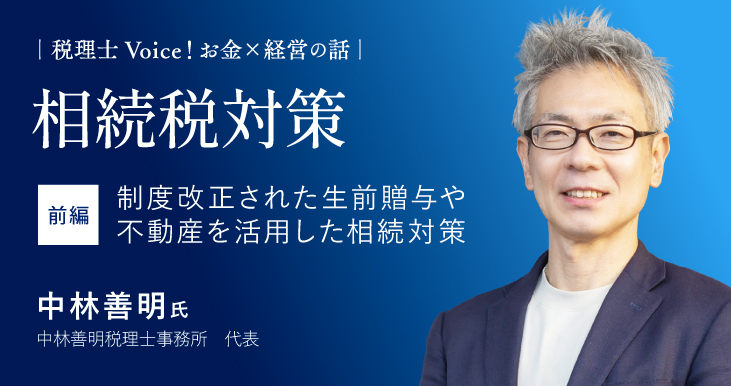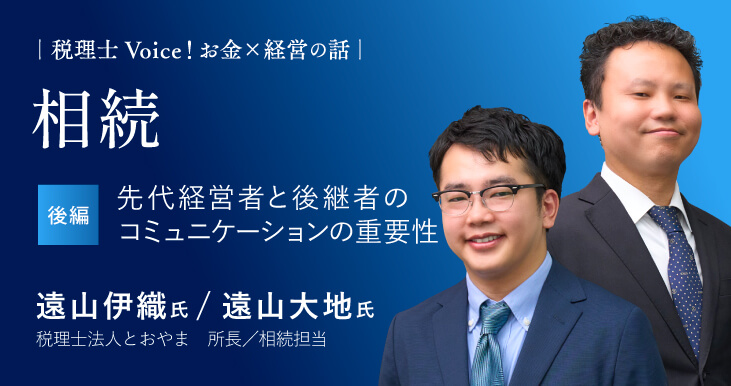【事業承継 後編】減る親族内承継、増える中小企業のM&A これからの事業承継に必要な準備とは
雨宮会計事務所 代表 雨宮英希氏M&Aの前に従業員への承継を検討する
――子どもなどの親族に後継者が見つからなかったら、「親族外承継」「M&A」が選択肢になる、というお話がありました。そうなった場合、M&Aを考える前に、まずは社内で候補者を探すべきなのでしょうか?
雨宮 もちろんケースバイケースではありますが、順序としては、まず役員や従業員への承継を検討するのがいいと思います。長く社内にいた人ならば、会社のカルチャーに親しんでいますし、仕事の回し方などにも慣れていますから、比較的スムーズに事業を引き継げる可能性があるでしょう。
「そうはいっても、社内に適任者はいない」とおっしゃる経営者も多いのですが、あえて「本当にそうですか?」と申し上げたいんですよ。それは、誰かを後継者にしよう、という視点で社員を見てこなかったからかもしれません。
――確かにそうです。
雨宮 もしかすると、この会社を継ぎたい、という思いを持っている社員がいる可能性もあるわけです。ですから、後継者の適性のある人が本当に社内にいないのか、もう一度見直してみる価値はあると思うのです。
――親族外承継の場合は、後継者が株を買い取るかたちになるのが一般的、というお話もありました。その場合、後継者側にその資金があるかどうかがネックになりませんか?
雨宮 やはり株価が高い場合には、個人がお金を用意するのは難しいケースがあるでしょう。ただし、例えば新たに持ち株会社をつくって、そこが株を買い取るかたちにするなど、後継者に過大な負担がかからないスキームを設計することは、可能なんですよ。
そうやって、後継者側に自分の持っている株を買ってもらえれば、先代社長はまとまったお金を手にすることができます。
――会社のことをわかっている人に経営を譲ることができる、さらには持っている株をお金に変えることができる。そうした点で、親族外承継にはメリットがあるということですね。
雨宮 実は、結果的にM&Aに進んだ場合にも、親族外承継の検討というステップを踏んだことには、意味があると思うのです。
――それは、どういうことでしょう?
雨宮 M&Aになると、経営者が変わるなど、従業員は新たな環境で働くことになるでしょう。「先代の都合」でいきなりそういうことになったら、不満の声も起こりやすくなります。仮に、本当は自分が継ぎたかった、という思いの人がいたりすれば、なおさらです。
――なるほど。社内からの後継者の起用も含めて、あらゆる可能性を検討してM&Aを選択したということならば、社員の気持ちはだいぶ違うかもしれません。
雨宮 ただし、あくまでもそこは、社長が自分の経営してきた会社をどうしたいのか、という思いにもよります。単純な話、M&Aがうまくいけば、親族外承継の場合よりも会社が高く売れる可能性がありますから。
M&Aにも準備が必要
――M&Aの道を選択した場合には、そもそも買い手がつくのか、どれだけの条件で買ってもらえるのかがポイントになります。
雨宮 税金の話とは逆で、高い利益が出ていたり、優良な資産があったりすれば、会社は売りやすいでしょう。利益はそんなに出ていなくても、光る技術やノウハウを持っている、あるいは販売網が整備されている、といった点も買い手にとっては魅力的です。

とはいえ、すべての中小企業がそうしたセールスポイントを備えているわけではないはず。自社をいい条件で売却するためには、買いたくなるような価値を高める努力も必要になると思います。
――M&Aを成功させるためにも、準備が必要なのですね。どんなことをしたらいいのでしょうか?
雨宮 必要に応じて中小企業診断士などの専門家の力を借りて、事業の見直し、磨き上げなどを行うのはお勧めです。必ずしもM&Aありきということではなく、会社の基盤強化、体質改善が期待できます。
M&Aは一種のブームのようになっていますが、いきなり売ろうと思っても、なかなか希望通りにはいきにくい現実もあります。事業承継に当たっては、そうしたことも念頭に置くべきでしょう。
承継後のフォローも欠かせない
――事業承継に必要な準備を中心にお話をうかがってきましたが、引き継いだ後に注意することはありますか?
雨宮 親族内、親族外に限らず、承継後に先代がいきなり会社に関与しなくなるというのは、避けたほうがいいでしょう。後継者や会社の状況にもよりますけど、1年なり2年なりは、アドバイザーのような感じで後継者をサポートするのが望ましいです。
――後継者は、トップに就いてみて初めて気づくこともあるでしょう。先代のフォローがあれば、安心できます。
雨宮 社内や取引先などの社外からも、経営者の急なチェンジに対しては、マイナスの反応も起きやすいですから。先代としては、肩書や株だけでなく、経営者としての仕事をきちんと次につなぐことができて、はじめて事業承継の任務を終えた、という姿勢を持つことが大事だと思いますよ。
まあ、反対にリタイア後も社内にずっと居座って、新社長にあれこれ指示したりするのは、考えものですが(笑)。
――M&Aについては、実行したあとに従業員が不満を募らせる可能性がある、というご指摘が、さきほどもありました。
雨宮 買い手の会社とカルチャーが違ったりすれば、やはりいろんな問題は起きやすくなりますね。親会社から送り込まれてきた社長が自分より若かったら、ベテラン社員は面白くないかもしれません。そういうことが原因で、M&A後に多くの社員が辞めていった、という事例を、私も経験したことがあります。
「企業は人」ですから、肝心の「人」、特にキーとなる人材がいなくなってしまえば、企業価値も下がってしまいます。
――そういうパターンは、決して例外ではないようです。
雨宮 他方、カルチャーの違う会社のM&Aはすべて問題なのかといえば、必ずしもそうではないと思うのです。例えばですが、上場企業のグループ会社となることで知名度が上がり、商品の販路が広がった、というようなことがありえるわけです。
その判断は、けっこう難しいものがあります。M&Aを考えるときには、そうした点も含めた、より深い検討が必要になると感じますね。
事業承継は誰に相談すべきか
――考えるべきことの多い事業承継ですが、今現在どうすべきか悩んでいる経営者がいたら、誰に相談するのがいいのでしょう?
雨宮 まずは、最も身近な顧問税理士だと思います。会社の財務状況などを熟知していて、日頃経営面での相談に乗ってくれている先生だったら、的確なアドバイスをもらえる可能性があります。

ただし、事業承継はある種特殊な分野でもあるため、税理士の中にも積極に関与する人と、そうでない人がいます。不得意な先生にフォローを頼んでも、良い結果は期待できません。
そういう場合には、実績のある人や事務所に、スポット的に依頼するのがいいでしょう。事業承継に失敗すれば、会社自体が傾いてしまうかもしれませんから、今の顧問税理士に遠慮したりする必要はありません。後継者とフィーリングが合うならば、顧問税理士をそちらにチェンジする、という選択もアリではないでしょうか。
――事業承継に詳しい先生は、どのように探したらいいのでしょう?
雨宮 そうですね、事務所のホームページというのは、一つの参考になると思います。ビスカスさんのような税理士紹介会社に頼んでみるというのもいいでしょう。
あとは、私自身金融機関にいたという話もしましたけど、彼らもM&Aも含めた事業承継のサポートに力を入れるようになりました。取引金融機関に相談に行けば、専門家を紹介してもらえるはずですよ。
一方、M&Aが視野に入ると、専門の仲介会社に依頼するケースもあるかと思います。上場企業も含め多くの会社がありますが、事業承継のスタートからそこに相談するのは、あまりお勧めしません。
――それは、なぜですか?
雨宮 彼らは、M&Aを成立させて利益を得るのがビジネスですから、どうしても「M&Aありき」になります。最初に相談するのは、やはり顧問税理士がベターだと思います。
――わかりました。事業承継を控える経営者にとっても、後継者候補にとっても、とても有意義なお話でした。最後に、貴事務所の今後の展望について、聞かせてください。
雨宮 経営者の高齢化に伴い、事業承継の案件は、これからも増えていくと思います。中でも、親族外承継やM&Aのウエートが、さらに高まっていくのではないでしょうか。我々のような専門家も、そうした世の中の流れをキャッチアップしつつ、お役に立てるよう努力していきたいですね。
事務所としては、生まれ育った多摩地域の事業者のお客さまを中心に、税務・会計に関する総合的なサービスを提供できる存在として、成長していくのが目標です。そのためにも、人員などの拡大を目指していきたいと考えています。
――本日はありがとうございました。
監査法人、コンサルティング会社、金融機関での経験を活かし、中小企業のよきアドバイザーとして、経営者に寄り添う会計事務所。会計税務だけではなく事業承継・M&Aも得意としており、多摩エリアを中心にコンサルティングサービスを提供する。
URL:https://amemiya-cpa.com/