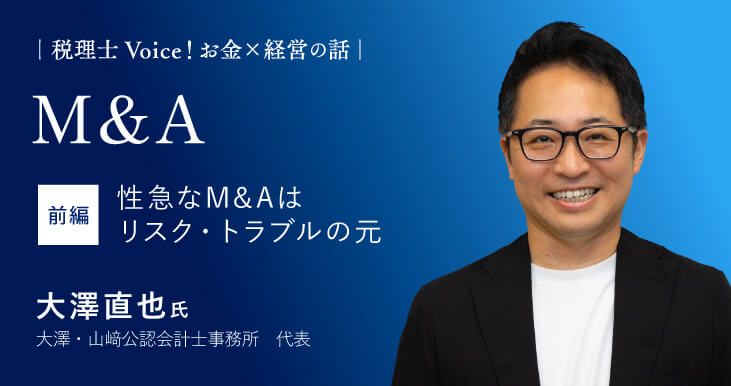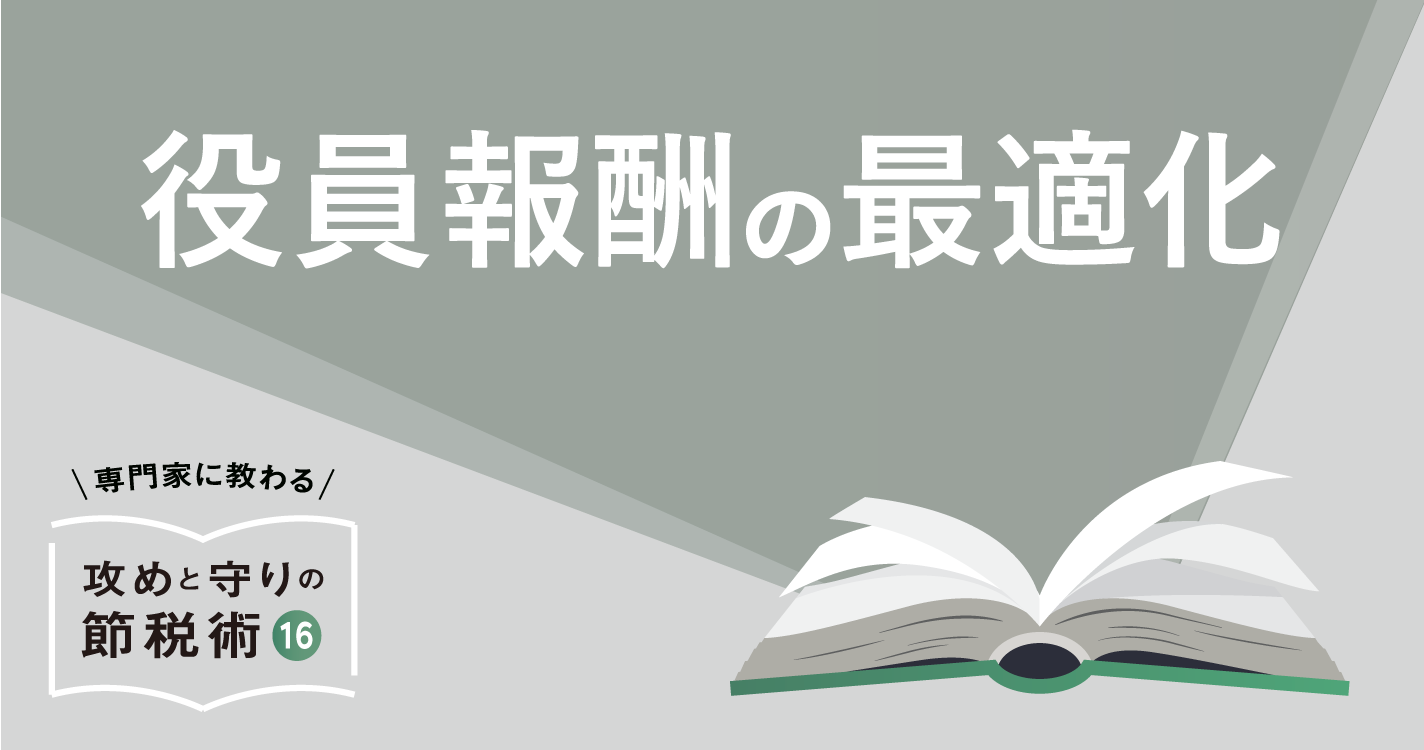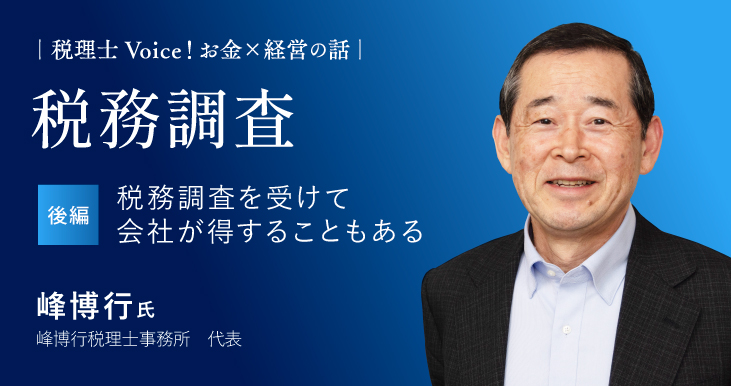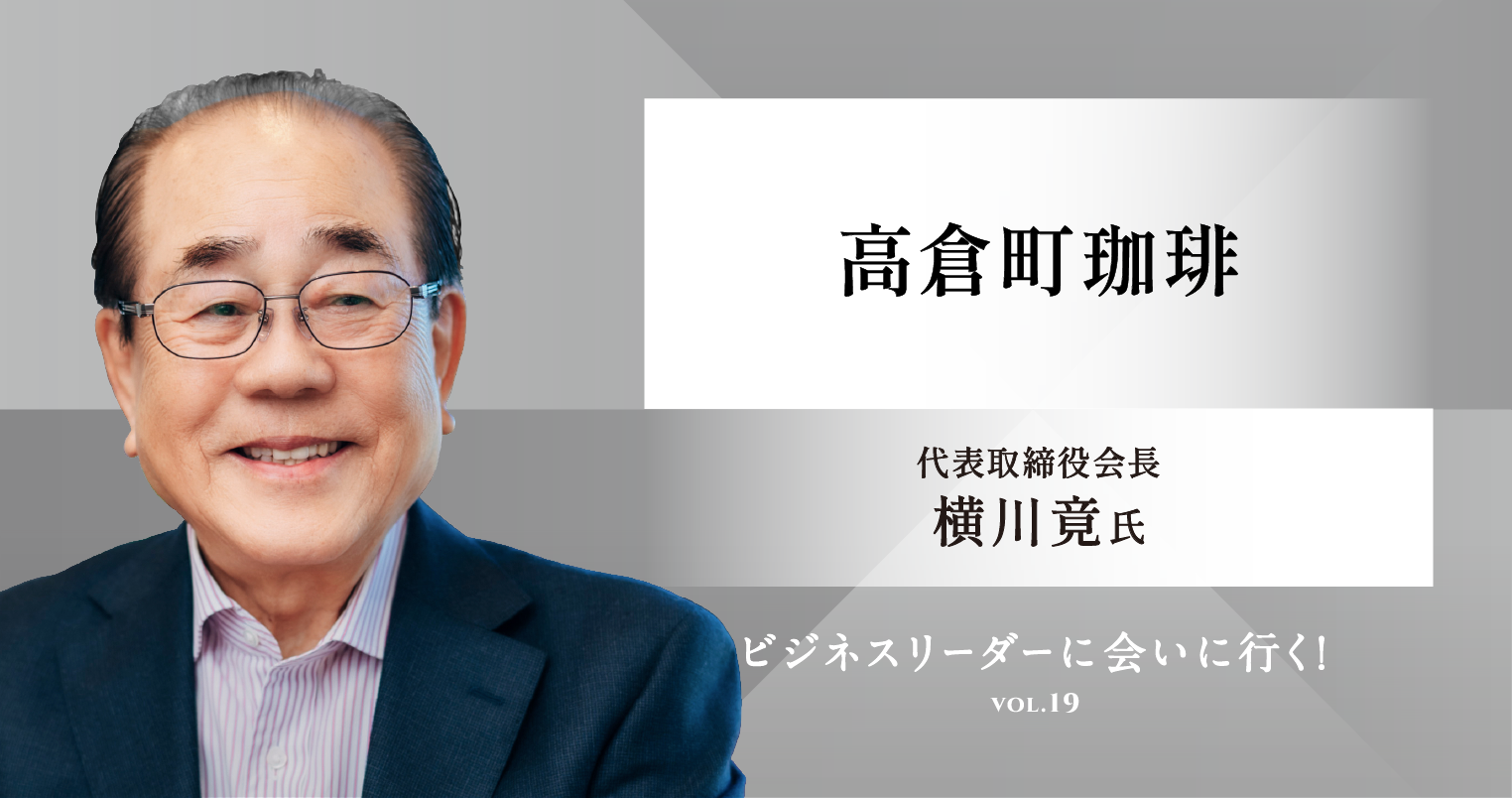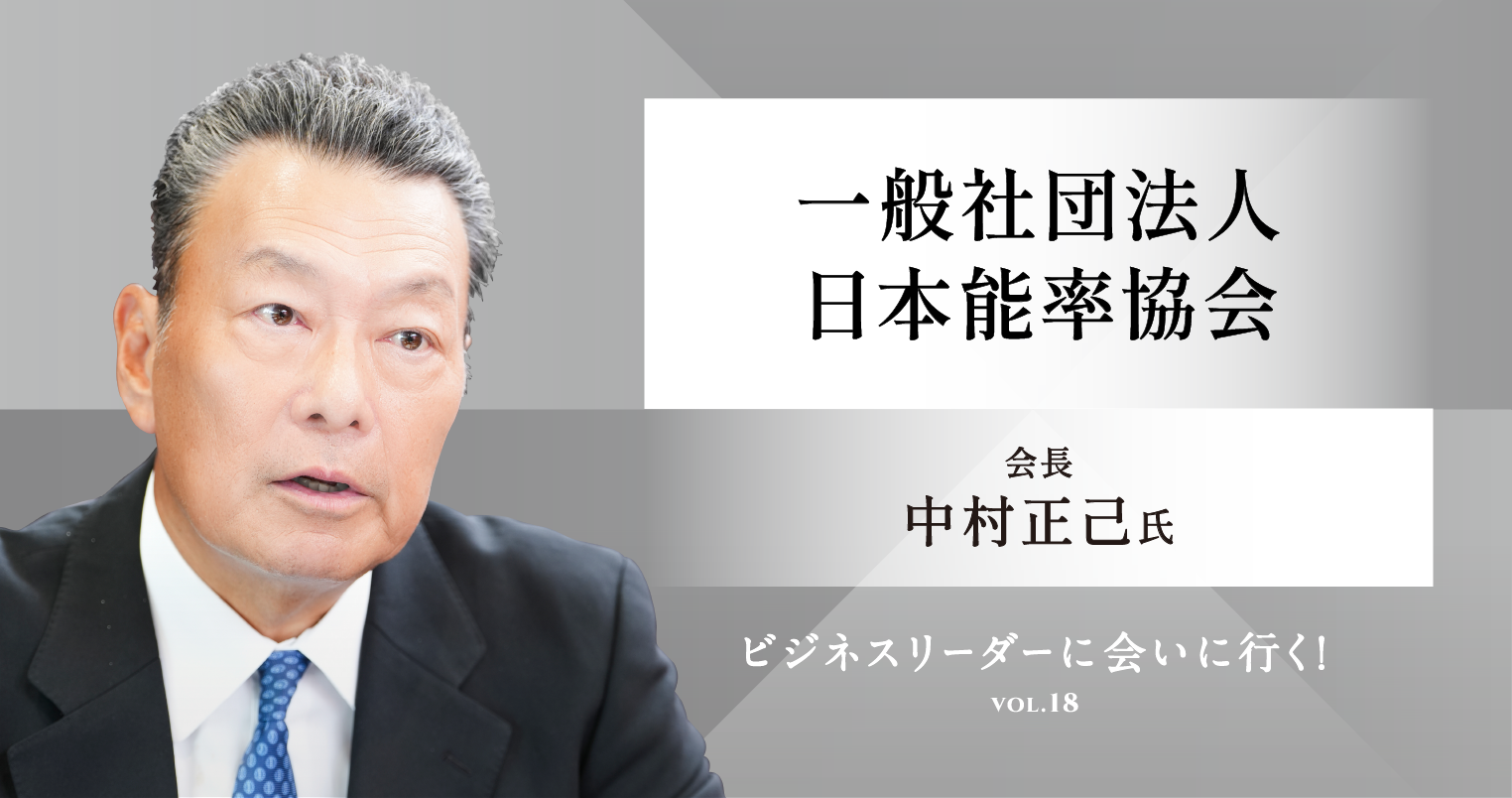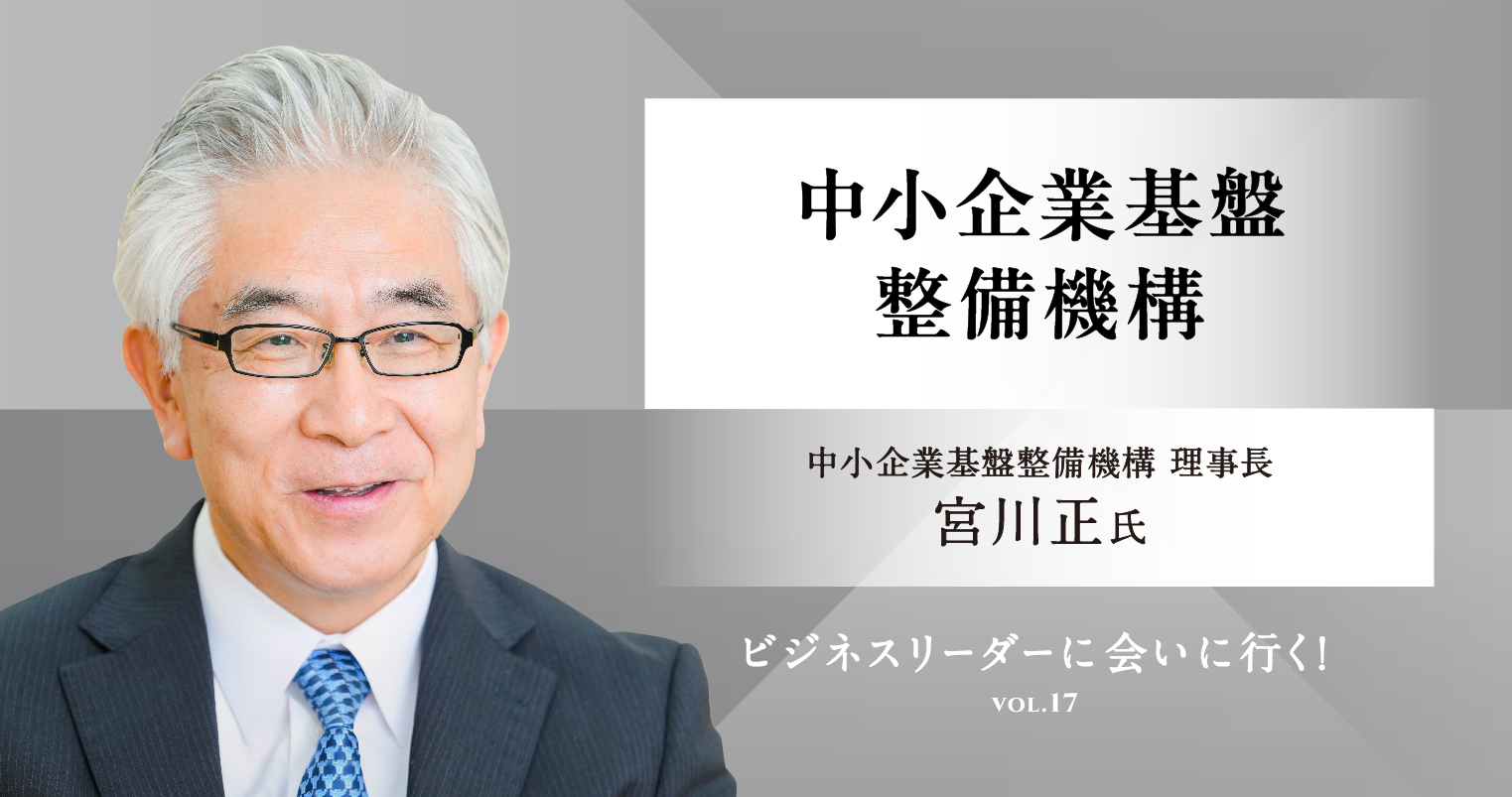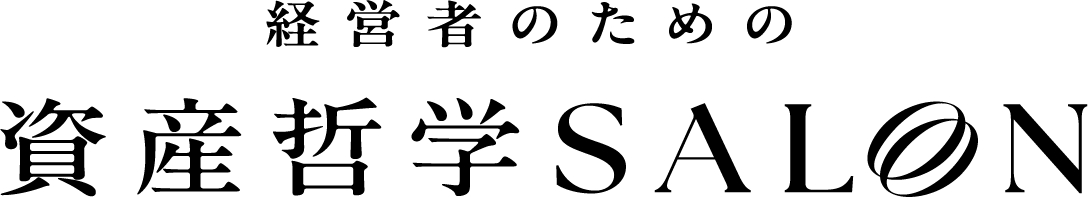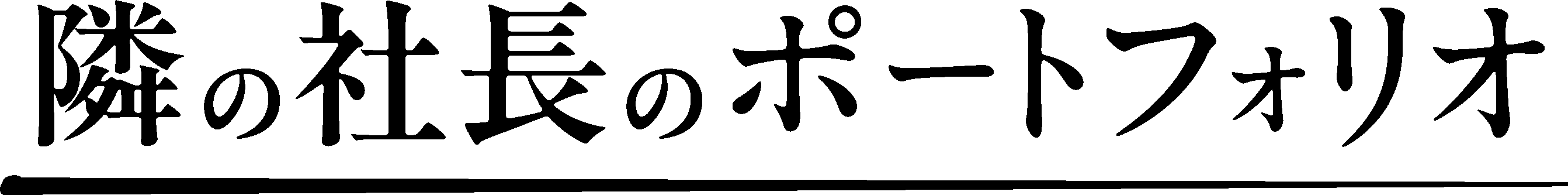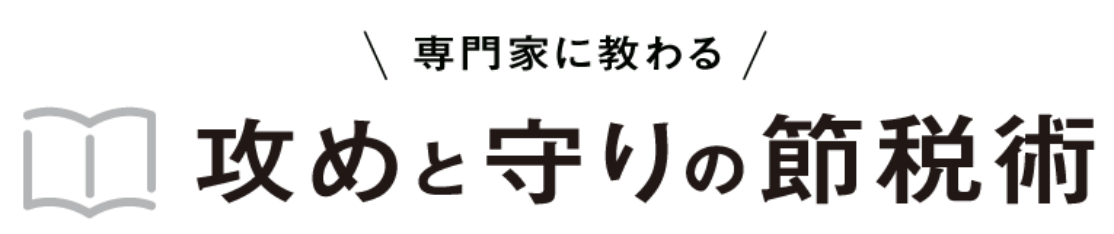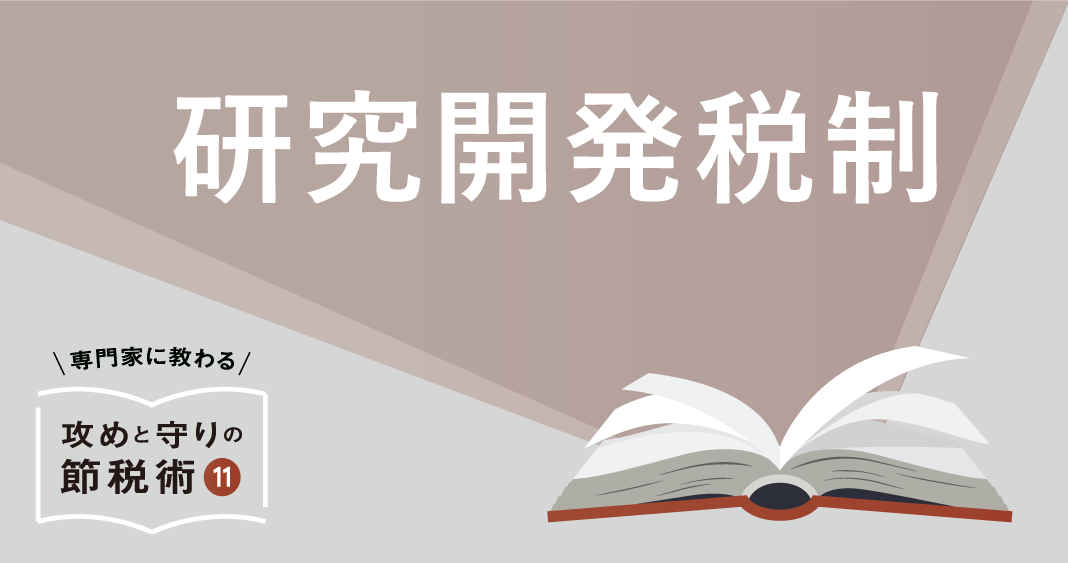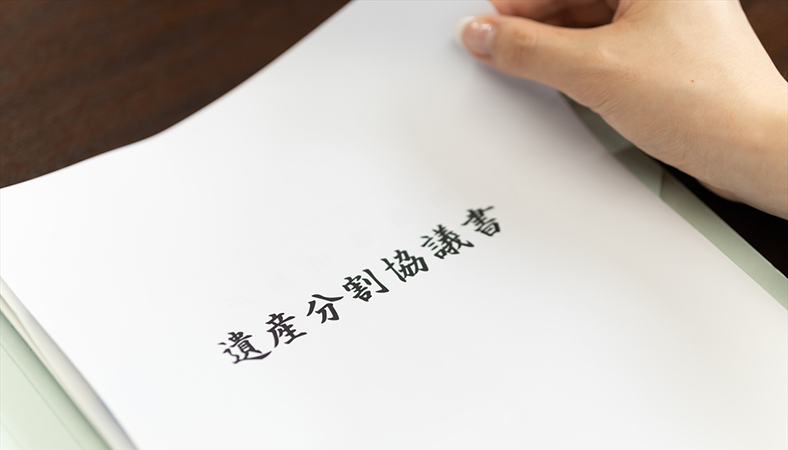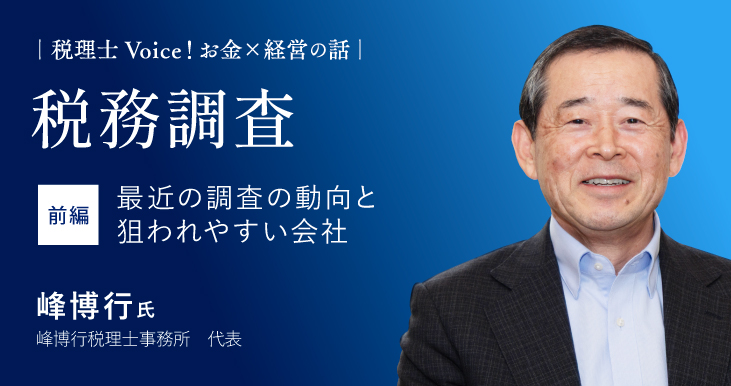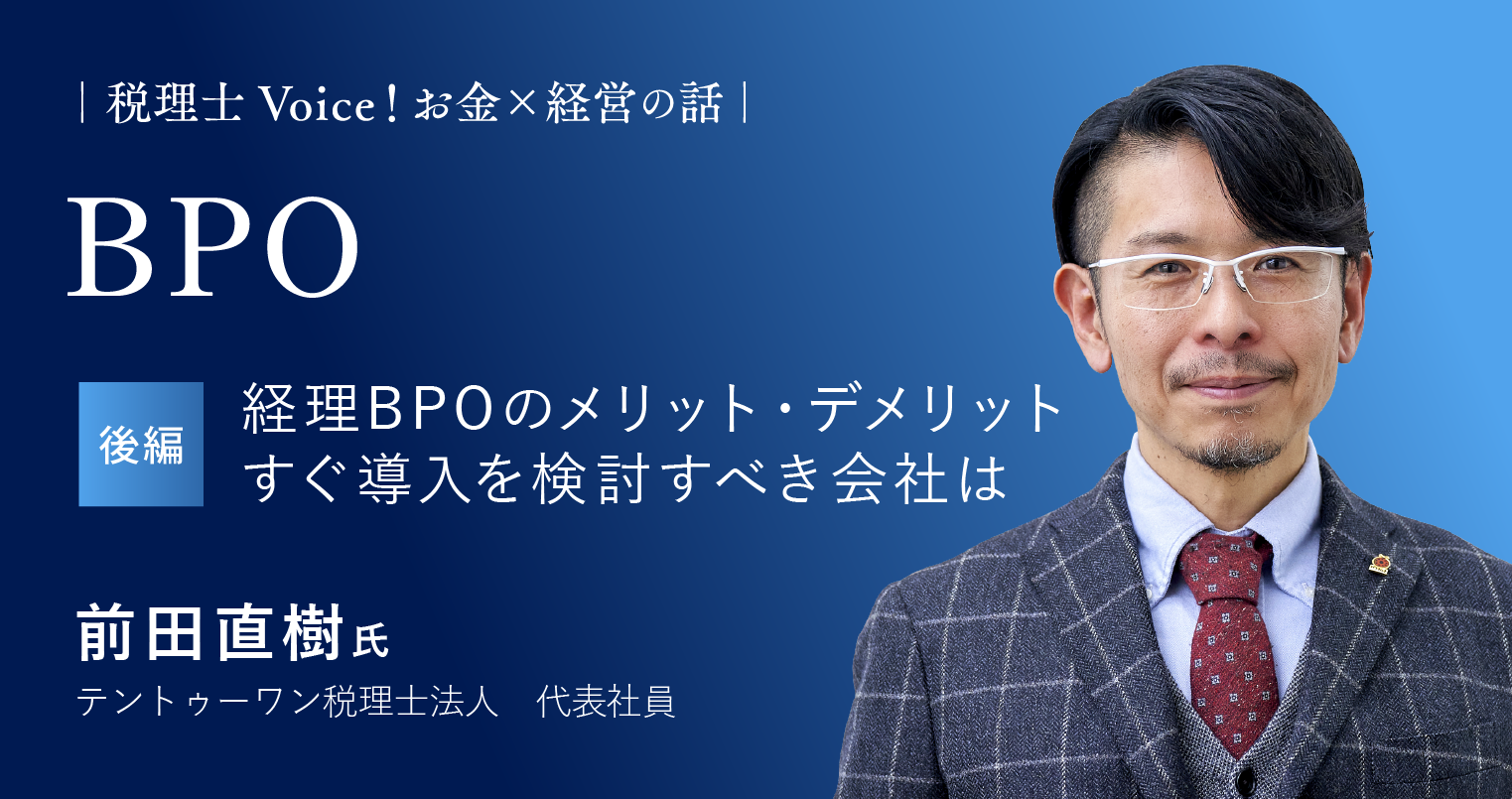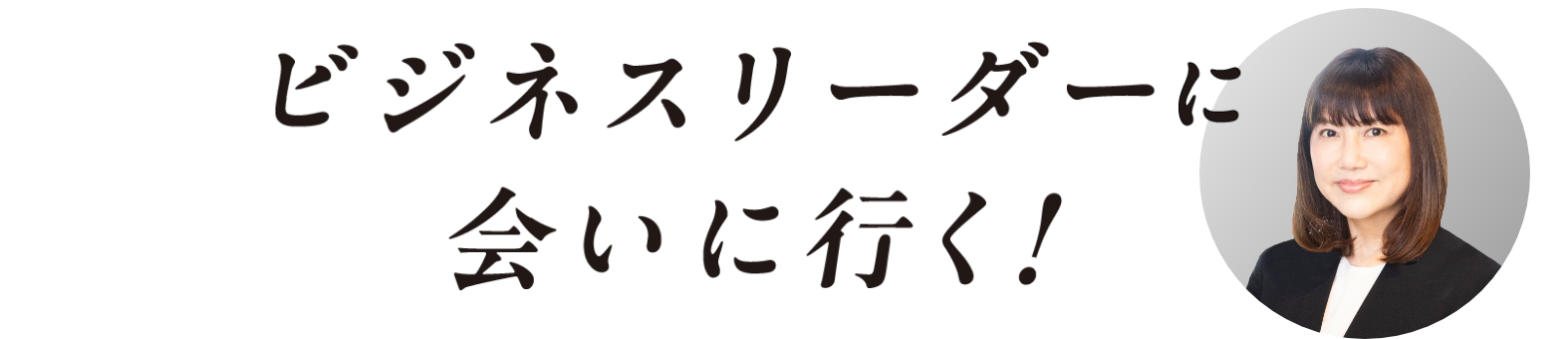
株式会社ビスカス社長 八木美代子と
ビジネスリーダーとの対談を通して
“企業経営を強くし、
時代を勝ち抜くヒント”をお伝えします。
経営者一人ひとりが
資産運用の考え方とスタイルに
磨きをかけるためのスペシャルコンテンツ。
新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025参院選】選挙公報・政見放送の見方と政策比較のポイントを徹底解説
-
【2025参院選】立候補にかかる費用とは?選挙活動の実態と供託金・公費負担を解説
-
【2025参院選】参院選で私たちの生活はどう変わる?各政党の政策を徹底比較・完全解説
-
【2025年参院選】選挙運動のやり方とルールを徹底解説!NG行為とは?
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ
税理士事務所への取材を通して、
お金と税金の最新情報をお届けします。