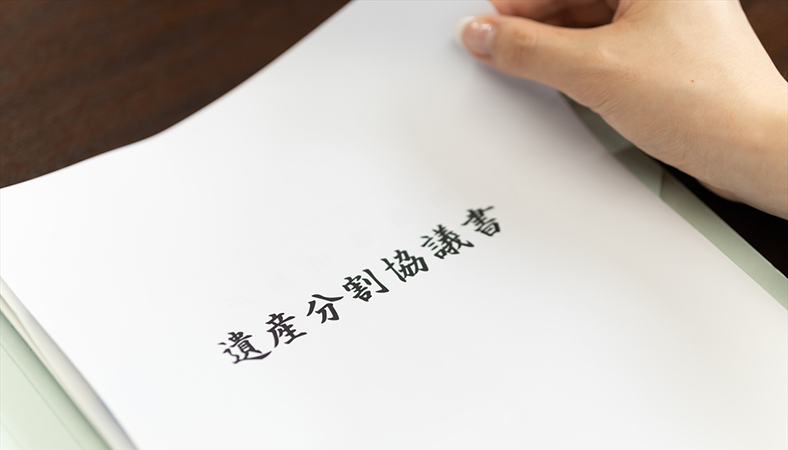法人の利益にかかる税金はいくら?納税に苦労しない方法を解説

「黒字倒産」の一因に法人の利益にかかる税金が挙げられます。現金収支に関係なく利益が計算され、税金が課税されるためです。その一方、現金預金の残高が多くても利益や税金を少なくすることも可能です。そこで、法人の利益にかかる税金で納税に苦労しない方法について解説します。
利益に対してどのぐらい税金を納めるのか
個人事業主や法人を問わず、利益(所得金額)から利益(所得金額)に対する税金を差し引いた残額が手元に残るお金です。借入金の返済をしている場合、利益(所得金額)から税金を差し引き、さらに返済元金を差し引いた残額が手元に残るお金となります。法人の税金は利益(所得金額)に一定の税率を掛けて計算します。まずは具体的な税目の割合は次の通りになります。
法人の利益に対する税金の割合
法人の税金は利益(所得金額)に一定の税率を掛けて計算します。まずは具体的な税目の割合は次の通りになります。
(1)法人税
株式会社や合同会社など営利目的の普通法人の税率は次の通りになります。
| 区分 | 税率 | |
|---|---|---|
| 資本金1億円以下の法人 | 年800万円以下の部分 | 所得金額×15% |
| 年800万円超の部分 | 所得金額×23.2% | |
| 資本金1億円超の法人 | 所得金額×23.2% | |
(2)地方法人税
「上記(1)の法人税×10.3%」になります。
(3)法人市民税
東京23区の場合、法人税割の税率は次の通りになります。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 資本金1億円以下および法人税が1,000万円以下の法人 | 上記(1)の法人税×7% |
| 上記以外の法人 | 上記(1)の法人税×10.4% |
なお、法人税割のほかに赤字でも課税される均等割が年7万円以上あります。
(4)法人事業税
東京都の場合、普通法人の法人事業税の税率は次の通りになります。
| 区分 | 所得等の区分 | 税率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 不均一課税適用法人の税率 (標準税率) |
超過税率 | ||||
| 軽減税率適用法人 | 年400万円以下の所得 | 所得金額×3.5% | 所得金額×3.75% | ||
| 年400万円を超え 年800万円以下の所得 |
所得金額×5.3% | 所得金額×5.665% | |||
| 年800万円を超える所得 | 所得金額×7% | 所得金額×7.48% | |||
| 軽減税率不適用法人 | ― | 所得金額×7% | 所得金額×7.48% | ||
具体的には次の図のフローチャートにより、「1.標準税率または超過税率」および「2.軽減税率適用法人又は軽減税率不適用法人」を判断します。
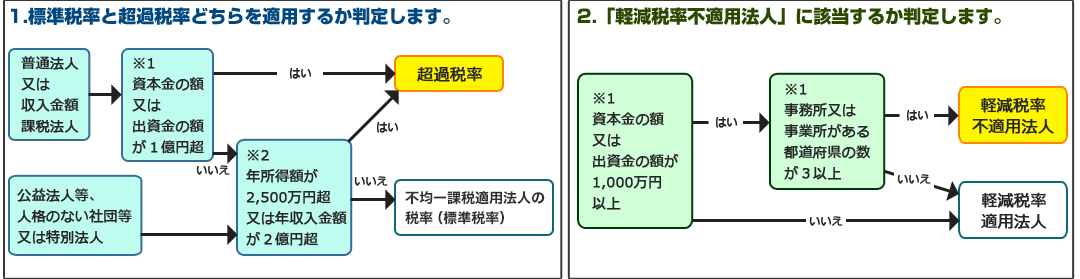
出典:東京都
つづいて、具体例から利益に対するトータルの税率を見ていきましょう。このトータルの税率を「実効税率」といい、利益から手元に残るお金の概算額の計算に用いるパーセンテージになります。
例)資本金300万円の中小法人で所得金額(拠点は1ヵ所)が1,000万円の場合の納税額(百円未満切捨て)
(1)法人税
- 年800万円以下の部分:800万円×15%=120万円
- 年800万円超の部分:200万円×23.2%=46万4,000円
- 納税額166万4,000円
(2)地方法人税
上記(1)の法人税166万4,000円×10.3%=17万1,300円
(3)法人市民税
- 所得割:上記(1)の法人税166万4,000円×7%=11万6,400円
- 均等割:7万円
- 納税額18万6,400円
(4)法人事業税
- 年400万円以下の所得:400万円×3.5%=14万円
- 年400万円を超え年800万円以下の所得:400万円×5.3%=21万2,000円
- 年800万円を超える所得:200万円×7%=14万円
- 納税額:49万2,000円
(5)利益に対する納税額
251万3,700円
所得金額1,000万円に対して納税額は251万3,700円になり、実効税率は約25%という結果が得られました。
利益の計算方法
利益は事業活動での物の動きに対する採算額を示したものであり、収益と費用を発生主義により計上し利益を計算するため示すため、現金収支とは違います。そのため、「勘定(利益)合って銭(現金預金)足らず」に陥らないためにも法人の利益の計算方法はぜひ知っておきましょう。たとえば、資本金300万円のWeb制作会社が掛取引でホームページを1,000万円で納品(=物の動き)し、ホームページ制作にかかる外注費400万円を現金払いしたとします。利益ベースで見れば、売上高1,000万円を収益として計上して、外注費400万円を費用として計上しますので利益は600万円となります。一方、現金ベースで見れば売上が掛取引であるため入金は0円、費用が現金払であるため支払は400万円となり、400万円のマイナスとなります。これが「勘定合って銭足らず」の状態を示しています。
税金の存在により資金繰りが苦しくなることも
利益と現金収支が一致しないため、利益に対する税金の存在で資金繰りが苦しくなる場合もあります。
前述の資本金300万円のWeb制作会社を例にすると「売上高1,000万円-外注費400万円=利益600万円」に対して、現金収支はマイナス400万円です。そのため、「利益×実効税率25%=税金150万円」に対する納税資金が確保できません。
資金繰りが苦しくなるケース
現金収支に対する法人税などの税金の割合が実効税率(前述の例の場合は25%)よりも多くなるほど、納税資金の確保が大変になる傾向にあります。そこで、資金繰りが苦しくなるケースについて説明します。
借入金の返済額が多額の場合
借入金の返済が多額の場合、資金繰りが苦しくなる傾向にあります。借入金元本の返済額は経費に計上できないためです。そのため、利益から税金を差し引いた手取り金額(最終利益)から借入金元本を返済しなければなりません。言い換えれば、借入金元本が「手取り金額+利益に対する税金」を超えると資金繰りが苦しくなります。
たとえば、利益1,000万円の法人が、500万円の支払いをします。実効税率25%の場合、その500万円が外注費など経費に計上される項目である場合と借入金元本のように経費に計上できない項目の場合を、税金などの負担額を比較すると次の通りになります。
(1)経費に計上できる項目の場合
- 取引先への外注費支払い:500万円
- 法人税などの利益に対する税金:所得金額500万円×実効税率25%=125万円
- 負担額:625万円
(2)経費に計上できない項目の場合
- 借入金の返済元金:500万円
- 法人税などの利益に対する税金:所得金額1,000万円×実効税率25%=250万円
- 負担額:750万円
同じ支払額500万円にかかわらず、上記(2)の負担額は上記(1)よりも1.2倍になる結果が得られました。
固定資産を購入した場合
固定資産も購入金額を一括で経費に計上できません。たとえば、土地1,000万円の購入金額は資産計上をし、売却時点で売却原価としてはじめて経費で落とせます。土地と同じように商品や製品などの原価についても売上と同時に経費に計上するため、過剰在庫のある場合には資金繰りが苦しくなる傾向にあります。
税務調査で引っかかった場合
税務調査で間違いが指摘された場合、法人税など本税ののほかに延滞税などのペナルティも課税されます。しかも、本税は勿論のこと課税されるペナルティもは経費に計上できないため、借入金元本の返済と同じように利益から税金を差し引いた手取り金額により負担しなければなりません。
税務調査の時期について詳しく知りたい方は「「税務調査」はいつ来るのか? どんな場合に「狙われ」やすい?」をご覧ください。
納税の負担を軽くする方法
現金収支に対する税金の割合を少なくする方法をいくつか紹介します。
含み損を計上する
含み損とは売価が帳簿価額よりも下回る金額のことを指します。そのため、不良在庫や固定資産などを売却すれば、含み損は売却損として経費に計上できて、現金収支に対する税金の割合を少なくできます。たとえば、利益1,000万円の法人が帳簿価額1,300万円の固定資産を300万円で売却したとします。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 300万円 | 固定資産 | 1,300万円 |
| 固定資産売却損 | 1,000万円 |
「利益1,000万円-固定資産売却損1,000万円=所得金額0円」となるため、利益に対する税金は0円です。しかも、売却代金300万円だけ現金預金が増えるため、資金繰りもよくなります。
累積赤字(繰越欠損金)を利用する
青色申告の承認を受けている場合、累積赤字を経費に計上できる繰越欠損金の制度を利用すれば、所得金額と相殺できるため、節税につながります。たとえば、生命保険を解約して、解約返戻金がある場合、通常は解約返戻金(利益)に対する税金を差し引いた残額が手取り金額になります。しかし、過去に計上した同額以上の繰越欠損金があれば、解約返戻金にかかる利益との相殺ができますので「解約返戻金=手取り金額」にすることも可能になります。
優遇税制を活用する
中小企業投資促進税制の特別償却・特別控除などの優遇税制を利用すれば、利益を減らさずに法人税などを少なくできます。たとえば、200万円の新品のソフトウェアを購入した場合、税額控除により「200万円×7%=税額控除14万円(調整前法人税額の20%が上限)」を適用すれば、利益は同額でも法人税だけが少なくなります。優遇税制のなかには「所得拡大促進税制」のように、特別な対策を講じなくても定期昇給などで優遇措置が受けられるケースもあります。決算時には自社で該当する優遇税制がないか、詳細にチェックする必要があります。
まとめ
現金収支に対する法人税などの税金の割合を下げることが、納税の負担を軽くする方法になります。そのためには、在庫処分などの含み損を計上するなどにより、現金預金残高を減らさずに経費に計上することがポイントになります。
【関連記事】:中小企業のための法人税の特例~うちは中小法人?それとも中小企業者?~
▼参考URL
TAX(税金)ライター。会計事務所で約10年間の勤務により調査能力を身に付けた結果、企業分析の能力では高い定評を得、法人から直接調査を依頼される実績も持つ。コーチングスキルを活かした取材力で、HP・メディアでは語られない発言を引き出すのが得意。
新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025参院選】選挙公報・政見放送の見方と政策比較のポイントを徹底解説
-
【2025参院選】立候補にかかる費用とは?選挙活動の実態と供託金・公費負担を解説
-
【2025参院選】参院選で私たちの生活はどう変わる?各政党の政策を徹底比較・完全解説
-
【2025年参院選】選挙運動のやり方とルールを徹底解説!NG行為とは?
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ