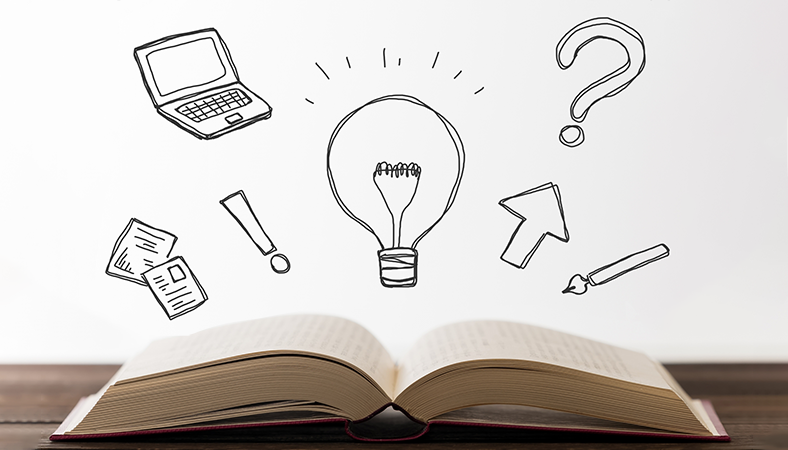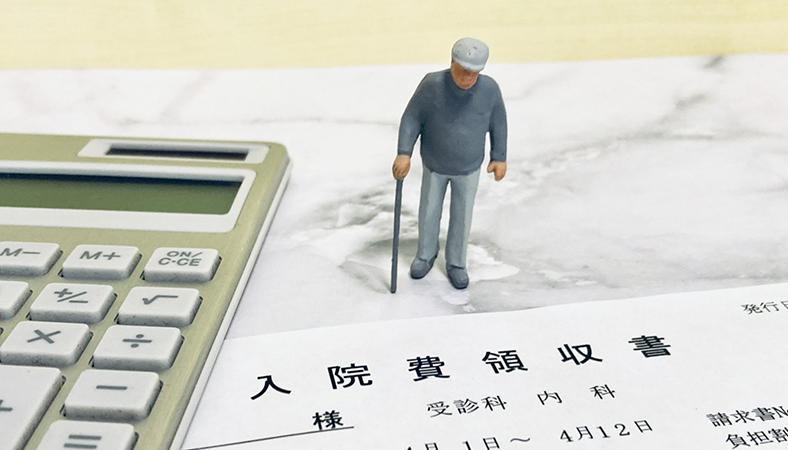会計事務所売却の成功ポイント|M&Aによる円満な事業承継とは?

会計事務所の多くが「後継者が見つからない」「人材不足が深刻」と、悩みを抱えているのではないでしょうか。特に高齢化が進む中、大切な事務所や従業員のほか、顧問先を守れなくなるかもしれません。
最近ではM&Aによる事業承継によってさまざまな課題を解決できることも増え、事務所を存続させるための選択肢として注目されています。この記事では、会計事務所のM&Aの動向やメリット、具体的な進め方などを解説しているため、廃業リスクを回避したい人は最後まで確認しましょう。
会計事務所の売り時とは?市場動向とM&Aの現状
近年、会計事務所業界では合併・買収などのM&Aが増加傾向です。背景として、業界が抱える「慢性的な人材不足」と「経営者の高齢化に伴う後継者問題」があります。特に、会計業務のIT化・DX化への対応、激化する競争環境など、単独での事業継続や成長に限界を感じる事務所が増えているからです。
ただし、いざ売却しようと考えても、すぐに成約につながるわけではありません。経営者が元気なうちに早めの準備を行い、少しでも有利な条件で取引ができるようにしておきましょう。
税理士業界の高齢化と後継者不足の現状
税理士業界が直面する深刻な課題の1つに、経営者の高齢化が挙げられます。日本税理士連合会の調査では、税理士の過半数が60歳以上であり、20〜30代は全体の1割強です。新規登録者が増えても高齢者の引退が止まらず、中長期的に見ても人材不足が深刻化する恐れがあるでしょう。
そのため、長年築き上げてきた顧客基盤やノウハウ、従業員の雇用を守れずに廃業を選択せざるを得ないケースもあります。ただし、M&Aを活用することで問題が解決できるため、多くの事務所が積極的に第三者への事業承継を検討し始めているのが現状です。
事業承継の選択肢としてM&Aが注目される理由
会計事務所にとって、M&Aは廃業を回避し、事業を存続させるための有効な選択肢です。税理士は、資格要件や業界全体の年齢構成からすると、優秀な後継者を親族や従業員から確保することが難しく、簡単に承継できるわけではありません。
一方、M&Aの場合は意欲の高い第三者へ引き継げます。買い手にとっても、顧客や人材を獲得する時間や労力を考えると、効率的に事業規模を拡大できるでしょう。
なぜM&Aが求められるのか?双方のメリットとは?
M&Aが求められる理由は、後継者探しや営業基盤を引き継げるだけではありません。双方にとって、明確なメリットがあることも大きな要因です。
例えば、売り手側では代表者自身のハッピーリタイアの実現も叶えられます。買い手は、即戦力となる有資格者や経験豊富なスタッフを獲得ができるなどの効果が期待できるでしょう。
売り手のメリット
売り手の最大のメリットは、多くの事務所が直面する「後継者問題」を解決できる点です。適任者不在のため廃業を考えていた事務所が、M&Aにより事業を継続できると、大事な顧問先を引き継げます。
仮に、大手や中堅の会計事務所グループに参画できると、経営基盤の強化や従業員の待遇改善、キャリアアップの機会創出にもつながります。また、M&A後も一定期間、顧問として関与するなど段階的な引退を選択できれば、経営者自身の精神的な負担も軽減されるでしょう。
買い手のメリット
買い手のメリットは「人材確保」と「顧客基盤」を同時に獲得できる点です。業界で採用難が続く中、経験豊富な税理士やスタッフを一気に獲得できるとサービス提供の質が向上できます。
また、新規で採用すると人材育成や見合うコストを解消できることも魅力です。自身にはない強みや専門分野を持つ事務所をM&Aできれば、さらなる相乗効果も期待できるでしょう。
仮に、地理的に異なるエリアに事務所がある場合、効率的な拠点の展開や広域でのサービス提供によって、事務所全体の競争力強化にもつながります。
どう進める?会計事務所M&Aの主な手法と流れ
M&Aを成功に導くために、まずは全体の流れや特有の手法(スキーム)について正しく理解することが求められます。一般的な株式会社のM&Aとは異なり、個人事業主が多い会計事務所では、事業譲渡が中心的な手法となるからです。
税理士法人の場合は、持分譲渡や合併も選択肢に入れておく必要があります。どの手法を選択するかは、譲渡対象の範囲、法人格の有無に加え、双方の意向によって進めていくことが大切です。専門家のアドバイスを受けながら、事前準備から交渉、契約、統合プロセス(PMI)まで、各ステップを着実に進めた上で確実に実現させましょう。
主なM&Aの方法や種類
会計事務所のM&Aには3パターンあり、ここでは特色を深堀りしていきます。
1.事業譲渡
個人経営の会計事務所で用いられる代表的な手法で、特定の顧問先やスタッフを始め、什器備品など必要なものだけを選定して譲渡できます。元の事務所を残しながらも、業務範囲を限定して資産整理を行える一方、従業員の雇用契約を再度結ぶ必要があり、個別の手続きが増えることに注意しましょう。
2.持分譲渡
税理士法人の手法で、出資持分を売買する形態で経営権を得られます。長年の運営によって蓄えられた利益が多いと、評価額が高騰するため買い手の資金調達が課題になるなど、譲渡前には評価額を減らす対策も必要です。
3.合併
税理士法人の場合に用いられるスキームで「吸収合併」と「新設合併」に分かれます。吸収合併の場合、既存の税理士法人が他法人を取り込みますが、新設合併は新たに設立した法人へ複数の法人が統合される手法です。
一度に資産や負債、契約関係をまとめて承継できるため、大手の税理士法人が小規模な複数の法人を吸収するときに利用されることが多いでしょう。
具体的なM&Aの流れ
具体的なM&Aの流れは以下の通りです。
1.事前準備とアドバイザー選定
譲渡時期や希望条件を話し合うとともに、M&Aをサポートする仲介会社やアドバイザーを選択します。決定後、自社の秘密情報を他社に開示する際に使用目的などを定める「秘密保持契約」を締結します。
2.譲渡先の探索
事務所の概要や希望条件を説明するとともに、先方の事業方針や財務力、拠点展開の考え方などを確認して候補を絞り込みます。
3.交渉と基本合意
候補先が見つかり次第、価格や雇用維持、顧問先の引き継ぎ方法などの条件を詰めた上で、基本合意書の締結です。合意後はデューデリジェンス(買収監査)に進み、実際のリスクや資産内容の調査に移ります。
4.最終契約とクロージング
デューデリジェンスの結果を踏まえ、価格や最終条件を再調整し、譲渡契約を結びます。契約締結後に譲渡代金を受け取り、資産や雇用契約などの移管が完了すれば終了です。
5.PMI(経営統合)
契約後も、顧問先やスタッフとの関係構築を円滑に進めるため、一定期間をかけて統合し始めます。円滑なPMIの実施は、離職や顧客流出を防げるため、M&Aの効果を最大化できるといえるでしょう。
いくらで売れる?会計事務所M&Aの価格相場と評価
会計事務所のM&Aを進めるにあたり、事務所の売却価格は重要なポイントです。基本的に「年間の顧問料」や「営業利益」が1つの目安ですが、顧問先の安定性や規模、将来性も考慮されるため一概には言えません。
また、優良顧客が多いほど評価額のアップにつながりやすく、普段から顧客満足度やスタッフのスキルアップを心がけることも重要です。
年間顧問料・売上高の〇倍?
個人が運営する会計事務所のM&A相場は「年間顧問料の1倍程度」や「営業利益の2〜3年分」です。例えば、年間の顧問料が2,000万円であれば同程度、年間の営業利益が500万円の場合は1,000〜1,500万円が相場でしょう。
会計事務所の収益は比較的安定しており、将来のキャッシュフローの予測が立てやすいため、顧問料や利益が目安になると考えられます。ただし、実際の評価額は専門性やIT化の進捗度も大きな要素であるため、専門家による詳細な評価を見て判断しましょう。
会社の価値を計算する具体的な方法
会計事務所の価値を計算する方法は「DCF法」「時価純資産法(修正純資産法)」「類似会社比較法(マルチプル法)」です。それぞれの評価方法について説明します。
1.DCF法
将来的に事務所が生み出すと予測されるフリーキャッシュフローについて、リスク等を考慮した割引率で現在価値に換算します。
2.時価純資産法(修正純資産法)
貸借対照表上の資産と負債を時価で評価し直し、差額を企業価値とする方法です。
3.類似会社比較法(マルチプル法)
上場している同業他社の株価や財務指標を参考に、評価する対象企業の価値を判定します。
これらの評価以外にも、交渉を通じて最終的な価格が決定されるのが一般的です。
より良い条件を引き出すには?
事務所を有利な条件で売却するためには「早期の決断」と「準備期間の確保」が必要です。自身が高齢となり体力的にも厳しくなると、余裕を持って交渉に掛ける時間を取れない可能性が高まります。
一方、特定の業種にかかる専門性の強化や高いITスキルを持つスタッフの育成など、価値向上に努めることも大切です。なお、所長や特定のスタッフに業務が偏り、過度に依存した状態は買い手のリスクとみなされます。業務マニュアルの整備、情報共有による体制強化も意識しておきましょう。
失敗しないための「M&A成功」のポイントと注意点
M&Aを成功させるメリットが大きい一方、予期せぬ問題に直面し、失敗に終わることもあり得ます。失敗を避けるには、情報管理の徹底や顧客・従業員への配慮に加え、信頼できる専門家の活用が大きなポイントです。
対応によっては交渉が決裂するだけでなく、従業員や顧客との想定外のリスクを被ることにもなりかねません。時間に余裕を持ち、交渉を重ねることで成約率を高めていきましょう。
情報が命!漏洩すると危険な落とし穴
M&Aの検討段階から、情報の取り扱いには細心の注意を払わなければなりません。交渉の過程で外部に情報が洩れると、従業員の離反や不安の高まる顧問先から信頼を欠くことで、契約解除を招く恐れがあるからです。
買い手は「情報管理もできない事務所」というネガティブな評価をする可能性も高く、交渉が打ち切られるリスクもあります。経営者や関与するアドバイザーは徹底した情報管理を図るとともに、細心の注意を払って進めなければなりません。
顧客・従業員が離れないための注意点
会計事務所における最大のリスクは、顧問先のケアです。税理士との取引は、信頼関係のもと契約が成り立っていることも多く、経営者の交代や事務所の統合は契約先を変更するリスクがあります。顧客離れを防ぐためには、M&Aの目的やメリット、サービスの維持・向上を説明し、スムーズな引き継ぎ体制を構築していきましょう。
また、従業員も自身の雇用条件や業務内容について、大きな不安が付きまといます。待遇面での配慮や丁寧なコミュニケーションによって不安を取り除くことで、新しい組織への円滑な統合を進めていかなければなりません。
信頼できる専門家(仲介会社等)の活用
会計事務所は「士業特有の規制」や「資格保有者の重要性」により、専門的な知識が必要です。数多くの専門家からパートナーを選ぶには、同業界でのM&A実績や経験の豊富さを意識しておきましょう。求められるのは「適切な相手先の選定」「客観的な企業価値の評価」「有利な条件での交渉」を任せられる担当です。
また、複雑な契約書類の作成支援、デューデリジェンスへの対応など、計画から実行までの全体のプロセスを通じたアドバイスも求められます。複数の専門家と面談し、実績、専門性、提供サービスの内容に加え、担当者との相性なども総合的に比較検討した上で、慎重に選定しましょう。
まとめ
経営者の高齢化や後継者不足が深刻な課題である会計事務所業界では、円滑な事業承継を行うためにM&Aを用いたスキームが増えています。例えば、売り手には円滑な事業承継や創業者のハッピーリタイアが期待できる一方、買い手には事業拡大や人材獲得などです。
M&Aを成功させるためにも、適切なスキームの選定や情報漏洩防止、顧客・従業員への徹底した配慮を行わなければなりません。会計業界に精通した専門家からサポートを受け、複雑な手続きや交渉を円滑に進められるよう、事前に準備しておくことが大切です。
早期の検討と具体的なアクションによって、円満な事業承継を築いていきましょう。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
税金・公共料金をスマホで簡単支払い!キャッシュレス納付の方法とお得な使い方
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説