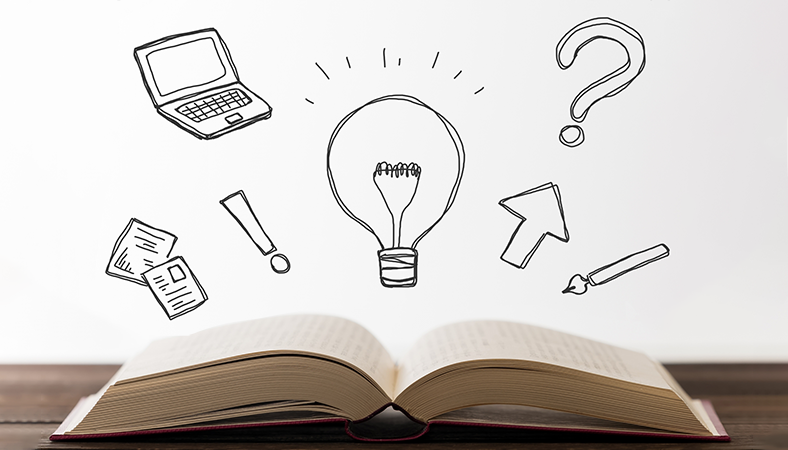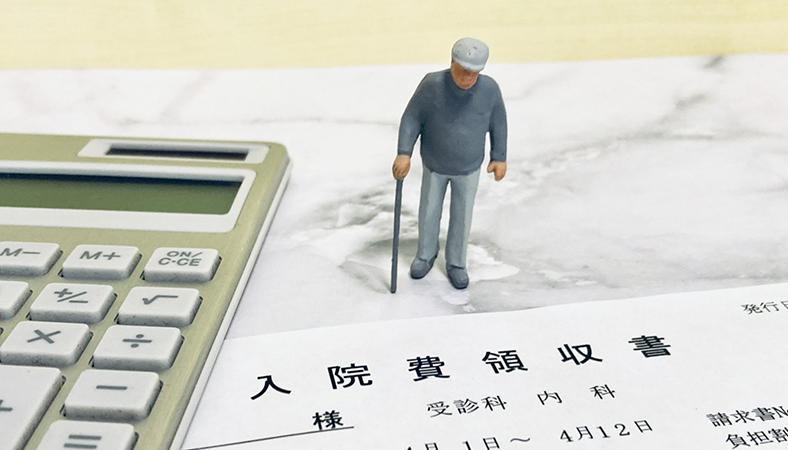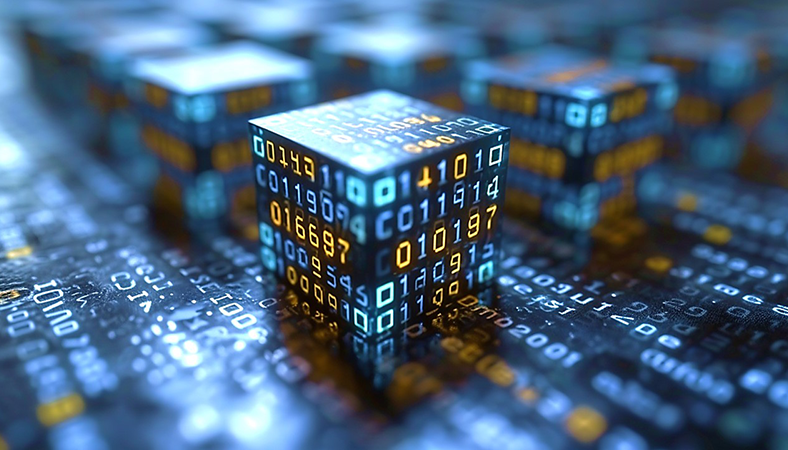税務調査が秋に増える理由とは?調査対象になりやすい企業の特徴と今からできる対策
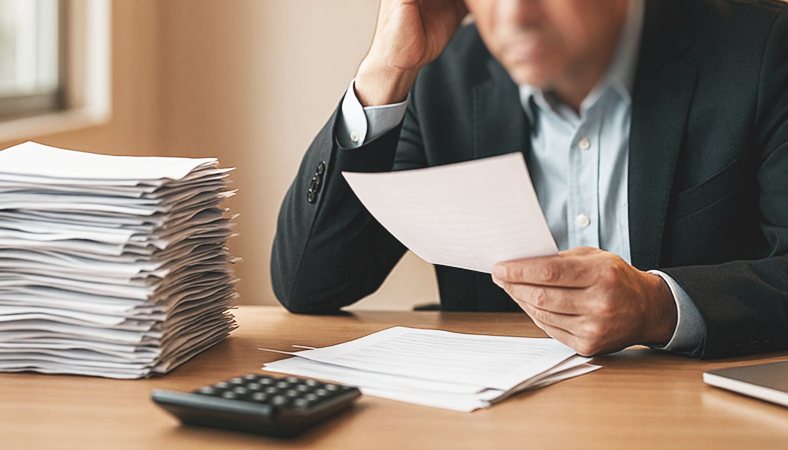

税務署の調査は、毎年9月から10月にかけて本格化すると言われています。特に売上や経費に変動があった企業や、帳簿管理に甘さが見られる企業は調査対象となりやすく、対応を誤ると追徴課税のリスクもあります。
本記事では、税務調査が増える時期的な背景から、調査対象になりやすい企業の特徴、そして今からできる備えや対応マナーまでを分かりやすく解説。中小企業経営者が秋に向けてやっておくべきことをまとめた、実践的なガイドです。
1. なぜ秋に税務調査が増えるのか?
「税務調査」と聞くと、いつ・どのタイミングでくるのか分からず、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。実は、税務調査が行われる時期には一定の傾向があり、特に「秋」は税務署がもっとも調査に力を入れる時期として知られています。
秋に集中する背景には、税務署の年間スケジュールや調査官の人事異動、さらには「成果重視」の体制が関係しているのです。秋に税務調査が増える理由を知っておくことで、必要な備えを早めに進められます。
この章では、税務署の内情を踏まえたうえで、なぜ秋に税務調査が増えるのかについて解説していきます。
税務署の「事務年度」が影響|7月〜翌年6月の運用スケジュール
7月〜8月は新しい年度のスタートにあたり、調査官は引き継ぎや調査対象の選定など準備に追われる時期となるのです。一方で、12月から翌年3月までは確定申告の繁忙期となり、調査活動が制限されることになります。
そのため、調査官が本格的に税務調査を行えるのは、9月から11月の秋の時期が中心となります。調査官には「増差額」と呼ばれる、一般企業でいうところの「ノルマ」があり、秋の調査で成果を出すことが昇進や評価に直結するため、調査にもっとも力が入るのです。
調査官の人事異動やノルマ消化が背景にあるケースも
税務調査官は7月10日に人事異動があるため、6月初旬までに担当している調査を終える必要があり、春の調査期間は実質的に3カ月弱と短くなります。さらに、1月〜3月は確定申告期間で調査が行いにくいため、春の調査は制限が多いのが実情です。
一方、秋の調査は最長で6カ月以上かけてじっくり調査できるケースが多く、調査官もじっくりと結果を出せるため、秋の調査は厳しく長期化しやすいのです。実際、秋の調査は、春の調査に比べて厳しさやペナルティの重さが増す傾向があります。
実際、税務署の年間計画と実績評価が強く影響していると思われるため、秋の調査は、春の調査に比べて厳しさやペナルティの重さが増す傾向があります。

税理士法人岡本会計事務所副所長 田邉 哲弥(税理士)
2. 税務調査に入りやすい会社の特徴とは?
税務調査は、すべての企業に等しく入るわけではありません。実際には、税務署が調査の必要性を判断した企業が優先的に対象となります。それでは、税務調査の対象としてどのような企業が選ばれやすいのでしょうか。
ここからは、税務調査のリスクが高まる企業の特徴を具体的に解説します。自社に当てはまる項目がないか、チェックしてみましょう。
売上の急増や、利益率の急変動がある会社
税務調査が入りやすい会社の代表例として、売上や利益の大きな変動がある会社が挙げられます。
これまで安定していた売上が突然急増した場合、税務署は「何か裏があるのではないか」と疑いを持ち、調査対象に選びやすくなります。売上が急激に伸びると、それに伴って申告漏れや不正がないかを詳しくチェックされる可能性が高くなるのです。
また、黒字の会社は追徴課税による税収増が見込めるため、赤字続きの会社よりも税務調査の対象になりやすい傾向にあります。売上に比べて利益の伸びが小さい、あるいは利益がほとんど変わっていない場合は、利益を過少申告している疑いを持たれやすくなります。
売上の増減や利益率の急激な変動は、税務署にとって疑念のもとになりやすく、調査のきっかけになりやすいのです。
売上や利益の急変動は調査対象になりやすいですが、「業種特有の季節変動」など正当な理由があれば、税理士法による書面添付制度などの事前説明でリスクを下げられる可能性はあります。

税理士法人岡本会計事務所副所長 田邉 哲弥(税理士)
赤字続きにもかかわらず設備投資を行っている
赤字が続いているにもかかわらず、多額の設備投資を行っている会社も税務調査の対象になりやすい傾向があります。通常、赤字企業は資金繰りに慎重になるため、大きな投資を控えることが多いものです。
それにもかかわらず、積極的に設備投資している場合、その資金の出所や経費の計上方法について税務署が詳しく調査を行う可能性が高くなります。
3. 事前にやっておくべき税務リスク対策チェックリスト
税務調査は、ある日突然やってくることも少なくありません。
調査官にとっては、普段どおりの業務や帳簿の管理状況が「その会社の本質」を映し出す材料となります。だからこそ、日頃からの備えが何より大切です。
ここでは、税務調査に備えて事前に見直しておきたいポイントを紹介します。日々の経理体制や税理士との関係、現金・貸付金の管理まで、今すぐ確認しておきたい実践的な対策をまとめています。
帳簿・領収書の整理整頓は基本中の基本
税務調査では、日々の記録がきちんと整理されているかがチェックされます。
売上帳・仕入帳・経費帳・在庫帳・現金出納帳など、帳簿は多岐にわたりますが、それぞれが正確に記入・保管されていることが大前提です。
帳簿だけでなく、請求書や領収書も整っている必要があります。調査官は、これらの書類から売上や経費の裏付けを取ることになるため、日時や金額、相手先などが正しく記載されていることが必要です。
税理士との定期的な相談・レビュー
税務の専門家である税理士は、税務リスクを最小限に抑えるための心強いパートナーです。
日頃から税理士に帳簿の内容を定期的に見てもらい、申告内容や経費処理に問題がないかを確認しておくことで、いざというときにも慌てずに対応できるでしょう。また、税務調査の際に税理士が立ち会ってくれると、調査官とのやり取りもスムーズに進みやすくなり、調査官の印象も良くなります。
税務調査と聞くと、「何か不正を疑われているのではないか」「高額な追徴課税を課されるのではないか」と不安になる方も少なくありません。
しかし、税務調査に入ったからといって必ずしも問題を指摘されるわけではありませんし、仮に修正すべき点が見つかったとしても、修正申告を行えば問題ないケースが多い傾向です。
意図的な不正がない限り、重い処分やペナルティを受けることは基本的にありませんので、過度に恐れる必要はありません。調査官からの質問には、できるだけスムーズに、落ち着いて答えるよう心がけましょう。
「あいまいな返事をする」「モゴモゴと自信なさげに答える」といった態度は、かえって疑念を招くことがあります。あらかじめよくある質問を税理士と共有しておいたり、気になる点があれば、事前に答えを整理しておいたりすると安心です。
万が一、その場で答えられない質問があったとしても、「確認のうえ、後ほど回答します」と正直に伝えれば問題ありません。税理士との信頼関係を築いておくことで、安心感が増し、調査への備えや対応の質が格段に高まります。
税理士への日々の相談を習慣にし、経理・申告内容に不明点があればその都度クリアにしておくことが、安心して秋の税務調査シーズンを迎えるための安心材料となるでしょう。
現金出納帳と貸付金の管理を徹底する
現金の流れや貸付金の管理があいまいな企業は、税務調査で特に目をつけられやすくなります。日々の出入りを記録する現金出納帳は、残高と実際の現金が一致しているかを確認するうえで重要な資料です。
また、貸付金がある場合には、それを明確にしておく必要があります。金銭のやりとりがあいまいだと、不正を疑われることもあるため、帳簿と証拠書類をそろえておくことが大切です。
4. 調査に入られたときの対応マナーとNG行動
税務調査の通知が届くと、多くの経営者が緊張を感じるものです。しかし、焦って対応を誤ると、調査官に不信感を与えてしまうおそれもあります。
税務調査は、調査官とのやり取りによって進められるため、その場での対応マナーや姿勢が調査の行方を左右する重要な要素です。
ここでは、調査に入られた際の対応のマナーとNG行動を整理してご紹介します。調査官と円滑にコミュニケーションを取るための基本的なマナーと、避けるべき行動を知っておけば、不要なトラブルを防ぐことにつながるでしょう。
税務調査官には冷静・丁寧に対応する
税務調査の通知が届いたら、まずは落ち着いて内容を確認しましょう。調査官からは、調査日・場所・対象となる税目や期間、提出すべき書類などが詳細に伝えられます。慌てて準備するのではなく、冷静に、かつ計画的に対応を進めることが大切です。
調査に必要な資料は、基本的に過去3年間分を提出するケースが多く、帳簿類や領収書、契約書などが含まれます。当日慌てることのないように、事前に準備をしておきましょう。
ただし、場合によって5〜7年間分をさかのぼるケースもあるため、必ずしも3年間分あれば良いというわけではない点には注意が必要です。
国税通則法第70条第5項において、偽りその他不正の行為がある場合(重加算税対象)は「7年」に延長されると規定されています。

税理士法人岡本会計事務所副所長 田邉 哲弥(税理士)
税理士がいる場合は、一緒に書類の確認や申告内容の見直しをしておくと安心です。不備やミスが見つかった場合でも、事前に修正申告することで、後からペナルティを受けるリスクを軽減できるため、必要以上に慌てないようにしましょう。
また、調査当日は、調査官が会社に来訪して実地調査を行うため、必要な書類はすぐに出せるように整理しておきましょう。質問には誠実に、丁寧に答える姿勢が重要です。
調査官も人間であるため、誠実で協力的に対応することで、好印象を持たれやすく、調査もスムーズに進みやすくなります。
「隠す・焦る・攻撃的になる」は絶対NG
税務調査において一番やってはいけないのが、隠し事をしたり、感情的に反応したりすることです。不審な点があった場合、正直に説明する姿勢が信頼につながります。
万が一、申告内容に誤りがあったとしても、誠実に対応することで調査官の印象は大きく変わります。
また、調査官との会話では、つい余計なことを話してしまいがちですが、聞かれていないことを積極的に話す必要はありません。特に、他社の噂話や批判などは不用意に話さないよう注意しましょう。
さらに、話の内容に一貫性があることも大切です。あらかじめ調査時に聞かれそうなことを想定・共有し、あいまいな記憶で受け答えしないように心がけましょう。
また、どのような調査官がきても、誠実な態度で向き合うことが一番です。税務調査は、日頃からの準備と冷静な対応によって、結果が大きく左右されるともいえるのです。
まとめ
税務調査は、秋の時期は調査件数が増える傾向にあり、企業経営者にとって決して他人事ではありません。税務署のスケジュールや調査官のノルマなど、調査が活発になる背景を理解しておくことで、早めの備えと心構えが可能になります。
また、売上や利益の急変動、赤字続きでの設備投資といった「税務署が注目しやすい特徴」に該当する企業は、特に注意が必要です。日々の帳簿整理や領収書の管理、現金・貸付金の記録といった、基本的な業務を丁寧に行うことが、調査リスクの軽減につながります。
秋の本格的な調査シーズンを前に、今一度、自社の経理体制や税務リスクを見直し、いつ見られても問題のない状態を整えておきましょう。日頃から体制を見直しておくことが、トラブルを未然に防ぎ、安心して事業に集中するための第一歩につながるはずです。
記事監修者 田邉税理士からのワンポイントアドバイス
税務調査は、税務署の事務年度や人事異動、調査官の成果目標などの要因から、毎年秋に件数が増える傾向があります。特に売上・利益の急変動や赤字での設備投資などは、調査対象として注目されやすい要素です。
日頃から正しい経理処理と証拠書類の整備を徹底していれば、税務調査がいつ来ても慌てる必要はありません。
日々の帳簿・領収書の整理整頓、税理士との定期的なレビュー、現金出納や貸付金管理の徹底など、基本的な経理体制を整えることが重要です。調査時には、冷静かつ誠実な対応を心がけ、不必要な発言や感情的な反応を避けることが、不要なトラブルを防ぐ最善策となります。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
ふるさと納税「ポイント還元」2025年9月30日で廃止へ!寄付者・自治体への影響と今後の活用法を解説
-
相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
-
防衛特別法人税とは?2026年4月から法人税に“1%の上乗せ”スタート
-
会社都合退職と自己都合退職の違いとは?失業保険の受給条件や給付制度について徹底解説
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
亡くなった人の口座は“凍結”される そのタイミングと解除する方法、注意点を解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
タクシーチケットの活用法とは?導入の流れや会計処理のポイント・注意点まで徹底解説!