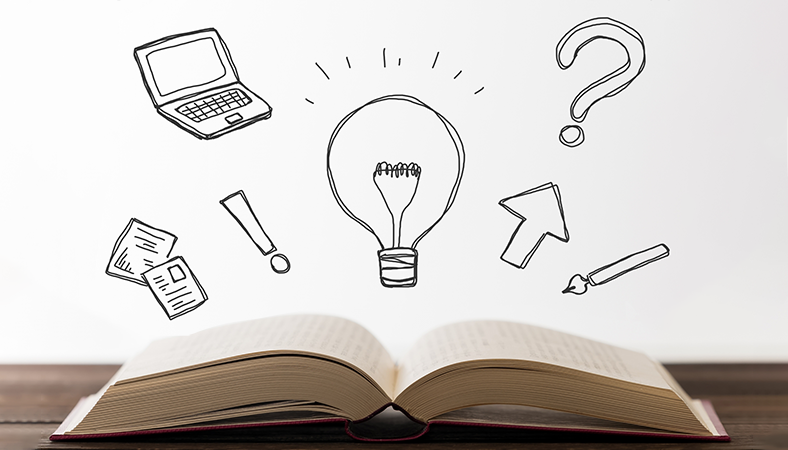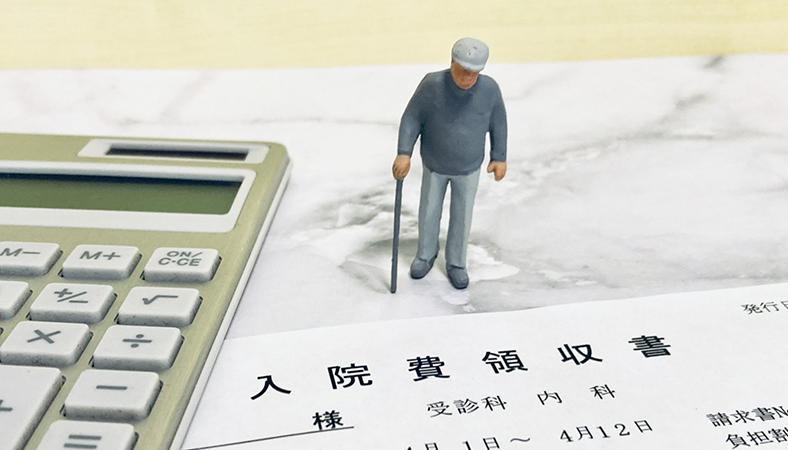【2025年版】ガソリン高騰!自動車に関する減税・節税策をわかりやすく解説

原油価格の高止まりやガソリン補助金の見直しにより、企業にとって車両コストはますます重くなっています。そのため自動車関連の減税や節税策が注目されています。この記事では、ガソリン価格の高騰背景にある政策動向や、業務用車両に関する減税制度・経費処理のコツを整理します。
1. ガソリン価格の現状と今後の見通し
ここ数年、ガソリン価格は大きく変動しています。日本では、輸入燃料の価格上昇がそのまま小売価格に反映されやすく、多くの事業者や一般消費者が負担増を実感しています。
燃料価格の高騰は、単なる日常生活のコスト増だけでなく、物流コストや製造コストを押し上げ、経済全体への影響が非常に大きなものです。
こうした背景を踏まえ、政府は国民や事業者の負担を軽減するための緊急対策として、燃料価格の急激な上昇による負担を和らげる補助金制度を設けていますが、その効果と課題についても注意が必要です。
ここでは、現在のガソリン価格がどのような状況にあるのかなどについて解説します。
補助金の段階的縮小と市場価格の影響
2025年5月22日より、政府は燃料価格の急激な上昇に対応するため、「燃料油価格激変緩和対策事業」を組み直し、定額の価格引き下げ措置を実施しており、ガソリン1リットルあたり10円を目安として、価格を引き下げることとしています。
しかし、この補助は段階的に適用されるため、価格がすぐに10円下がるわけではありません。在庫や流通などのタイムラグがあるため、実際の小売価格への反映には時間がかかり、徐々に反映されていくことでしょう。
給油のタイミングを見計らってガソリンスタンドに行列ができたり、在庫不足が生じたりといった混乱を防ぐためにも、消費者の冷静な対応が求められます。
政府は、経済産業省のSNSで情報を発信したり、全国のガソリンスタンドにポスターを掲示したりするなどして、この制度の周知に力を入れており、報道機関や一般の協力も呼びかけています。
業務用車両を多く使う業種への打撃
燃料価格の高騰は、特に運送業界など、業務車両を多く使う業種にとっては深刻な打撃です。ガソリンや軽油の価格が1円上がるだけでも、業界全体で年間150億円以上の負担増になるといわれています。
とりわけトラックを多用する運送事業者では、1台あたりの燃料消費量が一般車の100倍以上になるケースもあり、燃料費の上昇はそのまま経費増に直結します。大型車両ではエンジンの特性上、燃費がリッター2〜3キロ未満となることもあり、効率的な運転を心がけても限界があるのです。
しかし、燃料費の上昇分を運賃に上乗せできていない業者は多く、その背景には以下のような事情があります。
・価格交渉すれば、他社に仕事を取られてしまう恐れがある
・荷主企業側も物価高で経営が圧迫された状態である
・荷主との直接交渉が難しい立場にある
このように運賃交渉ができないままに、燃料高騰を受け入れざるを得ない運送業者も多く、なかには「荷物を運ぶほど赤字になる」という深刻な状況に直面しているケースも見受けられます。
2. 自動車関連の減税制度とは?
環境負荷の低減を目的としたグリーン化特例をはじめ、業務用車両の特別償却、さらには電動化・EV導入に対する優遇措置など、多様な制度が用意されています。これらの制度は、車両の種類や企業の規模、利用目的に応じて適用条件や効果が異なります。
適切に理解し活用することで、税負担の軽減につなげることが可能です。ここでは、自動車を使用する事業者が活用できる制度について詳しく解説します。それぞれの制度の仕組みやポイントを順に見ていきましょう。
グリーン化特例・重量税・取得税の仕組み
排出ガスや燃費の性能が優れている自動車については、その性能に応じて自動車税や軽自動車税が軽減されます。一方で、新車登録から一定の年数が経過した古い車は、自動車税や軽自動車税が重課されます。
自動車税のグリーン化特例は、環境性能に優れた自動車に対する税の軽減措置であり、自動車税および軽自動車税について、翌年度分の税額が軽減される制度です。
具体的には、電気自動車やプラグインハイブリッド車、燃料電池自動車、または天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)が対象になります。
対象となる自家用乗用車については、概ね75%の税額が軽減される仕組みです。また、現在の適用期間は、令和5年4月1日~令和8年3月31日です。
業務用車両の特別償却や減価償却のポイント
業務用車両の導入に際しては、「特別償却」または「税額控除」のいずれかを選択します。
ただし、同じ資産に対して両方の併用はできません。また、「税額控除」を適用できるのは資本金3,000万円以下の中小企業者等に限られ、それを超える場合は「特別償却」のみが対象となります。
「特別償却」は、減価償却費を前倒しして計上できる制度です。たとえば、30%のため(1,000万円の場合は300万円)、取得価額1,000万円の資産について、300万円を特別償却として前倒しした計上が可能であり、月割計算が不要なため、決算直前の上乗せ計上もできます。
一方、「税額控除」は、法人税そのものを直接減額できる仕組みであり、対象資産の7%のため(1,000万円に対しては70万円)、取得価額1,000万円の資産に対して最大70万円の法人税控除が可能です。法人税額の20%が控除限度ですが、使い切れなかった分は翌年度に繰り越すことも可能です。
さらに、通常の減価償却も併用できるため、一般的には税額控除の方が有利となる傾向があります。ただし、赤字や繰越欠損金の影響で法人税が発生しない場合は、税額控除の恩恵を受けられないため、事前にシミュレーションを行い、会社の状況に応じて適切な制度を選択することが重要です。
電動化・EV導入で受けられる優遇措置
環境負荷の低い車両への転換を後押しするため、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」が設けられています。運輸部門は日本のCO₂排出量の約2割を占めており、そのうちの約9割が自動車分野によるものです。
2050年カーボンニュートラル実現のためには、環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車の普及が重要なポイントとなるでしょう。この補助制度では、こうした電気自動車などの導入費用の一部を補助し、初期需要の創出と量産効果による価格低減を促進します。
また、V2H充放電設備など、家庭用機器の購入費・工事費も補助対象です。このような支援策により、企業の生産設備や研究開発への投資を後押ししながら、産業競争力強化とCO2の排出削減を両立することが目的とされています。
参照:令和6年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」
3. 日々の運用でできる「車両コストの節税術」
事業における車両コストは、経費の中でも大きな割合を占めることが多く、効率的な節税対策が重要です。適切な経理処理と管理を心がけることで、税務上のリスクを回避しつつ、車両関連コストを最大限に抑えることが可能です。
ここでは、日常的なガソリン代の経費処理のポイントから、車両管理の記録の付け方、さらにリースと購入の選択による費用化の違いなど、車両コストの節税術を解説します。
車両コストによる負担を軽減するために、具体的な方法を確認していきましょう。
ガソリン代の経費処理と支払いルール
ガソリン代を事業経費として計上する際には、車両費や燃料費、旅費交通費など、適切な勘定科目を選びます。その際、一度使った勘定科目は途中で変更せず、継続して使う統一することが、会計処理の整合性を保つポイントです。重要です。
これは、途中で科目を変えると、会計処理の信頼性が低下する恐れがあるためです。ガソリン代を経費に含めるためには、事業用の支払いであることを明確にし、領収書やレシートは保存しておきましょう。
また、もし自家用車を事業用とプライベート用の併用としている場合には、プライベートで使用した分は除外し、事業用の使用割合に応じて経費を按分する必要があります。
車両管理簿・走行距離・目的別利用の記録
節税を効果的に行うためには、日々の車両利用状況を詳細に記録しておくことが重要です。車両管理簿を用いて走行距離や利用目的を記録し、事業用とプライベート用の区分を明確にしておく必要があります。
事業用の車両にかかわる費用は、支出の内容によって適切な勘定科目が異なるため、車両費の複数のパターンを理解し、状況に応じて使い分けられるようにしておくことが重要です。
たとえば個人事業主の場合であれば、車両費を経費に計上する際は原則として家事按分が必要となります。その場合、合理的な基準に基づいて事業用とプライベート用の使用割合を算出しなければなりません。
そのため、按分の根拠となる運転記録などをしっかり残し、明確な証拠を用意しておくことが大切なのです。これにより税務調査への対応もスムーズになり、より確実な節税対策が可能になるでしょう。
リース vs 購入、費用化の違いに注意
カーリースと車両の購入、それぞれの方法には特徴があり、状況によってどちらがお得かが変わります。まず「購入」が向いているのは、走行距離が長く車の劣化が早くなると予想される事業者です。
購入した場合、車両返却時に追加料金が発生しないため、長距離利用が多い業種にはメリットがあるでしょう。また、資金に余裕がある事業者も購入がおすすめです。自己資金で購入すれば総支払額が抑えられるうえ、管理部門や経理部門が充実している場合は、管理コストを社内でまかなえるため、余分なキャッシュアウトが不要になります。
一方、「カーリース」が適しているのは、営業車など利用頻度や走行距離をあらかじめ計画できる事業者です。リースでは返却時に追加料金が発生するリスクがあるため、利用計画が立てやすい場合にはメリットがあるといえるでしょう。
また、資金的に余裕のない事業者は、まとまった資金を用意せずに合理的な月額料金で車を利用できるため、経済的な負担を軽減できます。さらに、車両管理業務に人手や時間を割けない事業者にとっては、メンテナンスリースの活用により管理業務を代行してもらえる点が大きな魅力です。
このように、事業や資金の状況に応じてリースか購入かを選ぶことが、節税効果や経費管理の最適化につながっていくのです。
まとめ
ガソリン価格の高騰が続く中、車両に関する税制・経費処理の見直しは企業のコスト管理に直結します。制度を正しく知り、活用できるところは活用して、無理のない節税を積み重ねていくことがカギです。
節税策は無理なく続けられる範囲で行うことが重要であり、日々の経費処理や活用制度の見直しが負担軽減につながっていきます。社内の経理体制の強化や社員への周知徹底も、効果的な節税対策には欠かせないポイントです。
今後も最新の税制情報にアンテナを張りつつ、必要に応じて専門家のアドバイスを取り入れるなど、賢く対策を進めていきましょう。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
税金・公共料金をスマホで簡単支払い!キャッシュレス納付の方法とお得な使い方
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説