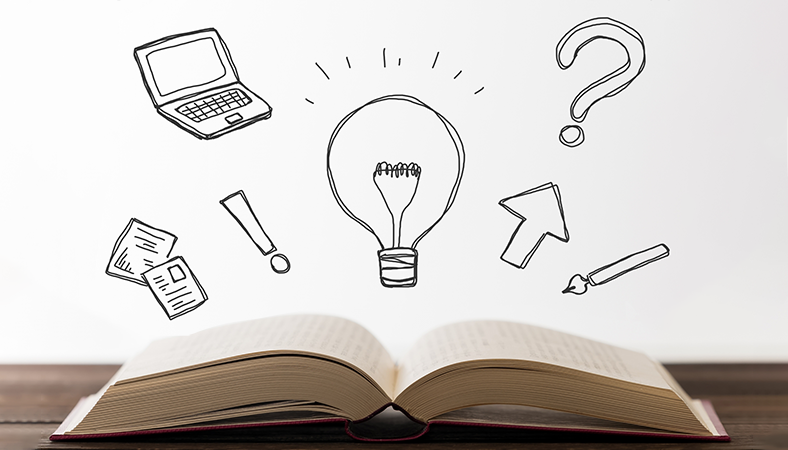【2025年参院選】選挙運動のやり方とルールを徹底解説!NG行為とは?

選挙が近づくと、街頭演説や選挙カー、SNSでの発信など、候補者による「選挙運動」が活発になります。しかし、何ができて、何が禁止されているのかは意外に知られていません。この記事では、2025年参院選における選挙運動の方法・ルール・注意点をわかりやすく解説します。
1. 「選挙運動」とは?定義と期間の基本
「選挙運動」や「政治活動」といった言葉を耳にすることもあるのではないでしょうか。しかし、それぞれの違いや、いつから何ができるのかといったルールについては曖昧なままにされがちです。
ここでは、公職選挙法に基づく選挙運動期間や違い、注意すべき点について解説します。
選挙運動はいつからいつまで?公示日から投票日前日まで
「選挙運動」は、公示日(告示日)に立候補を正式に届け出てから、投票日の前日までに限られています。たとえば、参議院議員選挙の場合、選挙運動期間は17日間です。
立候補届け出前などの選挙運動期間外に投票を呼びかけるような行為は「事前運動」とされ、法律で禁じられています。また、選挙期日は選挙運動に含まれないため、その点にも注意が必要です。
選挙運動と政治活動の違いとは?
「政治活動」とは、政治的な目的を持って行われる活動のことで、そのうち選挙運動にかかわる行為を除いたものを指します。
一方で「選挙運動」は、特定の選挙において、特定の候補者を当選させることを目的に、有権者へ投票を促す行為です。選挙運動は政治活動の一部に見えますが、公職選挙法上はこれらを明確に区別しています。
未成年者や企業が選挙運動できない理由
現在、日本では18歳以上が有権者として選挙に参加できますが、選挙運動に関しても年齢などによって制限が設けられています。まず18歳未満の未成年者は、選挙運動を行うこと自体が禁止です。
これは、公職選挙法によって定められており、違反した場合には、罰金や拘禁刑が科される可能性があります。さらに、違反者は一定期間、選挙権や被選挙権が停止されることになるため、注意が必要です。
また、特定の立場にある人々や団体も選挙運動を禁じられています。たとえば、選挙事務に関わる職員や裁判官、警察官などの「特定公務員」などの選挙運動は制限されています。
2. 街頭演説・選挙カーなど“アナログな選挙運動”
選挙期間中、街頭演説や選挙カーなどのアナログな選挙運動は、デジタル化しつつある現代でも根強く用いられています。ただし、これらの活動には法律で細かいルールが定められています。ここからは、それらのルールについて詳しく見ていきましょう。
拡声器・街宣車の使用時間・音量制限は?
選挙運動期間中、選挙カーに拡声器を設置して呼びかける行為、また街頭での演説は、公職選挙法で認められています。
ただし、活動が認められるのは午前8時から午後8時までの時間帯に限定されたものです。また、音量については法律で明確な上限が定められているわけではありませんが、学校・病院・療養施設等の周辺では静穏保持に努めることとされており、周囲の環境に応じた節度ある使用が求められています。
うるさいと感じる場面があっても、違法であるとは限らないことを理解しておく必要があるでしょう。こうしたアナログでの活動は、デジタルが主流になった現代においても、候補者が直接有権者に訴えかける手段として重視されているのです。
ビラ・ポスター・のぼりの使用条件と制限枚数
街頭演説に伴って使用されるのぼり旗や看板、ポスターにもさまざまな規制があります。
のぼり旗については、政党名やキャッチフレーズなどを記載することは可能ですが、候補者の顔写真や氏名を記載するのは原則として禁止です。ただし、弁士の掲載という形式であれば、顔写真入りの掲示物も一部認められるケースがあります。
これらの掲示物を使用できるのは、定められた期間のみに限られています。それ以前に使用すれば、「事前運動」として、違法とみなされるおそれがあり、注意が必要です。
また、設置場所にも厳格な規定があり、道路や信号、標識やガードレール、公共施設の周辺、自然保護区、私有地への無断設置は禁止です。消火栓や交通標識を妨げるような場所も、設置不可とされています。
さらに、自治体によってはのぼり旗の高さに関する制限もあり、高さ2メートル以下に制限されている場合があります。このように掲示物は、要件を満たしていない場合には認められないことがあり、細心の注意が求められるのです。
演説会や握手・チラシ配布はどこまでOK?
選挙期間中に候補者が行うチラシ配布や握手、演説会などの対面型の活動には厳密なルールがあります。
まず、選挙チラシの配布は、公示・告示日から投票日前日までの間に限って認められており、その方法として挙げられるのは新聞折込や街頭での配布です。これらには配布枚数や証紙の貼付、印刷者・頒布責任者の記載といった細かい規定が設けられています。
一方、告示日前には「選挙運動」は認められていません。しかし、政治活動としてビラの配布や握手、街頭演説を行うことは可能です。ただし、これらはあくまで選挙活動ではないという位置づけであるため、「立候補予定」など選挙の事前運動とみなされるような呼びかけは禁じられています。
名前の入っていないタスキをかけて駅前でビラを配る人や、後援会入会リーフレットを持って有権者の家を訪問する人の姿も見られますが、こうした活動は、政治活動として認められているものなのです。
このように、選挙期間外であっても、政治活動としてできることは意外に多く存在します。候補者が法律に抵触せずに認知度や支持を高めていくためには、こうした政治活動を丁寧に積み重ねていくことが重要なのです。
3. SNS・ネット選挙運動のルールと可能性
スマートフォン一つで情報発信ができる現代では、SNSや動画配信サービスを使った「ネット選挙運動」が一般的になりつつあります。しかし「ネット選挙運動」は、SNSなどを通じて気軽に情報が発信できるというメリットの裏に、リスクも隠れているものです。
ここからは、ネット選挙運動のルールや可能性について、詳しく整理していきます。
Instagram・X(旧Twitter)・YouTubeは使える?
現代においては、インターネットを利用した方法で選挙運動を行うことが認められています。たとえば、Instagram、X(旧Twitter)、YouTubeといったSNSや動画配信サービスを使って発信することが可能になりました。
ただし、電子メールを使った選挙運動は除かれます。「インターネット等を利用する方法」としては、具体的にインターネットのほか、社内LANや赤外線通信などの方法も含まれます。
このようなツールの活用によって、より多くの人が政治に関心を持ちやすくなりますが、定められた範囲内で正しく使うことが前提です。
候補者・政党・有権者ができること・できないこと
候補者や政党は、選挙期間中にブログやSNS、ホームページで政策や考えを広く発信することが可能になりました。これに伴い有権者も、自分の意見を発信したり、候補者の投稿を拡散したりできるようになりました。
ただし、有権者が候補者から受け取ったメールを転送するなど、電子メールを使った行為は、原則として禁止されています。また、未成年者は選挙運動が認められていないため、SNSでの発信を含め注意が必要です。
情報発信の自由度が高くなった分、ルールを理解した上で責任を持って発信する姿勢が求められます。
誤情報・なりすまし・誹謗中傷のリスクと対策
インターネットを使った選挙運動が可能になったことで、情報発信の自由度は高まりましたが、その一方で、誤情報やなりすまし、誹謗中傷といった問題にも注意が必要になりました。
法律では、こうした行為を禁じており、違反すれば処罰の対象となります。まず、候補者について虚偽の情報を公開することは決してしてはいけません。特定の候補者を当選させない目的で、事実に反する情報を広めたり、事実を歪めて発信したりした場合、公職選挙法により処罰される可能性があります。
また、インターネット上で他人の氏名や肩書などを偽って情報発信する「なりすまし」も禁止されており、これも処罰の対象です。当選させる目的であろうと、当選させない目的であろうと、同様に禁止されているものです。
さらに、悪意のある誹謗中傷も禁止されています。たとえ事実であっても、それを公然と明らかにして相手の名誉を傷つけた場合、処罰されることがあります。また、事実を明らかにしなくても、公然と相手を侮辱する行為は侮辱罪に問われる可能性があるため注意しましょう。
SNSやブログ、動画などで発信する際には、内容が事実に基づいているか、相手の名誉を不当に傷つけていないかを冷静に判断することが必要です。自由の裏には重い責任が伴うことを、常に意識しておきましょう。
4. 「違反にならない応援のしかた」と注意点
選挙期間中やその前後に、候補者を応援したくなる人も多いでしょう。しかし、選挙運動には法律で定められたルールがあり、違反すると罰則を受ける可能性があります。ここでは、違反にならない応援の方法と注意点、実際にあった違反事例などについて解説します。
個人での応援・シェア・リツイートは原則OK
インターネットを利用した応援や情報のシェアは、個人であれば基本的に可能です。しかし、どのような場合でも自由というわけではありません。特に注意が必要なのは、18歳未満の方による選挙運動は法律で禁止されているという点です。
18歳未満の方が以下のような行動を取ると、法律違反となるおそれがあります。
-
候補者を応援するメッセージをSNSや掲示板、ブログに書き込む
-
候補者の選挙運動の様子を動画サイトに投稿する
-
他人の選挙運動メッセージをリツイートやシェアで広める
-
選挙用のメールを受け取り、それを転送する(これは成人でも禁止)
選挙期間中にやってはいけないNG行動例
「〇〇候補に一票を」「△△党と書いてください」といった特定の候補者や政党に対する呼びかけは、選挙運動と呼ばれるもので、法律で認められた行為です。ただし、選挙運動が許されるのは、公示日から選挙前日までの限られた期間のみとなっています。
特に注意が必要なのは選挙当日です。この日は、候補者や一般の有権者を問わず、選挙運動が禁止されています。違反した場合には、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金が科されるおそれがあり、一定期間選挙権や被選挙権が停止されるという重大な結果にもつながりかねません。
なお、「投票に行こう」といった選挙参加を呼びかける表現には問題ありません。
公職選挙法違反になるとどうなる?罰則と実例
公職選挙法に違反すると、個人だけでなく、候補者や政党にも重大な影響があります。
以下に、実際に起きた事例を紹介します。
-
元衆議院議員が、投票を呼びかけるための選挙はがきとあて名書きの依頼文を母校卒業生宛に送ったことで、これが選挙運動とみなされ、罰金30万円の有罪判決を受けました。
-
現職国会議員がIR事業をめぐって海外企業から金銭を受け取り、組織犯罪処罰法違反で実刑判決となっています。
-
元経済産業大臣が東京都練馬区の有権者に香典や枕花などを渡し、罰金40万円と公民権停止3年の略式命令を受けました。
-
元法務大臣が妻の当選を目的に、地方議員100人に計2871万円を配布し、懲役3年と追徴金130万円の判決が下され、関係した地方議員全員が起訴されています。
このように、選挙に関する違法行為には、厳しい取り締まりがあります。一般の有権者も、自分が行おうとしている行動が法律に抵触しないか、常に確認することが大切です。
まとめ
選挙運動は「ただうるさいもの」ではなく、候補者と有権者がつながる貴重な場です。正しいルールのもとで行われる選挙運動は、私たちの知る権利や選ぶ自由を支える存在でもあります。ルールを理解して、フェアな選挙に参加しましょう。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
相続税がゼロ・申告不要でも要注意!必要になるお金の手続きについて解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
税金・公共料金をスマホで簡単支払い!キャッシュレス納付の方法とお得な使い方
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説