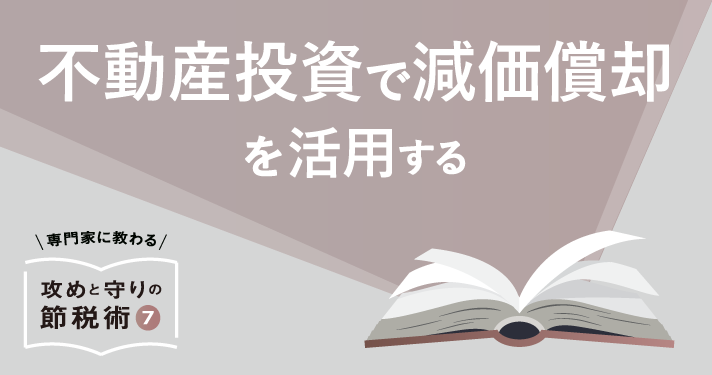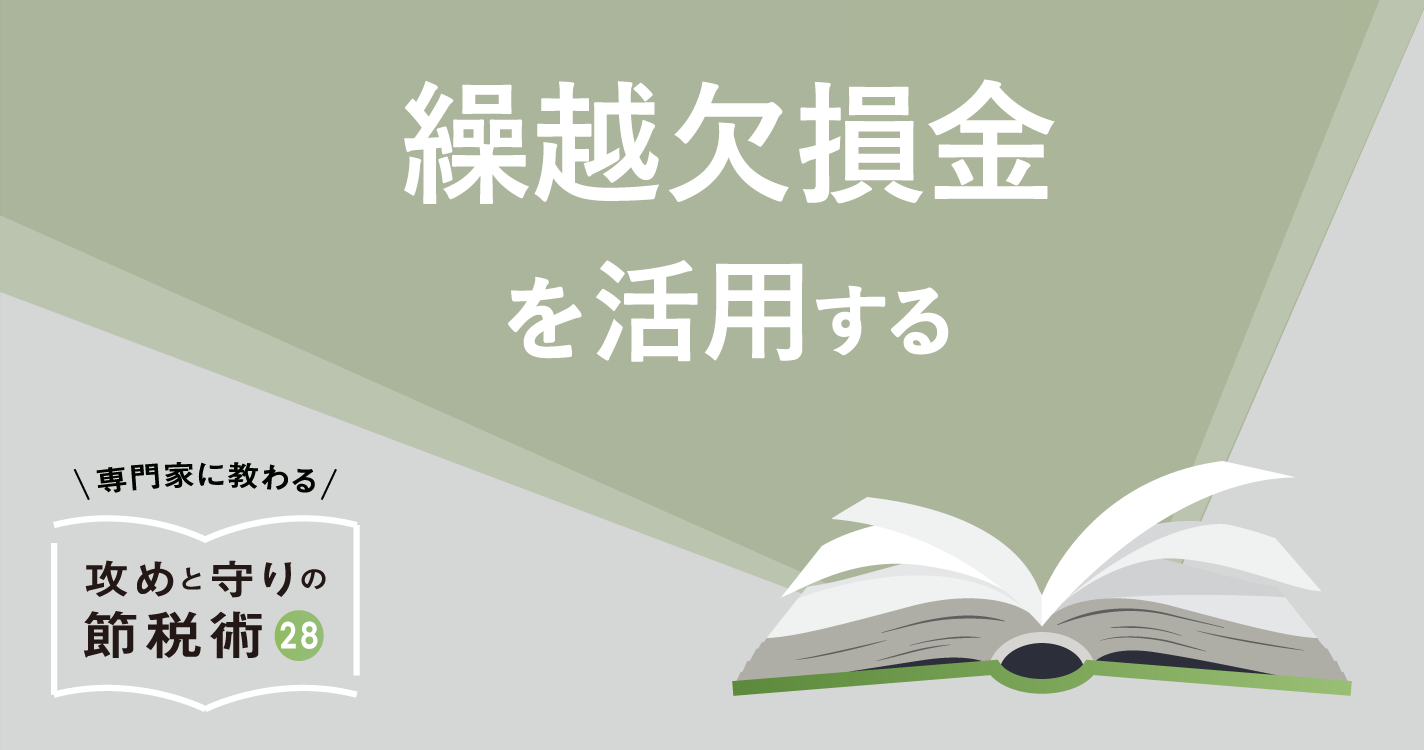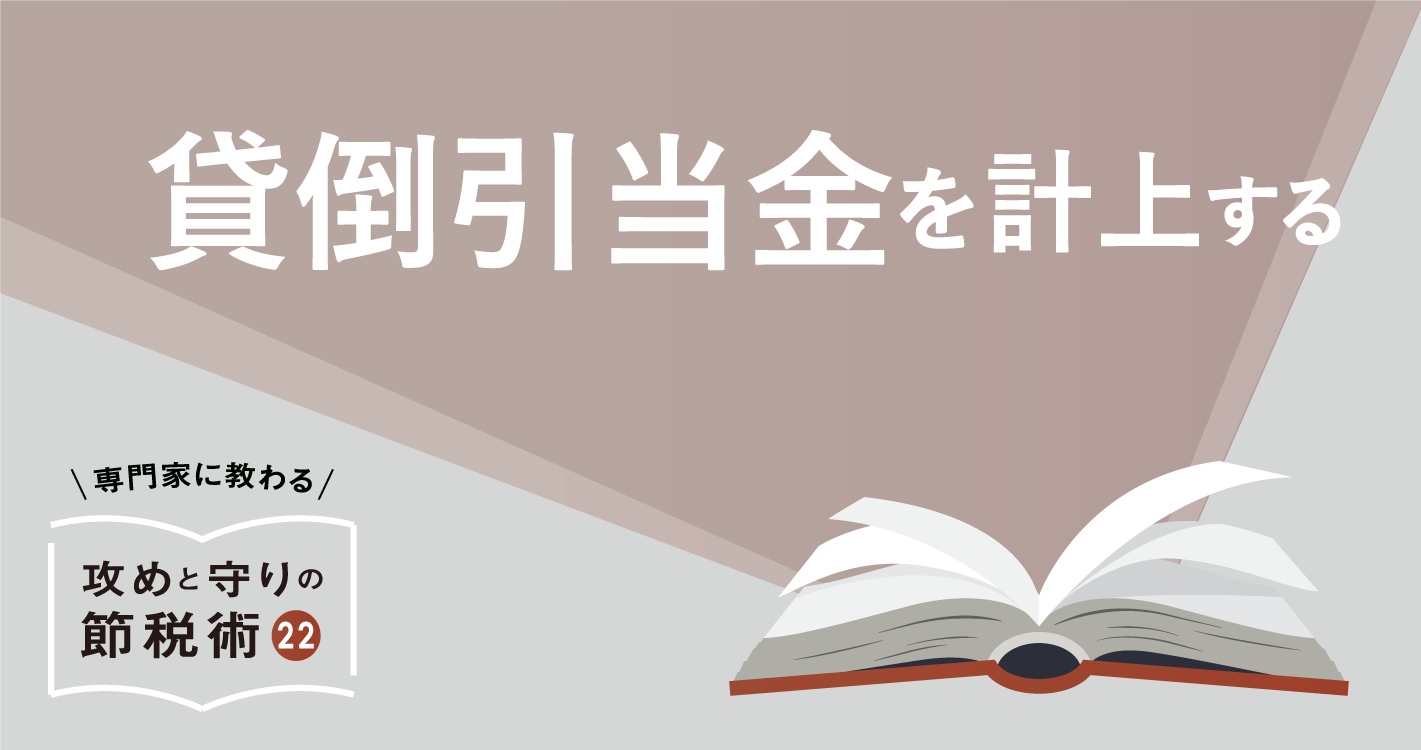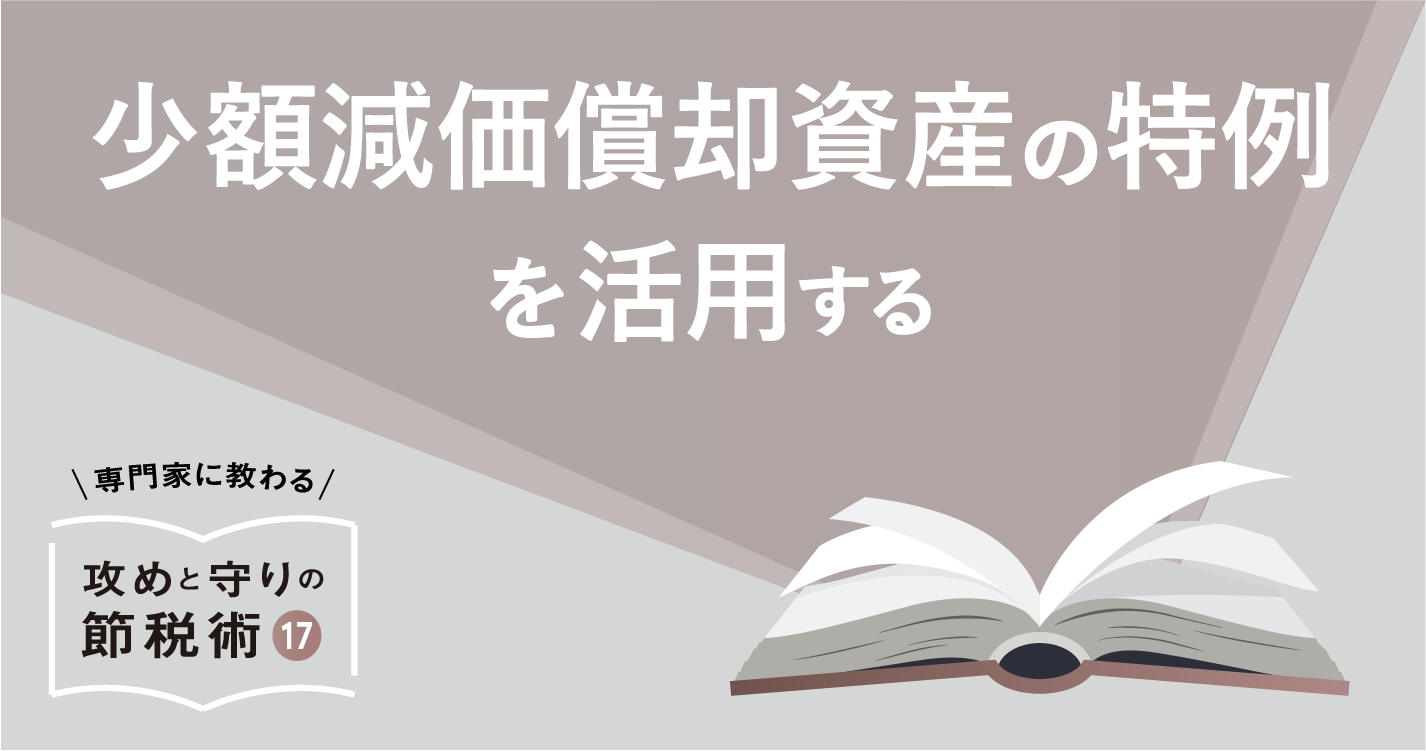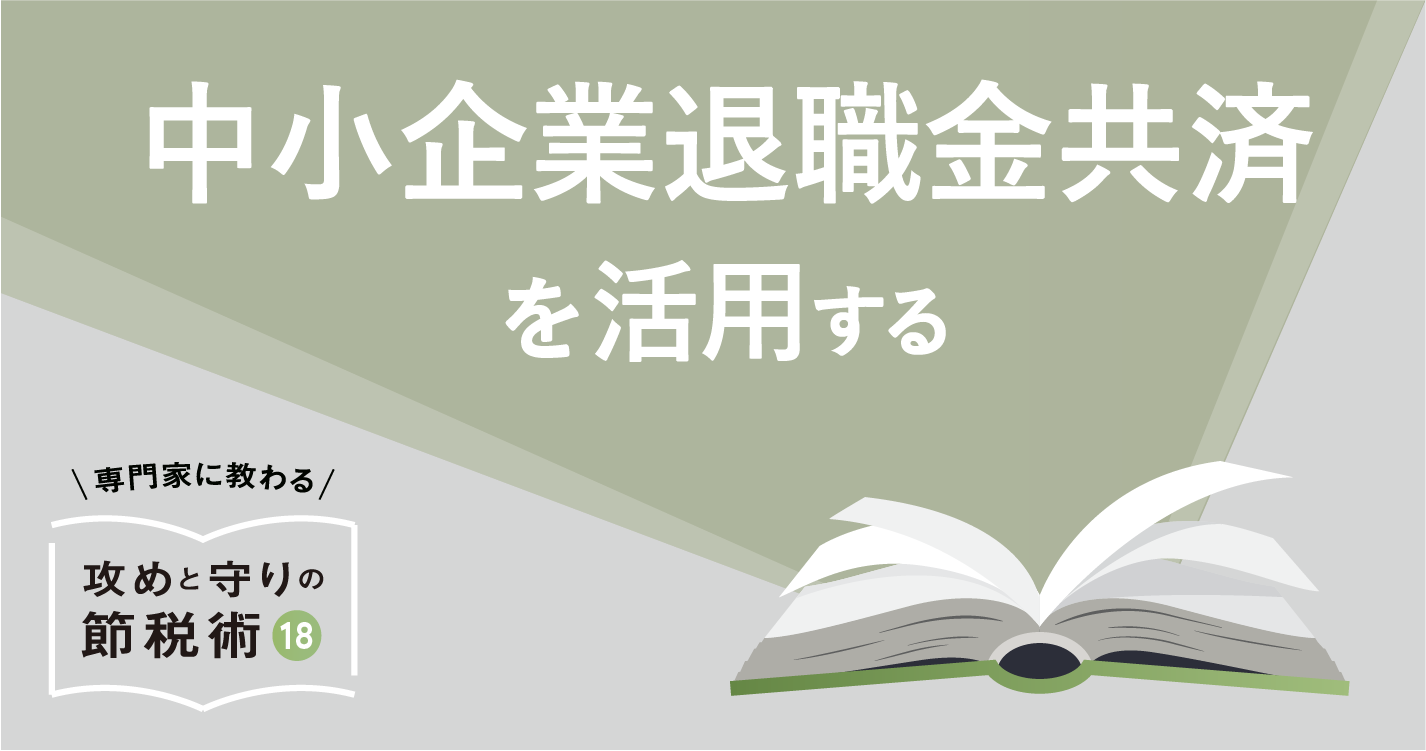
「中小企業退職金共済(中退共)を活用する」
という節税術
中小企業の経営者にとって、従業員の退職金制度をどのように整備するかは重要な課題のひとつです。しかし、自社独自で制度を構築・運営するのは負担が大きく、コストや運用のリスクも伴います。そこで注目されているのが「中小企業退職金共済制度(中退共)」です。
中退共は、国が運営する外部積立型の退職金制度で、掛金が全額損金算入できることから「節税しながら福利厚生も充実させられる」制度として、多くの中小企業に利用されています。
この記事では、中退共とは何か、その節税メリット、注意点、そして制度を導入する際の心構えまでをわかりやすく解説します。
中退共は、経営者や役員は加入できませんが、従業員の退職金準備と企業の節税を両立できる大変便利な制度です。会社の未来を担う従業員の定着率向上と健全な経営の両方を支える制度として、ぜひご検討をお勧めします。 (白兼公認会計士・税理士事務所 代表 白兼 道夫)
中小企業退職金共済(中退共)とは?
まずは、中小企業退職金共済(中退共)の仕組みと対象企業について、基本的な内容を押さえておきましょう。
制度の概要と対象となる企業・従業員
中小企業退職金共済制度(中退共)は、独立行政法人「勤労者退職金共済機構」が運営する、中小企業向けの外部積立型退職金制度です。主に中小企業が従業員の退職金を外部に積み立てる目的で利用されており、掛金は毎月企業側が負担します。
対象となるのは、以下のいずれかの条件を満たす一定規模以下の中小企業です。
常時使用する従業員数が一定以下の法人・個人事業主
例:製造業・建設業は300人以下、卸売業は100人以下、小売業は50人以下 など
資本金または出資金が一定以下の法人
例:製造業・建設業は3億円以下、卸売業は1億円以下、小売業は5,000万円以下 など
従業員1人につき、月額5,000〜30,000円の範囲で掛金を設定でき、パートタイマーは月額2,000〜4,000円での設定が可能です。掛金はすべて会社が負担し、従業員は退職時に直接中退共から退職金を受け取ります。
中退共と他の退職金制度との違い
多くの企業では、独自の退職一時金制度を設けるか、確定給付企業年金制度(DB)や企業型確定拠出年金制度(DC)などを活用しています。
これらの制度と比較した中退共の最大の違いは、「制度の設計・運用が非常に簡単であり、すべて国が管理してくれる安心感」にあります。中退共の主なメリットは以下のとおりです。
・企業側の運用負担が少ない
毎月掛金を納付するだけで、退職金の積立や運用に関する複雑な業務や運営コストは発生しません。
・給付計算と支給は中退共が担当
従業員の在籍期間や掛金額に応じた退職金を中退共が算定し、直接従業員に支給します。
・退職金の支払いリスクを軽減
給付が従業員に直接支払われるため、企業が将来の退職金支払いのために現金を確保しておくリスクが大幅に軽減されます。
このシンプルな仕組みによって、経営者は複雑な運用管理や将来の退職金原資の確保に悩むことなく、手軽に充実した退職金制度を構築・運営できます。
中小企業退職金共済(中退共)を活用する節税メリット
中退共は退職金制度として優れているだけでなく、企業にとってはさまざまな節税効果も期待できます。ここでは具体的な節税メリットを見ていきましょう。
節税メリット1 掛金を全額損金算入できる
中退共の最大の魅力は、掛金が全額損金(個人事業主であれば必要経費)として認められることです。安心して経費処理ができ、税務署に否認されるリスクもありません。
例えば、1人あたり月額3万円の掛金を10人分支払うと、以下のように年間で360万円を損金計上できます。
3万円×10人×12ヵ月 = 360万円
これにより、課税所得が360万円減るため、実質的に法人税や地方法人税の負担を軽減できるのです。
節税メリット2 退職金受取時に税制優遇がある
従業員が退職金を受け取る際には、「退職所得」として扱われ、給与所得とは異なる優遇税制が適用されます。特に「退職所得控除」や「1/2課税」により、同じ金額を給与で受け取る場合と比べて、手取り額が大きくなります。
これは従業員にとってもメリットが大きく、結果として会社の福利厚生制度に対する満足度向上にもつながるでしょう。
節税メリット3 社会保険料への影響がない
従業員への退職金準備として、もし給与の一部を原資に充てた場合には、その「給与」に対して厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料が発生します。企業はこれらの保険料の半分を負担しなければなりません。
しかし、中退共の掛金は給与や賞与とは異なり「福利厚生費」として扱われるため、社会保険料(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険など)の算定対象にはなりません。
つまり中退共を活用すれば、損金算入によって法人税が軽減されるだけでなく、社会保険料という固定費の増加も抑えられるのです。
これは人件費全体の最適化につながる、非常に重要な間接的効果といえるでしょう。
特に従業員数の多い企業にとっては、この社会保険料の負担軽減効果は無視できないメリットです。
節税メリット4 国からの掛金助成制度がある
中退共には、新規に加入する中小企業や、既に加入している企業が掛金を増額する場合に、国が掛金の一部を助成してくれる制度があります。これは、導入時の初期費用の負担を軽減し、制度の継続を後押しするためのものです。
この助成制度は、直接的な「節税」ではなく、実質的な「費用負担の軽減」といえるでしょう。とはいえ、企業のキャッシュフローにとっては大きなメリットです。
具体的な助成内容は以下のとおりです。
・新規加入掛金助成
中退共に新たに加入する企業に対し、加入後4ヵ月目から1年間、掛金月額の2分の1(上限5,000円/人)を国が助成します。
(例)月額1万円の掛金を設定した場合:
国が5,000円を助成するため、企業の実質負担は5,000円になります。
※短時間労働者向けの「特例掛金」(月額4,000円以下)には、さらに上乗せ助成があります。
・月額変更(増額)助成
掛金月額が1万8,000円以下の従業員に対して掛金を増額する場合、増額分の3分の1が1年間助成されます。
これらの助成制度を上手に活用すれば、初期コストを抑えながら退職金制度を整備できるため、特に導入を検討している企業にとっては非常に魅力的な支援策といえるでしょう。
中小企業退職金共済(中退共)を活用する際の注意点
中退共は非常に優れた制度ですが、導入や運用にあたってはいくつか注意すべき点もあります。代表的な注意点を確認しておきましょう。
注意点1 原則、途中での減額や中断は難しい
中退共の掛金は、一度設定すると、原則として途中で減額したり、支払いを中断したりはできません。
というのも、掛金は従業員の将来の退職金となるため、経営状況が悪化したからといって簡単に変更してしまうと、従業員の受け取る退職金が減ってしまうからです。そのため、事業主の都合による掛金の減額には一定の要件があり、容易には認められません。
ただし、著しい経営悪化など、特別な事情がある場合には、条件付きで減額が認められるケースもあります。
このため、中退共を導入する際は、無理のない掛金額を設定することが非常に重要です。将来の経営状況も見据え、長期的に安定して支払いを続けられる金額を設定するようにしましょう。
注意点2 掛金は事業主が全額負担
中退共の掛金は、全額を事業主(企業)が負担します。これは、従業員が退職金を受け取る際に税制優遇を受けられるなど、従業員側に大きなメリットがある一方で、企業にとっては毎月発生する固定費になることを意味します。
たしかに、掛金は損金として計上でき、社会保険料にも影響しないというメリットはありますが、実際には会社から現金が出ていくため、キャッシュフローへの影響は小さくありません。
そのため、中退共を導入する際には、助成金制度の存在も踏まえつつ、長期的に掛金を安定して支払い続けられるだけの資金計画が不可欠です。特に、新たに従業員を採用するほど掛金の総額も増加するため、将来的な人員計画も視野に入れておきましょう。
注意点3 短期離職者には退職金が支給されない場合もある
中退共は、従業員の退職金制度としての性質上、最低でも12ヵ月以上掛金が納付されていないと、退職金が支給されません。したがって、入社後1年未満で退職した従業員に対しては、企業が支払った掛金が「掛け捨て」となる可能性があります。
これは企業側にとってはロスとなる部分ですが、制度維持のためにはやむを得ない設計ともいえます。特に、従業員の入れ替わりが激しい業種や企業にとっては、この短期離職による掛金の掛け捨てリスクを考慮したうえで、制度導入を検討する必要があるでしょう。
注意点4 会社が退職金をコントロールできない
中退共では、従業員への退職金は企業を経由せず、中退共から直接支払われます。この仕組みにより、企業が退職金の金額や支給タイミング、条件などを個別に調整したり、柔軟にコントロールしたりはできません。
しかし、この「コントロールできない」という側面は、逆に支払いに関する従業員とのトラブルを未然に防ぎ、透明性の高い退職金制度を構築できるというメリットにもつながります。企業は支払い業務から解放され、従業員は制度の公平性に安心感を持てるでしょう。
もし、中退共の退職金に加えて、企業独自の退職金制度を設けたい場合は、中退共とは別に規程を設ける必要があります。
この節税術に必要な心構えとは
中小企業にとって中小企業退職金共済(中退共)の導入は、優れた節税対策となります。しかし「税金が減るから」といった短期的視点ではなく、中長期的に人材を育成し、組織全体を成長させるための基盤整備と捉えることが大切です。
中退共は、一度導入すれば終わりではなく、継続的な掛金支払いによってその効果を発揮します。自社の経営計画や資金繰りに合わせて、無理のない掛金設定が欠かせません。
また、制度の内容を従業員に説明し、「会社が将来に向けて投資している」という姿勢を示すことで、信頼感と定着率の向上も期待できます。
中退共は、節税と福利厚生の充実を同時に実現できる有力な制度です。導入を検討する際は、税理士など専門家の支援を受けながら、自社に合った制度設計を進めていきましょう。
経営者にとって、中退共は毎月の掛金を経費として計上できるうえ、退職金の管理・運用・支払といった複雑な業務を任せられるため、運営コストをかけることなく事務負担を大幅に軽減できるという大きなメリットがあります。
また、従業員にとっては、万が一の勤務先の倒産時でも退職金が保護される安心感や、退職所得控除による税制優遇がある点が魅力的です。提携施設の割引利用サービスも、福利厚生の充実をアピールする有効な材料となります。
長期的な掛金の負担はありますが、中退共を活用した福利厚生は、優秀な人材の確保や従業員の定着率向上に直結します。ぜひ、会社の成長戦略の一つとして積極的にご検討されることをお勧めします。
(白兼公認会計士・税理士事務所 代表 白兼 道夫)