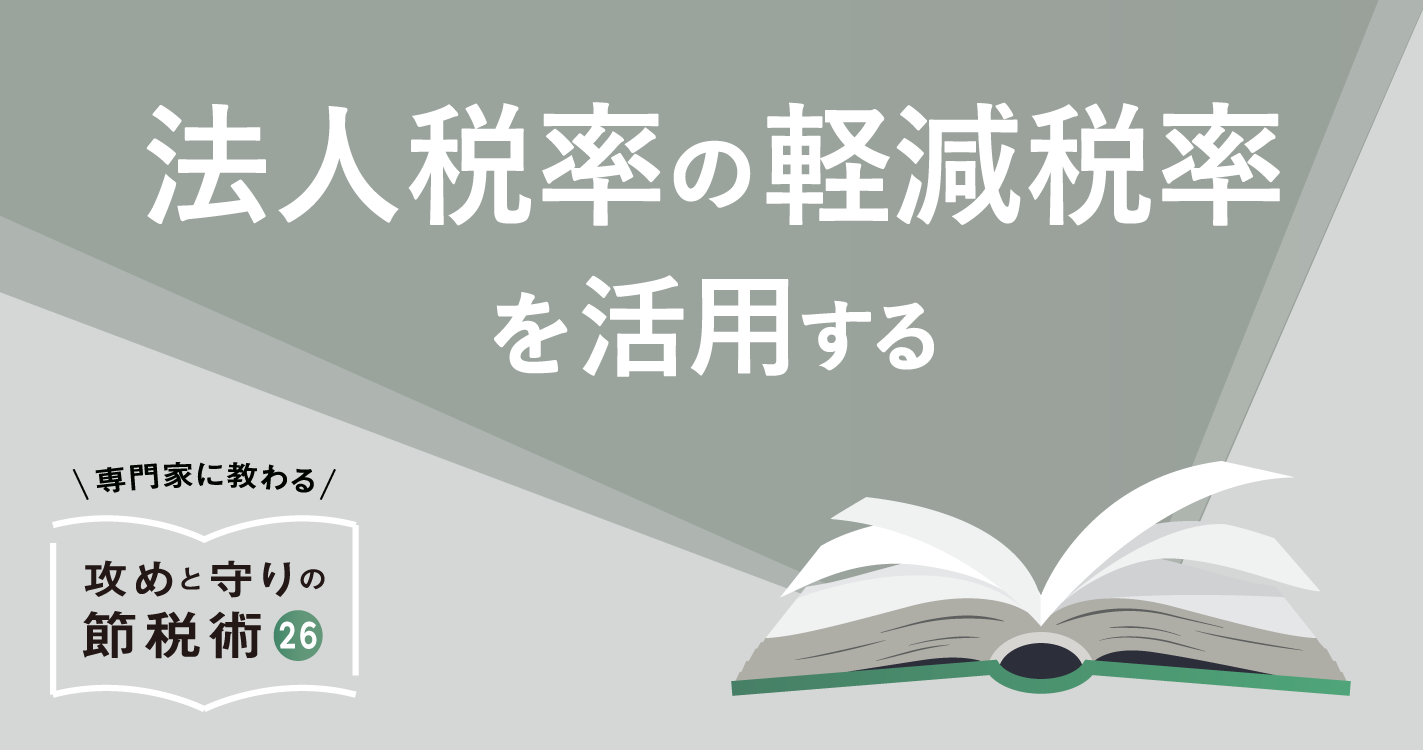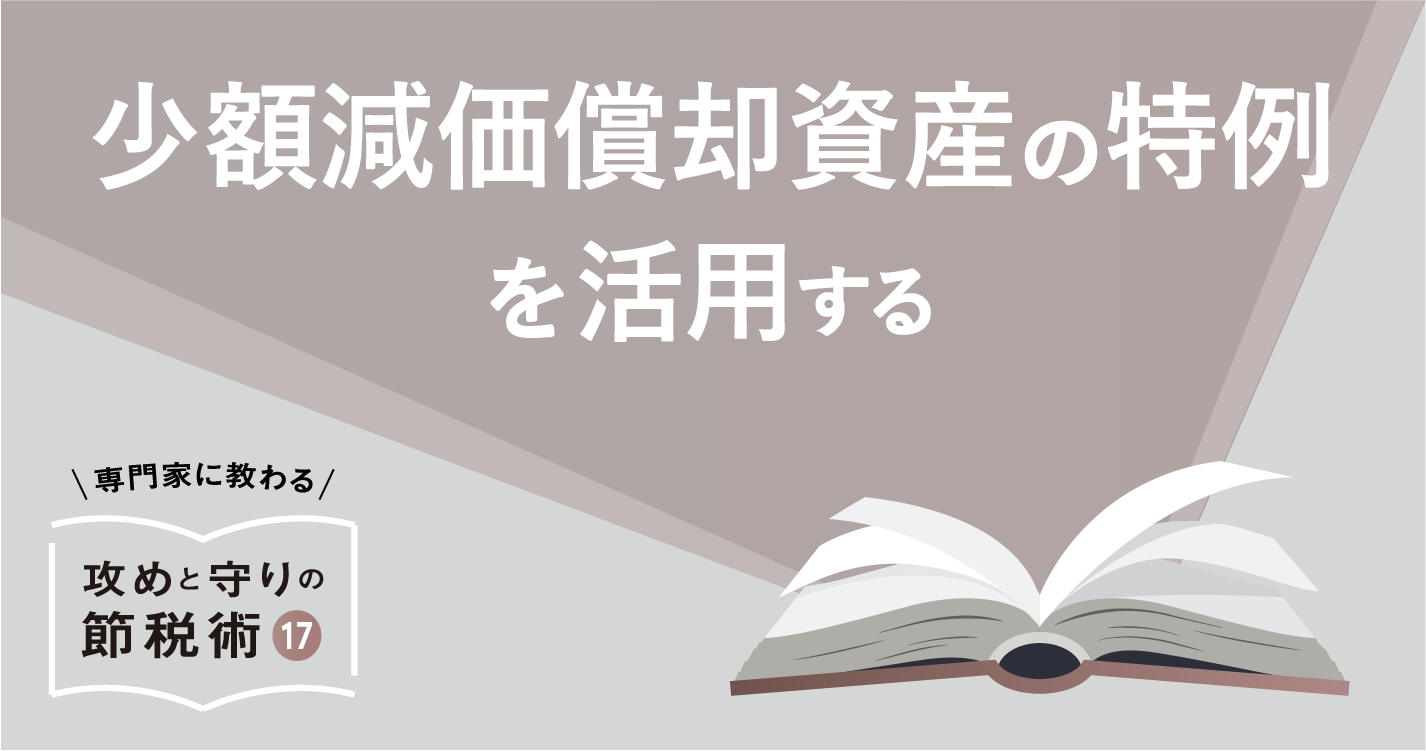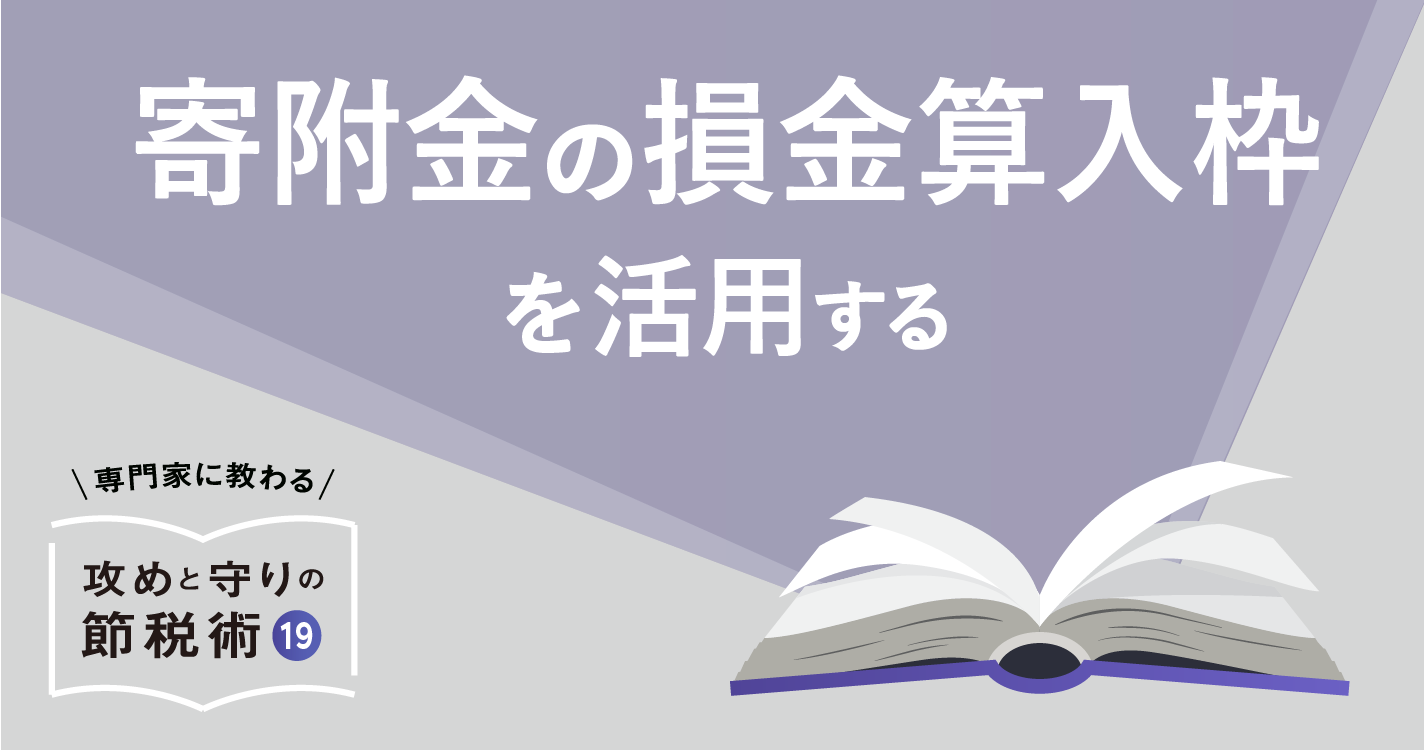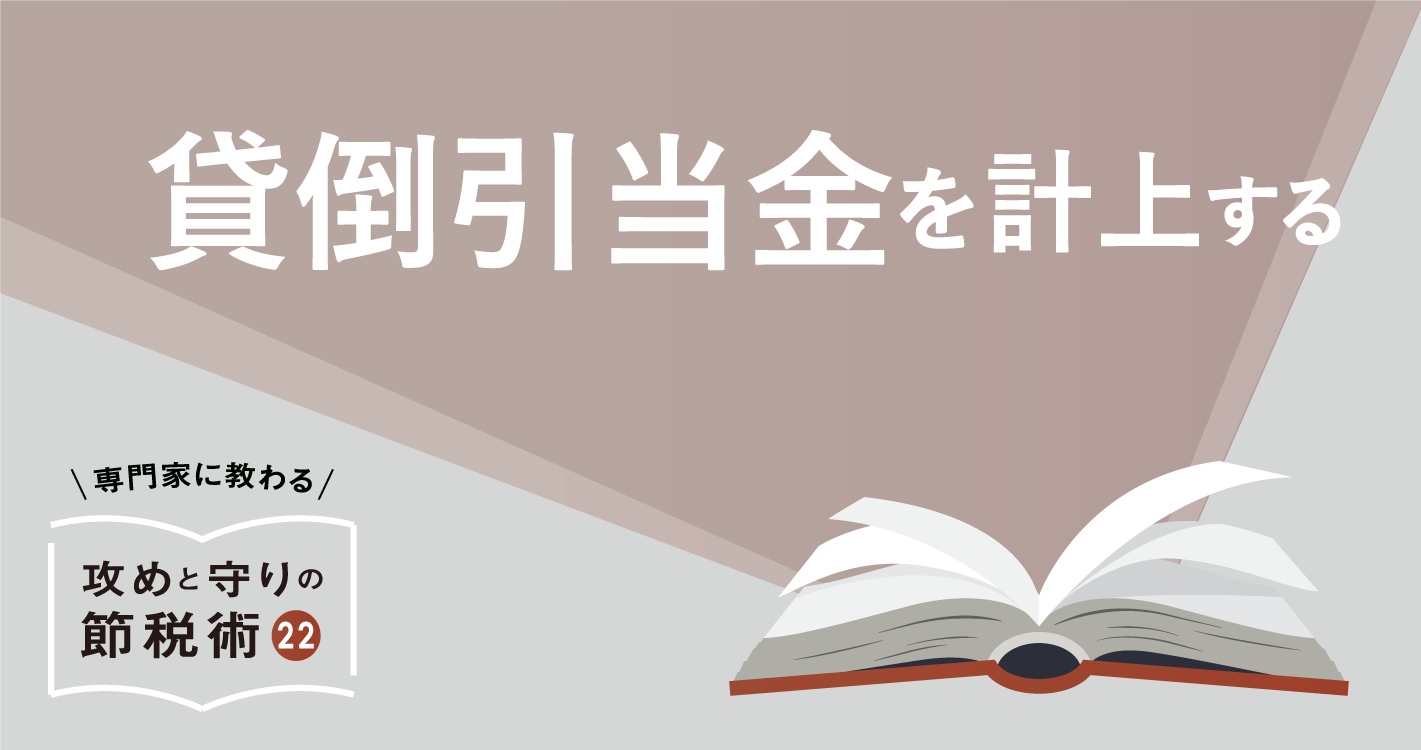
「貸倒引当金を計上する」という節税術
中小企業では、取引先の倒産や売掛金の回収トラブルに頭を悩ませることが少なくありません。昨今は物価上昇や資金繰り悪化など経済情勢の不確実性が高まっており、こうしたリスクはますます大きくなっています。
そのような状況でも、「貸倒引当金を計上する」という会計の仕組みを上手に活用すれば、将来の損失に備えつつ税金対策も可能です。この方法を利用すれば、実際に損失が発生する前に費用として計上でき、課税所得を減らして手元資金を増やせます。
本記事では、貸倒引当金の基本から節税メリット、注意点までをわかりやすく解説します。中小企業の財務体質を強化するために、ぜひ経営判断の参考にしてください。
貸倒引当金計上とは? 中小企業が計上する理由と節税の仕組み
「貸倒引当金計上」とはどのような意味を持つのでしょうか。ここでは、中小企業が貸倒引当金を計上する理由と、節税の仕組み(損金算入のポイントを含む)についてわかりやすく解説します。
貸倒引当金を計上することの意味
貸倒引当金とは、取引先が倒産したり売掛金が回収できなくなったりするリスクに備えて、将来の損失を見込んであらかじめ計上する「引当金」の一種です。
会計上は、売掛金や貸付金などの債権から差し引く形で扱われ、貸借対照表の資産のマイナス項目として表示されます。
この仕組みは、取引が発生した時点で収益や費用を計上する「発生主義」の原則に基づくものです。売上を今期に計上した場合、その売上に対応する貸倒れ損失も将来発生する可能性を当期に反映させることで、会社の本当の利益を正しく把握できます。
たとえば、売掛金が1,000万円残っている会社なら、過去の回収実績などを参考に数%を引当金として設定します。
勘定科目としては「貸倒引当金」が主で、費用側は「貸倒引当金繰入」として処理するのが通常です。貸倒引当金を計上することで、決算書がより現実的な姿を示し、中小企業の経営判断に大きく寄与します。
貸倒引当金を計上する理由
「貸倒引当金を計上する」理由は、単なる会計処理にとどまりません。特に節税の観点から大きなメリットがあります。税務上、一定の条件を満たせば、この引当金を損金(経費)として認めてもらえるため、課税所得から差し引くことが可能です。
実際の貸倒れが発生していなくても、事前に費用計上することで税負担を翌期以降に繰り延べ、当期の手元資金を一時的に厚くできます。具体的な理由としては、以下の3つが挙げられます。
- ①将来のリスクを可視化して経営を安定させる
- ②発生主義により期間損益を正確にし税務申告の信頼性を高める
- ③中小企業向けの簡易ルールで計算がしやすい、
資本金1億円以下の法人であれば、法定繰入率を使って簡単に計算可能です。過去の貸倒実績が少ない新興企業でも、業種ごとの標準率(卸売業1.0%など)を用いて引当金を設定できます。
節税のポイントは初年度の計上効果です。毎年繰り入れると戻入分が増えて相殺されますが、初年度は大きな繰入額を計上できるケースが多く、節税効果が出やすくなります。
2025年時点では中小企業向け貸倒引当金制度は継続していますが、税制改正の可能性もあるため、最新情報の確認や税理士への相談が安心です。
例えば、初年度1年目の貸倒引当金計上額が100円の場合は損金(経費)100円、貸倒引当金100円、2年目の貸倒引当金計上額が150円の場合は損金(経費)50円(150円-100円)、貸倒引当金150円になります。(増田晃士税理士事務所 代表 増田 晃士)
貸倒引当金を計上する節税メリット
貸倒引当金を計上することで、以下のような節税メリットが得られます。たとえば、課税所得を減らすことで手元資金を即座に増やせます。
節税メリット1 課税所得を圧縮し、実質的に納税を先送りできる
一番の魅力は、法人税の課税所得を直接減らせる点です。たとえば、売掛金総額5,000万円の会社が法定繰入率1.0%(卸売業例)で50万円を引当金として計上すると、その分だけ帳簿上の経費が増え、税金が約15万円(有効税率30%想定)軽減されます。
実際の現金支出は伴いませんが、税負担を繰り延べることで、手元資金の余裕を一時的に確保でき、キャッシュフロー改善に直結します。中小企業で運転資金が厳しい場合、こうした「見えない節税」は経営の助けになるでしょう。
節税メリット2 将来の貸倒れリスクを事前に織り込み、財務の安定化を図れる
節税だけでなく、リスク管理の面でも引当金は有効です。貸倒引当金を計上することで貸借対照表がより現実的な数字となり、財務内容の透明性が高まることで、銀行や取引先からの評価向上にもつながる可能性があります。
たとえば、貸倒懸念債権を個別に評価し、状況に応じて引当率(例:50%)を設定することで、潜在的な損失を事前に帳簿上で吸収できます。これにより、急な取引先倒産による損失の影響を緩和し、経営の安定化に役立ちます。
不透明な経済環境においては、この安定化効果は節税効果以上の価値を持つ場合があるでしょう。
貸倒れが発生した事業年度は貸倒損失の計上により赤字になる可能性がありますが、事前に貸倒引当金を積立てておくと「貸倒引当金戻入益」を利益計上することができ、貸倒損失を吸収することが可能になります。(増田晃士税理士事務所 代表 増田 晃士)
節税メリット3 税務申告の柔軟性が高まり、中小企業のキャッシュフローが改善する
中小企業(資本金1億円以下)向けの特例では、貸倒引当金の計算方法が柔軟であることも大きなメリットです。実績繰入率と法定繰入率のうち、より有利な方を選択できるため、貸倒実績の少ない会社でも節税上有利に活用できる可能性があります。
青色申告の事業所得や不動産所得の債権も対象で、法定率(例:最大5.5%)まで計上可能です。これにより、決算期に応じて引当金を調整することで、キャッシュフローをコントロールしやすくなり、年末の資金繰りも楽になります。
節税メリット4 突発的な貸倒れによる資金繰り悪化を予防できる
引当金を活用する会社では、債権の質を定期的に見直す習慣が身につきます。これにより、信用度の低い取引先を減らすなどの判断がしやすくなり、長期的に不良債権を防ぐことに役立つでしょう。
IPOを目指す中小企業であれば、会計の透明性を高めることで投資家や金融機関からの評価向上につながる可能性もあります。貸倒引当金は、節税効果だけでなく、経営管理の補助としても活用でき、財務の安定や健全な資金繰りの維持に貢献します。
貸倒引当金を計上する際の注意点
貸倒引当金を計上する際には、いくつかの注意点があります。特に、中小企業で多く用いられる一括評価の計算方法(法人の場合は法定繰入率または実績率、青色申告の個人事業主の場合は期末債権の5.5%まで)を誤ると、税務否認のリスクがある点には十分注意が必要です。
注意点1 計算方法(一括評価・個別評価)の選択を誤ると税務否認のリスクがある
中小企業で最も利用される計算方法は「一括評価」です。これは、資本金1億円以下の法人や青色申告の個人事業主が対象となり、期末の金銭債権(売掛金など)の帳簿価額から実質的に債権でない額を除いた残額に対して計算を行います。
法人の場合は、業種ごとに定められた法定繰入率(例:製造業0.8%、卸売業1.0%) を掛けて計上します。これに対し、青色申告の個人事業主の場合は、残高の最大5.5%(金融業は3.3%)までが限度額です。
一方、「個別評価」は、回収不能リスクの高い債権(倒産寸前や債務超過の取引先など)に絞り、状況に応じた率(破産申立て債権で50%など)を設定するものです。どちらの方法を選ぶかは、会社の規模や債権の特性に応じて判断すべきでしょう。
過大計上や不適切な方法の選択は、税務署から否認され、追徴課税のリスクにつながるため、十分な注意が必要です。
その債権は個別評価に該当するか?、該当する場合は貸倒引当金をいくら計上することができるか?、といったことは専門的知識が必要になるため、税理士に相談することをおすすめします。(増田晃士税理士事務所 代表 増田 晃士)
注意点2 対象債権の選定基準を明確にし、過少・過大計上を避ける
貸倒引当金の対象となるのは、売掛金や貸付金などの金銭債権に限ります。逆に、銀行への預金(普通預金など)や、将来費用となる仮払金・前払金、手付金などは対象外です。
対象債権の選定基準を曖昧にすると、過少計上によって将来のリスクが残る一方、過大計上は利益操作と疑われる可能性があるため、十分な注意が求められます。
実務では、社内ルールを整備し、取引先の財務状況を定期的にチェックすることが重要です。中小企業の場合、売上比率の高い取引先から優先的に評価することで、企業全体のリスク管理の精度を高められるでしょう。
注意点3 仕訳処理(洗替法・差額補充法)のタイミングを守り、会計・税務の整合性を確保する
貸倒引当金の仕訳には、洗替法と差額補充法の2種類があります。
洗替法は、前期の引当金を全額戻入した上で当期の新規引当金を計上する方法です。一方、差額補充法は、前期残高との差額のみを調整します。
税務上は、原則として洗替法が推奨されており、決算期末に処理することが重要です。タイミングを誤ると、会計と税務の整合性が崩れ、修正申告や税務調査のリスクにつながります。
たとえば、前期の引当金残高が40万円、当期の見積額が50万円の場合、洗替法では前期分40万円を戻入し、新たに50万円を繰入します。仕訳の正確性を保つために、クラウド会計ツールの自動化機能を活用するのも有効です。
注意点4 税務調査対策として、根拠資料をしっかり残す習慣をつける
税務調査では、貸倒引当金の計上根拠を確認されるケースが多く見られます。そのため、計算の根拠となる資料を整理して残すことが重要です。具体的には、債権リスト、繰入率の算定資料、取引先の信用情報などを一元的にファイル化します。
IPO準備中の企業では、内部統制の強化と合わせて管理すると、信頼性が高まります。また、2025年現在、デジタル化が進んでいるため、電子帳簿保存法の要件に沿って電子保存で管理することも有効です。
こうした対応により、万一の否認リスクを減らし、節税効果を確実に活用できます。
この節税術に必要な心構えとは
貸倒引当金の計上は、単なる会計処理にとどまらず、資金繰りの改善や経営リスクの可視化など、中小企業にとって大きなメリットをもたらす節税術です。
しかし、計算方法の選択や対象債権の評価、仕訳処理のタイミングなど、細かなルールを誤ると税務否認や追徴課税のリスクが伴います。特に初年度の設定や毎期の見直しは、経営判断と税務知識の両方が求められるため、社内だけで完結させるのは容易ではありません。
節税効果を最大限に活かしつつリスクを回避するためには、実務に精通した税理士へ早めに相談することが最も確実な方法です。
プロの視点を取り入れることで、最新の税制改正や業種別の繰入率にも対応でき、将来の資金計画も見据えた最適なスキームを設計できます。
将来の貸倒リスクに備えながら会社の成長を守るために、ぜひ信頼できる税理士と連携し、安心・確実な節税対策を進めていきましょう。
取引先が倒産したり売掛金が回収できなくなったりするリスクに備えて、将来の損失を見込んであらかじめ計上する貸倒引当金は単なる会計処理にとどまらず、節税の観点から大きなメリットがあります。税務上、一定の条件を満たせば、貸倒引当金を損金(経費)として認めてもらえるため、課税所得から差し引くことが可能になります。
その他、将来の貸倒れリスクを事前に織り込むことで財務の安定化を図れるため、銀行や取引先からの評価向上にもつながる可能性があります。
一方で、貸倒引当金の計上にはいくつかの注意点があるため、税務否認のリスクを回避すべく、税理士に相談するといいと思います。
将来の損失に備えつつ税金対策も可能な「貸倒引当金」、是非活用してみてください。
(増田晃士税理士事務所 代表 増田 晃士)