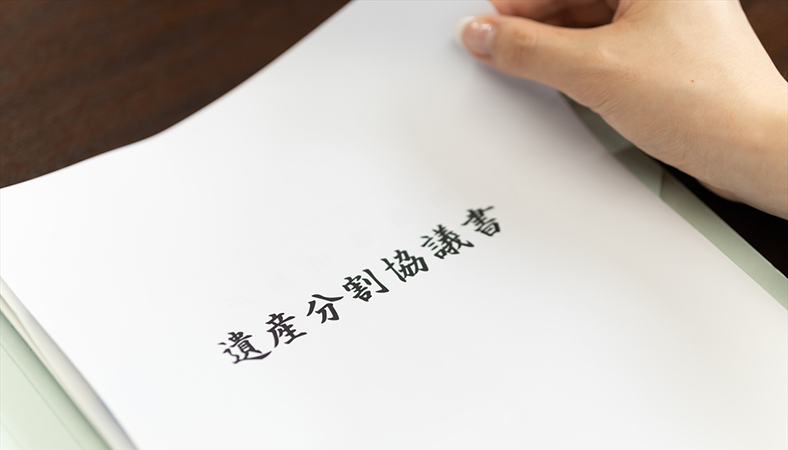【2024年最新版】確定申告と年末調整の両方が必要なケースとは?
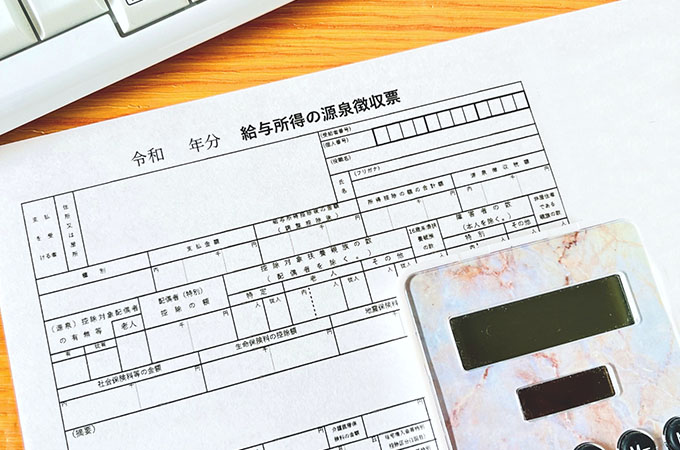

所得税に関する手続きに、確定申告と年末調整があります。「会社員なら年末調整、個人事業主やフリーランスなら確定申告」と認識している人も多いでしょう。実は、確定申告と年末調整の両方が必要な場合があるのをご存じでしょうか。該当するケースを紹介します。
確定申告と年末調整の両方が必要になるケースは?
基本的に、会社員などの場合、年末調整をすれば確定申告は不要です。しかし、なかには確定申告しなければならないケースもあります。確定申告と年末調整の両方が必要になるのはどんなケースでしょうか。見ていきましょう。
主に、以下のケースでは年末調整をしていても確定申告が必要になります。
・副業の所得が20万円を超える場合
働き方改革を受けて、会社員でも副業をする人が増えてきました。副業の所得が20万円を超える場合、年末調整をしていても確定申告が必要です。給与所得以外の所得合計金額が20万円をこえる場合、申告する決まりになっています。
・2カ所以上の勤務先から給与を受け取っている場合
年末調整は、1人につき1カ所だけで行える手続きです。ダブルワークなどで2カ所以上の勤務先から給与を受け取っている場合、1つの勤務先でしか年末調整はできません。一般的に、メインで給与を受け取っている勤務先で年末調整することになります。もしメインの勤務先以外の給与が20万円を超えるなら、確定申告が必要です。
アルバイトの掛け持ちをしている方も多いと思います。
アルバイトも給与収入には変わりませんので、年末調整は1つの勤務先でしか行えません。
なお、掛け持ちをしているアルバイト先のすべてで源泉徴収されていないのであれば、年末調整も確定申告の必要もありません。

河鍋公認会計士・税理士事務所代表 河鍋 優寛(税理士・公認会計士)
・年の途中で転職し前職の収入を年末調整に反映できなかった場合
年の途中で転職した人もいるでしょう。一般的には前職の勤務先から交付された源泉徴収票を提出し、まとめて転職先で年末調整を受けることになります。しかし源泉徴収票の提出が間に合わなかったなど、前職の収入を反映できない場合は確定申告しなければなりません。
・ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用できない場合
給与所得者がふるさと納税をした場合、確定申告せずに寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用することができます。ただしワンストップ特例制度を利用できるのは、1年間で寄附した自治体が「5つまで」の人です。6つ以上の自治体に寄附している場合、確定申告をして寄附金控除を受けることになります。
・一定金額以上の医療費がある場合
1年間の医療費が「10万円」または「総所得金額等×5%」のいずれか低い方を超えた場合、医療費控除を受けることができます。医療費控除は確定申告しないと受けられません。控除を受けたい場合、年末調整していても確定申告が必要です。
・災害などで自宅や家財に損害を受けた場合
災害・盗難などで自宅や家財に損害を受けた場合、雑損控除を受けられる場合があります。医療費控除と同様、この雑損控除も確定申告でしか受けられない控除です。
・住宅ローン控除1年目の場合
一般的に住宅ローン控除は、年末調整で手続きできます。しかし、1年目だけは注意してください。税務署が確認するため、1年目は確定申告が必要になります。
住宅ローン控除を確定申告で受けるためには、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成しなければなりません。記載内容が難しいため、住宅ローン1年目に該当する確定申告は税理士に任せた方が間違いないでしょう。

河鍋公認会計士・税理士事務所代表 河鍋 優寛(税理士・公認会計士)
・特定口座の株式運用益で節税をしたい場合
源泉徴収アリの特定口座は確定申告が必要ありませんが、以下の場合、申告しなければなりません。
〇複数の口座それぞれで生じた利益と損失を相殺して還付を受けたい場合
・年末調整で申請し忘れた控除がある場合
年末調整で申請し忘れた控除がある場合、自分で確定申告をすれば、控除を受けることができます。
そもそも確定申告と年末調整では何が違うの?
確定申告も年末調整も、所得税に関する手続きであることには変わりありません。では、その違いはどこにあるのでしょうか。確定申告と年末調整の違いを説明します。
確定申告とはどんな手続き?
確定申告とは、所得税額を申告する手続きです。1年間の収入から経費などを差し引いて、納めるべき所得税額を自分で計算して申告します。主に事業所得のある個人事業主やフリーランスが行う手続きですが、会社員でも年末調整を行えない場合は確定申告をすることになります。例えば1年間の給与が2,000万円を超える人は年末調整できませんから、確定申告をする必要があります。
年末調整とはどんな手続き?
年末調整とは、給与所得者が本来支払うべき所得税額を計算し、その年の給与から差し引いた源泉徴収額との差額を清算する手続きを指します。
毎月の給与からあらかじめ所得税を差し引いて、会社が本人に代わって納税する源泉徴収という仕組みがあります。この源泉徴収額はおおよその金額で、正確な納税額ではありません。年末調整で正確な所得税額を算出し、源泉徴収額との差額を清算するのです。源泉徴収額が本来の所得税額より多ければ還付されますし、反対に少なければ追加で徴収されることになります。
確定申告と年末調整の違い
確定申告と年末調整の違いは以下のとおりです。
| 項目 | 確定申告 | 年末調整 |
|---|---|---|
| 手続きする人 | 本人が手続きする | 本人に代わって会社が手続きする |
| 対象 | 全ての人 | 給与所得者 |
| 受けられる控除 | 年末調整でできる控除に加えて ・医療費控除 ・雑損控除 ・住宅借入金等特別控除の1年目 |
・扶養控除 ・基礎控除 ・配偶者控除、配偶者特別控除 ・保険料控除 ・社会保険料控除 ・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の2年目以降など |
確定申告と年末調整を両方する場合の注意点
ここで、確定申告と年末調整を両方する人に向けて注意点を説明します。年末調整後の確定申告では、以下の点に注意してください。
・源泉徴収票を保管しておく
2019年4月1日以降、給与所得の源泉徴収票の確定申告書への添付が不要になりました。しかし、確定申告書の作成には源泉徴収票が必要です。しっかり保管しておくようにしましょう。
・スマホ申告できない場合もある
給与取得者は、スマホで確定申告することができます。ただし、不動産所得があったり個人事業主としての事業所得があったりする場合、手軽なスマホでの申告ができません。スマホで簡単に済ませられるからと後回しにせず、対象になる人は早めの準備を始めてください。
なお、副業所得が20万円を超えるなど確定申告が必要にもかかわらず申告しないと、延滞税などのペナルティが発生する場合があります。また、確定申告しないことで、本来受けられる控除や還付が受けられなくなる可能性もあるでしょう。年末調整を済ませたからと言って安心せず、確定申告が必要でないかしっかり確認することが大切です。
事業所得や不動産所得がある方はPCを使ってe-Taxでの確定申告をしましょう。
もし難しければ税理士に依頼することで電子申請を行うことができ、青色申告特別控除を最大限受けることができます。

河鍋公認会計士・税理士事務所代表 河鍋 優寛(税理士・公認会計士)
まとめ
自分は会社員だから確定申告はできない、必要ない、と考える人もいるでしょう。しかし説明してきたように、確定申告と年末調整の両方が必要なケースもあります。確定申告が必要なのに手続きしなかった場合、ペナルティが発生するかもしれません。せっかくの控除や還付が受けられなくなる可能性も考えられます。両方必要なケースに該当しないか、もう一度本記事を振り返ってみてください。
▼参照サイト
記事監修者 河鍋税理士からのワンポイントアドバイス
2024年は定額減税の実施もあり、年末調整に関する書類様式も増えました。
年末調整も確定申告もいずれも「個人の所得税を確定し、精算する手続き」という点で共通していますが、それぞれが対象になる人や控除の種類や書類様式は全く異なります。
会社員の方で今まで年末調整で済んでいた方でも、現在は副業や複数箇所で働く方(ダブルワーク)も増えていますので、確定申告の必要性が出てきた方も多くいると考えられます。
年末調整を受けた後に確定申告をする場合は、年末調整を行った勤務先での源泉徴収票が必要になりますので大切に保管するようにしましょう。
年末調整を行った後は年が明け、確定申告期限までは2ヶ月程度しかありませんので、確定申告で特に事業所得や不動産所得のある方は税金面で損しないように準備をしっかり行いましょう。
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。

新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
米国向け輸出入企業必見!トランプ関税が導入されたら?国別影響と対応策を仮想シナリオで徹底解説
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ
-
裏金問題とは?政治資金の透明化と不正の実態を解説
-
【2025参院選】参院選で私たちの生活はどう変わる?各政党の政策を徹底比較・完全解説
-
オフィスの観葉植物は経費計上できる?正しい仕訳方法と注意点を解説